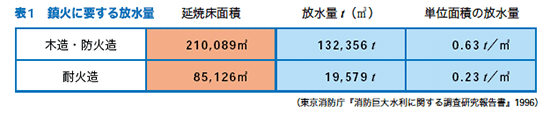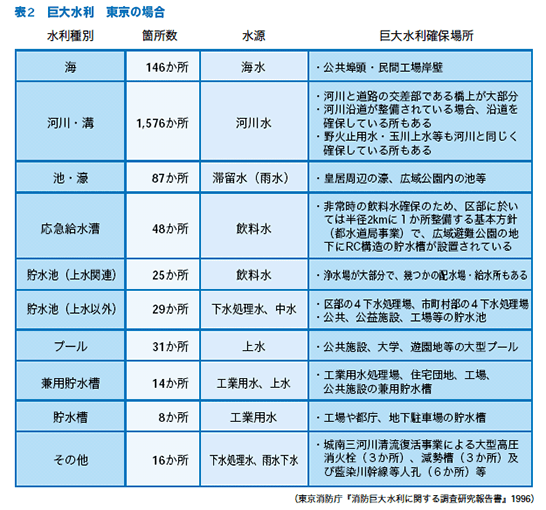機関誌『水の文化』20号
消防
-
編集部
消火にはどれくらいの水が必要か?
火災は千差万別。一つとして同じ現場はなく、木造住宅火災でも火元、風向き、隣家との距離、火勢などに応じて、現場の消防士は消防戦術を立てる。
当然、各ケースごとに使用水量も違うのだが、ここに東京消防庁による興味深いデータがある。管内で発生した1990年(平成2)から1994年(平成6)までの部分焼以上の火災について、延焼床面積と鎮火までに要した放水量を集計したのが表1だ。
これは平時の火災だが、地震による同時多発火災の場合にどれくらいの水が必要なのか。同じく東京消防庁の調査では、阪神淡路大震災では1平方メートルあたり、平均で0.51立方メートル(t)の水を要したと報告している。(東京消防庁『消防巨大水利に関する調査研究報告書』1996)
この水量は多いのか? 少ないのか?
仮に木造3LDK、約78平方メートルの家が火災となった場合を想定すると、約40tの水が必要となる計算だ。
これがどの程度の量かというと、家庭の風呂(おおよそ300L=0.3t)にすると約130杯、小学校25mのプール(約250t)でいえば、約6分の1の水が1軒の鎮火に必要となる。
消防水利は安心か
日本では都市の不燃化を強力に押し進めた結果、平成15年の人口1万人あたりの出火件数は全国で4.4件/万人、年間死者数は2248名となっている(『消防白書平成16年版』)。これは海外と比べても低い数字といわれている(日本火災学会編『火災と建築』共立出版、2002)。
防災インフラの一つに、消防水利の整備が挙げられる。
消防車が消火に使う水が消防水利で、1964年(昭和39)に定められた「消防水利の基準」には、消火栓、防火水槽、プール、河川・溝、濠・池、海・湖、井戸、下水道が例示されている。
これら消防水利は「常時貯水量が40t以上、または取水可能水量が毎分1t以上で、かつ、連続40分以上の給水能力を有するものでなければならない」と定められている。この根拠は、標準的な木造住宅の火災を延焼させないために必要な水量が40tであり、消防ホース1本あたり毎分500Lの放水を、2本で40分間続けると想定して導かれている。これを、おおむね80〜120mおきに設置しなくてはならないのだ。
消火栓は水道につながっているので、平時はきちんと働くだろう。しかし、地震などによる同時多発火災になれば、消火栓は頼りにならないかもしれない。これが阪神淡路大震災の教訓だった。そこで、耐震貯水槽の整備が始められたのだが、「消防水利基準」で定められた最低貯水量40tとなると、家1軒の消火で耐震貯水槽を使い切ってしまう計算になる。
巨大水利
もしも大地震によって同時多発火災が起きたとき、東京消防庁では消火栓を使わずに、防火貯水槽をはじめとした「無圧水利」を使うという。
貯水槽は、250mの正方形地域(地図上のメッシュ)の中に、おおむね100tまたは40tの水を確保するように整備されている。かつ、750m正方形の中に、750〜1500tの水を整備するという、二重の規制がかかっている。
この背景にある考え方が「巨大水利」というコンセプトである。阪神淡路大震災の消防水利不足を教訓に、都市に大量の防災用水を蓄えようというものだ。
巨大水利は、河川などの「無限水利(涸れない水)」と、大規模貯水槽のような1500t以上の水量を有する「大容量水利(大量の水)」から成る。表2は、1996年時点での東京の巨大水利の確保場所を示した図で、どんな水を想定しているのかがよくわかる。
一見してわかることは、海や河川・溝、池など、自然の水がまず挙げられていることだ。しかし、こうした水利がとれないと思われている地域では、大容量の貯水槽を設けることで水の量を稼がざるをえない。
ちなみに本誌に登場した丸の内消防署管内には、消火栓が474、防火水槽等が117、河川・溝が7、池・濠が26ある。狭い範囲に117カ所の貯水タンクが整備されており、量的には充分といえるものだ。丸の内で見た貯水槽群はその一つとしての役割を果たすものである。
丸の内はビジネスに特化したまちで、消防士というプロフェッショナルが安全を守っている。不燃化された建築物は、ちょっとやそっとでは燃えないだろうし、万が一火災が起きても消防のプロがすぐ消し止めてくれる場所という安心感がある。そういう意味では、100%公に託されたまちといってよいだろう。
しかし、目には見えない多数の貯水槽で確保された安全とは別に、お濠や日本橋川という「手近で目に見える巨大水利」に安心を覚えてしまうのは、なぜなのだろう。
消防団は何をする
日本には、2004年(平成16)4月1日時点で、91万9105人の消防団員がいる。あなたは、消防団の働きと権限を知っているだろうか。
消防団員とは、別に本業を持っている消防のためのボランティアで、消防の権限と責任を持つ非常勤特別職の地方公務員と規定されている。わずかながら、報酬も出る。平均年齢は37.4歳で、地域によってその姿は大きく異なっている。かつてはムラ社会の時代からある地域密着型の組織で、青年団から自動的に消防団に入ることになっていたが、そんな姿も昔のものになりつつある。
農家も含めた自営業者が多い地域では活発だった消防団活動も、夜間に人が住まないオフィス街や、昼間は男手が働きに出るサラリーマンのベッドタウンとなると、なかなか勧誘も大変なようだ。
ちなみに、消防団は消防署と「ともに」地域を守る組織で、消防署の管轄下に入るものではない。このことは消防組織法でも定められている。実際の現場では、消防署が火を消し、現場を離れた後の残火整理を消防団が受け持つなど、その土地に応じた両者の業務分担がある。さらに忘れてはならないのが、水防も彼らの重要な役目の一つだ。
身近な消防水利が私たちの消防力を育てる
阪神淡路大震災を教訓に、自主防災組織を立ち上げようという運動が活発だ。平時には防災訓練や資機材の共同購入などを行ない、災害時には初期消火、避難誘導、負傷者等の救出・救護、情報の収集・伝達、給食・給水、災害危険箇所の巡視などを行なうこととされている。婦人防火クラブや少年消防クラブなど、全国で約11万2000の組織が設置されているという。
しかし、延焼の危険が迫ってきたとき、近くの水を使って本当に消火できるのか。台所で発火した、天ぷら油を正しく処理できるのか。想像すると、気がはやるばかりで、火を消すことはなかなか難しい。
消防に必要なことは、技術と人のつながりだ。でも、いざというときに体がすぐに動くかどうかは、「消防の志」の問題。消防署のみなさん、消防団のみなさんだけではなく、おそらく普通の生活をおくる私たちもちょっとした志を持つべき時代が来ているのだろう。
しかし自分で貯水槽の蓋を開けた経験がある人は、ほとんどいないはずだし、どこに消火栓、貯水槽があるか知らない人も多い。さらに、近くの川・水路が、消防水利として使えると認識している人は皆無に近いだろう。
日本の都市で暮していれば、平時の火災だけではなく、地震による「非常時の火事」も気にかかる。「いつも使える手近な水」を消防水利として意識していれば、普段も安心して暮らせるし、いざというときに大きな差が出る。国は「消防力」を「消防の責任を十分に果たすために必要な施設と人員」と規定するが、同時に、住民自身が「いつでも汲める涸れない水」を使いこなすことや「いつも使える手近な水」の所在を意識していることも必要なのではないだろうか。
大切な命や財産がかかっているのだから、機械じかけの大層な安全だけではなく、目に見える自前の安心も欲しいものだ。