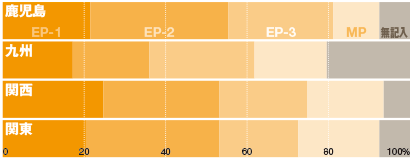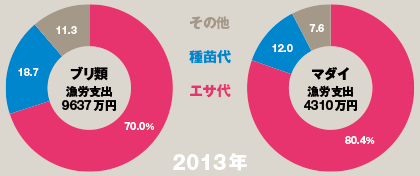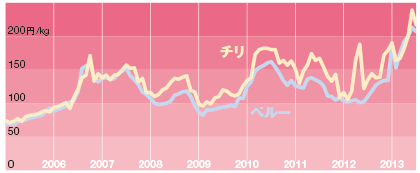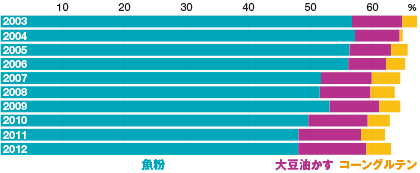機関誌『水の文化』49号
エサの変遷とこれからの養殖

養殖魚の味には「エサ」がとても大きな影響を及ぼしている。そこで養殖魚のエサの研究開発を行なっている独立行政法人 水産総合研究センター 増養殖研究所の山本剛史さんに話を聞いた。話題は養殖魚のエサの変遷にとどまらず、地域ごとに異なる味の好み、さらにエサを起点にした育種にまで及んだ。
-

-
独立行政法人 水産総合研究センター 増養殖研究所
養殖システム部 飼餌料グループ グループ長
水産学博士
山本 剛史(やまもと たけし)さん -
三重大学生物資源学研究科 客員教授、農業資材審議会 専門委員(養魚飼料、遺伝子組み換え)、日本水産学会 編集委員なども兼務。
養殖魚のエサの主流は生き餌から配合飼料へ
養殖魚に与えるエサは、淡水魚、海水魚ともに以前は小魚をそのままエサとする生餌(なまえ)でしたが、今は配合飼料が主流となっています。
まずは淡水魚から。ニジマスの養殖が始まったのは明治時代で、最初は家畜の内臓や蚕のさなぎなどを与えていました。しかし、鮮度や栄養価の問題があり、魚粉にビタミンやミネラルなどを混ぜて固めたDP(ドライペレット)が開発されました。それが普及して、今はニジマス、アユ、コイなどの淡水魚の養殖はほぼ100%DPを使っています。
一方、海水魚は長年、近海で獲れる小魚をそのままエサにしていました。ところが、養殖が盛んになるにつれ生魚が不足したり、生魚の品質が不安定で魚に病気が出たりしました。また大量の食べこぼしが海を汚染するとして環境問題にもなりました。そこで生魚と粉末配合飼料を混合して粒状にしたMP(モイストペレット)に切り替えが進み、さらに栄養価が高く保存が容易なDPに中心が移っていきます。1989年(平成元)には、より消化吸収のよいEP(エクストルーデッドペレット=多孔質飼料)が開発されて、今はこのEPがスタンダードになっています。
これらの配合飼料は生餌に比べて栄養価が高く、バランスがいいといえます。とはいえニワトリやブタなど家畜ほど魚の飼養技術の完成度は高くありません。魚はどのような栄養をどれくらい与えればいいのかを標準化することが非常に難しいからです。
魚は変温動物ですので、水温が下がると極端にエサの消化能力が落ちます。また、飼育密度や水質、海流の向きなど、環境が少し異なるだけでエサへの食いつきがまったく変わります。隣同士のいけすですら成長にばらつきがあるほど。そうしたなかでトライアンドエラーを繰り返し、少しでも多くの魚にとって成長効率のよいエサの研究開発を、私たちは日々行なっているところです。
おいしさの基準は地域や年代で違う
エサは、養殖魚の味を決める重要な要素となります。では、おいしい魚とはどんな魚でしょうか。
実は、味というのは食材そのものの味だけでなく、見た目から感じる先入観や地域性などが複雑に影響しています。公正に評価することはとてもやっかいなのです。
エサや飼育方法の異なる魚を食べ比べて味を評価する「食味試験」があります。アユの塩焼きでこの食味試験を行なったところ、同じ条件のアユでもきれいに焼けているか、それとも少し焦げているかで、おいしさの評価が分かれてしまいました。味は同じなのに、見た目の良し悪しが味覚の判断に影響したわけです。
例えばブリの切り身を買うとき、血合いが鮮やかな赤色のものと灰褐色のものがあった場合、消費者の多くは前者を選ぶでしょう。血合いが退色しているものは鮮度が悪く、味も落ちると判断するからです。
このように見た目は味に大きく影響しますが、この点についてはエサに配合する成分によってある程度の調整が可能です。ギンザケの赤い身やタイの体の赤みなどは、エサに天然魚と同じ色素を配合しているからです。また切り身は輸送中に酸化が進みますが、エサにビタミンCやE、ポリフェノールなどの抗酸化物質を添加してできるだけ酸化を抑制し、血合いの退色などを防いでいます。
脂質も魚の味を決める大事なポイントだといわれます。脂質を多く含むエサを与えれば、脂ののった魚をつくることができますが、たんに脂が多ければおいしいという単純なものではないようです。
脂質含有量の異なるブリについて、脂質とおいしさの関連を調べる食味試験を、九州(鹿児島除く)、鹿児島県、関西、関東の4つの地域・県で年代別、男女別に試験を行なったことがあります。すると九州では脂質の少ない魚が好まれ、関東は中程度の脂質の魚、関西は脂質の多い魚が好まれるという結果でした。おもしろいのは、同じ九州でも鹿児島県だけは脂質の多い魚を好む傾向があったことです。
年代でみると、10代は特に脂質の多い魚を好み、年代が上がるにつれ脂質の少ない魚の評価が高くなる傾向がありました。また女性は男性よりも脂質の少ない魚への評価が高くなりました。
これらの結果は、養殖ブリに対する消費者の志向を表しているわけではなく、食べる人の年齢や性別、地域によって好みが多様であることを示しています。養殖魚のマーケティングを考えるうえで参考になるかもしれません。
魚粉に代わる植物性原料のメリットとデメリット
現在、配合飼料が直面している最大の課題は、主原料である魚粉の確保です。日本では魚粉のほとんどを輸入に依存していますが、世界的に養殖業が盛んになり、その結果、エサの原料となる魚粉が品薄になって価格が高騰しているのです。
養殖業では経費の6〜7割をエサ代が占めているため、原料となる魚粉の価格が上がることは業者にとっては死活問題です。その反面、日本では魚粉が多いほどいいエサだという考えが根強く、なかなか魚粉の配合率を下げることができないのです。今後、海洋資源保護の観点からも魚粉の使用量を減らさなければなりませんので、当研究所でも大豆油粕やコーングルテンといった魚粉に代わる植物性の代替飼料の利用を促すための研究に力を注いでいます。
大豆油粕やコーングルテンは、食品加工等の副産物として大量に生産されるため、魚粉より安価に調達できます。ただし、今は魚粉を減らして植物性原料を配合しても、期待されるほどコストは下がりません。植物性原料は魚粉に比べてたんぱく含量が低いので、減らした魚粉に相当するたんぱく量を補うには配合量を増やさなければならないからです。
さらに植物性原料を増やすと、成長が低下したり、生理障害が出たりすることがあります。この問題は、タウリンなどの成分を補足し栄養面を強化することで解決できますが、こうしたプラスαの部分でどうしてもコストがかかってしまうのです。
育種技術を高め価値を引き出す
植物性原料を配合した安価な飼料だけで養殖魚を大きく育てることが理想です。私たちはそれを育種(注1)の技術によって実現できると考えています。
実際に私たちは、アマゴに植物性原料を配合した安いエサを与え、そのなかで大きく育った個体のみを選抜して交配を繰り返す実験をしてみました。すると二世代目には、植物性原料の多いエサだけで育てても従来のエサで育てたアマゴと同じくらい成長するようになりました。育種を適切に行なえば、植物性原料配合のエサに対する摂餌効率が高く成長率もよい系統の魚がつくれるはずです。今、各方面と協力し、カンパチで同様の実験を進めています。
育種が進み、遺伝的に優れた集団ができてくれば、養殖魚も牛や豚のような本格的なブランド化が可能になります。消費者の多様な好みに合わせ、いけすごとにエサを変えて「このいけすの魚はこういう味で、こうした料理が合う」と提案できるようになれば、味にばらつきのある天然魚に対する強みになるでしょう。
これまで養殖はいかに天然魚に近づけるかに腐心していましたが、最近では「養殖魚と天然魚は別もの」との認識が広がっています。養殖魚は、飼料安全法(注2)のもと与えるエサが管理されていますし、漁獲量によって市場価値が変動する天然魚に対して、計画的に生産・出荷できる利点もある。個性や特色をもったブランド養殖魚も現れています。
消費者や流通業者が「養殖魚には養殖魚のいいところがある」という意識をもう少しもつようになれば、養殖魚の価値はもっと高まっていくのではないでしょうか。そのためには養殖業界や研究者がしっかり連携して、育種や飼育環境の改善、ブランド化など、一つひとつの取り組みを地道に重ねていくことが重要です。
私たちもエサという側面から、養殖魚の価値を高める努力をこれからも続けていきたいと思っています。
(注1)育種
自然な状態では偶然でしか現れない優良な形質を、それが発現している魚同士を交配させて、常に現れるような系統をつくり出すこと。色や形が異なるフナを交配させて生み出したキンギョが有名。交配によるため、品種や系統を生み出すまでに時間がかかる。
(注2)飼料安全法
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律。農林水産省では国内で生産、あるいは海外から輸入される飼料の安全性を確保するため、飼料安全法に基づき各種規制(飼料添加物の使用量、有害物質の残留基準、帳簿の備え付けなど)を実施。対象は全31種類で、家畜は牛、豚、鶏など、養殖水産動物はブリ、マダイ、ギンザケなど。
(2014年12月15日取材)