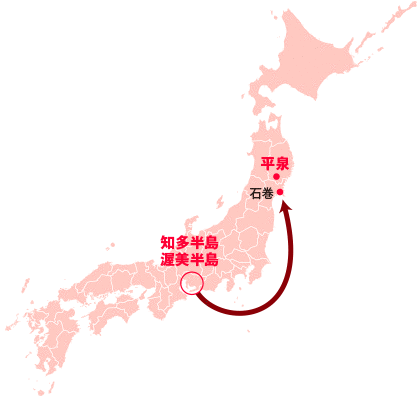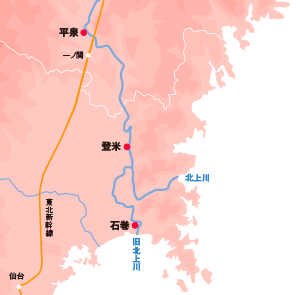機関誌『水の文化』54号
Story2
陶器がつなぐ奥州と東海

石巻市の水沼地区にある亀向山龍泉院(きこうさんりゅうせんいん)で大切に保管されていた江戸時代の常滑焼と伝わる大壺
東北地方は米や鉱物など豊かな資源に恵まれ、それらを日本各地に送り出す一方で、衣料品や醸造食品、陶磁器などさまざまな工業製品を受け入れてきた。東北学院大学教授の斎藤善之さんは「すでに古代末期の12世紀には東海地方から東北地方に向けて大量の陶器が送られていたことがわかってきました。奥州藤原氏の拠点であった平泉から常滑焼(とこなめやき)と渥美焼(あつみやき)が大量に発見されたからです。江戸時代になると仙台藩の米が廻船で江戸に運ばれ、帰りには江戸から古着や薬、陶器などさまざまな物資がこの地にもたらされました。北上川流域には今でもその当時の記録や痕跡がたくさん残されています」と語る。そこで斎藤さんにコーディネートと東北の取材同行をお願いし、北上川流域における中世と近世、二つの時代にまたがる陶器の流れを追うことにした。
-

-
東北学院大学経営学部 教授
斎藤 善之(さいとう よしゆき)さん -
1958年栃木県生まれ。1981年宇都宮大学教育学部卒業。1987年早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学、1995年「内海船と幕藩制市場の解体」で早大博士(文学)。日本福祉大学知多半島総合研究所嘱託研究員などを経て現職。専門は日本近世史、海運港湾史。主な著書に、『海の道、川の道』(山川出版社 2003)、『日本の時代史17近代の胎動』(吉川弘文館 2003、共著)など。
平泉で大量消費された中世の常滑焼と渥美焼
東北地方最大の河川、北上川。はるか昔より悠々と流れるこの大河は水上の道として利用されてきた。12世紀(平安時代末期)、北上川中流の平泉を拠点に東北地方を掌握していた奥州藤原氏は、太平洋の海運と北上川の水運を活かして遠隔地と結びつくことで、その繁栄を築いたといわれている。
その証拠の一つが、平泉の遺跡群から発見される東海産の常滑焼や渥美焼の出土品だ。この時代、重くて壊れやすい陶器を900kmも離れた東海から東北まで大量に陸上輸送することは不可能だった。これらは船で太平洋を渡り、さらに北上川を遡って平泉にもたらされたと考えられている。
斎藤さんから「中世の常滑焼と渥美焼に詳しい人」と紹介されたのが愛知学院大学非常勤講師の中野晴久さん。編集部は、知多古窯(こよう)址群の一つ「大池古窯」で中野さんのレクチャーを受けた。
中野さんは「中世において、常滑焼と渥美焼は大甕(かめ)や壺をつくる技術で他の窯業地を一歩リードしていました」と話す。
常滑焼は平泉の隆盛と同じ12世紀初め、愛知県知多半島の穴窯(あながま)で製造されるようになった。半島全体が粘土や砂の堆積した地層で、非常に掘りやすく、窯をつくるのに適した地盤だった。そのため、常滑を中心に3000基を超える穴窯が次々とつくられた。これは同時代の窯業地と比べても圧倒的な数だ。
「常滑焼に使われる土は、粘度が高く低温で焼き締められることから、大きくて堅牢な甕を安定的につくることができました。もう一つ革新的だったのは、焼締めの甕を赤色に焼きあげる技術を手に入れたことです」と中野さんは言う。
それまでの甕は、灰色や黒っぽいものばかりだった。常滑焼の工人たちは、窯内の空気の流れをコントロールすることで表面を酸化させて「赤く」焼きあげることに成功し、実用性、デザイン性ともに優れた常滑焼が全国に流通するようになる。
一方、知多半島に向き合うように延びる渥美半島でも、同じ時期に窯業が盛んになったが、常滑ほどいい土に恵まれず大量生産はできなかった。代わりに蓮弁文(れんべんもん)や袈裟襷文(けさだすきもん)など、ほかにはない文様の壺が生み出され、評価されるようになる。
「常滑焼は既製品、渥美焼はオーダーメイドというイメージです」と中野さん。国産の陶器では時代の先端をいく高級品として需要が高く、なかでも圧倒的な消費地が平泉だった。
武士の台頭で陶器が必要に
なぜ平泉で常滑焼、渥美焼が大量に消費されたのか。斎藤さんの紹介で平泉町まちづくり推進課の八重樫忠郎(ただお)さんにお会いした。
八重樫さんによると、その背景には、武家と酒の密接な関係があったという。12世紀は、武士が勃興した時代だ。武家にとって酒宴は政治的な場として重要だった。酒の席で序列を決め、主従関係を明確にし、強い武家が権勢を拡大していった。
酒宴が行なわれていたことを裏づけるのが、平泉各所で発掘される「かわらけ」という小さい素焼きの器。武士の酒席では、かわらけを使い捨ての杯として使うのが習わしだった。平泉の柳之御所遺跡(やなぎのごしょいせき)では、10トン以上のかわらけが山積みで発見されたという。いかに酒宴が多かったかが窺える。
酒は武家に欠かせないとすれば、屋敷で大量の酒を貯蔵あるいは製造していたことは想像に難くない。貯蔵容器となる大甕や、酒を注ぎ分ける際に使う甕・壺として常滑焼・渥美焼が重用された。立派な壺や甕でふんだんに酒を振る舞うことが、武家の権威の象徴となった。
奥州藤原氏が展開したダイナミックな海運交易
常滑焼・渥美焼は、どのように平泉まで運ばれたのだろうか。
斎藤さんは「太平洋側は強い海流や季節風などの影響で難所が多いため、日本海のような船による交易はなかったと考えられていました。ところがその説を覆し太平洋側にも海上交通の道があったことを立証したのが平泉の常滑焼や渥美焼の大甕でした。そして房総半島の外側を回るルートもあったと考えられるようになりました」と言う。
八重樫さんは「中世の海運交易の全容をつかむのは難しいですが、近年の研究では、かなり広いエリアだったことがわかってきました」と語る。
例えば中尊寺金色堂の螺鈿(らでん)細工に使われている夜光貝(やこうがい)は、奄美大島から平泉に運ばれたというのが今の定説だ。また金色堂の高欄(手すり)の部分は東南アジア産の紫檀(したん)でできている。中国からの壺や経典(きょうてん)なども多数ある。12世紀の平泉は、豊富に採れる砂金や材木を武器に、東シナ海まで商圏を広げていたようだ。
「10世紀の『新猿楽記』という書物を見ると、金儲けのために全国を飛び回る自由な商人がすでにいたようです。もしかしたら12世紀には、私たちが想像するよりずっとダイナミックな交易ルートが確立していたのかもしれません」(八重樫さん)
柳之御所遺跡の見学を終え、近くのバイパスから周辺を眺めた。御所の方向に広がる土地に、一段低い段差のようなものがある。八重樫さんから北上川に開かれた湊の跡だと教えられた場所だ。
斎藤さんは「ここは北上川に注ぐ支流が合流する地点で、入江になっていたようです。そこに北上川からの船を碇泊させて荷を揚げおろししたのでしょう。しかも柳之御所遺跡もすぐ近くです。河口からはおよそ80kmの地点ですが、北上川は河床勾配がゆるいため、海抜は20mほどしか上がっていません。日本の川にしてはゆるやかで舟運には向いていたのです」という。
陶器がつないだ石巻と東海の縁
1984年(昭和59)、旧北上川の支流・真野川の上流にある石巻市水沼地区で3基の窯跡が発見された。水沼古窯と呼ばれるこの窯跡は、12世紀前半、まさに平泉が常滑焼や渥美焼を東海から取り寄せはじめたころにつくられたものだった。八重樫さんによると、平泉の史跡からは水沼の窯で焼いた陶器も発見されていて、そこには渥美焼特有の袈裟襷文の文様まで施されていたそうだ。
奥州藤原氏はこうした優れた陶器を自分たちの手で生産したいと考えたのだろう。渥美焼の工人を石巻近郊の水沼地区に住まわせて、そこに窯をつくらせた。しかし水沼窯はわずか30〜40年で操業を停止してしまう。その理由について、八重樫さんは水沼の粘土が愛知県ほど焼き物に適していなかったことを指摘する。
「興味深いのは、水沼に来た渥美の工人らの子孫がこの地に定住したことで、その後も東海と石巻との文化的なつながりが長く続いたことです」と斎藤さん。
その足で水沼地区にある古刹、亀向山龍泉院(きこうさんりゅうせんいん)を訪ねた。
龍泉院は知多半島の内海(うつみ)にある性海寺(しょうかいじ)の末寺とされる。16世紀半ば、性海寺の和尚、天以乾斎(てんいかんさい)が奥州に向かい水沼に至ったときに迎えた水沼の有力者、亀山伊勢(かめやまいせ)が自分の山荘を与えて寺とした。それが龍泉院の創始と伝わる。
斎藤さんは「天以乾斎和尚が水沼を最終目的地としたのは偶然ではなかったのではないかと思います。亀山伊勢という名前にも伊勢湾、つまり東海との関係を感じずにはいられません」と語った。この地域に尾張姓や内海姓が多いとされるのも渥美の工人が移り住んだ名残だろうか。
「石巻では東海地方ゆかりの姓をもつ人が多いのです。そのなかには事業欲が旺盛な方たちも多くいました。後に北上川に内海橋をかけた水沼の豪農で酒造家でもあった内海五郎兵衛もその一人です」(斎藤さん)。
住職の泉孝雄(こうゆう)さんも「昔の人は『お寺を見るなら松島の瑞巌寺か龍泉院だ』とよく言っていましたね。それほど由緒ある名刹として親しまれていたのです」と話してくれた。
龍泉院には江戸時代につくられた常滑焼と伝わる大壺が今も大事に保管されている。平安時代末期の奥州藤原氏滅亡とともに平泉への常滑焼・渥美焼の流通は終わったが、尾張と石巻の結び付きまで途絶えたわけではなかったようだ。水沼地区の繁栄が、遠い東海地方とのつながりによって、もたらされていたことが見えてきたように思われた。
水運と陶器を追って石巻・登米を歩く
江戸時代になると、石巻は北上川の水運の基点として、奥州随一の湊と称されるほどの繁栄を見せた。仙台藩から江戸に納められる御穀米は、最盛期には30万石にも及び、江戸で消費される米の量の3分の1にも達したという。これらの米は、一関(いちのせき)や登米(とめ)から石巻港を経由して、弁才船で江戸まで運ばれた。そのため東北に入る陶磁器類は、帰り荷として江戸で仕入れられるものが主流となった。
斎藤さんの案内で、江戸時代の陶器の流通の痕跡を追った。
石巻の廻船主「武山家」
江戸から明治期にかけて廻船主として栄えた武山家を継いだ本間英一さんは、「石巻千石船の会」の事務局長も務めている。本間さんと斎藤さんは、武山家に残る『武山六右衛門家文書』を数年かけて解読し、一冊の本にまとめた。そこには千石船の積み荷の受領証や領収証なども含まれており、当時の流通を知る貴重な資料だ。これを見ると、たしかに江戸の商人から土瓶や茶碗などを仕入れていたことが記録されていた。
本間家(旧武山家)の土蔵に保管されている、貴重な古文書の原本も見せていただいた。
登米の廻船問屋「菅勧」
北上川の舟運の発展に伴い、河口の石巻と上流の盛岡周辺を結ぶ中間点として栄えたのが登米の湊だ。「河岸(かし)文化がよく残っているのです」と斎藤さんが言うように、登米は北上川の街道に沿ってつくられた武家町だ。今は堤防が高く川面が見えないが、かつては目の前に川岸が広がり、上りの舟と下りの舟が荷を積み替えていたはず。相当な賑わいだったに違いない。
「廻船問屋 菅勧(かんかん)資料館」は、館長の菅野(かんの)紀男さんと兄の芳郎(よしろう)さんが運営しており、土・日曜日を中心に開館する町屋ミュージアムだ。陶器や漆器、当時の帳簿など、往時の廻船問屋の商いや登米の文化の記録がそのままに残されている。
「これだけの資料が残っているのは貴重だ」と斎藤さんは言う。
石巻の陶器店「尾張屋」
石巻には老舗の陶器店が多い。「尾張屋」もその一つ。この地で古くから営業していた陶器店を、近藤良一社長の祖父母が買い取って今日に至る。店名の由来はわからないが、尾張と所縁がある可能性は高い。
近藤さんが物心ついたころには、すでに鉄道が走り、駅から店までの運搬は荷車だった。しかし、かつて店の前が運河だったことを近藤さんは知っている。「50〜60年前、周囲の道路を舗装するために掘り返したら、堀に使われていた厚い木の板が腐らずに出てきたのです。みんな驚いていましたよ」と語る。
東日本大震災のあと、店をたたむつもりだった。「でもね、少し生活が落ち着くと、茶碗でご飯を食べたい、湯呑みでお茶が飲みたいと思うんです。そうか、みんな同じ気持ちに違いない――そう考えて再び店を開けました」(近藤さん)。
石巻の陶器店・美術館「観慶丸本店」
最後に訪れたのは観慶丸本店。この店の創業者、初代須田幸助は、先に紹介した武山家の船「観慶丸」の沖船頭(雇われ船長)だった。江戸時代、千石船の船頭は船主からも一目置かれる存在で、江戸からの帰りの積み荷は船頭の裁量に任されていた。そこで目利きをして陶器を仕入れ、後に陶器店として独立したという。
ある時、観慶丸が米を運んで江戸に入船しようとしたところ、江戸の問屋街が全焼する大火災があった。船頭の須田幸助は積み荷の米50俵を速やかに下ろしすべて提供した。そのお礼として江戸から数年後に贈られたという布袋(ほてい)像が展示してある。現社長の須田佑(たすく)さんは言う。
「正確な年代はわかりませんが、かなり立派な品物なので特注品だと思います。感謝の気持ちを伝えるために問屋街の人たちがお金を出し合って、瀬戸あたりに注文したのでしょう。とてもいいお顔をされている。この布袋様は当家の宝です」
奥州と東海。遠く離れたこの二つの地域は、12世紀から陶器が縁でつながっていた。江戸の商人・河村瑞賢が幕府の命を受けて東廻り海運を成功させたのが1670年代。それよりもはるか昔から太平洋を行き来し、常滑焼・渥美焼、さらに工人や技術も導入しようと試みていたのだ。スケールの大きな交易と当時の人々の実行力に、圧倒される思いがした。
(2016年7月27~28日、8月29日取材)