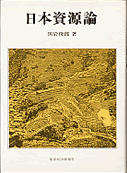機関誌『水の文化』17号
雨はどこへいくのか
-
編集部
比喩としての雨と循環
大江健三郎の小説に『「雨の木」を聴く女たち』がある。
「『雨の木』というのは、夜なかに驟雨があると、翌日は昼すぎまでその茂りの全体から滴をしたたらせて、雨を降らせるようだから。他の木はすぐ乾いてしまうのに、指の腹くらいの小さな葉をびっしりとつけているので、その葉に水滴をためこんでいられるのよ。頭がいい木でしょう」
と登場人物は説明する。雨の木が喚起する、命を与える宇宙のイメージをもとにした小説である。
昔も今も、雨は当然のように降り、空気のように意識させないが、無いと困る存在だ。にもかかわらず、雨にはいろいろな想像を喚起させる力がある。
雨は「恵み」であると同時に、災害を引き起こす「恐怖」の源であり、日常と非日常を区切る出来事でもある。これだけ技術が進んだと自負している現代人でも降雨は完全には予想できないし、降水量も思いどおりに制御できない。しかし「やまない雨はない」というとおり、放っておいてもやってくる「繰り返し」、「再生」の予感と期待があることも示している。
さらに想像を逞しくすれば、雨に濡れた髪は「艶っぽく」なり、登場人物がずぶぬれになれば、その場面は「緊迫」する。映画監督・成瀬己喜男は男と女の「やるせなさ」を描き、「やるせなきお」と呼ばれた手練であったが、成瀬にとって、雨は効果的な小道具だった。
倉嶋厚監修『雨のことば辞典』(講談社、2000)や、高橋順子・佐藤秀明『雨の名前』(小学館、2001)には雨の言葉・雨の比喩が多数掲載されているが、古今の庶民が雨にさまざまなイメージを託し、世界を理解してきたことがよくわかる。
その底にあるのは、雨は放っておいても降り、止む。そして雨には、人間の手が及ばないところにある、という畏敬の念があるように感じる。
健全な水循環?
この多様なイメージを持った雨も、単なる水の粒と捉えると「水循環の一つのステップ」となり、かつて理科の教科書で習ったことが思い起こされる。
ところが、この「水循環」という言葉が確立したのはそんなに古いことではないらしい。ビスワス『水の文化史』(文一総合出版、1979)によると、ヨーロッパの水文学の歴史では、雨よりも、泉や川がどこから生まれるかということが論争の的だったことがわかる。
レオナルド・ダ・ヴィンチは「川の水の源は海から地球の割れ目を通って山頂に上がってくる水と雨の両方である」と考えていた。しかし、一方で、ダ・ヴィンチは水が循環するというイメージも持っていた。彼は水循環の先駆的なイメージの発見者であった。
その後、この「水が循環する」というイメージは、雨量の測定、蒸発量の測定、さらには川の流量と流出係数と日最大降雨量と流域面積の関係を数式として定めるなどの作業が行われ、19世紀になると単なるイメージから科学的知識に変わり、確固とした常識となっていく。つまり、雨が水循環の一部分であることが科学的常識となったのは19世紀であり、水が地球をめぐるという比喩が、裏付けをもって使われるようになるのはそれほど古いことではないのだ。
この水循環という言葉が、さらに「健全な」という形容詞をつけて語られるようになったのは、もっと新しい。日本でそのような使い方がされてくるのは1980年代からで、ソーラーシステム研究グループが1982年(昭和57)に使った「都市の水循環」という言葉はきわめて早い例である。どのような条件が満たされると、水循環は健全なのだろうか。
高橋裕・河田恵昭編『水循環と流域環境』(岩波書店、1998)によると、「健全」とは
- 人間にとって安全にして快適であること、すわなち、洪水氾濫を押さえ、飲用、農業、工業用水などの水利用を適度に充たし、潤いと安らぎを与え、すぐれた河川湖沼景観を提示することなど。
- 自然の本来の水循環への復元、すなわち、開発などによって変化してしまった水循環を少しでも修復して本来の水循環へと近づけること。
- 多様な生物群との共生、本来それぞれの地域ごとに生育されていた生態系を維持できる流量、水質、河床や護岸、水辺などの連続性の確保。
- 持続的発展を保証できること。
という4つの条件を挙げている。
一読してわかるように、ここで「健全な」とは、暮らしを守ることと、生態系を含めた自然とを調和させることにあり、もしそれがうまくいけば、将来世代の選択を束縛しないという持続的発展が可能になるという意味で使われている。
1980年代に入り、水循環は「意識しないと守れない」もの、そして望ましさの尺度として通用する「社会的水循環」に変貌する のである。
人工的な環境で暮らすための術(すべ)が必要に
健全な水循環が意識されるようになった背景には、水循環が途切れることで発生するマイナス面が、誰の目にも明らかになってきたことが挙げられる。どこもかしこも舗装してしまう都市化による不浸透域の拡大、生活・工業廃水の汚染、水需要の増大、地球温暖化などの気候変動への危機感、等々が水循環を途切れさせる要因であり、誘因でもある。これらは1980年代に入って、社会的に意識されるようになった。また、地球温暖化についての初めての世界会議がオーストリアのフィラハで開催されたのが1985年(昭和60)。最近ではヒートアイランドという呼び名も現れ、言葉を追うだけで、社会で何が問題とされているのかがよくわかる。
さらに突っ込んで言えば、1980年代は、汚染者を一義的に特定すれば解決できるという「公害」問題ではなく、暮らしのさまざまな要因が複雑に関連している「環境」問題として捉えようという気持ちが生まれてきた時期だった。それは、汚染の原因と結果が矢印ですぐに結びつくという単純な世界から、多様な要因が絡み合った円環の中で、意図せざる結果が自分に降りかかってくるかもしれない(あるいは自分が意図せざる加害者になるかもしれない)という複雑な世界で暮らさざるをえない、という環境保全思想の転換でもあった。
「健全な水循環」などという皮肉な表現が生まれてまだ四半世紀しかたっていないにもかかわらず、現代の私たちは、このような厄介で難しい条件下で、健全な水循環を人為的に支えてやらねばならないという大きな課題を抱えることになっている。
当たり前の雨水が資源に
この変化の波をまともに被ったのが、雨のイメージだ。冒頭に記したように、日本には全国各地に多様で多くの雨の言葉がある。しかも、それは共通語で使われた言葉もあれば、その土地だけで使われた言葉もあった。それは、その土地だけに通用する知恵と情報を濃厚に表している。
だからこそ、和辻哲郎などは雨の文化論といってもよいその著作『風土』で、湿潤―乾燥という軸から日本人を論じ、その特徴を受忍的性格と描いた。恵みの雨は当たり前のもので、くよくよ考えても仕方がないものらしい。
ところが、「健全な水循環」という視点で雨を眺めると、雨は特別なもののように思えてくる。酸性雨、ヒートアイランド、天気の変化、こうした子供のころには体験しなかった大規模な自然環境の変化を雨は知らせてくれる。
そして一人一人にとって、ひいてはある地域に住む人々にとって大事な資源と捉えられた雨水は、利用が奨められるようになった。不浸透域の拡大によって生じた都市型洪水の観点から見れば、雨水利用は排水をいっきに増やさないで備蓄するという形で、都市型洪水防止に貢献していることになる。
雨水は、なりゆきの自然から、意図して守らねばならない大事な資源となってきているのである。しかしここで分けて考えなければならないのは、「雨」と「雨水」だ。雨は屋根なり地面なりに接した瞬間に雨水になって、資源として把握される。我々は、雨水を資源として捉え始めたが、雨はまそうではない。
求められる水資源観の転換
一方、水は資源といわれる。資源とは、生産活動や利用の源となるモノや情報という意味で、水や鉱物や石油などの物質や、食料、さらには最近では人でさえも資源と呼ばれたりする。資源は、そこに利用が想定されてはじめて資源になる。
「水の資源としての特徴は、 1. 生物の生存と成長に不可欠である、2. 自然に循環する、ことが挙げられる。それゆえ 3. エネルギー資源の基本的な特徴が転換であるのに対し、水資源の場合は時間的・空間的な調整が必要な資源である」等と述べているのが黒岩俊郎の『日本資源論』(東洋経済新報社、1982)だ。
私たちは雨からもたらされた水を貯水、治水、浄水などさまざまな技術を用いて利用している。
枯渇はしないが、不確実で不安定。これが水資源の一つの特徴だ。枯渇する石油、石炭などの資源は、枯渇するまでの時間を遅らせるために、節約と効率化につとめることが利用者の関心事となる。
また、食料となる資源も、再生可能なレベルを常に見定めながら、節約して効率的に使うことに利用者は骨を折る。節約と効率が促される裏には、それら資源に所有権や利用権などの、何らかの財産権がほぼ例外なく設定されているという事情もある。
ところが、1980年代から、水については、枯渇や再生だけではなく、きちんと循環させることが重要であるということが、切迫して言われ出した。節約と効率だけではなく、意識的に水の流れを断ち切らないことが求められるというわけだ。一ヶ所が切れたら通話できなくなってしまうというような昔の電話ではなく、どこかが切れてもどこかはつながっているというインターネットのような水の循環経路の多様性を人為的につくることが求められるようになったわけである。
利用する側の思いを超えて
雨水は、川の水や森林や貯水池、用水など、地表に達し誰かの入れ物に入ると誰かのものになり大事にされるのだが、雨そのものは「みんなのものであるが、誰のものでもない」
雨そのものを資源と見なすことの是非は大事な論点で、広い議論をしていかねばならないが、資源だからといって石油などの地下埋蔵物のように財産権を設定するわけにもいかないだろう。極端な話、雨が稀少なものになったとき、現行民法では土地所有権は上下に及ぶからと「私の敷地の上空と落ちた雨と地下にしみ込んだ雨は私のもの」と言い出す人が出てくるのだろうか。それとも、これは公水ということになるのだろうか。そんなことはあるまい。
雨そのものを資源と考えるならば、雨はみんなのものであるが、誰のものでもない。
一つのたとえ話だが、私たちは電話や通信手段を「ユニバーサルサービス」と捉えている。林紘一郎・田川義博『ユニバーサル・サービス〜マルチメディア時代の「公正」理念〜』(中央公論社、1994)では、OECDが定めたユニバーサルサービスの定義に含まれる4要素を紹介している。
- 全国どこに住んでいても電話を利用できること
- 誰でも経済的に電話を利用できること
- 均質サービスが受けられること
- 料金について差別的取り扱いがないこと。
これらの「電話」を「雨」に置き換えると、そっくり「雨のユニバーサル・サービス」となる。これもなかなかおもしろい雨の比喩である。雨を社会的に受け止めていくには、このような考え方を設定することも大いに参考になるのではないだろうか。「雨は自然に降ってくる」と自然に甘えては、龍神様に申し訳ない。
とはいえ、雨は昔から変わらず降り続けている。
電話システムは、人間が日頃から意識してメンテナンスしないと維持できないユニバーサルサービスである。意識しないと循環が分断される雨資源を、あえて同じような「人為的な仕組み」と考えてみたらどうだろう。
もしかしたら案に相違して、私たちは今よりも雨を大事にし、雨を真剣に受け止めるようになるかもしれない。「存在は意識しないが、無くなると困る」という従来の日本人の雨への感覚と、「みんなのものだが、誰のものでもない」という雨への資源観は対照的だ。
雨資源の言葉
このような資源観を育てるためには、雨資源の文化が不可欠だ。雨とつきあっていくためのスタイルと、それを可能にする社会の仕組みといってもよい。そこで言葉が思想を象徴し、牽引役を務めることは明白である。
ソーラーシステム研究グループが都市の水循環という考え方を世に問うたとき、「個人下水道」という言葉を象徴に据えた慧眼は驚くべきことだ。自分の世帯で排出する水は自分の世帯で処理するという考え方は、当時はなかった。現代でさえ、一般的に認識されているところには、まだ至ってはいない。言葉もなかった概念を広く示すには、まず言葉をつくることが必要なのだ。
例えば、自分の地所に降った雨を土に戻すことを「雨戻し」と呼び、その意味は「ともに暮らすために、当たり前の義務を果たすこと」、などと辞書にでも載るようになれば最高だ。人間というものは、結局は言葉で考え、言葉で文化を構築するからだ。もちろん伝達手段も言葉。そして、言葉は慣習を補強し、明文化された法律を補完していくだろう。
豊かに暮らすための雨資源の文化開発
言葉の次は、具体的な行動だ。例えば、自分で観天望気というのも、雨の文化をつくる一助になるのではないか。天気予報に頼り切らずに、自分で雨の兆しを感じてみる。
風呂や洗濯、トイレなどで雨水を利用するのは当たり前。
ガーデニングが流行る中、ぬかるむのを嫌い、庭をタイルなどで固めたりすることもあるようだが、むしろ土いじりを楽しむというのも一つのスタイルだろう。
歩道は石畳や透水性舗装。透水性舗装では車の重量を支えられないというのならば、いっそのこと都心部は車が入らないようにパーク・アンド・ライド方式を採用して、中心部へはおしゃれな路面電車(LRT)を利用するというのも一つの手だろう。ヨーロッパの都市では、いくつものケースが実現している。
また、現在水道料金の中に含まれ一括徴収されている下水道料金は、個別に徴収し、利用者が負担しているコストを認識できるようにするのもよい。
生活用に井戸を掘るのを支援したり、公園や広場の雨水タンクを増やしコミュニティで雨水を利用するという発想もいいだろう。
このように雨を「循環する資源」、「みんなのものだが、誰のものでもない資源」と捉え直すことで、私たちのライフスタイルが変わることを容易に想像することができる。
「資源」という言葉の裏に、利用する側からだけの都合を感じとる人もいるかもしれない。しかしもっと多面的、積極的に資源を見直したときに、利用することで新たな価値感が生まれ、より良好な関係が結べるのではないか。雨が私たちの暮らしにとって重要な資源となってきていることは、紛れもない事実だ。そして今「資源と財産権は一体である」という疑いもしなかった前提をひっくり返して、再検討することも必要なのではないか。近代の日本人は、財産権が設定されていない資源を社会で守るという経験を、ほとんど持ってこなかった。捉え難い雨をケーススタディとして、新たな性質の資源を新たなスタイルで守る出発点になるのではないだろうか。