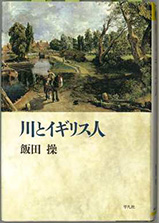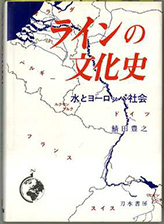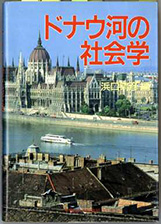機関誌『水の文化』19号
《西ヨーロッパ》
-

-
水・河川・湖沼関係文献研究会
古賀 邦雄 (こが くにお)さん -
1967(昭和42)年西南学院大学卒業、水資源開発公団(現・独立行政法 人水資源機構)に入社。30年間にわたり水・河川・湖沼関係文献を収集。 2001年退職し現在、日本河川開発調査会、筑後川水問題研究会に所属。
皇太子は1983年(昭和58)6月から1985年(昭和60)10月まで、オックスフォード大学に留学された。
研究テーマは「十八世紀におけるテムズ川の水運について」である。テムズ川はイングランド西南部グロースター州の丘陵地テムズヘッドに源を発し、河口域ロンドンまで約340kmである。徳仁親王著『テムズとともに』(学習院総務部 1993)の書で、水運の変遷を六つの時期に分けて描いている。(1)中世:河川は生活の場として漁民の簗、製粉業者の水車の利用(2)13世紀:製粉業者の対立が起こり、フラッシュ・ロックにより堰で船が通過できる移動式水門の設置(3)17〜18世紀:パウンド・ロックの設置で仕切り板の開閉によって船を通過。テムズ・ナヴィゲーション委員会は、河川改修を行ない、工事費は石炭の通行料を当てた。このころモルトが上流からロンドンに運ばれた。(4)18世紀末:石炭、染料、石材、みょうばん、ワイン、植民地産の砂糖、タバコ、米、茶等35種類以上の物資が輸送された。(5)19世紀:石炭が鉄道運送へ、さらにトラック貨物運送が主となり、水運は衰退。(6)現在:川はレクリエーションとして利用されることとなったと論じている。
ガヴィン・ウェイトマン著『テムズ河物語』(東洋書林 1996)は、テムズ川河口域ロンドン川の水運の盛衰を首都ロンドンの発展とともに描く。他にも、相原幸一著『テムズ河』(研究社 1989)、岩崎広平著『テムズ河ものがたり』(晶文社 1994)がある。
飯田操著『川とイギリス人』(平凡社 2000)は、川を動力、輸送手段、上下水道、レクリエーションの場として捉えている。同著『釣りとイギリス人』(平凡社 1995)、岡本誠著『テムズ川ウォーキング』(春風社 2004)を読むと、英国人はゆったりと水辺に身をゆだねているようだ。
1990年(平成2)11月建設省は、生物にやさしい川づくりの発想を持った「多自然型川づくり実施要領」の通達を施行した。いわゆる近自然河川工法、ビオトープ河川工法と呼ばれる。この工法の先進地ヨーロッパの川への視察が一時ブームとなった。新見幾男著『ヨーロッパ近自然紀行』(風媒社 1994)は、ライン川を下りながらスイス、ドイツの川づくりを訪ねている。チューリヒの路面電車線路敷、中空ブロックに土と草を詰め、雨水の地下浸透を図る。魚の生息環境を重視し、岸辺の直線化を回避。川には直線はない、自由にさせる思想が根付いている。2億円以上のプロジェクトは住民投票で決定したり、驚いたことは、釣り師は生物学や川の諸規則の試験に合格し、ライセンスを取らねばならない等の事例が紹介されている。
佐々木寧、中村幸人著『河を以って河を制す』(生態環境計画学会 1996)、バイエルン州内務省建設局著『河川と小川』(西日本科学技術研究所 1992)、ドイツ国土研究会訳『道と小川のビオトープづくり』(集文社 1993)は、川づくりに多くの示唆を与えてくれる。
保屋野初子著『川とヨーロッパ−河川再自然化という思想』(築地書館 2003)は、河川機能における再生を追求する。オランダはハーリングフリート河口堰の水門を開け生態系を回復させ、オーストリアは一万haに及ぶ「ドナウ河氾濫原国立公園」をつくり、河川を自由に氾濫させて、浸食、堆積、地下水、植生の変化からドナウ川の自浄作用の回復を行なうという。
このような自然保護を第一とする考え方は水法にみることができる。日本生態系協会編・発行『ドイツの水法と自然保護』(1996)によると、「河川、湖沼は生態系の構成要素であり、公共の福祉及び将来の子ども達のために近自然的条件に、すなわち生態学的に機能する状態に、可能な限り戻していかなければならない」(ドイツの連邦水収支法)と規定されている。
水法については、建設省内水法研究グループ訳『世界の水法−ヨーロッパ編』(ぎょうせい 1982)は、ベルギー、イギリス、フランス、イスラエル、イタリア、スペイン、トルコの水法が研究され、三本木健治著『比較水法論集』(水利科学研究所 1983)、同著『論集 水と社会と環境』(山海堂 1988)も特筆される水法の書である。
続いて、秋山紀一他著『川と文化』(玉川大学出版部 2004)は、ライン川、フランスの川、スペインの川を概観しているが、少なからずこれらの川はローマ帝国の文化の影響を受けている。 著『ラインの文化史』(刀水書房 1995)は、ライン川流域のスイス、オーストリア、リヒテンシュタイン、フランス、ドイツ、オランダの六カ国の歴史と文化を縦軸とし、水運をはじめ、水力(原子力)発電、上下水、漁業、憩いの場、祭礼などのライン川の機能を横軸として、あらゆる視点から論じ興味深い。
残念なことだが、1986(昭和61)年11月1日スイス・シュヴァイツアーノルのサンド薬品(株)の倉庫から出火、大量の殺虫剤や農薬がライン川に流れ込んだ。この事故について、石黒一憲著『国境を越える環境汚染』(木鐸社 1991)は、国際私法の立場から考察している。このとき、最下流のオランダは汚染水が自国の内水への流入を防ぐため、水門を開け北海へ放流する懸命な努力がなされた。
デルタ地帯のオランダは昔から水は敵であるが、同時に水は友であるという共存の思想を貫いてきた。平沢一郎著『オランダ水辺紀行』(東京書籍 1995)に、水上生活者の夫婦、ハウスボートの家族、冬は凍結の運河でのスケート大会等、水との共存を描き出す。ライン川については、小塩節著『ライン河の文化史』(東洋経済新報社 1982)、笹本駿二著『ライン河物語』(岩波新書 1974)、加藤雅彦著『ライン河』(岩波新書 1999)、浅井治海著『昔話でつづるライン川の旅』(近代文芸社 1999)の書がある。
ドナウ川は、ドイツの黒い森を源とし、オーストリア、スロヴァキア、ハンガリー、ブルガリア、ルーマニア、ウクライナを流れ、黒海に注ぐ約2900kmの国際河川である。中村光夫著『ドナウ紀行』(日本交通公社 1978)、加藤雅彦著『ドナウ河紀行』(岩波新書 1991)、浜口晴彦編『ドナウ河の社会学』(早稲田大学出版部 1997)が出版されている。1992年(平成4)ドイツのケルムハイムでドナウ川支流アルトミュール川から、フランクフルトを経てライン川と運河で結ばれた結果、北海と黒海がつながり、総延長3500kmが開通した。EUヨーロッパ共同体に果たす役割は大きい。
セーヌ川は首都パリと切っても切れない都市河川である。渡辺淳著『パリの橋』(丸善 2004)、泉満明著『橋を楽しむパリ』(丸善 1997)、坂田正次著『パリセーヌ河紀行』(神田川文庫 2001)、津田英作写真集『ラ・セーヌ 川辺の肖像』(明窓出版 2002)の書をひもとけば、シャンソンが聞こえてくるようだ。
医と病を主たる研究対象とするアナール派歴史学者ジャン=ピエール・グベール著『水の征服』(パピルス 1991)は、今日、衛生的な水が多量に供給されるようになったが、その水の征服がなされた過程を追求する。いまだ、清浄な水を確保できない国々も多い。このことは「世界水フォーラム」における課題の一つになっており、早急に克服せねばならない。
ヨーロッパの上下水道の発達については、今井宏著訳『古代のローマ水道』(原書房 1987)、鯖田豊之著『都市はいかにつくられたか』(朝日新聞社 1988)がある。西欧工業化と水力利用に関するT・S・レイノルズ著『水車の歴史』(平凡社 1989)は、動力エネルギーの水車がヨーロッパの近代化に果たした役割を論じている。