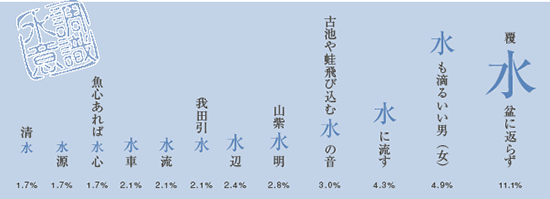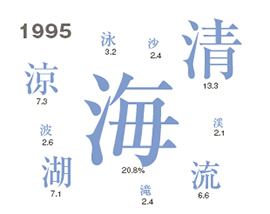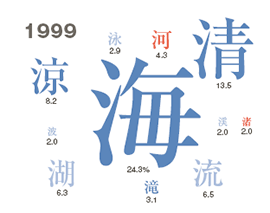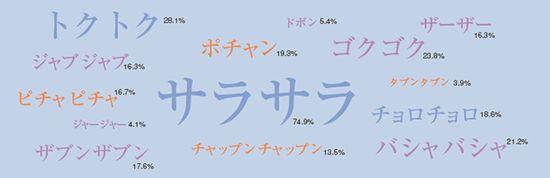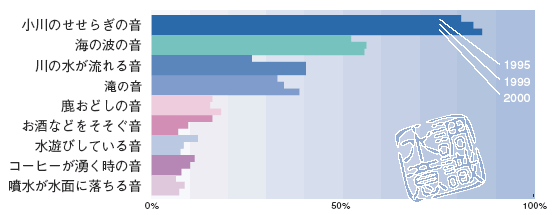機関誌『水の文化』27号
水への畏れや礼節を超える遊びの文化
愛でる楽しむ華やぐ

普段、何気なく接している水。豊かなで安全な水に恵まれている今の日本では、水に込められた深い意味を忘れがちだ。「水にかかわる生活意識調査」で浮き彫りになった水への思いを、鳥越皓之さんに民俗学の視点から読み解いていただいた。水とのかかわりが、私たちの精神の礎となっていると気づくことで、新たな価値観の創造につながるかもしれない。
-

-
文学博士 早稲田大学人間科学学術院教授
鳥越 皓之 (とりごえ ひろゆき)さん -
1969年東京教育大学文学部史学科(民俗学)卒業、1975年東京教育大学大学院文学研究科社会学専攻博士課程単位取得満期退学。関西学院大学社会学部教授、筑波大学大学院人文社会科学研究科教授を経て、2005年4月から現職。 専門は社会学、民俗学、環境問題、地域計画。主な著書に『水と人の環境史ー増補版』(編著御茶の水書房1991)、『柳田民俗学のフィロソフィー』(東京大学出版会2002)、『花をたずねて吉野山』(集英社新書2003)、『環境社会学』(東大出版会2004)ほか。
甜(あま)い水
日本には「旨い水」、中国でいうところの「甜(あま)い水」という発想があります。これは、考えてみると大変贅沢な話ですね。私たちは、水が豊かなだけではなく、旨い水が飲める民族だということです。
水の利用の第一は、なんといっても「飲む」ことです。
「仏様(神様)の水はどの井戸から汲みますか?」と聞くと、村で一番古い井戸がどこかがわかります。一番神聖な水は神様や仏様に捧げる水で、村の本来の泉、つまり村の発祥のときに中心となった泉から汲むことが多い。それでわかるんです。
日本語で水の出る所を指す言葉には二つあって、どちらも由来は不明ですが、一つは「ヰ」、音で言うと「ウイ」です。宇井さんという名字がありますが、これなんかは本来、井戸さんという意味なんでしょう。ヰケというと溜まっている水を表し、ヰケルという動詞にも変化します。古いワ、ヰ、ヱ、ヲで、W音が入っているのは今は「ワ」しか残っていません。
もう一つは「カー」です。これは勝手な解釈なんですが、湧き出て留まっているのがヰで、カーといったら、湧き出てからこちょこちょ流れている水を指すようなイメージがありますね。
大きな井戸を掘ったり水汲みをしたりしたのは、戸数が大きくなって湧き水だけでは足りなくなったから。その井戸も明治に入る以前は浅井戸です。
江戸時代の大阪では、間違いなく川の水を飲んでいました。大阪では井戸を掘っても良い水が出ず、かえって川の水のほうがおいしかったようです。
中国の北京も同様で、北京の井戸の水は「辛い水」だったといいます。辛い水というのは、どういうのでしょうかね。想像ですが、硬度が高い水をそう呼んだのかもしれません。軟水のほうが柔らかく感じられますから。「うたた水」という言い方で、柔らかくなった水を呼ぶ地方もあります。
しかし旨いのは圧倒的に湧き水。
これは、はっきり言って旨い。筑波山の辺りにも、琵琶湖周辺も、全国に湧き水が多い。イギリスにも、中国にもたくさんあります。
昨年、中国の太湖(たいこ)のほとりの無錫(むしゃく・江蘇省)に行ったんですが、やはり市民は湧き水を飲んでいました。市は水道を使えと言うんですが。
太湖のこの湧き水もやがて埋められてしまいます。政府は、住民たちの生活は見た目に汚いので高層住宅をつくって移住させ、村をなくしてしまうという計画を立てています。100も200もある家屋を全部壊して平らにして、西洋近代的な芝生にするというんです。うまいお茶が淹れられる湧き水を埋めてしまうというんです。残念ですね。
そこでは夕方になると、みんな集まってお喋りしているんですよ。高層住宅に移されたら、このような習慣もなくなりますよね。これは、かつての日本でも行なわれてきた「近代化」ですが、住民は政府には反対もできないといっていました。
洗濯の水
飲む水の次に「洗う」水があります。面白いのは洗濯なんですね。日本の洗濯の仕方は、何度か変遷を経ていますが、基本的に女性が行なうものとされてきました。
川で踏み洗いしているのが、記録に残っているもっとも古いスタイルです。なぜ足で踏んだかというと、そのころの衣服は、苧(からむし)などの固い繊維でできていたからです。
これは有名な話ですが、久米仙人(注1)の伝承に洗濯の仕方が垣間見られる話が出てきます。この伝承も江戸期になると川柳に詠われるようになって、
毛が少し 見えたで 雲を踏み外し 末摘花(すえつむはな)
などというものが残っています。
着物の裾をはしょり上げて、脛を剥き出しにして踏みながら洗う、というスタイルは、男性にとって大変刺激的だったという話です。
韓国は今でも砧(きぬた)で打って洗いますね。日本では、砧が洗濯のときに本当に使われていたかどうか、はっきりしないんですよ。
芭蕉は『野ざらし紀行 七』の中で、
砧打て 我に聞かせよや 坊が妻 松尾芭蕉
と詠っていますが、砧は繊維を光らせる効果も持っているんで、洗濯だったかどうかは明確にはわかっていません。しかし、少なくとも木綿が普及して踏み洗いから手洗いに移行し、もっと最近になればたらいを使い、洗濯板を使うようになり、私たちが経験した風景の記憶にもつながっていく。その後、洗濯機へと変わっていくのが、洗濯の流れです。
(注1)久米仙人
葛城山の麓で生まれ、吉野の竜門ケ岳(りゅうもんがたけ)で修行していたが、ある日空を飛んでいると、吉野川で洗濯をする若い女性の白い脛が見えた。それに目がくらんで神通力をなくして墜落し、俗人に戻り橿原市の久米寺を建てた、という伝説が『今昔物語集』巻十二本朝仏法部に残っている。
用水をすぐに排水にさせないシステム
ものを洗うにもルールがあって汚いもの、たとえば赤ん坊のおしめなんかを洗うときには、下流の人に迷惑がかからないような場所で洗いました。そして、洗った後の最後の排水は田んぼに流していました。
これは、用水をすぐに排水にさせないシステムなんです。無駄に捨てずに、繰り返し使うのです。
私たちは、水を用水−用水−用水−用水− としつこく使っていって最後の最後に排水にしてきました水に対して、そういう伝統を築いてきたんです。
住むのに適さず、畑もつくれない土地、悪水が滞る土地というのは利用価値のない「ダメな空間」ということです。伝統的な用水のシステムは、逆に考えてみれば「ダメな空間」をつくらない知恵でもあった。用水化することで、うまく下流まで持っていって排水にするというのは、用水システムであると同時に排水システムでもあったのです。
水道ができて、手を洗っただけで排水になってしまう今の「用水−排水」システムには、用水−用水−用水−用水− としつこく使ってから排水にしていた緊張感は失われています。
溜める水の文化から流す水の文化へ
実は溜める水は大変大切で、流す水よりずっと重要です。いかに流さないで溜めるか、ということがずっと課題だったからです。水は大切であると同時に半分魔物ですから、洪水の恐れのある水辺近くではなく、ちょっと離れた高い所に住み家をつくっていきました。その結果、水辺から住む所まで水を汲んできて溜めておく必要が生じたのです。
水汲みも、なぜかはわからないのですが女性の仕事です。場合によっては、子供も水汲みをしていました。沖縄の玉造村のフィールドワークで、水辺と村をつなぐ石の階段が、角が丸くなっていて、その労働の過酷さに驚いたことを覚えています。
こうして汲んでこられた水は大変貴重なものですから、必ず溜めて使いました。もちろん地域によっては例外もあったでしょうが、顔を洗うにも野菜を洗うにも、溜め水で洗うというのが基本。ですから、流しながら、ということは考えられないことだったんです。開発途上国では、今でも溜める水を使っています。
溜める水を使っている分には、排水システムはさほど必要ではありません。使用する水量が少ないからです。使った後に植木にやるとか庭に撒くとかすれば、地下浸透も可能です。
また小さな川を村の中まで引いてきて、せき止めて溜め、火災に備えました。防火用水とはいえ、水が溜まっていれば子供たちの遊び場になるし、野菜や果物を浮かべて冷やしたり、小魚が泳げばおかず捕りもしました。水が生活に近くあったということです。
例外的に水が豊富な地域では、トイレは川の上に板を渡して用を足していた。つまり川屋ですね。トイレのことをカワヤと呼ぶようになったことは、不思議なことですね。カワヤは普及していない、珍しい事例だったわけですから。
私は農村でカワヤを見たことがありません。自分より下流の人たちの生活を考えたら、上流で屎尿を流すなんて考えられませんよ。でも、庶民を人間だとは思っていなかった京の貴族階級が、もしかするとやっていたのかもしれません。
日本が近代化の過程で水道を導入したときに、緊急に排水システムが必要になりました。その結果、使った水がすぐに排水になってしまうという、とても不器用な排水システムにしてしまいました。そして、その排水システムは改善されないまま、今に続いています。
しかし、排水というのは住んでいる場所への影響が高い事柄ですから、本来は軽々にシステムを変えてはならなかったと思います。排水というのは使われなくなった水ということで、いわばゴミに変えていることなんですね。
昔、嘉田由紀子さん(現・滋賀県知事)と琵琶湖周辺を調査したときに、溜める水の文化から流す水の文化に、すごい勢いで変わっていくのを目のあたりにしました。溜める水の文化があったから、水を溜める器や工夫があったわけで、そういうものもどんどん失われていっています。
おいしい水を飲むことで、淡水を守る
水の生活意識調査でも、「おいしい水は?」という問いに対して40%の人が湧き水を選んでいます。私も旨い水を飲むためのNPOを立ち上げて、できる限りのことをやっていこうと思います。それは自然を守ること、淡水が守られることにつながるような気がします。アンチ水道化、です。
真面目に取り組もうとしたら、産廃と農薬とゴルフ場と闘わなくてはなりません。これらをストップさせるのは容易なことではないけれど、単なるストップだけじゃなく「おいしい水を飲む」という積極的な目的が大切なんですよ。結果的に反政府運動なんだけど、かわいいですよね、「旨い水を飲む会」だったら。
水の三大要素「姿が見える」「景色」「旨さ」
生活の中の水といったらいいと思いますが、「水は姿が見えるもの」でした。生活の中の水、身近な水だったからこそ「覆水盆に返らず」とか「水も滴るいい男」だとかいった言い回しもアンケート結果に出てきたのだと思います。
もう一つの側面は、身近な水だったから、「景色」としても重要だった。見るという行為を通して、水はきれいなもの、価値のあるものというプラスのニュアンスを育んできました。「好きな水辺」のアンケート結果でも、景色としての水がずいぶん意識されているようです。そういうことからも、景色としての水が私たちの生活の中で大切なものとして存在していたことがわかります。
三つ目には、飲料水としての重要性です。飲む水は「甜い水」として意識されてきました。
水道が日本に敷設された一番の理由は、「衛生」だったと聞いています。しかし水道は、今までの水の使い方を大きく変えてしまいました。水の三大要素を改めて意識してとらえ直してみたときに、水道水というのはこの3つを明確に裏切っています。
そして、この3つを裏切っているだけでなく、セットになって存在していたこの3つを分断してしまった。つまり水の機能の分断です。
もう少し我慢して工夫していけばよかったのに、一気に水道水に切り替えてしまったために、私たちは工夫と文化がない水システムに甘んじているわけです。
しかし、これには絶対に揺り戻しがあると思っています。世界中を水道水にしたら、統計的には淡水がなくなってしまうことはわかっているんです。それなのに、安易に水道化を進めようとしているのは、どうしてなのか。それは、水道水が常に肯定されたイメージを持ち、プラスの価値を持っているからです。
グアテマラにも日本のODAが水道を引きました。水道を引くということは、排水のシステムとセットで考えなければ衛生的に問題が出るかもしれないし、溜める水の伝統も失われてしまう恐れがあります。
そこでは、それまで湖に行って自由に水を汲んでいたのに、水道水しか使えなくなった。でも水道水は、ポンプを使って汲み上げるから料金が高くてお金持ちしか使えません。しかも排水は村に垂れ流されています。だから、反対運動が起こっています。
もちろん水汲みは過酷な労働ですから、女性や子供をそこから解放するという意義は大きい。でも、今のままのやり方は、正しいとは言えません。
民俗学の見地
日本人の自然観には、礼節を重んじるという発想がある。自然保護といっても、単に自然を守ろうという考え方ではないんです。それが西洋のエコロジーとはちょっと違う。だから[山に紅葉や桜を植えるというのは良いこと]であって、自然に対してローインパクトであろう、という発想ではないんですね。「自然保護か自然破壊か」という考えと、別の軸を持っているのです。
こうした感覚が、私たち日本人に独特の水文化を育みました。
民俗学は単に「古い」ものを扱っているわけではなく、普通に思っている世界、ありふれた世界、「日本人は流れている水を見るとなぜ手を洗いたくなるのか」といったようなことを対象にしています。
例えば水に関して考えた場合、農山漁村の「水」が近代化の中で変貌してきたことをどうとらえるか、ということです。
近代化するにつれ、生活がものすごく変貌を遂げてきている。洗濯などは典型的です。これは一体なんなんだろうか、どういう方向にいこうとしているのか、と問うていくのが民俗学なんです。
ですから、ともすると都市対農山漁村という対比になり、民俗イコール農山漁村となってしまいがちですが、そうではなく変貌の前と後でどう変ったのか、ということを問題としたい。先ほど言った「日本人は水を見ると何となく手を洗いたくなる」という感覚は、都市的とか農山漁村的とかでは分けにくいでしょ。
水神さまへの信仰もそう。確かに農村に行ったらたくさん見られるんだけれど、都市、農村という分け方では存在しない。
言葉を言い換えると、そのときは「日本民俗学は人間の存在のあり方を問う学問である」と言えるかもしれません。
民俗学の視点から水辺や水の本質について考えるとき、私は折口信夫(注2)が「春の大潮」と「雛祭り」のことを結びつけているのが、大変象徴的な事柄だと思います。
大潮は、春と秋の2回。このことは日本の国土に住む人にとっては、大変大きな意味を持っていました。つまり、「春になって暖かくなって木の芽が芽吹く時期に大潮がくるのはなぜか」と当時の人は考えたのです。
折口信夫は著書の中で、春の大潮のことを「常世波(とこよなみ)」と呼ぶ地域があると紹介していますが、この呼び方は「なぜ大潮が木の芽が芽吹く時期にくるのか」という一つの答えになっています。
常世というのはあの世のこと。しかし、悪いあの世ではなくて、難しい表現になるのだけれど妣(はは)という字を書いて、本源という意味のあの世。まあ、天国と訳してもいいのだけれど、その常世から押し寄せてくる波という意味です。
海から押し寄せる大潮は、湧水である泉にも川にも井戸にもやってくる。つまり、すべての水は底のほうでつながっていて、自分の村の共同井戸にも大潮の力がやってくる、という考えです。
だからその時期には、海べりや川べりでのお祭りというものがあった。そのお祭りはなぜか女性が行なうんですよ。小理屈をつければ「女性が神の化身だから」ということもできるのですが、その理由は本質的にはわからないんです。
ただ春の花、それは将来的に「サクラ」に集約されていくんですが、花を愛でる春の遊びというのは、なぜか女性が中心なんです。
そのうち、日が重なるのが吉ということで、3月3日に固定していきます。ただそれは暦ができてからのことであって、本来は大潮のときに女性が水辺に出て行って祭りをするのが、春の行事だったのです。
これがいわゆる雛祭りになっていきます。「ヒナ」という言葉の語源は、小さな、という意味。最初はヒトガタを川に浮かべる祭りでした。
(注2)折口 信夫(おりくち しのぶ 1887〜1953)
日本の民俗学、国文学の研究者。国文学の起源をマレビト信仰に基づく祝詞や呪言に求め、ヨリシロに聖なる霊魂が呼び寄せられるという学説を基にした独特の「折口学」の世界を展開した。詩歌もよくし、一時期「アララギ」にも参加している。
ミソギとハライ
ここからが民俗学の解釈になるのですが、これはミソギであろうと考えられています。
ミソギというのは難しい概念ですが、春の復活の力を得ることです。ところが、この雛祭りという行事は大変な勢いで変形していって、気楽に外に行かれなくなった高貴な女性たちは水辺ではなく自分たちの家でするようになっていきます。しかも、ミソギが終わったら水に流さなくてはいけないヒトガタを永久の人形にしてしまって、家の中に閉じこもって行なうようになりました。
今ではこっちのほうが、ふつうになってしまいましたよね。雛祭りは、家の中に閉じ込められた女性たちが執り行なうなんていう解釈も出るほどになっていますが、もともとは女性は閉じ込められる存在ではなかったのです。
では女性たちは、本来どんなことをしていたか。山に行って花を採り、遊びました。この「アソブ」というのも説明が難しいんですが、おもちゃで遊ぶというようなことではない。花を愛でて楽しむことで、本人たちが華やぐというようなニュアンスがありますね。
コミュニティにおいて、その空間において、「力を得る」ための行為が「アソブ」なんです。
ミソギという概念は、神様に対峙して見るように変わっていきます。神様の前に行くときにミソグという発想が出てくるんですが、本来は自分自身が力を得るために行なうことです。
もう一つ、非常によく似た概念がハライです。ミソギをして力を得るときに、自分の悪いところが除かれるんですね。それがハライ。
人間誰しも、よこしまな心を持っていて、年に一度ぐらいはそれをハラわなくてはならない。そのために庚申講(注3)というのができるぐらい、よこしまな心は問題視されていました。
だから可哀想な人形が人間のよこしまな心を肩代わりして、水に流されることで、人間は清められる。人形には、そのような役割があります。
水の生活意識調査のアンケート結果でさんずいがつく漢字の上位に「清」という字が登場するというのは、民俗学的な「水の解釈」を反映しているものなのかもしれませんね。
(注3)庚申講(こうしんこう)
庚申の日に営まれる信仰行事。道教では人の体内に三尸(さんし)という虫がおり、庚申の夜に人が眠ると天に昇って天帝にその人の罪を告げるので、長生きするためにはその夜は眠らないで身を慎むという信仰。次第に仏教的な色彩を帯び、民間に広まって村落社会の講組織と結びついていった。
若さが力であるという発想
日本における水とは、このように「力を得るもの」なんです。「水に触れることで、力を得るんだ」という信仰です。
若水の信仰も、同じ。ワカは力。「若返る」というのは力を得ることを意味します。「若水汲み」という行事は全国に広く分布し、暦にもなっていて、地域によって青年や女性の場合もあるんですが、多くは戸主が正月の明け方に水を汲みに行く行事です。
元旦だから家の長である戸主が行なうとされ、地域によっては、この日だけは料理も男性がすることになっています。
『水の文化』の26号に変若水(おちみず)の話が出てきますよね(26号 藤田紘一郎さんのお話)。若く変わる水というのは万葉集の当て字であって、理屈の通り書いたわけです。おそらく「若さが力である」という発想からきている。
変若水というのは湧水とほぼ同じ概念で、山が終わった辺りから、しゃらしゃら染み出してくる自噴水。昔、日本人が一番水を得ていたのは、そういう場所からだったことがわかります。
逆に言えば、変若水のある場所に村が形成されていったというほうが正確でしょう。村そのものが水に依存していたことが、伝統的な日本の村を歩いていくと実感できます。例えばイギリスでは、シティと呼ばれるところにはファウンテンが、農村にはやや規模が小さい湧水、スプリングが必ずあるところを見ると、これは世界共通ですね。
水に力があるということは、末期(まつご)の水のときにも表れます。死ぬというのは、身体から魂が出ていくことですから、魂が出ていかないように水を与えるんです。それにもかかわらず出ていった魂は、第一段階として少し高い所から自分の身体を見下ろしている。このとき間髪を容れずに屋根に上り、「○○ちゃん、帰ってきて−−−」と叫ぶと呼び戻すことができる、という信仰もあります。霊呼(たまよ)ばいといって、関東に多い。
しかし、これもどんどん形骸化していって、演劇のようになっていく。本来は切実な気持ちから発せられて行なわれたものが、形骸化して「虫送り(注4)」のように行事化していくということは、自然な成り行きかもしれません。
末期の水も若水も、ともに力を得るためのもので、水はそのように位置づけられてきました。日本の歴史の中でいろいろな変移があるとしても、原則的に水は力を得るためのものであったのです。
(注4)虫送り
平安末期の武将、斎藤実盛が稲の株につまずいて倒れたところを討たれたため、その恨みから害虫になって稲を食い荒らすという伝承が各地に広まった。農作物の害虫は悪霊に寄ってもたらされるとし、悪霊を藁(わら)の人形に移し、鉦(かね)や太鼓で囃しながら、村の田を一巡して村境に送り出す行事。江戸時代に始まった。
水旱(すいかん)を自由に操る水の神様との結婚
昔話の中には水の神様との結婚という話がよく出てきます。水の神様と結婚できたら、水旱(すいかん)を自由に操れる。つまり、水のコントロールが可能になるのです。
みなさんがよく知っている例に、蛇女房の話があります。村の子供たちが蛇をいじめているところに若者が通りかかり、蛇を助けてやります。蛇は無事に逃げて湖に帰る。夜になるとその若者の家の戸をトントンと叩く者がいる。娘に泊めてほしいと言われるまま泊めてやり、やがて二人は結ばれて子供ができる。女房は「子を産むところを見ないでほしい」というのですが、若者は思わず見てしまう。すると、女房は蛇の姿に変わっていた。以前助けた蛇であることがわかってしまうのです。
蛇は「姿を見られたからには、ここにはいられない」と湖に帰っていきます。この場合、子供は後に歴史上大きなことをした人物と結びついていきます。また、蛇は水の神を意味します。
吉野山にも水分(みくまり)神社があり、奈良盆地の水を差配しています。水がないときには、水源まで行って拝んだり、水の神を怒らせるようなことをしたりします。
いずれにしても神様は水源に住んでいると思われていました。
しかし、亀とか河童は神様にはなりませんねえ。私が民俗学の聞き取りを始めたころには、まだ河童と相撲を取ったというおじいさんがいました。「おじいさん、本当なの?」と聞くと「本当!」と答えたことを思い出します。
さすがに最近はこういう人とは出会わなくなりましたが、河童というのは水の神が零落した姿なんですね。神が信仰を失うと化け物になるんです。雷(いかづち)もそうです。チというのは神様を意味しているんですが、信仰を失った天の神の姿です。一つ目小僧もそうです。信仰がなくなると異形(いぎょう)に姿を変えて、化け物に零落します。
それに比べて、蛇は水の神として日本だけでなく、東アジア全般で不動の地位を持っています。
魂の内の浄化されたものが神様になる
物事すべてに霊(たま)が宿る、という発想は、日本で強くみられます。アニミズムという西洋的解釈は好きではないので、あえて言い換えますが、「霊(たま)論」なんです。すごい強固な魂(たましい)論が、日本にはずっと存在してきたんです。
シンボリックな事柄として、お精霊(しょうろ)舟があります。お盆には先祖の霊が家に帰ってきて生き御霊と死霊が、まあ家族団欒をするわけです。お盆が終わると、先祖の霊はふつう、山に帰っていきます。しかし、琵琶湖の辺りでは山ではなく琵琶湖に帰っていく。そのときに先祖の霊は、お精霊舟に乗っていくのです。これは、多くは藁(わら)でつくられます。
こうした根強い魂論が脈々としてあるからこそ、水のシンボルとしての水の神が存在し、人間も一人ひとりが魂を持っていて、亡くなった人の魂も拝めば浄化される、だから拝まなくてはいけない、と考えるわけです。
そして魂の浄化されたものが神様になる。氏神様などはそうした神様ですね。つまり、神様は自分たちにつながっており、しかも浄化された神様だから、悪いことはしない。もし災害が起こったとしたら、自分たちに対してサジェッションをしてくれている、と解釈します。
水害で、東北のある村落が全滅したことがあるのですが、それに対して「日頃私たちはついつい川に対しておろそかになっていた。安易にゴミを捨てるとか、手入れをしないとか。山の神(=水の神)はそれをお怒りになって、洪水を起こしてゴミを浄化してくださった」という解釈をするんです。これは典型的なことです。
ですからこの霊論が弱化してくると、当然礼節というものが弱化していく。対象に対する態度が変わってきますよね。
しかも、その霊論に変わる価値観がまだ生まれてこないのも問題です。ただ、心の底には、まだかすかに霊論が根差している。私たちは初詣のときに「もしや」という気持ちで願い事をし、お賽銭を上げます。
お墓に行くのが恐い、というのも同じです。幽霊というのは拝まれなくなって浄化されない霊ですから、「魂なんてない」と思っていれば恐くなんかないはずです。
礼節はなくなったのに畏れだけがあるのかといえば、そんなこともないでしょう。
調査先のトカラ列島で丸木舟ができあがったときのことなのですが、初めて水に浮かべる際の儀式として、沖で左に3回、回るんですよ。それで、私はあれっと思いました。民俗学での事例で、同じことを経験していたからです。その内の一つは、牛を育てていた人が出荷する際に牛を連れて神社を左に3回、回ること。もう一つは、人が亡くなったときに墓に入れる前に棺桶を左に3回、回すんですよ。これの意味するところは「挨拶」なんです。丸木舟も、牛や死者も言葉を発せられないので、左に3回回ることで挨拶をさせている。
これは生きている人たちが作法として、こうしたことをきちんと心得ている、ということでもあります。
この気持ちが、まだ私たちの中にあるような気がします。ただ、弱くはなってきていますよね。
礼節論に変わる新しい価値観
この礼節論というのは、日本人を理解する上で大変魅力的な側面です。ただ、これをうまく説明できてこなかったことが、礼節論に変わる新しい価値観を生み出せない原因かもしれません。
南方熊楠が民俗学者になった理由というのが明快で、最初は民俗学なんて馬鹿にしていたそうです。
ところが熊楠は、30歳でヒダル神(注5)が憑く経験をするんです。
また私の恩師で、イタコ(巫女)の研究者である故桜井徳太郎先生が言うには、恐山では、力のないイタコは屋根が半分ないようなあばら家に住んでいて、力のあるイタコはものすごい裕福だそうです。その一番力のあるイタコが1カ月間山にこもって、小さなご飯茶碗1杯しか食べずにトレーニングをしても、なかなかハラエないのは水子の霊だそうです。産んですぐに殺された子供の霊は、母親にしがみついて離れないんだそうです。
本来、人間には守護霊が1個憑いているんだそうです。ところが転んだときとか、ひょんな拍子で憑いていたはずの霊がころーんと落ちてしまうことがある。そうすると、心が空っぽになって0になってしまうのです。
問題なのは、自分たちの身体に本来は1個ずつ入っている魂が生きている間にどれだけ健全で、亡くなってからは浄化されて神様になっているか、ということです。
このように、日本人は自然や祖先に対して礼節を重んじる伝統を培ってきました。逆に言えば、自分の意思や努力ではどうにもならないものに対する、賢い知恵だったということかもしれません。
「水をコントロールできる」というのは、長い人間の歴史から見たら大変なことですよね。ですから水に対する畏れや礼節が失われつつあるのは、コントロールすることが可能になったからとも言い換えられます。
しかし、水を完璧なコントロールの支配下に置いたことは、本当に良いことなのかどうか。コントロールのあり方を、考える必要があるんじゃないでしょうか。
八丈島で調査したときのことですが、その人のお父さんは貧しい小作で水番をしていたそうです。雨が降ると、真夜中でもお父さんは走り出て田んぼに行き、水がうまく行き渡っているか夜じゅう見回りをしたそうです。その人はそんなお父さんの姿を今でも思い出すと言い、「親父が跳ね起きて水を配分しに行った、そんなことを我々はもう経験することができないじゃないか」と言ったのがとても印象に残っています。
どんどんコントロールできてしまうことは便利なことです。でも、便利というのがハッピーになるための道筋なのかどうかということについて、私たちは哲学を持っていません。
今まで便利を追求してきたけれど、コントロールを強化することが、本当にハッピーなことなのか。それは、明らかに違う。そうであれば、どうコントロールすることが私たちにとってハッピーなのか。それを探っていく必要があります。
そこで求められるのは「遊び」の精神かもしれません。プレイとは違う、昔女性たちが山で花を愛でたような遊び。そのことが、コントロールの現状を変えてハッピーに近づくためのヒントのような気がします。
水は力を得るために、今も昔も必要不可欠な存在なのです。
(注5)ヒダル神
人間に空腹感をもたらす憑きもので、主に西日本に伝わっている。北九州ではダラシと呼ばれる。人知れず死んだ者が祀られることなく周囲をさまよう怨霊となり、人に取り憑く。歩いている最中に突然、飢餓感や疲労を覚え、そのまま死んでしまうこともある。山道、峠、四辻、行き倒れのあった場所などで憑かれることが多い。ヒダル神を山の神や水神の仕業とする土地もある。