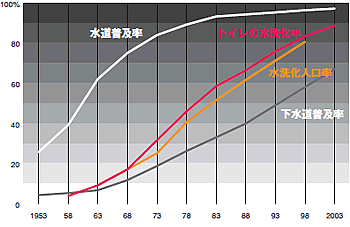機関誌『水の文化』31号
水洗化がもたらした、見えざるイノベーション
現代のトイレ志向をつくった技術改革

現在の都市生活者にとって、なくてはならない水洗トイレ。その大切な設備が、産業史の視座から語られることは、かつてありませんでした。 開発者をはじめ、節目節目に現れたキーパーソンに温かいまなざしを注ぎながら、膨大な資料を収集し、まとめ上げられた前田裕子さん。衛生設備の生産技術改革が、日本の金具産業を一新させるほどのイノベーションを引き起こしたように、人類に不可欠なトイレには、再び、新たなイノベーションが期待されています。
-

-
神戸大学大学院経済学研究科講師
前田 裕子(まえだ ひろこ)さん -
愛知県生まれ。一橋大学大学院社会学研究科修士課程修了。
民間研究所、NGO、NPO勤務を経て、神戸大学大学院国際協力研究科博士課程修了。博士(学術)。
主な著書に『戦時期航空機工業と生産技術形成-三菱航空エンジンと深尾淳二』(東京大学出版会2001)『水洗トイレの産業史―20世紀日本の見えざるイノベーション』(名古屋大学出版会2008)
なぜ、トイレなのか
なぜトイレなのか。
私自身は技術には弱い人間なのですが、三菱重工の戦時下の活動について調べて航空エンジンの生産技術のことを1冊の本にまとめたんですね(『戦時期航空機工業と生産技術形成―三菱航空エンジンと深尾淳二』東京大学出版会2001)。その取材の中で、航空エンジンの部門に非常に優秀な技術者である杉原周一さん(1907〜1972年)という方がおられ、その後TOTOの社長さんになられたことを知りました。
衛生陶器のTOTOさんで、なぜ航空技術エンジン技術が生かされたのかなあ、と。私が今、専門にしているのは日本の産業技術史なので、そのことに大変興味を引かれました。しかも異分野から来た途中入社の方が社長にまでなるというのは、どうしてかなあと考えたのです。
それで自分なりに少し調べてみましたら、杉原さんという方は便器をつくったのではないということがわかったんです。そうではなく、金具をつくられたんです。
業界では水栓金具と呼ばれているのですが、これで給排水システムにつながっていないと便器はただの穴開きオマルであって、水洗トイレとしては機能しません。
ですからTOTOさんというのを、私はずっと衛生陶器の会社だと思っていたけれど、そうではなくて金具の会社、金具で業績を伸ばした会社だったということです。
それで航空エンジンと同様に、戦時期からの生産技術移転というのを調べてみたいと思ったわけです。それでTOTOさんの小倉の本社に通い始めました。
ところが、業界関係者を別にして、TOTOさんに金具のことを知りたいと言って行った人はほとんどいないらしい。私が調べたいと思ったことについては、くわしいところまでよくわからなかったんです。その内、「せっかく来たんだから衛生陶器も見て行きなさい」と言っていただいたりするうちに、衛生陶器と水栓金具の初期のころの話を書くことになりました。
歴史って、やっているうちに「これはどうしてだろう」と遡る傾向があるんですね。それで、私も大倉孫兵衛(注1)、和親(注2)という親子に行き着き、気持ちの中で恋人化していきました。
現代の日本の都市部に暮らす人間にとって、水洗トイレが使えなくなることは、飛行機が飛ばなくなることより、携帯電話やパソコンが使えなくなることより、ガスや電気が止まることより深刻です。たとえ1週間でもそんなことが起これば、私たちの生活がたちまち悲惨な状況になるということを、例えば大災害を経験した人は痛いほど理解しているのではないでしょうか。
この圧倒的な重要性にもかかわらず、トイレの水洗化について、その工業化過程を明らかにした研究は、企業の社史を除けばほとんどなかった。
それで、日本の水洗トイレ黎明期から本格的普及の始まった1970年初めあたりまでのおよそ100年間の歴史を、この工業化の視点から書いてみようと思ったわけです。
(注1)大倉 孫兵衛 (おおくらまごべえ 1843〜1921年)
実業家。家業の絵草紙屋から独立して絵草紙屋・萬屋を開店し後に大倉書店、大倉孫兵衛洋紙店(現・新生紙パルプ商事)を設立した。夏目漱石の初の単行本「吾輩ハ猫デアル」も大倉書店から刊行された。また、森村市左衛門との出会いから日本陶器(現・ノリタケカンパニーリミテド)、大倉陶園の設立に参加し日本の陶磁器産業に多大なる貢献をした。
(注2)大倉 和親 (おおくらかずちか 1875〜1955年)
大倉孫兵衛の長男。慶應義塾卒業後、森村組に入る。アメリカのイーストマン・ビジネス・カレッジ修了後、ニューヨークのモリムラブラザース入社。森村組から分離された日本陶器(現・ノリタケカンパニーリミテド)の初代代表社員。
水洗トイレを概観する
水洗トイレはそれ自体が偉大な発明でした。そして排泄設備における歴史的イノベーション(新機軸)でしたが、それが普及することで二重、三重に大きなイノベーション(革新)をもたらしました。
まず第一のイノベーションは、都市の公衆衛生を改善することで、人間の健康維持に実質的に貢献しました。
都市に人間が集住することにより、衛生の悪化という大問題が生じることになります。フランス・パリの例で言えば、道路に捨てられたゴミや汚水、し尿による汚泥水を排除するためにセーヌ川に通じる溝が切られたのが12世紀末。溝はすぐに詰まったため、14世紀には下水道が建設されます。当時、し尿は不浄なものと考えられていたため、川に流さず別途収集されていましたが、満足のいく状態にはほど遠い状況でした。
19世紀後半のジョルジュ・オスマンのパリ大改造計画(「家の中心は水まわり」参照)によって大幹線下水道が完成し、パリでは1880年に住居のトイレ排管を下水道につなぐことが許可されました。イギリス・ロンドンでは1815年、アメリカ・ボストンでは1833年、ドイツ・ハンブルグでは1842年、アメリカ・フィラデルフィアでは1850年に、パリより早く許可されています。
下水道は本来、雨水と生活雑排水を集めて流すことで、都市を水害と不衛生から守るための設備でした。しかし、水洗トイレの発明によって、その意義と性格を変えていきました。ほかならぬ「トイレの水洗化」が、下水道建設の目的の一つとなったのです。
第二のイノベーションは、「清潔」にかかわるものです。つまり悪臭や害虫の発生という不快な住環境に対して「不潔」感を覚え、より快適な環境へ改善しようとする意識改革を促しました。
また、上下水道が整備されたことで、水汲みから解放された人々は、比較にならない量の水消費を享受することになりました。19世紀初頭までのパリでは、1日1世帯あたりに必要な水は5〜7リットルと考えられていましたが、19世紀中ごろには100リットルを超え、20世紀初頭には200リットルを超えます。
こうして都市生活者は、飲料水以外の生活用水の、そのほとんどを汚れを洗い流すために使うようになりました。言い換えれば、上水は衛生と清潔のために給水され、排水されるようになったのです。密室の中で排泄行為が行なわれ、排泄物は瞬時に目の前から消えてなくなるようになりました。
今日、人々が衛生設備機器メーカーに対して、「清潔」かつ「好ましい」イメージを抱いているとすれば、それはまさしく水洗トイレがもたらした社会心理面でのイノベーションにほかなりません。
そして第三のイノベーションは、個々人の内的な排泄行為への感覚を刷新し、排泄空間における快適性の追求を顕在化させたことです。加えて、汚物を遠ざけるのみならず、その存在を意識から抹殺したいとする心理を生みました。
水洗トイレの快適性がもたらしたイノベーションは、人々に己の廃棄物の行く末を忘れさせ、水資源の貴重さへの意識を薄めることになりました。
結果的に、環境への負荷(汚水処理と水資源の多用)があることを認識させるための教育が、新たに必要になってきたと思います。
こうした意識にまで及ぶ「水洗トイレ」がもたらしたイノベーションは、都市機能そのもののイノベーション、つまり給排水システム(上下水道)の構築の上に成り立つものです。
日本の特殊事情
日本は、人口の割に耕作地が狭く地味が痩せていて、牛馬をはじめとする家畜の数が少ない。そのため、人間のし尿が極めて有効な肥料になりました。
江戸の町も17世紀あたりまでは、まだし尿の垂れ流しが行なわれていたようですが、次第に汲取りのシステムが整っていきます。
肥料としてのし尿は、干鰯などと違って遠隔地への輸送は不向きですから、トイレの視座から眺めれば、人口集積の度合いと近郊農家の規模、し尿肥料化の知恵と工夫などのバランスが、近世日本の大都市を誕生させたと言っても過言ではありません。またその資源が活用される農業は、日本では伝統的に尊ばれていましたし、そこには循環の思想が生きていました。
ただ、1910年代後半から1920年代にかけて(ほぼ大正期)、日本全体でみても都市人口が増大するとともに、農村では化学肥料の使用量が急増します。そのため、東京市では広域下水道が完成する前に、し尿需給のバランスが大きく崩れ始めるのです。
1918年(大正7)には農家や業者における汲取りが停滞し、未処理のし尿が下水や川に密かに捨てられて問題になります。1919年(大正8)には市費を投じて無料汲取りを開始しますが、処理量の増加に追いつけず、1921年(大正10)には一部地域で有料化に踏み切りました。
1922年(大正11)に三河島汚水処分場の運転開始によって、ようやく東京市の下水道は、水洗トイレ取り付け可能(直接放流可能)の指定を受けました。とはいっても、日本におけるトイレの水洗化は遅々として進みませんでしたが。
明治のころ、し尿は農村に還元されていましたが、当時それでも水洗トイレをつけたいという人、例えば外国人なんかは便器は輸入の既製品を買ってきて、パイプなどの足りない部分は水道屋さんが手づくりしていました。バルブなど金属部品は、輸入から、次第に国内の金物屋が専業化してつくるようになりますが、概して品質は悪かった。
アメリカやヨーロッパでは、金属機械産業というか、金属パイプとバルブのネットワークの中に位置づけられてこそ、水洗トイレが成立し、金属機械産業の一環として設備機器産業が現れる。はじめに金属ありきです。
何もトイレだけではなくて、ガスもそうですし、空調とかスチーム暖房もそうですね。そういうものをセットとして金属機械産業として設備機器産業が発展していった。
アメリカ的な特色でもありますが、ちょうど世紀の変わり目ごろから、大企業がぐっと伸びていく。一つは、金属機械産業というのは産業としても発展性がありますよね。だから、そういう大企業が、ネットワークのほんの一部分を占める便器や洗面器をつくっている衛生陶器メーカーを吸収合併してさらに成長していく。この経緯は極めて自然に思えるわけです。アメリカンスタンダード社なんかその典型といえるでしょう。
ですから設備機器メーカーと便器メーカーとは、非常に異なるものなんです。設備機器メーカーが便器メーカーを吸収するというのは簡単ですが、便器メーカーが設備機器メーカーになるというのは、すごい飛躍が必要なんです。
それなのに、日本ではほんの小さいほうの陶器のほうがリードして、世界的なメーカーになってしまった。アメリカなどと比べてまったく逆だというのが面白いなと思います。
日本の生活を近代化する志
TOTOの創業に深くかかわった大倉孫兵衛は、シカゴ博覧会(注3)で純白の水洗便器に触発されただろう、と書いたのは私の完全な推測です。ただ、シカゴ博覧会に孫兵衛が行ったことも、そこにたくさんの水洗トイレが据え付けられていたことも事実ですから、あながち見当外れでもないと思います。
ただトイレ研究が難しいのは、なかなか写真が残らないということなんですよ。
ところで、企業としていえば、便器を製造したTOTO(当時の東洋陶器株式会社)以前に日本陶器(現・ノリタケカンパニーリミテド)があり、その母体は日本最初期の輸出商社の森村組でした。創業者の森村市左衛門(注4)は貿易業で大成功した人物ですが、大倉孫兵衛・和親父子も、この貿易業から多大な恩恵を受けています(注5)。
私がすごいなと思うのは、製造業、それも窯業はキツい仕事で当時は機械化も難しく、利幅も少なくて大変だったのに、大倉父子はそれをやった。ものすごいお金持ちだから、苦労してやる必要はなかったのに敢えてやったんです。
しかし、努力しているうちにノリタケ・チャイナという大変優れたものが生まれて成功しました。その辺のことは理解できますね。大倉陶園にしても、お金持ちの趣味人の道楽と見れば、絵草紙屋さんの美意識があってヨーロッパに負けない美しい美術陶器をつくりたいとかね。
ただ、食器とか碍子というのは需要があって、良いものをつくれば売れるとわかっていたわけです。ところが衛生陶器は輸入品で充分でしたから、需要がないんです。それなのに、なぜつくったのか。
それは、日本の生活様式を近代化したい、という願いだったかもしれません。大倉和親は、キャリアとして最初からアメリカ・ニューヨークのモリムラブラザーズ駐在からスタートしているんですね。若いころからの経験があったからかもしれません。そういう感覚からすると、彼らにとってはテーブルウェアも便器(サニタリーウェア)も同じだったのかもしれませんね。近代化をかなえる生活様式のものを全部つくっていこう、という気概だった。
必ず、いずれ必要になるときがくる。必要になったときに、輸入に頼るということが嫌なわけですね、この時代の人は。
日本では1970年(昭和45)でも30%程度の普及率ですから、実際は見込み違いだったのですが、もっと早く水洗トイレ時代がくると思っていたみたいですね。もしかすると輸出産業としてアジア地域に便器を輸出することは、視野に入れていたかもしれません。しかし、どう考えても私(わたくし)の利益のための事業ではなかったはずです。
(注3)シカゴ博覧会
コロンブス大陸発見400周年を記念して、1893年(明治26)にミシガン湖畔で開催された。純白に塗装されたホワイトシティーと呼ばれるパビリオン群と、フェリスの大観覧車を展示。アメリカがヨーロッパより工業力に勝ることを誇示する博覧会となった。日本も輸出振興、近代化、工業化を世界に印象づけるために出展している。
(注4)六代目 森村市左衛門 (もりむらいちざえもん 1839〜1919年)
森村グループの開祖。江戸末期、京橋の老舗武具馬具商の長男として生まれ、1859年の横浜開港の直後、渡日した外国人から欧米の品々を買い込んで江戸で売る商売を始め成功。年の離れた異母弟豊(とよ)を慶応義塾で学ばせて、2人で直輸出貿易会社、森村組(匿名組合)を1876年(明治9)に設立する。ニューヨークにも進出しモリムラブラザーズを開店。
(注5)森村グループ4社
(現在の株式会社ノリタケカンパニーリミテド・TOTO株式会社・日本ガイシ株式会社・日本特殊陶業株式会社)のルーツは、1876年(明治9年)森村市左衛門と豊の兄弟によって設立された森村組にある。我が国の貿易業界の草分けともいうべき森村組は、1904年(明治37)愛知郡鷹場村字則武に、日本陶器合名会社を設立した。1917年(大正6)には、同社の衛生陶器部門を分離して東洋陶器株式会社が、1919年(大正8)には碍子部門を分離して日本碍子株式会社が設立された。1936年(昭和11)には、日本ガイシのNGK点火プラグ部門が分離して、日本特殊陶業株式会社が設立される。創業者である森村市左衛門をはじめ、大倉孫兵衛、幹部社員は長者番付の常連であった。
開発にかける情熱
磁器というのは日本で昔からつくられているんですが、あんまり真っ白じゃないんですね。日本陶器は、白色硬質磁器と呼ばれる真っ白なのをつくりたかった。そして、その磁器を使って立派なテーブルウェアをつくりたかった。この開発は、先程言ったようにノリタケ・チャイナという大変優れたものが生まれて成功します。
一方便器は、大倉さんが日本陶器の工場用地の一部に新しい試作工場を私設して試作されます。推測ですが、のちに別会社にしたのも便器をきれいな食器と同じ工場でつくることに抵抗があったことも一因じゃないかな、と感じます。
ヨーロッパの有力メーカーは、両方つくっているところが多い。当時の日本はその辺の感覚が繊細だったのかもしれません。TOTO(当時の東洋陶器株式会社)は、ヨーロッパ流ビジネスモデルを取り入れて両方つくります。
便器にするには、白色硬質磁器とは材料が違うわけで、硬質陶器と呼ばれるものです。日本にはいろいろな種類の焼き物がありますが、硬質陶器というのはなかった。硬質陶器というのは吸水性が低いので、水だけではなく臭いや汚れにも強く、便器に適していたんです。そのために大倉さんは基礎研究から立ち上げるんですね。
硬質陶器より器のほうが吸水性が低いという点では優れていましたが、器は金属分を多く含むため有色であるのに対し、硬質陶器は白色磁器ほどではないけれど、それに近い白さを持つのです。
つまり硬質陶器は、硬さ、白さ、低い吸水性、機械工業への適性、価格面での優位性といった、従来の軟質陶器、器、磁器にはない総合的特質を持ち、実用性に富む素材でした。硬質陶器の開発には、佐賀出身の松村八次郎が成功していますが、特許も申請せず、日本の陶器産業の発展に尽くす道を選びました。
私が感じるのは、こういう気概を持っている日本人というのが、そのころたくさんいたんですね、今みたいな豊かな時代よりもね。しかし、そういう人たちの中で、帝大卒のエリートなんかは、こんなに地味な生活まわりのことではなく、鉄道を敷くとか大きな橋を架けるとかにいっていましたよね。だから、土木なんかでは優秀な人がたくさんいました。
生活まわりという意味では大倉さんより前に活躍された配管屋さんたちの中にも、すごく立派な方がいました。本の中で西原脩三さんと須賀豊治郎さんを紹介していますが、自力で会社を興され、技術開発された起業家です。今回の話には関係ありませんけれど、イタリア翻訳家の須賀敦子さんは須賀さんのお孫さん、経済学者の青木昌彦さんは西原さんのお孫さんです。そういうDNAがあるんですね。西原さんも須賀さんも、そして大倉さんも国民の衛生のために、いわば縁の下の仕事を続けてくれた。
また、給排水というと下水管も必要ですが、この陶管(下水用土管)をINAXの前身の伊奈製陶がつくることになり、大倉さんはそれも支援しています。
INAXの創業地である愛知県の常滑には、横浜居留地の下水道建設を管理していたブラントンという技師に依頼されて、1872年に鯉江方寿という人が国産第一号の陶製下水道管の製造に成功した、という歴史があります。
真焼土管(まやけどかん)と呼ばれるこの土管は、従来の素焼きの土管よりも高温で焼締めて吸水性を減らし、漏水し易かった継ぎ手部分を改良したものです。鯉江は常滑の陶祖ともいわれ、その後、常滑の陶業が隆盛した礎となりました。
便器から金具へ
TOTOとしては、非水洗のものをつくっているうちはいいんですが、水洗トイレをつくる上では国産の水栓金具がちゃんとしてこないと困るわけです。日本でも輸入品に遜色ない金具をつくるメーカーも出てきますが、なにせ供給量が少なくて価格が高い。だから金具の問題というのは、ずっとTOTOの問題であり続けていくんです。
アメリカンスタンダード社とかコーラー社とかは、もともとが金属機械系のメーカーですから、衛生陶器が1つ売れれば、金具もそれにセットして売るわけです。TOTOも意欲はありながら、長い間、実現できずにいて、そんな状態で戦時期に入るのです。
もちろん当時の日本の技術でも、水が洩れない水栓金具をつくることはできたと思います。ただ、そういう能力がある工場では、船とか機械とか、もっと難しいものをつくっていたのです。まだ、そんな時代だったんです。
そんな質の悪い金具でも、全部そろえたら結構高いものにつきました。質の良い便器より質の良くない金具のほうが高い。
だからTOTOとしたら、自分のところでつくれたほうが格段にいいんですが、窯業と金具産業とは全然違う技術で相性も悪いんです。特に真っ白な陶器をつくるときに、金属粉などが混入するとまずいんです。
戦後TOTOで衛生陶器工場と金具工場が隣接していたときの話ですが、工場見学をするなら衛生陶器が先で金具は後、その逆はダメだったとのことです。
ですから、そういう環境で金具部門にいた杉原周一さんが社長(1967〜1972年在職)になるというのは、相当に強烈なことだったはずです。そのころは会社名も東洋陶器でしたから、技術者といったら窯業技術者を指す時代。そこに機械技術出身の杉原さんを据えるというのは、大変な決断だったと思います。
時代を変えたキーパーソン
杉原周一さんは、東京帝国大学工学部機械工学科を卒業後すぐに三菱重工に入社、当時花形となりつつあった航空エンジンの開発に携わります。ここで燃料噴射装置及び、その噴射量自動制御装置の開発に成功し、その量産のための専門工場の工場長として生産ラインの立ち上げを任されます。
しかし、敗戦後はいろいろと複雑な想いや事情が重なったのでしょう。いったん社内の自動車部門の研究職に就いたものの三菱重工を辞し、郷里大分で農業を営む決心をします。一時期、大分県工業試験場長の職を経て、小倉の東洋陶器へ入社します。口をきいたのは、三菱重工時代の上司でした。
当初杉原さんが任命されたのは工務課長であり、コンベヤその他の設計製作というような肩書き通りのものでしたから、杉原さんに求められたのは、生産技術改革だった。当時は機械工業に比べ、窯業の生産技術が相当に遅れていたからです。
しかし杉原さんはその後、製陶関係の生産技術ではなく、金具製造の工場を率いることになりました。これがTOTOにとって大きな転換点になります。
もしも戦前期の金具生産のレベルが高かったら、そんなに簡単には抜かれませんよ。しかし、杉原さんの主導した改革により、TOTOは10年経たないうちに、日本で断トツの金具メーカーになるんです。ああいう小さなパーツですから、統計がどれぐらい信頼できるものかわかりませんが、日本の総売上の5割近くを生産して、しかも品質の良いものをつくってしまった。
これはTOTOの成果でもありましたが、日本の金具産業全体をあっという間に変えることにもなったんです。
TOTOで衛生陶器より金具の売り上げのほうが大きくなったのは、1962年(昭和37)のこと。陶器のマーケットと金具のマーケットとでは、発展性もまったく違っています。その時点で既に陶器屋さんでなく、金具屋さんになっていたわけですよね。そのほうが実態を表していたんだけれども、我々はずーっと陶器屋さんだと思い込んできたんです。
1970年(昭和45)に東洋陶器株式会社から東陶機器株式会社に社名を変更しているのは、象徴的な出来事です。東陶機器と名乗ることは、企業の姿勢をよく表していて、つくるものもそうですが、リクルートの際にも会社の体質をわかりやすくしています。また、創業時からの主要生産品目の一つであった食器から完全撤退して、企業の方向性を明確に示します。
そして、生産品目が多角化していく。そういうところからウォシュレットや、現在でいえば食洗機なんかも生まれていくことになります。
ちなみにINAXの場合はシャワートイレといいますが、金具の部門ではなく陶器の部門から開発されたそうです。会社の体質が出ていて、面白いですね。
ユーザーの意識も変革
銀座にショールームをつくったのも、杉原さんの時代です。コマーシャルもそのころから派手になっています。
今ではTOTOもINAXも単なる衛生陶器のメーカーではなく、衛生設備機器メーカーになっているわけですが、かつて衛生陶器というのは個人が選ぶものではなかった。家を建てるときも、どこかの工務店に頼めば工務店が適当に発注して取り付けていた。そういうのが、今では個人が「こういうものが欲しい」と主張するようになった。コマーシャルの影響は大きいですね。
そういうことで、私たちの感覚も変えられていったように思います。みんなが隠していると、なかなか言い出しにくいですが、表に出てくることによって「話しても大丈夫なもの」に変化した。タブーでなくなっていく。そういうことが、商品に対する清潔感を植えつけていったんです。まあ、日本の場合は欧米と比べると、それほど便器やトイレに対する忌避感が強くないというか、もとからおおっぴらだった一面もあると思いますけれど。
こうしてユーザーの要望が高まって、商品開発にも影響していくようになっています。一般消費者にとっては、身近でより快適なものがつくられる傾向にあるんじゃないでしょうか。
いったん、品質の良い水洗トイレを使い始めると、人々がその清潔感を増したトイレに求めるものは、どんどん変わっていきました。
昔、外にあったトイレに行くのが嫌で、家の中にあっても子供時代は夜は怖いと思ったりした。今、そんなことは思いませんよね。今のトイレは、そういう不浄感や怖さを払拭しました。
暖房便座一つでも全然違います。昔だったら、寒いからなるべく我慢して行く回数を減らしていたものが、今はなるべく長く座っていたい快適な空間になっています。
あとは臭いがなくなりましたね。水洗にしたら臭いがなくなるわけではありませんから、それなりにすごい工夫をされているんだと思います。
求められるイノベーション
ただ一方では、それが良いことかどうかわかりません。排泄や臭いといった人間が持つ本来の姿を見えなくしてしまっているからです。その結果、私たちはそういうことをすっかり忘れ去ってしまいました。
住宅設備が消費財になっていったかというご質問ですが、便器は、まあ建て替えやリフォームのときぐらいしか、そう簡単には取り替えられない商材でしょう。ただ、便器は取り替えられなくても、暖房便座だけとかシャワー機能だけとかを付加することができるようになりました。水栓金具の成熟には、そういうメリットもありますね。
そういうやり方で、便器のライフサイクルを伸ばしていくことに、貢献できているとは思います。
本著では、敢えて水洗トイレと環境との問題には立ち入りませんでしたが、地球上のすべての地域に水洗トイレをくまなく普及させる方向性が良いとはいえないでしょう。
水には、NGO時代から興味がありました。農村開発で一番大切なのは飲み水で、第二は適切な排水処理をして衛生管理することなんです。つまり、「安全な水」と「適切なトイレ」です。
既に莫大なお金をかけて下水道が建設されている所では水洗トイレに優位性があると思うんですが、そうでない所では他の選択肢もあると思います。
と言いますのも、水洗トイレはやはりものすごく水を使いますから。これから先の水資源のことを思うと、違うことを考えなければなりませんね。もちろん、節水型の水洗トイレの開発は行なわれていて、初期は1回のフラッシュで20リットルも使っていたのが、今は6リットルを切っていますけれど、それでも将来的には水が問題になっていくと思います。
バイオトイレもいいんですが、これだけ人間が集中して住んでいる都市部で、それがやっていかれるかどうかはわからないと思います。
メーカーさんは売れるものをつくるという命題があり、どんどん付加価値を高めていかないとならない。それがないと製造業はダメになってしまうのですから、本当に大変だと思います。良いものをたくさんつくったら、価格が下がってしまうわけですからねえ。それでまた新しいものをつくる。
ですから、先程のお話でいえば、暖房便座とかシャワー機能とか、替え易いところを開発するというのは、メーカーとしてもいいことなんでしょう。
これからの一番大きな課題は、環境問題との折り合いをどうつけていくか。
日本の場合は欧米と違って、し尿が肥料として重用され、農村で管理していたという歴史があります。そのことでトイレの水洗化が遅れたわけですが、その時代はそのやり方でちゃんと循環し、機能していたわけです。
それが下水道が完備するまでの過渡期には、あまり性能が良くない単独浄化槽を使ったり、海洋投棄したりしていたわけですよ。
単独浄化槽の新設が禁止されるのは、ようやく2000年になってから。それ以前に設置されたものは、そのまま放置されている状況です。1989年の統計(石井勲・山田國廣共著『浄化槽革命―生活廃水の再生システムをめざして』合同出版1994)によれば、水洗化人口の実に20%が単独浄化槽を使っています。
だから、衛生的な水洗トイレといいながらも、水に流して目の前から消えてなくなっているだけで、決して本当の「衛生的」な設備にはなっていなかった。それは欧米でも経験され、今日なお世界各地でみられる状況でした。
こういったことは、お百姓さんがし尿を肥料として使っていた時代よりも、ある意味では後退したと言っていいでしょう。
世界人口の増加と水資源の分布、水質汚染の進行などを考慮し、下水道が完備しながらも、なおかつ循環型システムが求められるようになった今、人類に不可欠なトイレには、再び、新たなイノベーションが期待されているということです。