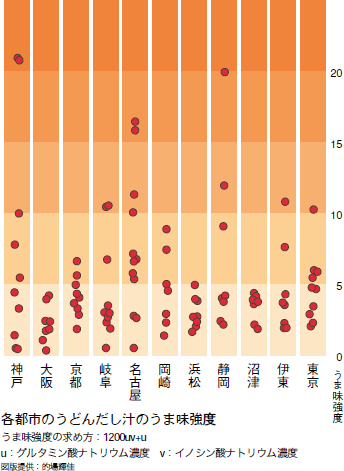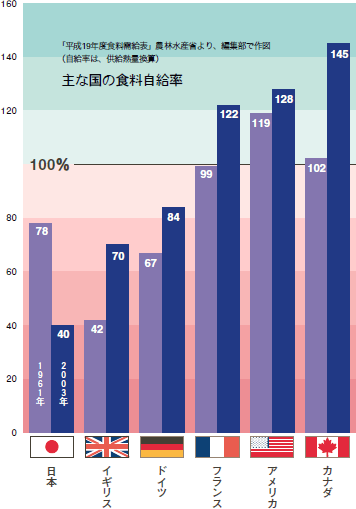機関誌『水の文化』33号
現代嗜好に迎合しない味を守る
米食風土が育んだ、だし文化
食育基本法が制定され転機を迎えた日本の食生活。 調理科学の視点から、食文化を研究する的場輝佳さんは、今のような贅沢ができなくなっていけば、手に入る食材からいっても、日本料理が本来持っていた調理方法や味つけが見直されていく、と言います。 野菜と魚介類中心で生活するようになれば、必然的にだしの復権が果たされるでしょう。
-

-
関西福祉科学大学健康福祉学部栄養学科教授
的場 輝佳(まとば てるよし)さん -
1972年、京都大学大学院農学研究科博士課程(農芸化学専攻)修了。同大学食糧科学研究所助手・助教授、奈良女子大学生活環境学部食物科学専攻教授を経て、現職。専門は食品化学、調理科学。
主な著書、論文に『西洋料理のコツ』(共著/学習研究社2003)、『料理のなんでも小事典』(日本調理科学会編/講談社2008)、『だし汁の東西味紀行-東海道うどんの地域的特徴-』(日本醸造協会誌2005)、『食材の健康増進機能に対する調理の意義』(日本料理科学会誌2007)ほか。
食べものを生活者の視点で
私は、学生時代は農学部農芸化学科に籍を置いていたのです。教養部時代は、自由で気ままな生活。ところが、3年生になる直前に肺炎になって下宿で寝込んでいた時期がありました。そのとき、いろいろ考えることがあって「勉強っていいなあ」と思ったんですよ。
では、何を勉強しようか。
そのときに手にしたのが、栄養学の本だったんです。それで食べもののことをやろうとした。
卒業後、食糧科学研究所で「苦い味のペプチド」で学位論文を取得。味のことは、それが始まりです。当時の食糧科学研究所はバイオ全盛だったけれど、私自身は食べもののことをやってきました。
奈良女子大学に移って、当時、家政学部食物学科に所属したので、食べものを生活の視点からとらえる、ということをテーマに研究を進めました。京都にいたときには、どうしても生産者の立場から食品を見ていたけれど、生活者の立場から見たら面白いな、と思ったんです。同時に調理というものを研究してみると、わかっていないことが多い分野だということにも気づきました。
一貫して食べもののことをやってきたけれど、生活者としての視点から食べものをとらえるという姿勢は変わっていません。
料理はでき上がったもの、調理とは操作です。料理科学とはいわないけれど、調理科学とはいいますね。
調理にはまず食材が重要です。食材はその地域に生まれたものですから、その特徴は風土や環境が反映されています。そして、その食材の持っている食べものとしての能力を最も引き出して、食べやすくおいしくするのが調理です。
献立をイメージして、食材を選んで、前処理をして、加熱するなど手を加えて、味つけをして、盛りつけて「料理」になる。この調理操作のプロセスの中で、だしは調味に位置づけられるでしょう。
日本料理では、煮ることと、だしとが強く結びついています。
だしの定義は、「日本料理の味覚を特徴づけるもので、鰹節、昆布など海産物や干し椎茸などを中心に煮出した透明な汁のことで、うま味をベースとしたもの」。このようなだしを取るのは、日本だけです。鶏ガラで取るのはスープであって、だしとは違うものだと思います。
スープと決定的に違うのは、だしには油分が少ないところ。上品で癖のない風味が日本人の口に合って、おいしいと思われたから広まったのでしょう。
だし汁の東西味紀行
2000年5月に文部科学省、厚生労働省、農林水産省の3省から出された「食生活指針」では、単に栄養面だけでなく、日本型食生活の再評価を求め、地域固有の風土で培われた独自の食嗜好(食文化)の重要性を指摘しています。
一般に「関西の薄味、関東の濃味」といわれていますが、それは本当のことなのでしょうか。江戸時代とは違い、現代では人の移動や情報の伝播も活発で、この通説がそのまま通用するとは思えません。
そこで、東海道沿い、神戸市から東京都の間の12都市を訪ね歩いて、うどんのだし汁を解析してみました。
結果は総合的に見ると、塩味・甘味などの味覚の点ではかなりのばらつきがありました。
だし汁の色の濃さだけに限ってみると、讃岐うどんの流行で、東海・関東地域にも色の薄いだし汁のうどん店はあったものの、関西圏3都市(神戸市、大阪市、京都市)では、調査した限りですが、関東風の色の濃いだし汁を出す店舗は1軒もありませんでした。
関西人の「薄い色のだし汁」のうどんへの、強いこだわりを再認識する結果になりました。
意外だったのは、関西は「色は薄いが、だしが利いていてうま味が強い」という通説がくつがえされたことです。うま味を感じる成分であるグルタミン酸ナトリウムやイノシン酸の量は、総合的に見て関東の濃い色のだし汁のほうが多かったのです。
それなのに、なぜ、だしが利いていてうま味を強く感じるのでしょうか。その理由は、多量の濃口醤油で味をつける関東風のだし汁の場合、芳醇な醤油の香りが強く出てしまって、だしの香りを消してしまうからではないか、と私は考えました。
薄い色のだし汁は、昆布や節類の香りが消されずに残っているために、たとえうま味が薄くても「だしが利いている」と感じるのです。
醤油にも薄口と濃口でこのような違いがありますが、味噌も同様です。
名古屋の赤味噌は、普通の味噌に比べて香りが強いですね。醤油も同様で糖分とアミノ酸が反応して、だんだん香りを出して、最後に色ができるんです。だから醤油も味噌も、色が濃いもののほうが香りが強いのです。
食べものを味わう感覚は、舌(味覚)であると思いがちですが、実は私たち日本人は、味と香りが一体となったものを味覚と錯覚しているのです。鼻をつまんで何かを食べれば気づくことです。香りがなければ、おいしく感じません。牛肉と豚肉の区別もつきませんよ。口の中は鼻とつながっていて、味と香りを同時に感じているのです。
日本の料理人は畑で大根を味見するときに、バッと折ってかじります。しかし、ヨーロッパの料理人は折った大根に鼻を突っ込む。香りへの感性は、彼らのほうが強いかもしれませんね。だから、日本料理も香りをもっと意識して食べれば、いっそう繊細さが広がると思います。
食育と日本料理アカデミー
戦後、昭和20年代後半を、私は小都市で小学生としてすごしました。私の実家の食卓は、今日のように豊かではありませんでした。水道もなく、井戸水を手動式ポンプで水瓶に移していたし、炭火が赤々と熾っていた七輪に鍋をかけ、薪をくべて竈でご飯を炊きました。
当然、冷蔵庫はありません。母は食材を小買いして、食事をつくっていました。好き嫌いが無かった私は「ご飯もいろいろなおかずも思いっきり食べてみたい。食卓がもっと豊かになれば家族はもっと幸せなのに」と思っていました。
やがて、水道がついて、七輪や竈はガスコンロや炊飯器に替わり、台所にシステムキッチンと食器棚が並んで食空間は明るくスマートになりました。
特に、炊飯器は母を家事労働から解放し、冷凍冷蔵庫は生鮮食品の保存性を飛躍的に向上させたのです。
戦後の貧しい生活を経験した私たちの世代にとっては、今日のように豊富な食材が流通していて、欲しいと思えば何でも手に入る食環境を、何と素晴らしいものかと思います。
ところが、児童・生徒の個食や孤食、偏食や欠食など、家庭でのコミュニケーションを育む食卓の風景が失われたり、若年層、特に女性の低栄養状態や、壮年層のメタボリックシンドロームなどが年々問題になっているのです。さらに、世代を超えて不確定な情報に振り回されて、サプリメントや偏った食品に依存する異常な食行動(フードファディズム)が目立ってきています。
このような背景の中で、特に子供たちの食生活の乱れを憂慮して、2005年に食育基本法が施行されたのです。
京都に日本料理アカデミー(注1)という組織がありますが、京都市教育委員会と連携して「日本料理に学ぶ食育プログラム」を小学校で始めています。
私は今年から「食育カリキュラム推進委員会」の委員長を務めています。
京都市の教育委員会と日本料理アカデミーが食育カリキュラムをつくって、小学校で3年生から6年生までに実践しています。
単なる料理教室ではなく、料理を通して、3つのことを教えています。
- だしの味を知る
- もてなしの心を知る
- 食材の命をいただいていることを知る
京都の料理人は「だしを取る」とは言いません。「だしを引く」と言います。小学生にも「だしを引いて、日本で一番おいしい澄まし汁をつくろう」という授業をします。
ここでは一流の料亭の料理人が指導をし、普通の家庭では使わない利尻産の最高級の昆布や鰹節を使って、だしを引かせるのです。
やっているうちに「良い香りがする」と言ったり、味も覚えていきます。子供たちは、実に興味津々で取り組むようになってくる。
同時に「家の人に野菜を食べさせよう」と調理も教えます。ある子供はおばあちゃんが冬瓜が好きなので、冬瓜を煮ようとしますが、歯が悪いのなら隠し包丁を入れたらいい、という調理のコツを、プロから教わっていました。
面取りの仕方や包丁の使い方も教えます。子供たちはすごく真剣で、多分ここで習ったことは一生忘れないと思います。
そして、料亭で使う漆塗りのお椀に盛りつけて、味わうところまでやります。そして最後に「僕なら、こんなお汁をつくりますよ」と、プロが見本をつくって見せるんです。そうすると、子供たちが寄って来て「うわー」と感動する。「ビューティフル、ビューティフル」と手を叩いて踊っている子供もいました。プロの仕事は、それほど子供の心に訴えるんです。料理人が極上の食材で一流の調理をすると、こんなに感動を呼ぶんだということが、よくわかりました。
授業風景の一端を紹介します。
ある学校では、普段は残飯をコンポストに入れて堆肥にしているんですが、捨てに行こうとした子供たちに料理人さんが「チョット待って、こんな上等な昆布や鰹節を捨てたらもったいない。私らはふりかけや塩昆布をつくるよ」と言って、それも教えてあげる。
命を教えるときも、同じです。子供たちにものを教えるときは、本能的に訴えることです。生きた車エビをパッと切ると、みんな「残酷!」と叫びます。しかし、その後の調理人の手さばきや盛りつけた見事な料理を見ると、本当に目を輝かせて感動する。その間、たった2分間ですよ。2分前までは、「残酷!」と言っていたのに。
かぶら蒸しをつくったこともあります。私たちは小学生には無理だろうと言ったのですが、料理人たちは大丈夫だと言う。それで挑戦して大成功。蒸している途中で味見をさせたんです。蕪に火が通って甘くなっていて、野菜嫌いの子供たちが「おいしい!」と言いました。
子供たちが食材に触れ、調理を体験して食の大切さを料理を通して本能的に体得することが、食育の原点だと思います。
まだまだ改善の余地はあるかもしれませんが、このような食育授業を、京都市内では今年は17校で行ないます。
(注1)日本料理アカデミー (Japanese Culinary Academy)
将来を嘱望される世界の若手料理人を京都に受け入れ、日本料理の真の姿を学んでもらうための海外料理人向けの京都研修プログラムを中心事業とし、日本が誇る食文化を広く世界に普及し、次代にむけて、日本料理のグローバルスタンダードを確立することを目的とする。
日本食は水を食べているようなもの
だし昆布を捨てずに、調味して塩昆布をつくりました。食べていた子に、「おいしいかい?」と聞くと「おいしい!」と元気いっぱいに答えてくれた。そして「先生、白ご飯が欲しい」とも言っていました。
日本食の原点はご飯。これほど特徴のない、水のような存在の食べものが、だしを大事にする日本料理を育んだのだと思います。
水とだし、水と米との相性も大事です。食べものというのは、それ自体にたくさんの水を含んでいます。平均して60〜70%でしょうか。食パンは、あんなにパサパサしているけれど40%も水分があるんです。
ご飯は、多分60%以上が水。だから、私たちが食べているものは、圧倒的に水なんですよ。ですからその水に癖があったり、においがあったりしたらいかんのです。
おいしい水にちょっと昆布のだしが出ただけで、うま味がすごく感じられるという、非常に繊細な文化が育まれたのです。そのセンスを、私たちは意識しなくてはいけないと思います。
日本の風土には米の栽培が適していたのです。ヨーロッパにはデュラム小麦という硬質小麦があります。これはパスタしかつくれなかった。イタリア人がパスタが好きだから、デュラム小麦を栽培したのではなく、これしかできなかったのです。日本の米の文化と同じです。
なぜ日本人がだしのうま味を好んだかは、わかりません。しかし、小さいときから慣れ親しんだ味が、引き継がれてきたんじゃないでしょうか。
食べ歩き番組のレポーターを務めたこともある俳優の渡辺文雄さんが、最後の晩餐に選んだのは、飯ごうで炊いたご飯。炊き上がったら蓋に取って醤油をかけ、もう一度焼いて、それをおかずにご飯を食べる、というものでした。醤油の焼けた香ばしさやおいしく炊けたご飯を好む、日本人らしさ、お米の持つ力が、よく表われている話だと思いました。
残したい日本の味
外国人にとって、日本人が長寿で健康なのは、米と魚を食べているからだと思っているようです。つまり、日本型食生活が注目されているのです。
米と魚が主役ですから、世界で今流行っている日本食は、寿司です。彼らは酢漬けの魚は食べ慣れていますから馴染み易いのかもしれません。
しかし、物足りないのでしょうか。一緒にハンバーガー風の寿司などを出す店もあります。まあ、日本の回転寿司も同じような状況ですがね。
日本料理のもう一つのベースに、塩味がありますね。ご飯に砂糖をかけてもおいしくない。ご飯には塩が合うのです。だから高血圧傾向が出る。そこでだしを利かせると塩が少なくてもおいしく感じて食べられる。二重の意味で、だしは健康につながっているのです。
以前、来日したフランス料理のシェフに「あなた、日本食で自慢できるもの、残すべきものはなんだと思いますか」と聞いたことがあります。
そうすると、一つは魚だと。これだけ多くの種類の魚を、いろいろな加工法で食べているのは日本だけだと、彼らは言うのです。
もう一つは野菜です。
健康が注目されている今、どちらも自分たちの調理法に取り入れていきたい食材である、と。
魚はそれ自体にうま味がありますからいいとして、野菜はインパクトがない。それには、だしが重要ですね。
健康な生活を送る上でも、野菜を食べたほうがいい。しかし、野菜は生で出されたら食べにくいものです。300gの生野菜をどーんと出されても食べられたものではない。でも野菜は茹でたり煮たりすれば、柔らかくなるし、かさも減るし、おいしく食べられるようになる。
だしは、このように野菜をおいしく多様に食べるために、非常に効果的なのです。郷土料理に野菜は欠かせません。その煮方はその地方の文化や伝統から生まれたのです。それが「お惣菜」です。
メリハリを利かせて
だしの利いたおいしいものを食べようとしたら、手間がかかります。働く婦人が増えていますから、普段の食事のときに、じっくりだしを取った手間のかかる料理はつくりづらいでしょう。
家庭からだしが衰退したのは、一つにはかつての家事労働がキツかったからです。昔は女性だけが、そのキツい仕事を担っていました。そこから解放されることは、ある意味で生活の豊かさの実現であったのです。
簡単な焼肉料理は満足度も高く、豊かさを感じさせるものがあります。
私は、アメリカで2カ月間単身赴任生活を体験しました。そのとき誓ったのは、車で通勤して帰途には必ずスーパーマーケットに寄って買い物をして、自分で食事をつくることでした。
その結果、おいしいからほとんどが野菜と肉の炒めものでしたね。手の込んだ料理は、つくるのが大変であることを実感しました。
せめて、日曜日か正月かだけでもいいから、だしを引いて、手の込んだ日本料理をつくってほしい。子供たちも、小さいうちから食べ慣れていないと、外国人のように、野菜や魚介類をおいしいと思えない味覚に育ってしまうのが心配です。
音楽のことで言いますと、たまには劇場に行ってオペラを楽しむ。そういう贅沢は、暮らしの中で必要なものです。
同じように、ときには一流の料亭に行ってリッチな気分に浸って、心がリセットされるのも良いことです。しかし、料亭の食事ばっかり食べていたら、飽きてしまうでしょう。
家庭料理のおいしさと、料亭でのおいしいものは違います。しかし、おいしいものを求める気持ちは同じです。
家庭料理の良さは、毎日食べても飽きないところにあります。それは味つけが一定でないので同じ味にならないからだ、という人もおりますが、それだけではありません。
例えば、肉じゃが。我々はよく味が染み込んだほうがおいしいと思いがちだけれど、実は味が染み込むと全部が同じ味になっておいしくない。特に市販のお惣菜は、つくってから時間が経っていて、全体が同じ味で味に変化がないから、すぐに飽きてしまうのです。
プロの料理人も3分の1ぐらい染みているのがおいしいんだ、と言っています。染み込んだところと、まだ染みていないジャガイモそのままのところがあるから、おいしいんです。しかも、薄味です。
最近、家庭では味が濃くなる傾向があり、子供たちは濃い味に慣れてしまい、薄味だと物足りないと感じています。子供たちの要求に応えられるのは、焼肉でありハンバーグかもしれないけれど、慣れていくことでだしの味をおいしいと感じるような人間に育ってほしいと思います。
精神論ではなくて
子供たちの箸の持ち方も変わりましたね。みなさん、実験で使うピペットをどう持ちますか? 私たちが学生のころは人差し指で空気量の調整をしました。30年あまり前にアメリカに留学したとき、あちらでは手が不器用な人が多く、親指でやっていた。親指を使ったほうが楽ですが、デリケートな操作ができないんです。
日本でもいつからか、親指でピペット操作をする学生が増えてきました。しかし、それでは作業の合理性も悪いのです。
だから箸の正しい持ち方も、しつけという風にとらえないで、作業の合理性という切り口で教えていったらいいと思います。
日本人は器用で真面目で勤勉で、といわれてきたけれど、本当はそうじゃないのかもしれません。努力したから、器用で勤勉であったのかもしれません。
今の風潮として、楽な方向に流れて、無理をしないで気楽に過ごせればいい、何で努力せんならんの? という若者が多いんです。でも、それは違うと思います。
安易に物事を進めないで、高い志を持って、自分自身から逃げないで、正直にやっていってほしい。周りが便利になって、努力しなくても簡単に満足できる環境がいけないのかもしれません。
好みの問題、でも・・・
私は関西の人間だから、関東風のものは味が濃くて好きになれないんですが、それでも2つだけ関東風のほうがおいしいと思うものがあります。
一つは天丼。関西は天ぷらを白絞め油で揚げますが、関東はごま油。それに関西は汁をかけすぎる。汁かけ飯みたいなんです。
鰻丼も関東風のほうが好きです。さっぱりとしてメリハリがあり、冷めてもおいしい。
今まで食べた中で一番変わっていたのは、青森県津軽地方で食べたうどんです。変わっただし汁だったので厨房を見せてもらったのですが、小魚でだしを取っていました。生魚だったと思いますよ。そのだし汁に濃縮されたような醤油を調合していました。その辺り一帯は、みんな同じでしたね。
食べものの好みは理屈ではない。個人の自由。食べものの好き嫌いまで他人から押しつけられたらたまりません。わがままを通したいところですね。
しかし、こんなに日本人の食生活が豊かになったのは、つい最近のことなんです。海外からこんなにも大量に食材を輸入できるのは、日本が貿易収支の面で優位に立っているからです。
しかし、エネルギーや地球温暖化の問題で、これまでのような贅沢な食生活が続けていかれなくなるのはわかりきったことです。
日本と外国の食料自給率を比較したデータがあります。40年ほど前と現在を比べてみます。かつて日本の食料自給率が高かった時代には、イギリスやドイツは低かったのです。ところが国の政策として、これらの国は自給率向上に取り組んで成功させました。
食料自給率40%の国なんて、アラブの砂漠地帯や土地を持たないシンガポールを別にして、今までどこにもなかったですよ。
国が豊かになって生活レベルが上がると、人件費が上がります。当然のことですが、農家の収入も上がらないと、生活できずに離農せざるを得なくなります。
日本の高度経済成長時代に起きたことは、既にイギリスが経験済みのことでした。しかし、イギリスはそれを克服して食料自給率を上げることに成功しています。
人件費がかかる国内農産物は、価格が高い。だから、日本人は価格の安い輸入農産物をどんどん買うようになった。それで、今の農業の状況が引き起こされています。
食品加工というのは、本来、加工しないと利用できないものに施す技術です。お米は、粒食としてそのまま食べるのが一番効率的でおいしいのです。
そういう観点から、米粉のパンを批判的に見るむきもありますが、水田はいったん畑に変えたら、水田に戻すのは難しい。水田を維持するためにも、米の消費量を支えなくてはなりません。
なぜ残すのか
50年後に、大人になった子供たちが、誰も日本料理をつくれないようになったとしたら、ちょっと悲しいですね。
ただ、消えるべくして消えるのであれば、それもまた文化かもしれません。江戸時代と現在とでは、食べているものも調理方法も、ものすごく違います。だから残るものは残るけれど、消えていくものは消えていく。この先、日本料理が見直されるようになったとしても、外国料理からの影響を受けて、食のグローバリゼイションは進むでしょう。
しかし今日のように、世界中から好きなだけ食料を輸入するような状況は、いつまでも続きません。
この先、国内自給率は上げていかざるを得ないでしょう。国内で栽培できる農産物や近海で捕れる魚介類を中心に、日本の風土に適した食材を使わざるを得なくなります。牛を放牧することには、限界があります。
そうなると手に入る食材からいっても、本来の日本料理が持っていた調理方法や味つけが、見直されていくでしょうね。どうしても元の食文化、野菜と魚介類中心になり、必然的にだしを使った食生活になるでしょう。
そんな事態には、ならないほうがいいという人もいるでしょう。しかし、地球に棲む人間として考えたら、世界中から食べものをかき集めて贅沢をするよりも、地産地消に重きを置いた食生活のほうが、自然なのではありませんか。
そう考えると、将来のために、日本型の食文化を再評価して、継承していくことが大切だと思います。
禅宗寺院の山門前に、「不許葷酒入山門」(葷酒山門に入るを許さず)の碑があります。ニンニク、ニラなどのにおいの強い野菜や酒を寺に持ち込むなとの、戒めです。この仏教の教えの影響を受けて、「強い香りを生かした料理」よりも「食材を生かした控えめな味と香りの料理」を好み、おいしい水と癖のないご飯が、四季を愛でる日本人の繊細な感性と相まって、「だし」をベースにした日本料理を培ってきたと思うのです。