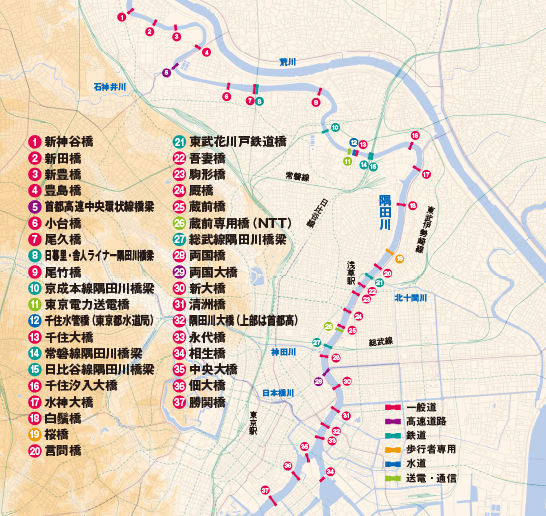機関誌『水の文化』47号
帝都復興における橋とデザインの思想

震災復興事業の第一号として1926年(大正15)に架けられた永代橋は、御年88歳。ペアでデザインされた清洲橋とともに、都道府県の道路橋として初めて、国の重要文化財(建造物)に指定されています。「構造物は、技術者の思想や創造性によってつくられている」という中井祐さんに、橋梁デザインの一世代を築いた復興局の働きと、その時代の橋梁技術者のこと、橋の持つ公共性についてうかがいました。
-

-
東京大学大学院教授(工学系研究科社会基盤学専攻)工学博士
中井 祐(なかい ゆう)さん -
1968年愛知県生まれ。1991年東京大学工学部土木工学科卒業、1993年東京大学大学院工学系研究科土木工学専攻修了。同年、株式会社アプル総合計画事務所入社、1996年東京工業大学大学院理工学研究科助手、1998年東京大学大学院工学系研究科助手、2003年同大学院専任講師、2004年同大学院助教授を経て2010年より現職。主なプロジェクトに、岸公園(島根県)、河戸堰と松田川河川公園(高知県)、片山津地区街路及び水生植物公園(石川県)、ベレン地区公園図書館(コロンビア・メデジン市)、被災者の心をつなげる場所と風景のデザイン[ヤタイ広場](岩手県)、竹田城下町再生のまちづくり(大分県)、岩手県大槌町復興支援(岩手県)がある。
主な著書に、『グラウンドスケープ宣言』(共著/丸善 2004)、『近代日本の橋梁デザイン思想 三人のエンジニアの生涯と仕事』(東京大学出版会 2005)、『GROUNDSCAPE〜篠原修の風景デザイン』(共著/鹿島出版会 2006)、『風景の思想』(共編著/学芸出版 2012)ほか
土木における橋の性質
日本における近代土木史には、お雇い外国人から始まるいくつかの段階があります。河川や港湾のように、日本固有の自然や風土、地形を相手にする分野では、比較的早い時期に欧米先進国の真似から脱して、日本の特徴に適合した技術が生み出されました。
ところが同じ土木の分野でも、その土地固有の自然環境が形を直接規定する度合いが低い橋のデザインにおいては、創造的なものが生まれづらいというハンディキャップがあったように思います。
それでも明治末期から昭和初期にかけて、橋梁デザインが隆盛を見た時代がありました。その気運は戦争へ向かう中で潰(つい)えてしまうのですが、私はその時代に実績を残した3人の橋梁デザイナーについて、『近代日本の橋梁デザイン思想 三人のエンジニアの生涯と仕事』(2005 東京大学出版会)という本に書きました。
3人の橋梁技術者
建築の分野では、丹下健三さんとか安藤忠雄さんとか、一般の人も名前を知っている建築家の名がいくつも挙がるかもしれません。しかし土木技術者、特に橋梁技術者のことをご存知の人はほとんどいないのではないでしょうか。
技術の歴史は、単に個々の工学上・技術上の歴史的事実の積み重ねではありません。技術史上の事実の背景には、必ず主要な役割を担った技術者が存在します。構造物は、技術者の思想や創造性によってつくられているのです。それにもかかわらず、従来は技術者の創造の根拠についてあまり言及されてきませんでした。
私が取り上げた3人、東京市の市街橋を手がけた樺島正義(注1)、帝都復興橋梁の設計をリードした太田圓三(えんぞう)(注2)と田中豊(注3)の存在は、日本の近代橋梁デザインにおいてエポックであると見なしていいと思います。
一番年長の樺島は、旅を愛し、風景を愛し、生涯一貫して風景のための橋の在り方を追求しました。樺島の考え方は、現代にも充分通用しますし、同じ風景デザインを志す者として深く共感できます。
私が最も思い入れを持った太田圓三は、夏目漱石とほぼ同時代の人で、漱石と同様の言質を残しています。確証はありませんが、若き日の太田は漱石が日本の近代化に苦悩する姿に共鳴し、日本の近代化の矛盾に直面しながら、土木技術者としての自我と格闘を始めたのだと思います。
最後の田中は、最も技術進歩主義的な思想を持ったエンジニア・アーキテクトでした。彼の設計には駄作がほとんどありません。永代橋、清洲橋、言問橋などの隅田川橋梁群は言うに及ばず、万代橋、総武線の一連の鉄道橋、田端大橋など、いずれにおいてもそのプロポーション感覚に一切のぶれがありません。
(注1)樺島正義(1878〜1949年)
東京帝国大学工科大学土木工学科で、港湾工学の父といわれた廣井勇(ひろい いさみ 1862〜1928年)の教えを受け、卒業後に渡米。カンザス市のワデル・ヘドリック工務所で4年半にわたり橋梁設計を修業し、帰国後に東京市の技師となり新大橋、鍛冶橋、呉服橋、神宮橋など多くの市街橋設計の実績を残した。1921年(大正10)には東京市を退職し、日本初の橋梁コンサルタントとされる樺島事務所を開設している。
(注2)太田圓三(1881〜1926年)
樺島の3年後に、東京帝国大学工科大学土木工学科を卒業。鉄道院に就職。1923年(大正12)の関東大震災直後に設立された帝都復興院(のちに内務省復興局)の土木局長に抜擢される。特に橋梁デザインに力を注ぎ、永代橋、清洲橋をはじめとする隅田川橋梁群の設計に尽力するも45歳の若さで自殺。
(注3)田中豊(1888〜1964年)
東京帝国大学工科大学土木工学科を樺島に遅れること12年後に卒業。鉄道院を経て、太田の部下として帝都復興院土木局橋梁課長に就任。のちに鉄道技師・復興局技師兼務のまま、東京帝国大学教授に就任し、後進の指導にあたる。日本近代橋梁史上最も著名な技術者であり、土木学会田中賞の名称の由来となった。
首都・東京の実状
明治から大正初期にかけて、東京は江戸という封建時代の城下町から近代国家の首都へとモデルチェンジを図っていました。それまでの履歴はすべて切り捨て、近代的なイデオロギーに基づいた都市、もっと言えば、国際競争に勝てる帝国主義的近代国家の首都にしていく必要がありました。
しかし、それはなかなかうまくいきませんでした。大正のころまでの東京は、橋を例に取ればほとんどが木橋です。しかも橋の手前で道が鍵型になったままのところも多かった。明治の市区改正でつくり替えられていたのは表通りなど目立ったところだけでした。生活の表面上は文明化しますが、都市インフラそのものは大正初期まで城下町のままだったのです。
夏目漱石は「日本の開化は外発だ」と言い、無理をした近代化を「ただ上皮(うわかわ)を滑って行き、滑るまいと思って踏張ると神経衰弱になってしまう。どうも日本人は気の毒と言うか憐れと言うか、誠に言語道断の窮状に陥ったものだ」と表現しています(1911年〈明治44〉に4回行なわれた夏目漱石の講演のうち、和歌山で行なわれた第2回講演『現代日本の開化』から)。
しかも国をあげて殖産興業を行なう必要がありましたから、地方の農村部の次男、三男が東京に出稼ぎにやってきました。東京をはじめとする大都市への人口集中は、既にこの時代から始まっていたのです。スラムに近い状態が至る所に誕生していて、そこを大地震が襲いました。時代が求めるものと都市の実質に生じたギャップを天災が突いた、という形です。
帝都橋梁にかける想い
ですから、帝都復興は単に地震被害からの復興ではなく、城下町江戸から近代都市としての帝都東京へと、都市の実質を変える一大プロジェクトでもあったのです。国が帝都復興にあれだけ力を入れたのは、こういう背景によります。
当時内務大臣だった後藤新平が、強いリーダーシップを発揮しました。復興を進める帝都復興院の中心に若い専門家たちを抜擢したことはその現れだと思います。
帝都復興事業における橋梁設計の特徴は、実に多様な橋梁形式が用いられたところにあります。中でも、隅田川六大橋(相生橋、永代橋、清洲橋、蔵前橋、駒形橋、言問橋)には、すべて異なる形式の橋が採用されました。帝都復興以前に樺島が行なった架橋は、地点の場所性や都市空間の文脈を重視するものでしたが、太田は「橋自身に内在する〈形〉の可能性」を追求しました。多様な形式の採用は、そのためだったのかもしれません。それは、西洋の物真似ではなく、オリジナルデザインを目指した結果だったと考えられます。
永代橋と清洲橋
復興局は115の橋を架けましたが、隅田川六大橋に使われた予算は全体の約3分の1。そのうち約半分が永代橋と清洲橋に用いられています。
清洲橋は田中がドイツ留学時代に実見したケルンの吊橋(1911年〈明治44〉コンペで選ばれた)をモデルにしています。これを忠実にコピーしたのは、当時の最新の構造を採用し技術的発展の布石としたいと考えてのことでしょう。
またケルンのコンペの上位3案の内の一つが、日本で最初に径間長100m超を実現した永代橋の素案となっています。このコンペ案は、清洲橋と永代橋をペアの橋デザインにすることにもヒントを与えています。
くぐるのも橋
私たちは今、陸の時代に生きていますので、どうしても〈つなぐ〉という観点で橋を見がちなのですが、川が中心の時代から見れば、橋は渡るだけではなく、くぐるものでもありました。
川を船で行くと、次々と現れる橋を次々にくぐる。その一連の感覚をどうデザインするかという意識が、おそらく帝都復興の橋梁デザインの時代まではかろうじて残っていて、その象徴が隅田川の橋なのではないでしょうか。
隅田川以外にも、たくさんの橋が架けられました。復興局だけでなく東京市も310もの橋を架けているのですが、例えば当時の舟運取扱量の1位と2位である外濠川と神田川は、ほとんどがアーチ橋となっています。想像ですが、たくさん船が通るからアーチにしたのかもしれません。
どのような橋を架けるのか、たくさん架けるときは橋梁群としてとらえてどうデザインするのかが考えられていた時代です。橋は陸の人のためだけではなく、川を使う人のためでもあるという発想。昔の人は、粋ですね。
標準設計を善しとした時代
土木に豊かなオリジナリティが発揮された時期もありましたが、私が大学で土木を専攻していたころは標準設計が目指されて、画一的な質のものをつくることが善しとされていました。設計の標準化というのは、誰がやっても同じクオリティを得られることを目指したものです。10人の設計者が同じ条件で設計しても十通りの土木構造物ができるはずなのに、同じものをつくって何が面白いのだろうと思って、土木に物足りなさを感じていました。
建築と比べて、土木は設計者に許される表現の範囲が狭いのですが、本来、狭いからこその工夫があると思います。例えば俳句は五七五という限界的な文字数で表現することが求められますが、奥深い表現に成功した名句もあれば駄句もあります。したがって、制約条件が厳しいからオリジナルなものや面白いものがつくれない、というのは違うと思います。
私は、いったん大学から出てデザイン事務所で働いたころ、歴史的な土木遺産に触れる機会があり、昔はダムとか川にもユニークなデザインのものがたくさんあることを知りました。明治〜大正ぐらいまでは、日本における土木構造物は鉄道などを除けば試行錯誤の時代であり、その過程で設計者や計画者の考え方が感じ取れるような土木施設がつくられていたのです。歴史的土木施設の勉強を少しずつ始めてみると、「なんだ、大学で教えてくれなかっただけじゃないか」ということがわかりました。
設計思想は、設計にかかわった人間や、その時代の状況とか価値観とかいうものに左右されます。その時代、その場所、その人だからこそできるものなのです。いちいちそんなことを考えていると効率が悪いし、均質なものを大量につくらなければいけない時代には、標準化を目指さざるを得なかったのでしょう。
空間スケールの大きさ
私が「土木も面白いな」と思い始めたのは、空間デザインのスケールが大きいというところに気づいたからです。建築は、敷地条件に合わせてグリッドで区切っていき、機能を満たす空間に仕立てていくわけですから、その敷地の中で完結しています。限られた空間の中でパズルを解くような仕事で、知的な面白さが得られます。
一方、土木は自然条件を相手にしなくてはなりませんから、すべてを把握することはできません。自然は、人間の思うようにはなりません。土木構造物が人間の想いを超えた自然とともにあるんだなあ、と気づいたときに、土木が非常に奥の深い世界であることを知りました。
二つの公共性を満たす
土木には、二つの公共性が求められます。
一つは寿命が長いということです。後世の人に少しでも良いと思ってもらえるもの、ネガティブな言い方をするとしたら、少しでも不快感を軽減するものをつくる責務があります。
もう一つは、私たちがどのように世界を認識するのかという〈図面〉を土木がつくっているという自覚です。実際に土木に携わっている人でも意識している人は少ないと思いますが、これは土木特有の公共性です。
いったん橋ができたら、つくられた場所からしか〈日本〉を見ることができません。逆に言えば、道や鉄道や橋というのは、そこから見た〈日本〉をデザインしていることになります。ですから、うまく橋をつくると〈日本〉という国は美しく見えるし、変につくると大したことがないな、と見えてしまいます。そういう意味での公共性を背負っているのが、土木構造物であるということができます。
言うなれば、国土は土木によって認識されるとも言えるでしょう。日本の自然と折り合いをつけながら、人間が社会を築いて生きていく。その姿は、たとえば道や橋や鉄道がないと、具体の風景として見ることはできません。言い換えれば、土木があってはじめて、私たちは国土の具体像をイメージし、理解することができるのです。
そう考えると、土木というのはとても大切な仕事であって、思想がなければできない仕事でもあると思います。ところが高度経済成長期には、思想ではなく効率が重視されて、まったく逆の方向へ行ってしまっていたのです。
最初にお話しした土木の標準設計というのは、まさに中央集権的な手法です。これからはそうではなくて、個々の地域が環境をつくる主体となって、知恵と工夫と思想を持って試行錯誤しながらつくり上げていくことが必要なのかもしれません。
帝都復興が示唆すること
社会的矛盾が際立ってきたときに自然災害に襲われると、一番の弱点がさらけ出される。日本の不利は、そういう地勢的条件というか宿命を持っていることです。
そういう背景を持っている日本は、やり方にしてもでき上がったものにしても、欧米に比べて柔らかい。近代化を目指していたときにはその柔らかさは価値を持ちませんでしたが、東日本大震災からの復興は、ある意味、そういった柔らかい都市インフラをつくり直すチャンスかもしれません。
とはいえ、日本だけ近代以前に戻って孤立するわけにはいきません。日本は明治以来、どんなにストレスフルであろうと涙をのんでつき合っていかなくてはいけない状況(グローバリズム)に対応してきたのです。
これからの国づくりは、日本独自の豊かさやそれを実現していく文化的パワーと、グローバリズムの両方を、どうやって折り合わせていくかにかかっているのだと思います。それにはかなりタフな精神力が必要で、そのタフネスを、我々日本人が持っているかが問われているのだと思います。
(取材日:2014年3月6日)