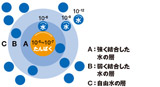機関誌『水の文化』58号

質にこだわらずにはいられない文化
── オリーブ・しょうゆ・ジェラート
(香川県小豆郡小豆島)

小豆島の高台から望むオリーブ畑と瀬戸内海
人口減少期の地域政策を自治体などに提案する中庭光彦さんが、「地域の魅力」を支える資源やしくみを解き明かす連載です。今回は瀬戸内海に浮かぶ小豆島を訪ねました。
-

-
多摩大学経営情報学部事業構想学科教授
中庭 光彦(なかにわ みつひこ) -
1962年東京都生まれ。中央大学大学院総合政策研究科博士課程退学。専門は地域政策・観光まちづくり。郊外・地方の開発政策史研究を続ける一方、1998年からミツカン水の文化センターの活動に携わり、2014年からアドバイザー。『コミュニティ3.0─地域バージョンアップの論理』(水曜社 2017)など著書多数。
映画『二十四の瞳』で一大観光地に
「当時の小豆島は、風光明媚ではあったが、丸金(まるきん)醤油とわずかの塩とオリーヴの実が生産されるだけで、訪ねる人は八十八ヵ所めぐりをするお遍路さんくらい、ガサついた東京から繰り込んだ撮影隊の眼には、風景は美しいが、全く文化果つる村という感があった。」
この「当時」とは1953年(昭和28)。木下惠介監督で大ヒットした『二十四の瞳』。主演女優の高峰秀子は、後年『わたしの渡世日記』で小豆島の印象をこう記した。この映画のヒットを機に小豆島は観光の島となった。あれから約65年。2016年の小豆島観光客は約114万人。オリーブ、しょうゆ、そうめん、佃煮と多彩な顔をもつ。ここにもいるオモシロイ事業者たちが、小豆島の魅力化へ突き動かした力は何か?
実は同じ発想のジェラートとカクテル
小豆島には土庄(とのしょう)港、池田港、草壁港、坂手港、福田港、大部港といくつもの港があり、瀬戸内海の中継点だ。各港まちが高松や神戸、姫路、日生、岡山と結ばれ、取引相手地との関係が共存しつつ、全体としては海に囲まれ隔絶しているという、中継点としての島によく見られる特徴があるようだ。
まず訪れたのは、草壁港の海沿いに建つしゃれた古民家店舗。昼間は若い観光客で混雑する「MINORI GELATO(ミノリジェラート)」だ。レモン、チョコといった定番商品のほかにもしょうゆ、生姜、アスパラといった地元野菜のジェラートが並んでいる。焼きナスのジェラートを食べたが、隠し味のしょうゆが甘みを強めうまい。
この製造を担当するのが市川雅史さんだ。東京でソムリエやバーテンダーとして20年間過ごし、2年前に移住した。小豆島の魅力を質問すると、「食材の豊かさがすばらしい。オリーブの木がそこらじゅうにあるし、レモンの木もある。瀬戸内の魚介類も独特で、東京で流通しない地元だけのものも多く、おいしい」と話す。
野菜は毎朝地元農家から仕入れる。形は悪いけど質はよい野菜を持ち込み「何とか活かせないか」と言う方もいる。そうしたいろいろな朝摘み野菜・果物を仕入れるのだが、なぜジェラート屋さんに?
「ジェラートとカクテルの発想は同じです」と市川さんは言う。
バーテンダーは即興的にその場の素材の持ち味を引き出しカクテルをつくる。それを液体として出すか、ジェラートとして出すかの違いだけで、実は同じというのだ。
「バーテンダーは素材をおいしく処理するプロ」。聞いて納得だが、これは素材からもっとも高い付加価値を生む仕事との意味でもある。
だからこそ市川さんの存在は貴重だ。自ら人気店を運営し、農家にとっては流通しづらい野菜・果物に価値を与える存在だからだ。
しょうゆの郷は「菌の郷」だった
「質が新たな価値を生む」という言葉が頭に浮かびつつ次に伺ったのが、「醤(ひしお)の郷(さと)」と名づけられたしょうゆ蔵の集積地である。しょうゆは小豆島の伝統的地場産業。小豆島醤油協同組合には14社が加入しているが、全国で一番木桶が使われている産地ということはあまり知られていない。ここで木桶のしょうゆにこだわり、木桶づくりまで手がけるヤマロク醤油五代目社長の山本康夫さんにお会いした。
蔵の入口から中を見ると両側に大きな木桶が並ぶ。驚いたのは、間近に見ると、桶がふっくらとした綿をまとっていること。「それは菌です。他のしょうゆ蔵とは菌の種類や生態系が違うそうですが、これがなくてはうちの味になりません」。綿の正体は菌だった。
「うちには桶が66本あります。人力で行なう攪拌は大変ですが、それをしないといいしょうゆにならない。菌がしょうゆをつくるので、攪拌はその手伝いです」という言葉を、私は桶の綿を見て納得した。
大きなステンレスタンクで醸造する場合、タンクは生産のための貯蔵容器である。しかし、ヤマロク醤油では、菌が棲む木桶と蔵、さらには菌が浮遊する島の風土を、うまいしょうゆをつくる資本と見なしているのだ。
したがって、山本さんに島でしょうゆ事業を続ける理由を聞くと「ここで木桶でつくるとうまいからです。木桶を残さないと孫、ひ孫の代にこの味がなくなる。うちで木桶づくりを始めたのは本物の味を残すためです。孫やひ孫が墓参りに来て、あの祖父さんの時に桶屋がなくなったからもうつくれんわ、と言われたら腹が立つじゃないですか」と言うのも当然だ。
とはいえ木桶は壊滅的な状況だ。山本さんは、大工の友人たちと木桶をつくりはじめた。材は吉野杉。たまたま島を訪れた吉野の林業者と出会い、取引が始まった。
一般に企業は年単位で収益を考えるが、しょうゆ屋は「代」単位で収益と循環を考える。山としょうゆの時間感覚に納得しつつも、山本さんという「質にこだわるおもしろい事業者(イノベーター)」がいるから、現在もうまいしょうゆにありつけていることにホッとしてしまう。
この幸運を生む構図は、オリーブでも同じであった。
オリーブの量ではなくあくまでも質で勝負
小豆島で本格的にオリーブが栽培されるようになったのは明治時代末期だ。日露戦争後、日本は北方漁場を獲得したが、そこで水揚げした魚介類の保存・輸送のため油漬けが必要となった。この油となるオリーブオイルを自給しようと、農商務省により1908年(明治41)、三重、小豆島、鹿児島で試験栽培され、唯一うまくいったのが小豆島。搾油がスタートしたが、1959年(昭和34)のオリーブ製品輸入自由化を機に、輸入品に押され生産は減少していく。
このような歴史をもつオリーブだが、現在は食用油や化粧品の原料として高値で取引されている。とかく作物そのものを売ろうとする傾向の強い日本の農業で、オリーブは少数派だろう。その経緯を農業法人井上誠耕園(せいこうえん)園主の井上智博さんに聞いた。
井上さんの祖父が柑橘の栽培に始まり、オリーブを植えたのは1946年(昭和21)。1964年(昭和39)に生まれた井上さんは若い頃、神戸中央卸売市場青果物の仲卸だった経験をもつ。1980年代前半、当時の小豆島の柑橘類は量が少なく弱小産地扱いされ、市場で買い叩かれていたのを見た。1980年代後半に井上さんは実家に戻るが、当時のオリーブ市場は小さいうえに先発企業が何軒かあり、参入しても商売にならなかったという。そこに転機が訪れる。
1988年(平成10)、井上さんは小豆島のオリーブ関係者の一員としてスペイン・アンダルシア州ハエンの生産地を視察した。そこで目にしたのは広大な敷地でオリーブが大量生産される姿。井上さんは「これは勝てない。いくら合理化しようと、小豆島中にオリーブを植えようと無理。量で攻められないなら、品質で勝負しよう」と決めたのだ。井上さんは、オリーブの木を三分割して、上部を「天成(てんな)り」、中部を「懐成(ふところな)り」、下部を「裾成(すそな)り」と名前をつけた。そして天成りの実を搾った極上モノとして化粧用オイルをつくった。
「おやじは百姓ですけれど、農業試験場の先生に『オリーブオイルは食べてよし、塗ってよし』と言われ、50年以上前に化粧品製造許可をとった。これはおやじの大金星ですね」と言う。
「商業ベースで見ると島はありがたい。よいイメージをもたれている。若いときは都会に行きたかったけれど、わかってくるとすばらしい島ですよ。そうするために先人がどれだけ苦労したのかが理解できる。この島を次の世代につないでいかないと」と言う井上さんは、小豆島の農地だけではなく、島の観光イメージも資本と見なしている。だからこそ観光客にオリーブに浸ってもらうためのレストラン・店舗をつくり、新たな小豆島のイメージを発信している。
ここにも質にこだわる事業者の姿があった。
質にこだわる競争と共存の島
地域資源という言葉を多くの人が使う。小豆島ならば、オリーブやしょうゆを挙げる人もいる。でも、今回わかったのは、頑固な事業者が農産品というモノに質を与えるために格闘して工夫したことで魅力が付加されている事実だ。まさに「質にこだわらずにはいられない文化」が小豆島にはある。
そして、三人とも「食材と風土のすばらしさ」を指摘する一方、「市場で埋もれてしまう危機感」という共通経験をもっていた。
瀬戸内海でゆるく隔絶された小豆島という中継地。そのなかに、対岸消費地との結びつきを背景にした競争と、事業を続けるのに必要な「質を高めるために、工夫せずにはいられない文化」から生まれる島内事業者の共存を読みとることは、いきすぎた想像かもしれない。しかし、質を高めるプラットフォームが生まれつつある小豆島は、現在に通じる地域づくりの先進例と私には思える。
〈魅力づくりの教え〉
質にこだわる、頑固でおもしろい工夫を施す事業者は、その土地を元気にする。
参考文献
香川県小豆島町『小豆島オリーブ検定公式テキスト』(香川県小豆島町オリーブ課 2008)
(2017年10月26〜28日取材)