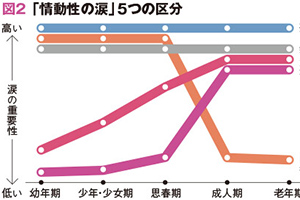機関誌『水の文化』22号
温泉の効用 ?
-
編集部
温泉偽装事件の裏にあるもの
有名な温泉地で、入浴剤を入れている現場を写真撮影され、日本中が「温泉もここまできたか」とショックを受けたことは記憶に新しい。未曾有の温泉ブームはまた、「源泉、掛け流し以外はニセ物」と決めつける考え方も生んだ。こうした期待に応えるだけの湧出量や温泉の質が維持できなくなったことにも、温泉偽装の誘因はある。
温泉湧出は、自噴と動力揚水に分かれているが、自噴の湧出量はほぼ横ばいで、1995年以降は低減傾向にある。一方、1970年には自噴とほぼ拮抗していた動力揚水の湧出量は、2003年には2.7倍に増加している。温泉の湧出量が低減したのは、過剰な動力揚水が原因なのではないかと疑われる理由がここにある。宿泊収容定員数は、同じ期間に1.75倍に増えており、動力揚水量の伸びとほぼ一致している。
温泉ブームが、温泉が枯渇するのではないかという危機感や、温泉偽装問題の要因になっているのは皮肉なことだ。
しかし入浴剤入りの温泉に浸りながら、日々の疲れを癒し、満足して帰っていた人が多いことを思い返すとき、一体日本人は温泉の何に癒されているんだろう、という疑問が頭をもたげる。
日本人はなぜ、温泉に癒されるのだろう
昔は、病気になったら民間療法か温泉が身近な解決法だった。病を治すために、長期間湯治に出かけることもあったから、温泉にかける真剣さは今日とは比べるべくもない。治療を目的とした療養や、労働の疲れを癒す保養が、かつての温泉に求められた主な目的であることは理解できる。だからこそ逆に、科学医療全盛の現代においては、保養はともかく療養が期待される割合が減っているのは当然だ。1泊ぐらいで、効能があるとは思えないからである。
そう考えると、温泉偽装を知らされたときに感じたショックは、温泉の効能についてではなく、もてなしや信頼感の心を踏みにじる裏切り行為を受けた、というところに根源があったのではないだろうか。
江戸時代に『養生訓』を書いた貝原益軒は、「汲み湯には気が無い」と書いたが、一方では「御汲湯」として温泉の湯を江戸城にまで運ばせた将軍もいた。1667年に4代将軍家綱は、熱海の温泉を真新しい檜の湯樽に汲み、江戸城までたびたび運ばせている。また群馬県・草津温泉の湯は、8代将軍吉宗によって「御汲湯」の栄誉を受けている。つまり、気を第一とする貝原益軒タイプの温泉ファンも、成分による効能を重視する徳川タイプの温泉ファンも、どちらも今に始まったことではなく、長い歴史を持つ。
加えて温熱作用、水圧作用、浮力作用、浸透効果、皮膚への刺激などの化学的作用による純粋な療養、転地療法による気晴らし、大浴場に浸かる解放感、仲間との非日常の無礼講、などなど、温泉の魅力は挙げれば切りがないほど広がっていく。
温泉を細分化すればするほど、「これこそが温泉の魅力の根源」と確信できるものから遠ざかる。はっきり言って「よくわからない」のが正直なところだ。
人たちの輪
とはいえ、温泉には今まで見過ごされてきたが「縁」を強める力がある。温泉を資源としてとらえると、量や温度といった物性や効能に目がいきがちであるが、鳴子の農民の家にしても、野沢温泉のスキー客にしても、旅先で出会った客同士、客と宿との間に親密な関係ができることで、魅力がより深まることがわかる。
しかし「縁」を強める効用が果たしてきた、もっとも大きな功績は村人同士の関係を築いていることだろう。野沢温泉村で道祖神祭りが続けられるのも、共有システムによる源泉の管理が維持されてきたのも、野沢組をはじめとする三夜講や湯仲間、スキークラブと幾重にも重なった「人たちの輪」の中で、信頼関係を構築しながら暮らしているからにほかならない。
本来、サロンのような閉じた人間関係は、排他的になりがちだ。しかし、小さな「人たちの輪」が、少しずつ重なり合いながら形作る大きな円は、相互の結びつきを一層深めるだけでなく、閉鎖性を緩和する働きも持つ。野沢でいえば、新しい湯仲間を加えない外湯でも、外部の人間が共同湯を使うことは認めているのがそのよい例だ。
もちろん、どこの地域でも湯仲間や、惣代による温泉の総有という野沢式手段が当てはまるわけではない。しかし、「何かを守る」という目的意識を持つために、その強い絆が果たしてきた役割から学ぶべきものは大きい。
資源が目的ではない
竹下政権が「ふるさと創世事業」(1988年)で地方自治体に1億円を配ったとき、多かった使い道が温泉掘削であった。しかし、活気のない町に温泉が出ればすべて解決するのだろうか。枯渇しそうな温泉を地域で守って復活させれば、あとは安泰なのか。それだけで解決しないことは、温泉という資源に頼り切って、例えば、もてなしの心という資源を持たない観光地が、衰退していくことからも明らかである。温泉のように価値の高く見えるものを持っていると、ほかのものが見えなくなってしまいがちだが、自分の地域にある資源は何なのかを意識することが大切だ。
地域には、さまざまな素材が眠っている。それを掘り起こして、価値が認められるものになったときに「資源」として意識される。今までは、その価値がすぐ金銭や市場原理に置き換えられ、そうでないものを認めない傾向があったが、資源というのは本来もっと幅広いものであるはずだ。
資源を何のために生かし、何を守らなくてはいけないかという、目的をはっきりわかっている「人たちの輪」は、資源に振り回されることがない。
活きている形に美しさがある
これからの温泉場は、その地域社会の「ハッピネス」のために、受け入れ可能なキャパシティも視野に入れることになるだろう。それは市場原理が優先してきた観光地としての温泉に、変化を強いることになる。
野沢のような生活の湯が残る温泉場でも、現在、花開いた黒川のような観光温泉場でも、共通しているのは、強い絆を持っていることだ。少子化による後継者不足や客の減少といった悩みはあるものの、自立して活気にあふれた温泉場は、訪れた観光客の目にとても魅力的に見える。
使い込んだ道具を美しいと感じるのは、その姿を通して、道具の持つ機能性や使っている人の人間性に触れるからだろう。同じように、ちょっと立ち寄っただけの観光客にも、人が活きている温泉地の使い込まれた外湯の美しさを通して、「人たちの輪」が感じとれるはずである。ここに、強い絆を持った集団が無形の資源となる秘訣が隠れている。
世代を超えて
温泉の魅力の根源は、はっきりとはわからない。とはいえ、なぜかみんなが魅力的に感じる。この事実は、「温泉だからできること」の可能性の大きさを指し示し、私たちに希望を与えてくれる。温泉が世代を超えて、大切に使い続けるべき共有資源であることには間違いがないだろう。しかも、「すべての日本人にとっての財産である」と言っても異論を唱える人はいまい。
観光客として温泉を訪れたときに、温泉を持つ地域で使い守る人たちと温泉を共有することで関係を築き、お互いの信頼感を高めることができていたら、果たして温泉偽装事件は起こったであろうか。共有資源である温泉をいかに使い続けるかは、他人事ではなく、私たちの問題でもあった。
温泉は、温泉を持つ地域で使い守る人、外から来る観光客というような区別がないことは言うに及ばず、まだ見ぬ私たちの先の世代とも共有していくべき資源である。
温泉は、地域も時間も軽々と超えてしまう大切な存在なのだ。
【麻布十番温泉】
東京・六本木の鳥居坂を下りきった谷間のビルの3階、4階が「麻布十番温泉」。写真でわかるように湯船は大きいものではないが、立派な大広間が備えられている。この日は大学のゼミが貸切っていた。1階にある銭湯「越の湯」も温泉。
都市部では、ほぼ100%内湯が完備したにもかかわらず、大変な賑わいを見せる銭湯がある。温泉ブームを反映して、深層地下水型温泉を利用した「スーパー銭湯」も大流行りだ。その逆に利用客の減少や、きつい労働条件のために後継者に恵まれず廃業をやむなくされる銭湯もある。そんな銭湯の代わりになっているのが、実はスポーツクラブの平日会員制度。利用時間や曜日の制限があるものの、大変リーズナブルな設定になっている。「仲間とサウナでお喋りするのが楽しみ。うちの風呂掃除をしなくてすむしね」という利用者も多い。