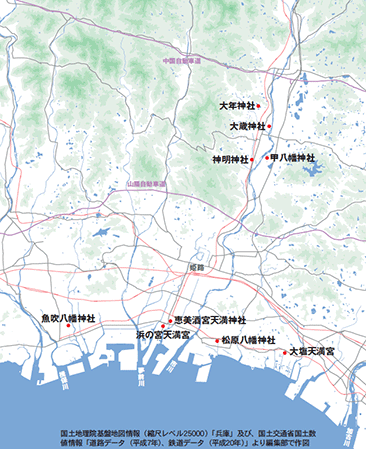機関誌『水の文化』37号
社会があるから文化がある

見るのと聞くのでは、大違い、ということが如実にわかる接待のための桟敷席。灘のけんか祭り本番の日には、祭りへの熱狂ぶりを表わす風景が、繰り広げられる。 写真提供:合田博子
失われゆく伝統文化〈祭り〉を守れ、といわれるととても危機感を覚えます。しかし、合田博子さんは伝統の創造なきところには、継続なし、と言います。 社会生活が失われたところには文化も残り得ません。形骸化した文化を保存するのではなく、生きた文化が創造される社会を強くすることに、祭りが寄与できることはなんでしょうか。
-

-
兵庫県立大学環境人間学部教授
合田 博子(ごうだ ひろこ)さん -
1946年生まれ。東京都立大学大学院社会科学研究科博士課程単位取得中退、社会人類学博士(東京都立大学)。
主な著書に『宮座と当屋の環境人類学』(風響社 2010)、論文に「山・川・海をつなぐ水陸両用の神々と水の技術」(桑子敏雄編『日本文化の空間学』東信堂 所収2008)、「入が池と丹生都比売」(岡田真美子編『地域をはぐくむネットワーク』昭和堂 所収2006)、「森を守る法・森を破壊する法」(橋本政良編『環境歴史学の探求』岩田書院 所収2005)ほか。
開かれて閉ざされる
村の神社は、いわゆる産土(うぶすな)神で神主さんもいないことが多いので、祭りのときに働くお当番が当屋(頭屋)です。
当屋の仕事は大きく分けて二つあります。場合によっては、神主さん、宗教者の代わりを務めます。地域や時代によって差がありますが、長い所では1年間、少なくとも1カ月は水ごりをするんです。海のそばだったら、潮水で。1カ月から1週間前になると、夫婦の営みも断って。
もう一つは直会(なおらい)。祭りのあとには、必ず神との共食があり、そのご馳走を全部まかなったのです。
村落共同体の維持には、集会と神聖な慣行が大きな意味を持ちます。祭りは、村の一層の共同と合意を図るために有効な手段だったのです。
当屋に当たることは、名誉なことであると同時に、経済的に大変な負担です。それでも、その負担に耐えられる家であることを見せるためにも、引き受けていました。
今でも都市のど真ん中に、当屋が続いている所があります。姫路の北平野という所で、姫路獨協大学のそばです。浜のほうから見ると少し高くなった辺りに北平野があって、薪で炊事をした時代には、夕餉(ゆうげ)の煙が上がるのが見えたそうです。ところが祭りの日は当屋の家からしか、煙が上がらない。朝、昼、晩と40戸からの全員に食事を振る舞ったといいますから。
ですから、〈開かれて閉ざされる〉と言いましたけれど、同じ村人でもある程度の力のある人でなければ、当屋は引き受けられないのです。
ですから宮座にも上層村人しか当屋になれない〈株座〉制のところがありました。逆に村人であれば、誰もが当屋になれる〈村座〉もありました。〈株座〉が先にあって、徐々に開かれていって〈村座〉になったのだろう、という説が一般的です。
当屋を経験した人は、村人として一人前と認められるので、やがて村長になったりします。村長になるような人が当屋に選ばれるという、逆の場合もあったでしょう。ただ、単にお金がいっぱいあるから当屋になれる、というものではないのです。当屋になるには、いろいろ条件があるのです。
専門用語に〈儀礼階梯制〉という言葉がありますが、段階を少しずつ上がっていって、地域の中で旦那衆として認められていくのです。これは、何も農村に限らず、都市の祇園祭りも同じです。責任と義務を果たすことができる、という資質を公に見せていったんですね。
特定の人がずっとやるわけではないので、一面だけ見れば、持ち回りのように見えますが、そこに〈開かれて閉ざされる〉原理が働いています。持ち回りというのは、〈開かれている〉一つの形ではあるのです。それは〈村座〉の在り方に表われています。
しかし、もっと前の段階には、村人にも格があって、嫌な言葉ですが水呑百姓とかいわれた階層があった。その人たちが、もしも当屋になりたいと思ってもできなかったはずです。
〈内部で資格を持つ者の間にある平等性〉は、外部に対する閉鎖性でもあります。これは、より広域での〈市場の論理〉に抵触するのですが、そこに〈宗教的なるもの〉を介入させる。〈宗教的なるもの〉は、私権ではなく神につながるので、閉鎖性が破られる、と考えられます。
かつて存在したイエの家格などは、封建的と否定されて平等になっていったように見えます。
しかし、今でも基本的には本家の長男が資格を持っている。分家ができてそこの長男にも資格を与える場合もありますが、増えては困るという所は、宮座を複数つくっています。
つまり、本家の長男だけが所属する宮座と、分家しか所属できない宮座です。長男、という条件はいつでもついて回るんですけれど。そして分家のグループには別に何々座、という新しい名前をつけて、お手伝いのようなことをやらせています。やはり、そこには序列ができます。ですから、開けているように見えて、構成員を選んでいる。
組織って何でもそうですよね。フェミニズムの団体だって最初は女性しか入れない、黒人解放運動も最初は黒人しか入れない。入る人の条件を狭めていますよね。それがやがて世間に認められるようになると、「こんなことをしていたんじゃ、世間に認められない」といって開いていく。
だから、いきなり広げるということはできなくって、その組織がきちっとするまでは閉鎖的。でも閉鎖的のままだったら広がっていかないから、開いていく。しかし、ある時期にまた、必要に迫られて閉じていく。実はオープンに見える〈村座〉にも、本当に平等な〈村座〉というのはないんですよ。
中核村人であった家でも、未亡人になったとか、後継者がいないとかの場合は、「今回は休みね」とか「半人前」と言われて順番を飛ばされます。これが続くと、本当に弾かれて、当屋から抜かれることもあります。
国内に目を向けるきっかけ
私は兵庫県立大学の環境人間学部で、環境人類学を担当しています。もともとは文化人類学者として、フィリピンとかインドネシア、ベトナムを研究していたのです。社会組織の研究とか、結婚のルールなどを調べていました。
その東南アジアの研究の中で、地元には独自の慣習法があることを知りました。その人たちにはルールがあって、ちゃんとした法律にはなっていないけれど、慣習法となっている。暮らしの中の慣習法というのは、いわば不文律なわけです。
日本の祭りに興味を持ったきっかけは、兵庫県立大学の前身のうちの一校、姫路工業大学に1998年(平成10)環境人間学部が設立されて、そこに着任したことにあります。
兵庫県立大学というのは2004年(平成16)に神戸商科大学、姫路工業大学、兵庫県立看護大学の兵庫県立の3大学を統合して誕生した大学なのです。
フィールドワークというのは人類学なら当たり前ですけれど、そうでない学部で必修にしている学部というのは、当時はなかった。私は文化人類学者だから、そこを担当させられたんですね。でも、毎年必修だから、大勢の学生を海外に引き連れて行くには無理がある。それで国内でできる所を探しました。
自分でも国内、それも本州は全然やっていなかったんですが、急遽、播磨(はりま)をフィールドにしました。そして、祭りをとっかかりにすると入りやすいから、まずは祭りから入ろうと考えました。文化人類学というよりも民俗学ですかね。でも祭り自体を研究するというよりは、現代社会全体を見ようとしたところが文化人類学的です。
2年生の必修だったので、1年目は暇でしたから、まずは自分が先に研究しておこう、と県に申請して「自治会組織と現代の地域集団及び祭り集団との関係」というようなことを研究テーマに据えました。
それで、姫路の灘のけんか祭りの調査をやりました。ここは播磨の気質が色濃い所で、ポンポン会話が弾んで面白い。私はもともと東京出身で早口なので、播磨のポンポン言う人と気性が合ったようです。
姫路・灘のけんか祭り
農業は衰退しても、青年団や消防団が継続する地域はあります。しかし、続いてはいるものの無理矢理やらされている、という感覚で、祭りも隔年になってしまったり。そういう地域と、灘のけんか祭りは、どこが違うんでしょうか。
ダメになっている祭りもあるのに、なんでここだけこんなに盛り上がるのか、と思いますよね。やはり屋台合わせという見せ場をつくったことが大きいのかもしれません。以前は、余興みたいなこともたくさんあったんですよ。そういう余興がまだ残っている地域もあって、そこでは女の人も祭りに参加できます。しかし、灘ではそういう余興をカットしていって、男っぽい、非常に荒々しい祭りに特化していった。それは明治以降のことといいます。
この地域の祭りは、10月の初旬から始まって、最後は23日の網干の魚吹八幡神社で終わるまで次々と行なわれます。でも、一番有名なのが、姫路市の南東部に位置する旧7カ村で行なわれている灘のけんか祭りなんです。
祭りの日には、公務員だろうがサラリーマンだろうが、みんな公休を取るんです。盆も正月も帰ってこなくても、祭りには帰ってこいよ、と。
「もし、祭りに帰ってこなかったらスゴイ噂が流れる」と言うんですね。帰ってこられない所にいる、と言われるそうです。外国かな、と思ったのですがそうではなく、刑務所にいると思われるそうです。
祭りにかかわるきっかけになるのは、子供です。子供の学校区と神社の範囲が一緒なんです。灘中学校区というのは、江戸時代の村だと7カ村に相当していて、それが松原八幡神社の範囲。ここは旧・社格の郷社で明治後も県社になった、結構大きな神社なんです。
その7カ村が旧・東山とか旧・松原とか、いまだに昔の名前で出ているのです。歌謡曲に、そんな題名の歌がありましたよね。
現代自治会組織でありながら、祭りの日には江戸時代の氏子集団、村落組織が、顕在化するわけです。
灘のけんか祭りの場合は、特殊な例かもしれません。農村と違って、祭り以外でその集落が結びつく必然性がありませんから。しかし、祭りがあるお蔭で、各家の家族編成とか、普通では細かく知ることができないことまで、わかります。ですから、NPO活動などへの協力も、祭りをきっかけにして積極的になっているように思います。
祭りは10月14、15日で必ずしも土日にならないのですが、だからといって祭りの日にちを変えたりはしていません。ウィークデイに当たったときには、小中学校は休みになります。高校は休みにならないのですが、灘地区では、「あの地区は祭りになると東から西にインフルエンザが流行するね」と言われています。高校生は、もう神輿(みこし)の大事な担ぎ手なので、先生も黙認というか。できるだけ中間テストの時期に当たらないように、とか、灘では学校も祭りに協力しています。
いろいろなところでサポートがあるんですよ。みんながやりたいから、自分たちの裁量の範囲で、自然にそうなっていく。小中学生は、16日の朝は、始業を少し遅らせてゴミ拾いをしています。
灘地区の自治会は、祭りが近くなってくると掲示板に「誰某さん、村入り」とあって「酒1升持ってきた」と書いてあったりします。今、宮座・当屋はないですが、自治会でも祭りと密接にかかわっているからなのか、古いそういう風習が残っている。普通の自治会ではそこまでしないと思うんですが。
逆にいえば、今の自治会には「魅力がないから入らない」と言う人もいます。だから、そこまでされても、入りたくなるような魅力を自治会が持っているということで、これも祭りの恩恵でしょう。
水をもらった感謝
中世の水帳(みずちょう)というものが残っていて、どれだけ他所(よそ)の地区から水をもらったかが、きちんと記録されています。それに対しては米何俵かをお礼に贈っているのですが、そういう具体的、経済的お礼だけではなくて、祭りのときに接待しているんですね。
灘でいまだに旧村の結束が固いのは、こういう歴史的な積み重ねが生きているからかもしれません。
私がそれを類推できたのは、滋賀県の琵琶湖周辺の宮座の研究がヒントになったからです。
灘でも地域の人がちゃんと研究していて、自治会発行の本まで出ていて。そのお蔭で私も中世のことがわかったんです。
水の利用の範囲と祭りの当番地域が、実は重なっているということは、そこから発見しました。井戸のある所から神水を汲んだとか、当番から外れた地域からも馬を出したとか、何らかの協力をしてもらっています。そこは現在の祭りの当番地区ではないですが、水を媒介とした歴史的つながりがあった所なのです。
水の慣行というのは、水源に近い地域が一番力を持っていて水を先に取ってしまうわけではありません。特に、井堰(いせき)や溜め池といった人工構造物によって水を得る場合、水源に近い地域だけでは、それらが維持できないんです。ですから、それにお金を出す人が現われる。そうすると、水源であってもそっちに水がいかない場合もある。土地の地形的な上下関係が、そのまま社会的な上下関係にはなり得ないんですね。
そういう事情を反映して、水をもらったり、何らかの恩恵をこうむった人たちが、もらった人に対して接待している。
彼らは接待の場というのを設けていて、昔はお旅所といって、神社から少し歩いて行った所に段々畑があって、コロシアムみたいになっています。江戸時代から桟敷(さじき)があったかどうかはわかりませんけれど、呼んできて接待しています。そこの前のすり鉢状になった所で、一番の見せ場である屋台のすり合わせというのをやります。
元はみかん畑か何かだったようですが、今はもう、作物はつくらないで、設けた桟敷席の畳何枚かのスペースを、1年1回のために何十万円か出して借りるんです。
みんな、そこを借りたいんですが、数に限りがあるから、持っている人に余程のことがないと、新たに借りることもできません。接待ということで、信州の御柱祭りと共通するところもありますね。
最近は神社の境内にも野球観戦のようにボックス席をつくって売り始めました。1席5万円で何十倍、という競争率みたいです。すぐに売り切れちゃう。実際、こういう席でないと、見れません。危険ですしね。何年かに一度は死人も出るほどです。
今は県知事とか市長とか、芸能人を呼んだりするのですが、当時だって取引上のお客はいるはずなのに、そういう経済的なつながりのある人たちだけではなく、水で恩恵を受けた相手にお礼をしています。
祈願に代わる地域愛
もう農業はやっていないし、ここで神様にちゃんとしておかないと来年収穫が望めない、なんていうことは、現代人はもう考えていません。実は、自分たちがやっているのは何神社の祭りかさえ、知らない人もいるんです。さすがに神社の名前は知っているけれど、「神様はなんですか」と聞いても、「知らん」と言う人が多いほど。
では、その人たちは何を求めて祭りに参加しているのでしょうか。私は、その人たちが地域を愛していて、地域を住みやすくしたい、と思う気持ちで動いているのだと思っています。
そして子供たちに、「ここに住んでよかった」と思ってほしい。どんどん他所に出て行っても、祭りになったら帰ってくるような場所であってほしい。本当のふるさとだ、と。
そのふるさと感覚が持てて、地元に生きている人間が同じ地域の人間であるというつながる気持ちを、せめて祭りの日には分かち合いたい、と思っている。
非日常(ハレ)のときだからこそ、それを感じていると思います。しかし、それが単に守るためだけに形だけやっていたんでは、そういう気持ちも出てこないでしょう。
祭りの魅力は一言では言えませんが、あるおじさんに密着して取材していたときに、「普段は、こんにちはって言って終わりだけれど、祭りの日はもっとゆっくり話ができてうれしいじゃないの」と言ってくれました。そういうことを感じているんですよ。
民俗学や文化人類学でも、祭りは地域を統合する機能がある、といわれていますが、現代でもそういう働きは続いています。
現代の組織は、意識を持っていつでも入れて、いつでも抜けられる集団になる傾向があります。社会学で、アソシエーションと呼ぶ組織のことです。
そういう中では、責任感と目的意識を持った、非常に限られた上に立つ人たちだけが会を運営している。下のほうの構成員は、義務を課すと窮屈がって辞めてしまいます。ですからNPO法人などをつくっても、みんなが目的意識を共有しないと、なかなか活動が活発にならない。
ただ、人が用意したものを消費者的に享受する楽しみではなくて、汗を流して、クリエイティブなことをするというのは、やはり楽しいはずです。
祭りはある意味、とても面倒なことを強いられるけれど、かつてはそれでつながっていないと入会の山が利用できなかったり、流域の水路を利用できなかったり、地域の中で生きていかれない現実があった。草刈りは面倒だけれど、その草は貴重な肥料になったわけです。ですから義務と権利の関係が、絶妙なバランスであったと思うのです。そういう意味の輪っかができていた。リサイクルじゃなくてサイクルがね。
日本では〈職の体系〉(上から下へ次々と土地の管理などを請け負わせていく中世以来の体制)が統治の論理の根本にあったから、西欧でいわれるようなコモンズの悲劇は起こりません。入会地はローカルコモンズとして、循環の仕組みが構築されていたのです。
モノも行為も輪っかになっていた、そのサイクルが断ち切られた現代で、何をすれば新しいサイクルができるのか。そのヒントが祭りに隠れているような気がしています。
社会化する機能
もう一つは社会化。ソーシャリゼーション。子供が大人になっていく過程で、どうやって社会に適応させていくかという問題ですね。赤ちゃんのときは条件反射のようなものですが、その次にしつけ、学校教育、社会教育・職業教育といった段階があって、その場、その時に応じて社会化していく。
自分たちが生まれた社会の中で、自然に身につけていくので、その社会の人間になれるわけです。今は家庭も崩壊していたり、学校教育に頼れないような状況にありますけれど、祭りのときは社会化がスムースに行なわれるんですね。私が調査を始めた十数年前は、茶髪とかロンゲが流行り始めたころでした。高校を卒業して大学に進む子も入れば、職人さんになる子もいる中で、中学のときにお友達であっても、普段はなかなか話す機会もなくなっていく。しかし、祭りのときは、彼らが一緒になって神輿を担ぐんですよ。茶髪の子に親がやめろと言ってもやめないけれど、祭りの長老が「やっぱり祭りのときは角刈りにしよう」と言ったり、たとえ言わなくても自発的に角刈りにしてくる。
それが岸和田のほうでも同じ現象が起こっているようで、〈だんじりカット〉と呼ばれています。
普段は暴走族に入っているような男の子でも、力持ちだったり、面倒見がよかったり、そういう場の仕切りに優れていたりして、見直されたりしています。彼らも、普段は発揮する場がないのですが、祭りのときにはその能力が光るんです。逆に有名大学に行ったり、一流企業に入った人でも、そういうことができなかったりね。
〈連中〉という特別のグループがあって、大人になってからも友人関係をずっと続けています。
ちゃんと続いている良い祭りには、必ず、こういう人間関係があります。
祭りも伝統の創造
親戚とかたくさん来て、自分の家に入りきれないから、みんな旅館に泊まるんだそうです。だから、毎年、予約で埋まっていて、調査のために泊まろうとした旅館には、最初は断られたんです。それで布団部屋でもいいから、と言って無理に泊めてもらったんですが、お風呂もなければご飯も出ないよ、と言われて。
ここはもう、観光客なんか、相手にしている場合じゃないんですよ。確かに観光客は来ますけれど、地元の人の知り合いがいないと、本当の見せ場とか面白さは理解できないような祭りなんです。チェーンのコンビニとかは開いていますが、商店街、全部しまっちゃいますからね。
観光客の多さでいうと、祇園祭りなどが典型ですね。しかし、あれも商店街のイベントとしてやっているのではなく、やはり祭りとして地域の氏子である商店街の人がかかわっているのではないでしょうか。
イベントであってもそのときに感じられる高揚感は、祭りと共通すると思いますが、私はイベントと祭りは、別だと思います。○○サンバ祭りとか、○○阿波踊りとか。
本場の阿波の阿波踊りはいいんですよ。一太郎をつくった株式会社ジャストシステムがわざわざUターンしてね、新入社員は連で踊るんだそうですね。そういう郷土愛がある。
もちろん出発点はイベントであっても、それが引き継がれて歴史になることはあると思いますが、○○阿波踊りが果たして50年間続くかどうか。
では、イベントと祭りの線引きはどこにあるのでしょう。祭りが既に神事としての意味を持たなくなった現在、祭りが持つイベントとは違う力というのは、なんなのでしょうか。
神事が本来持っていた意味、農業だったり、漁業だったり、生業と結びついていたから保たれていた意味みたいなものが、現代においてどう変換されていくのか。それはやはり地域愛、郷土愛なのかもしれません。イベントであってもそういう気持ちが想起されて、毎年来たいと思わせるようになったら、祭りと呼んでもいいかもしれません。
ですから、やはり祭りというのも、古いことをただ守っていたんじゃダメなんです。社会学や歴史学でもいわれていることですが、「伝統の創造」ということがないと、続いていかない。伝統もクリエイティビティの部分を革新していかなくては、守られない。
たとえ室町であろうが、平安であろうが、その時代の若い人は、その時代なりの革新的な考えを持つのですから、絶えず新しくなっていくんです。それを否定して、頑なに古いものを守ろうとした場合、それらは滅びていきます。
今、生きている祭りというのは、若い子供たちが〈祭りデビュー〉を待っている祭りです。
大人たちが伝統だからとか、文化財で守らなくちゃいけないからとかではなく、自分たちが楽しいから参加する、という姿を見て、子供たちが自分たちもやりたい、と憧れるんですね。
社会があって文化がある
祭りの役割を諄々(じゅんじゅん) とやってきた人が、「この人は仕事もできるし常識もある」と他から認められるようになって本物の村人として受け入れられていく。そういう人たちが、合議制に則った村の政治をやっていたんですね。
時代が下がってくると、小さな講が、弁天様や瀬織津姫(せおりつひめ)を信仰して溜め池や川の取水口などを祀るようになるんですが、本来は地域全体を統(す)べる行政としての村が、全体の一部として水神様を祀っていたはずです。
九州大学の河川工学者島谷幸宏さんからうかがったんですが、佐賀藩の鍋島家は、治水のこと、どこにどういう風に溜め池をつくったとか、水害の状況なんかもくわしく記録しているそうです。
島谷さんはかつて河川事務所の所長として、具体的な水利の技術とか、現状の川の在り方を聞きに行っていながら、気づかないうちに民俗学的なフィールドワークをしちゃっていたんですよ。それは民俗学の調査でもなく、河川工学の調査でもなく、いわゆる環境学みたいなものだったわけです。
私は近年、島谷さん、東京工業大学の桑子敏雄さん(環境哲学)、兵庫県立大学の岡田真美子さん(環境宗教学)とチームを組んで、さまざまなプロジェクトに取り組んでいます。領域を超えてつなぐことで、同じ情報からでも今まで見えなかったことが見えてきました。この4人は他の仲間とも一緒に、まるで旅の一座のメンバーのように活動しているんですが、島谷さんも「今までは、地元の人の話の中に神様のことが出てきても、その神様がどういう位置づけにあるのか、わからなかった。でも、この一座で話していくうちに、そのことが重大な意味を持っていることに気づいた」と言っています。
文化人類学では、地元の情報提供者のことを、インフォーマントというんですが、地元の人は一次インフォーマントで、島谷さんは私の二次インフォーマントになってくれたんです。それで、一緒にまた現地を訪れたり。
このような領域を超えた視点が、これからの社会に新たな発見、示唆を与えられるような気がしています。民俗学というのも、本来、祭りなどの民俗を通して、現代に示唆を与えるものだと思います。過去のことを掘り下げるところで止まってしまってはいけないのです。
近年、祭りは保存すべきものとして、また文化財として保護されています。補助金も出るし、地元の人たちは改めて価値を再発見する。しかし、それはお仕着せのものにしか過ぎません。
地域というのは社会集団なんです。しかし、ともすると、〈社会〉が抜け落ちて〈文化〉だけが一人歩きする。アメリカや中国、ベトナムなんかでも少数民族の文化を守ろうとして、国も補助金を出して文化が続くことを奨励します。しかし、その人たちのコミュニティ、社会組織まで復活しちゃうと分離独立しちゃうとか、デモになるとかいって、制限する。
祭りは芸能としてすごく援助するのに。しかし、文化だけ残ることなんてあり得ない。その人たちの社会が生きていないと、文化や祭りも続かないのです。