機関誌『水の文化』64号

ひとしずく(巻頭エッセイ)
蒼いダイヤモンド

降り積もった雪が自らの重みで氷となり、じりじりと動きつづける氷河。
融ければ水として流れ、海に落ちれば氷山として漂う 撮影:石塚元太良
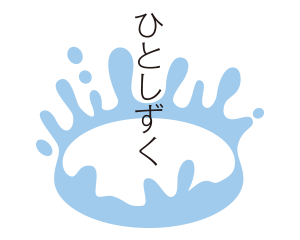
-
写真家
石塚元太良(いしづか げんたろう) -
1977年東京生まれ。10代のころから世界を旅行しはじめ、1999年バックパッカー旅行をしながらアフリカを縦断し、アジアを縦断しながら撮影した『Worldwidewonderful』でエプソンカラーイメージングコンテスト大賞を受賞。8×10などの大型フィルムカメラを用いて、独自のイメージを提起している。近年は氷河、パイプライン、ゴールドラッシュなどをモチーフにアラスカやアイスランドなど主に極地方でランドスケープを撮影。
氷河は読んで字のごとく、氷が河のように流れている様のことを言うが、実際の氷河の風景を見たことがない人にはあまりピンとこない話であるに違いない。
山頂に残り続ける万年雪は、自らの重さで山の中腹にかけて、ズリズリと横滑りを続けていく。日本のように冬と夏の寒暖の差が激しく、夏の間に十分にその雪や氷が溶けてしまうほど暖かければ、氷の流れは断続してしまうが、アラスカの太平洋沿岸部の山岳地帯や、スイスのアルプス山中など、一年を通して氷点下を保っている環境下では、氷とてその自重で山の斜面を削りながら、流れ続けていくのだ。
その流れがやがて海まで続き、氷河の末端が崩落していく様を海岸氷河というが、現在、言われているように氷河はその後退が著しく、僕が長年通い続けているアラスカの土地でも、かつての小規模な海岸氷河は今ではもう海まで到達していないというのが実際である。
僕が初めてそんな海岸氷河なるものを、アラスカで見たのは16、17年ほど前のことになる。雑誌の企画でアラスカ全般の撮影を依頼されたのがきっかけだった。
アラスカに行きたいが為に受けたオファーだったのだが、いかんせん編集部に潤沢な予算がなく、氷河の撮影に関しては、一般的な氷河クルーズ船などに乗り込む予算もなし。けれどどうしても氷河の絵だけは欲しいという要望で、シーカヤックをレンタルして、人力で海岸氷河までたどり着こうという、今考えると無理な算段だった。
地図を見ると、バルデーズという街からシュープ氷河とよばれるアラスカで最も街から近いその氷河までの直線距離は、約15キロほどである。
が、漕ぎ出してすぐにたいした距離ではないだろうとタカを括っていた自分の愚かさを何度も嘆くことになる。風と潮の流れ(氷河のあるフィヨルド地形は干満の差が非常に激しいのです)に翻弄された僕は、一日では帰って来れず(もちろん野営の装備は持参して行きましたが)野生の熊に怯えながらテントで夜をあかす。
けれど、その時苦労してやっとの事で辿りついたシュープ氷河の、シーカヤックから仰ぎ見たその氷壁の美しさは、今でも忘れることができない。大自然が、その奥底に隠し持っていた神秘とでも言ったら良いのだろうか。4、5階建ての団地くらいの大きな物体は、当たり前であるがすべて氷で出来ていて、見たことのないような蒼いダイヤモンドのように澄んでいる。長い年月をかけて巨大な単一結晶と化した氷河の物体は、物質としてもとても強固で、紫外線に近い青色光線は氷河という物体を通過できないため、ただ蒼く見えるのだという。
また地球環境そのものは、途方もない時間感覚のなかで、数えきれないほどの前進と後退を繰り返してきたこの氷河というものに多大な影響を受けてきた。どんなに遠く離れていても僕らもまたこの大自然の奥底にあるこの蒼い巨大な物体と、深く繋がってもいるのだろう。
その時の撮影は、以来毎年のように氷河を撮影するためにアラスカへ渡航していることを考えると、写真家としての僕のキャリアを大きく決定づけることとなってしまったと言っても過言ではない。
対岸でシーカヤックを降りて、ひとり飽くことなく海岸氷河の末端の最も蒼い部分を眺めていると、曇天の空の下で、氷河は蒼と言わず、紫色にさえ見える時があるようだった。透過光に輝くその巨大なモチーフは、優れて写真的なモチーフであると、あのとき直感したのだった。




