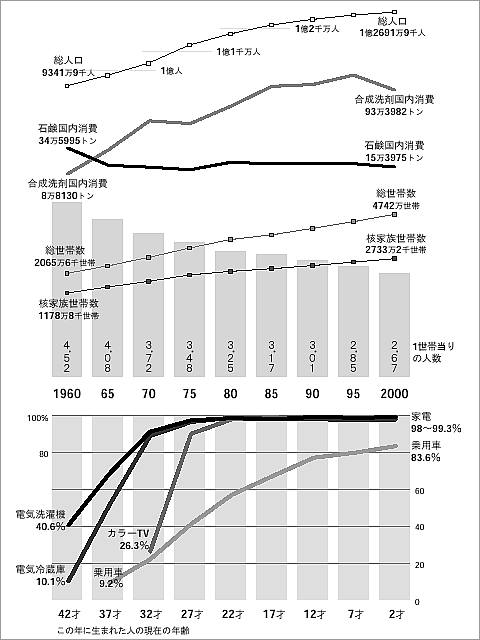機関誌『水の文化』11号
清潔感を洗う
-
編集部
「洗う」で何が見えてくるのか
京都・清水寺を訪れると、音羽の滝で水を飲む人々の姿を見ることができる。アルミのひしゃくを使い、みんなが代わる代わる水をすくい取って飲む、日本ではおなじみの風景である。しかしよく考えてみると、抗菌グッズが売れ、ミネラルウォーターに金を投じる時代になった現在、一方で他人が口をつけているひしゃくを汚いとも思わないのは、少し不思議な気がしてくるものである。人は、音羽の滝の聖性にそのようなことは気にならない力を感じるのか。それとも、多くの人が飲んでいることに安心感を覚えるのか。大いに気になるところである。
手を洗う、心が洗われる、身を浄める、布巾を洗浄する、垢を落とす、洗車をする、野菜を洗う‥‥。「洗う」という行為一つをとっても、そこには多様な「水とのつきあい方」が存在する。すべての文化が、気候、風土や地域、民族などの背景を持って形成されてきている以上、「洗う」文化も例外ではありえない。
今号のテーマは「洗うを洗う」。洗うことをいろいろな観点から掘り下げてみると、その多様性に驚かされ、それは同時に洗うという言葉の持つ多様性ともなってくる。これらを交通整理することで、重なりあって見えにくくなっていたものを浮き上がらせる試みをしてみた。洗うというからには、落とさなくてはならない「汚れ」があるはずだ。その落とす行為が「洗う」ことである。「洗う」が多様性を持っているのは、この「汚れ」に多様性があるゆえである。
2つの「汚れ」を洗う
1つは、単純な泥汚れ、油汚れ、垢じみた汚れなどである。汚れが落ちた状態は、目で見て「きれい」になっている。この汚れは不純物が付着したと考えられ、付着物の性質に応じた落とし方が開発されてきた。その手段、方法は、高度経済成長期に飛躍的に変化して、現在に至る。
もう1つは、「穢れ」(けがれ)である。穢れは精神性の汚れであり、宗教や信仰とも密接な関係を持つ。穢れが意識されると、その穢れを払う宗教的な機能も発達していったことは想像に難くない。穢れを払った後の状態は「清い」と表現される。
日本では清めの儀式に広く使われる塩は、実際に防腐効果も持っている。葬式の帰りに玄関先で蒔く塩は、「家の中に穢れを持ち込まない」と同時に「腐敗した死体、あるいは伝染病の死体に接したあとの消毒」のためでもあると考えられる。
この点について検討したのが文化人類学者のメアリー・ダグラスであり、今や古典となっている『汚穢と禁忌』(塚本利幸訳、思潮社、1995)(原題はPurity and Danger :An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo )やMary Douglas & Aaron Wildavsky,Risk and Culture ”(University of California Press,1983)の中で、リスク感覚と穢れと秩序の関係に注目している。
穢れたものは危険なものでもあったが、その穢れや危険と捉える感覚と意思決定は文化により異なることを指摘している。これを彼女は世界各地の原住民の生活等から導き出した。要は、「公衆衛生」観念が誕生する前は、安全の保証と「穢れを浄める」ことが、同じレベルで用いられていたのである。では、高度経済成長期に飛躍的に進化を遂げた、目に見える汚れについても追ってみよう
清潔感は新しい
私たちが常識と思っている清潔感の歴史は、実は意外と新しい。例えばフランスの社会史家ジャン=ピエール・グベールの『水の征服』(パピルス社、1991)を読むと、19世紀フランスの富裕層でも毎日身体を洗うことが例外的習慣であったことがわかる。お湯の入った小さな壺が運ばれてきました。
「今日はどこを洗おうかしら。」
「そうですね。」
アルザス出身の女中が、ためらいながら、お国なまり丸だしで答えた。
「顔にしますか、首にしますか」
「首ですって。だめよ。そこは昨日洗ったもの」
「そうですね。じゃ腕を肘まで洗ってはどうでしょう・それじゃ袖をまくってください」
ここには「清潔」を、ことさら気にする風情は感じられない。まあ匂いがしないぐらいに洗っておこうという程度なのだろう。水が豊かな日本とフランスでは比較できないだろうと思われる方も、日本の入浴史を見れば納得できるはずだ。入浴は日本でも日常的な行為ではなかったことに変わりはなかった。日本の風呂は、空間的にはハレの場として位置づけられており、現在に近い「きれいになるための入浴習慣」が現れたのは、近代風呂が家庭に普及する大正時代になってからのことである。
その風呂もけっして清潔というわけではなかったらしい。民族学者の吉田集而は『風呂とエクスタシー』(平凡社、1995)の中で、風呂の本来の用途をシャーマニズムにおける「恍惚感」を得るためと推測し、かつては「風呂に入る」ことと「きれいになる」という価値とは切り離されていたと述べている。
この大正時代頃からの風呂の在り方の変化は、家の間取りにも現れている。例えば、1910年(明治43年)に箕面有馬電気鉄道(現阪急電鉄)が大阪郊外の池田町で開発した住宅の平面図を見ると、風呂はどこも北の片隅の台所に隣接して置かれ、外から入るようになっている。外風呂が家に隣接しているという感覚だ。これが住宅営団(後の住宅都市整備公団)規格の集合住宅の間取り(1942年、昭和17年)になると、ほぼ現在の風呂のイメージと変わらなくなり、部屋の一つとしての内風呂になっている。おのずと、風呂の役割としての「ハレ性」は薄れ、部屋に求められる「清潔性」が風呂にも現れるようになってきた。どうも、風呂における清潔感覚の常識は、大正時代頃に端を発しているようだ。
それでは、洗濯はどうなのだろうか。
ライフスタイルの変化は清潔感を変える
ライフスタイルが激変すると、人々の清潔感も変わってくる。かくして洗濯の技術も、変遷を余儀なくされるのである。
かつては、ほどほどに汚れが落ちれば良かった。服の素材は綿が主であったし、油性の汚れも家庭ではそれほど多くなかったことだろう。ところが、洗濯機と洗剤が普及し、汚れが目に見えて落ちるようになった。なおかつ、その白さはきらきらと光る「真っ白」、漂白された白さであったし、青味付けして強調された白さであった。清潔な「匂い」もついていた。いつのまにか消費者は「白く」ならないときれいになったと思わなくなり、「きれい」を判断する術が失われていった。
「何を見て清潔と感じるか」という点について、スーエレン・ホイは『清潔文化の誕生』(紀伊国屋書店、1999)の中で興味深い指摘をしている。19世紀後半から、アメリカ人の生活の中で清潔感が衛生感と同じ意味で使われ、白もの信仰が蔓延するようになったというのだ。この書は、白もの信仰が、アメリカン・ライフスタイルと密接なつながりがあることを教えてくれる。
「清潔感」とは
ここまで何気なしに「清潔感」という言葉を使ってきたが、広辞苑の「清潔」の項には、「茶の湯は清潔にしてさはやかなるを本とし」という、1665年に浅井了意により書かれた『浮世物語』の用例が引用されている。清潔の「清」は「きれい」という意味で、英語の pure と beautiful の両方の意味をもっている。また、「潔」は、「潔斎」という言葉からもわかるように、心身の穢れを断ち、清浄を保つことを意味している。「茶の湯は清潔・・」というのは、この三つの意味がミックスされて用いられているのだ。ここで、冒頭で述べたきれいと清いが登場する。日本語の清潔の言葉の中には、両方の意味が込められているのだから、洗う概念が整理して受け止めにくいのもうなずける。
もう一つ「清潔」と同じ意味で用いられている言葉に、「衛生」という用語がある。おおざっぱに言うと、病原菌や有機物、有害物質などを限度以上に含まないことである。この「衛生観念」が広く日本に持ち込まれたのは、実は明治時代になってからのこと。衛生という言葉も、英語のhygiene を、長与専斎が漢字に直したものだ。
長与専斎といえば、幕末、緒方洪庵の適塾に学び、明治維新にあたっては岩倉遣欧使節に加わり帰国後は内務省衛生局長を歴任して、コレラ予防など日本における医療、衛生行政の設計者となった人物である。水道の整備も、元はと言えばコレラ予防が発端となっている。水道水には衛生的な意味で清潔であることが求められる。大腸菌はゼロ、一般細菌も規準以上含んではいけない衛生的な水道水は、結果として「安全さ」を保証した水となる。この「衛生的な清潔」は約150年前の明治時代になってから入ってきた観念だ。
衛生観念の誕生
そもそも、明治維新まで庶民と汚れの距離は非常に近かった。『洗う風俗史』(未来社、1984)の著者、落合茂は、江戸時代末期の洋学者佐久間象山による妻の心得を説いた言葉を紹介している。「夫の衣類をば心に入れて度々見及び垢つきたるをば濯ぎ清め、損ねたるをば取り繕い、いささか粗末なきようあるべし」(『女訓』)「夫の衣類が汚かったら、きちんと洗いなさい」と説いているのだが、わざわざ諭すぐらいなのだから、逆に暮らしの現場では汚れがごく身近であったことがよくわかる。
日本の洗剤の歴史について記した文献は数少ないが、その中でも秀逸なものに花王(株)が創業83周年記念に制作した『日本清浄文化史』(1971、非売品)がある。それによると庶民は灰汁などを石鹸の代わりに用いてきたが、文明開化の1873年(明治6年)には民間最初の石鹸工場・堤石鹸製造所が創業を開始。以後、続々と石鹸メーカーが現れ、日本中に石鹸が普及していく。「美洗粉」と呼ばれる現在でいうシャンプーも登場する。
大正〜昭和時代になると家庭生活も近代化し、1930年(昭和5年)に東京芝浦電機(現東芝)が国産電機洗濯機第1号(回転式)を発売する。これは1940年(昭和15年)までの間に5千台を製造したというが、庶民向けのものではなかった。
その後第二次世界大戦、敗戦、戦後復興をはさむこととなるが、何と言っても洗濯に革命的な変化をもたらしたのは昭和30年台の水道普及・家電革命・高度成長だった。高度成長によるライフスタイルの激変は、洗濯における清潔感をも大きく変えることとなったのである。
家電革命と家事省力化
まずは、水道の普及。上水道が日本の各家に普及したのは昭和30年代(1955年〜1965年)だ。1960年には約40パーセントだった普及率が、10年後の70年には80パーセント近くまで伸びた。
家に水道が引かれるまで、水がどこから来てどこへ流れていくのかということは、生活者と身近な関係にあった。しかし、上下水道の普及により蛇口と排水口以外に水は見えなくなってしまった。かつては、用途に合った水を、井戸、川、わき水、天水など異なる水源から求めていたが、現在は常に衛生的にきれいな水を、用途おかまいなしに水道が供給してくれる。
この水道普及に合わせるように、洗濯機も爆発的に普及した。世帯当たり普及率も1960年からのわずか10年間に倍増し、70年には10軒に9軒が保有するまでになった。
同様に、洗剤の消費量も爆発的に増えた。戦後の洗剤史は合成洗剤の時代とも言えるもので、その国内消費高も洗濯機と同様、急カーブで増加した。
まさに家電革命と言われた時期。それは特に主婦に何をもたらしたのだろうか。NHK放送文化研究所の『日本人の生活時間2000』(NHK出版、2002)は、主婦の家事時間(洗濯、炊事、掃除)の推移をまとめている。1960年、主婦は4時間26分を家事に費やしていたが、40年後の2000年には3時間49分と37分下がっている。
家電製品が女性の家事省力化をもたらしたことは確かだが、家事時間がその分減ったというよりも、むしろ、洗濯をしながら「掃除」「炊事」などをする、「・・ながら行動」が可能になった。このため、並列的に家事をこなすことができるようになり、家事の省力化が大いに進み、洗濯は手軽になった。手軽化したというとは、清潔な水を得ることも手軽になったし、汚れの程度を判断する必要もなくなったということだ。
清潔感のバランスを取り戻すことはできるのか
風呂も、洗濯も、洗いものも、トイレも、すべて衛生的な水道で得られる膨大な生活用水がまかなってくれる。そして、いつのまにか衛生的にきれいな水でないと、すべての用途に対しても満足できない人々が増大してしまった。このことは、衛生感が客観的な装いを持っているだけに、歯止めをかけるのが難しい。
しかし、こうした衛生感の膨張は、水道普及、家電革命など、かなり人為的な条件が重なり作られたものであることもわかってきた。ならば、時代に応じてわれわれ自身のライフスタイルやものの見方を少し変えてみることで、「洗うこと」における人と水とのつきあい方も変えることができるのかもしれない。
まず、自分たちが洗う場面における「清潔」感覚や、そこに使う水を点検してみる。洋式トイレの便座は毎回消毒しなくはいけないのだろうか。車は毎週洗わなくてはいけないのだろうか。売られている野菜には泥がついていてはいけないのだろうか。なぜ日に干した洗濯物の太陽の香りは心地よいのだろう。なぜ、なぜ・・求められる清潔感が一様でないことにちょっと気づくだけで、水とのつきあい方は違ってくるだろう。
第二は、水が地域の共有資源として認知されていると、自ずと「汚いものは出さないように」とか「無駄な水は使わないように」などと、水に気を遣うようになる。汚い水を排出しないようにルールも生まれるし、自分の水の使い方が地元に適しているのかチェックさせられる。滋賀県長浜市でつい10年ほど前までは井戸番が生きていたし、温泉をコミュニティとして守り管理している例は、地域として求められる清潔感を残していくことにつながるだろう。
第三は、衛生感覚が膨らみすぎた個々人の清潔感を、バランスのとれたものにする試みである。衛生観念の誕生は、明治からたかだか150年。それ以前は、経験値から得られたいわば生活の知恵の範囲内で、きれいな状態のバランスを保っていた。数値や流動する価値観に惑わされず、自分の物差しと余裕が欲しい気がする。
住宅の外壁を洗う商売があるが、付いた汚れは洗い流せても、外壁そのものが紫外線や風雨に曝されて変質してしまえば、その汚れは落とすことができない。これを「劣化」と呼ぶ。ところが面白いことに、劣化と同様に素材本体を変質させながらも美しく変身する例が「経年変化」である。
何百年もの歳月を風雪に耐えた神社仏閣の欅(けやき)の柱、はき込んで体に馴染んだジーンズ、髪の脂が染み込んで飴色に変わった柘植(つげ)の櫛。これらを劣化した、きたない、と感じる人間がいるとは考え難い。落とすべきものは汚れであるのだから、経年変化したものに落とすべきものは見当たらないし、劣化してしまった素材のきたなさは落とす手段が見出せない。したがって、これらは洗えない汚れなのである。洗う必要がないものまで洗うことを見直し、洗わなくてもすむものを使っていくことも、これからの時代は選択肢に入れるべきであろう。
清潔嗜好が助長されつつある現在、洗うことに欠かせない水が、いかに重要な存在であるかが改めて認識される。用途に合った水利用に気づくこと、水を共有財産として意識すること、きれいに対する自分の物差しを持つことの3つが、とりあえず今の段階で私たちができることなのではないだろうか。
清潔感が社会の水の消費を左右するならば、少しばかり「洗う文化」、「洗う感覚」を見直して、バランスの取れたものにしていきたいものである。