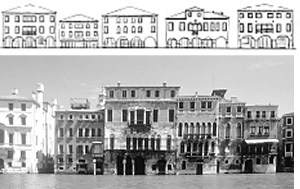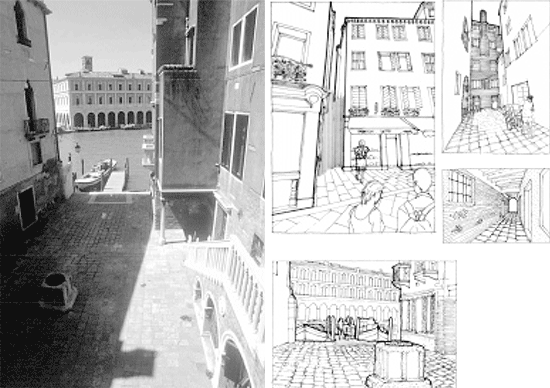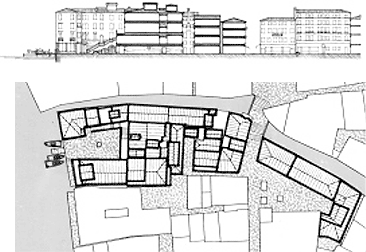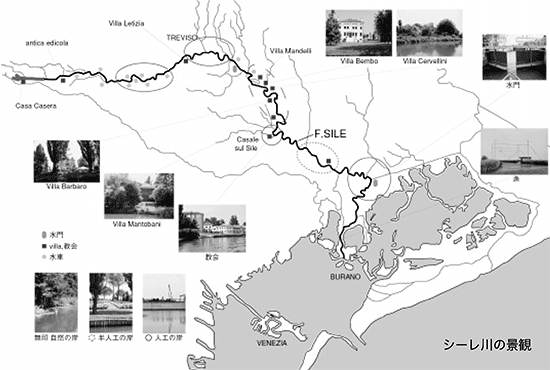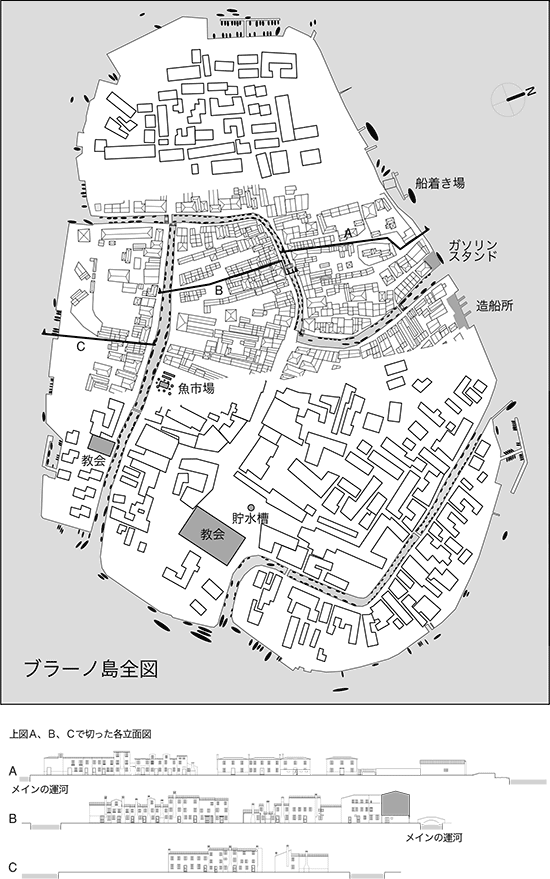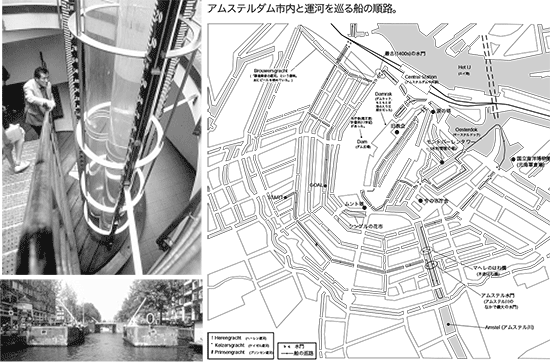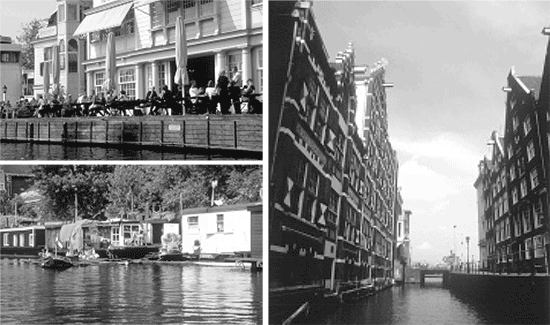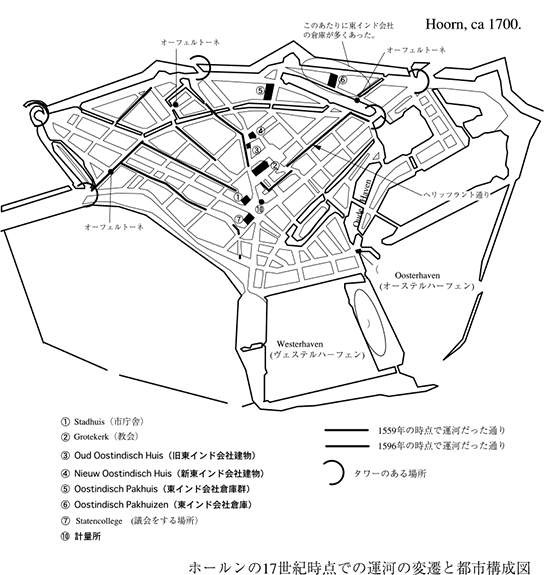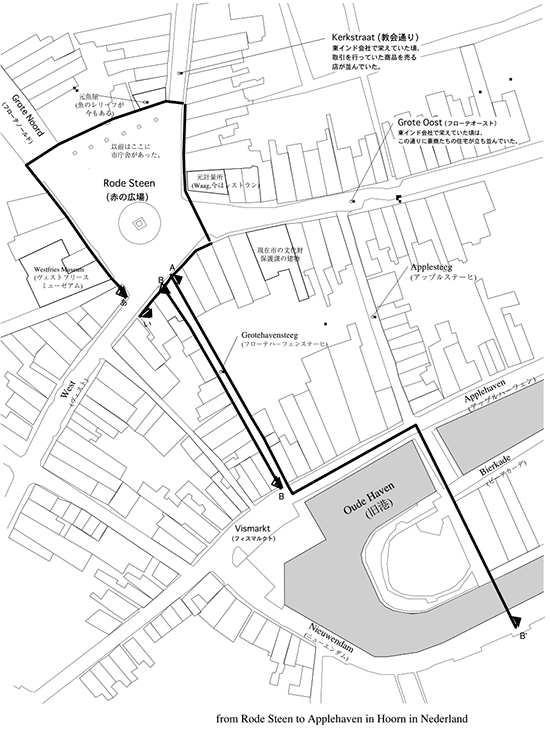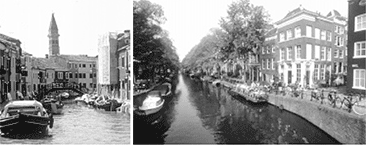機関誌『水の文化』8号
ヴェネツィアとアムステルダム水が彩る交易都市
-
法政大学教授
陣内 秀信 (じんない ひでのぶ)さん -
1947年生まれ。東京大学大学院工学系研究科建築史専攻修了。工学博士。1973 年イタリア政府給費留学生としてヴェネツィア建築大学へ留学。ユネスコ・ローマセンター、東京大学助手を経て1982 年より現職。専攻、ヴェネツィア都市形成史、イスラム都市空間論、江戸・東京都市空間論。サントリー学芸賞、建築史学会賞、地中海学会賞他を受賞。 著書は、『ヴェネツィアー都市のコンテクストを読む』(鹿島出版会)、『都市を読む・イタリア』(法政大学出版局)、『江戸東京のみかた調べ方』(鹿島出版会)、『水辺都市ー江戸東京のウォーターフロント探検』(朝日新聞社)、『ヴェネツィアー水上の迷宮都市』(講談社)、『都市と人間』(岩波書店)、『中国の水郷都市』(鹿島出版会)、『南イタリアへ!』(講談社)、『イタリア小さなまちの底力』(講談社)等多数。
-
岡本哲志都市建築研究所代表
岡本 哲志 (おかもと さとし)さん -
1952年生まれ。法政大学工学部建築学科卒。都市の水辺空間に関する調査・研究に永年携わる。丸の内・日本橋・銀座などの調査・研究プロジェクトに関わり、都市形成の歴史から、近代都市再開発の問題や都市の「定着、流動」と都市の活力や創造力の関係性を検証している。 著書に、『水辺都市―江戸東京のウォーターフロント探検』(朝日新聞社、1989年)、『水の東京』(共著、岩波書店、1993年)等がある。
欧米にも舟運で栄え、魅力ある風景や個性的な文化を形成した都市は数多くある。それらは大きく見れば、形成された時代背景、立地する地理的条件の違いで、四つのタイプに分けることができる。
第一は、地中海世界に古代、あるいは中世から発達した港町で、山や丘陵を背景にし、入江を持つ海に開かれた場所につくられている。イタリアの地中海都市であるアマルフィやジェノヴァ、そしてフランスのマルセイユなどがその典型例である。成立年代はやや異なるが、日本でいえば瀬戸内海の鞆や笠島が同じようなタイプといえる。
一方、ヨーロッパ大陸では、海運と同時に古くから河川交通によって、内陸舟運も発達していた。海や内陸からの物資の集散基地として、河川沿いに成立した都市も多く、これが第二のタイプである。イタリアでいえば、ローマやピサ、フィレンツェ、ヴェローナ。ヨーロッパを北へ上がればブリュージュが交易の都として繁栄した。日本では、大きな河川がある東日本に内陸舟運が発達した。最上川の大石田、利根川の佐原は、江戸時代の活発な河川舟運によって、川沿いに蔵造りの町並みをつくりだした。
ヨーロッパでは、浅瀬のある内海や、満潮時に海面下になる場所に築かれ、特徴ある「水の都」として発展した都市もある。これが第三のタイプで、水との戦いを克服できれば、不利な自然条件を有利な条件に転換することができる。つまり、直接、船で外海と結びつくことができるため、舟運による交易には極めて有利な条件に反転した。ラグーナに浮かぶヴェネツィアや低湿地に築かれたアムステルダムは、運河網を整備することで建設用の土地を確保していった。その結果、都市内部にはきめ細かく運河が巡り、それに沿って港の機能を備えるという「内港システム」といえるものをつくりだした。運河に沿っては倉庫ばかりか、華麗な様式美の建築が水辺を彩っていった。後には、都市の外部にも立派な港湾機能をつくるが、内部の運河・掘割を用いた舟運は活発に機能し、この水辺に顔を向けた建築群が都市の主役であり続けた。こうして「水の都」の輝きが持続した。かつての江戸や大坂、新潟も、こうした「内港システム」が発達した都市であった。だが、舟運が廃れるとともに都市内部の掘割の多くは埋め立てられ、水辺の活気が失われた。
一九世紀以降につくられた港湾都市は、「内港システム」をもつ第三のタイプであるヴェネツィアやアムステルダムとは全く異なる港の形態をとった。ニューヨークやサンフランシスコが示すように、外港に桟橋を発達させ、そこに大型船が接岸した。これが第四のタイプとなる。明治維新を迎えた日本でも、横浜や神戸に桟橋のある港をもつ都市がつくられていくが、都市内部には運河が巡ることはなかった。
私たちは2000年夏に「内港システム」をもつヴェネツィアとアムステルダムでフィールドワークを行った。この両都市はどちらも水と戦いながら形成されてきた歴史をもっている。しかし、それだけではなく、私達の興味をかき立てるのは、今も運河に船が行き交い、また水辺の環境が現代の人々のニーズに応えながら見事に活用されていることである。この点は、舟運が廃れると同時に水の空間が見向きもされなくなった日本の都市と大きく異なる。この二つの「水の都」の生き方から学ぶことは多いのではないか。
今回の調査で、私たちは両都市の周縁部にも目を広げてみた。ヴェネツィアでは、ラグーナの島に形成された居住地の古い構造を残すブラーノ島とキオッジアを調査対象に加えた。さらに、内陸との結びつきを理解するために、ラグーナに注ぎ込む幾つかの川の一つ、シーレ川をトレヴィーゾからブラーノ島まで船で下ってみた。
アムステルダムでは、東インド会社(V O C )(注1)の拠点が置かれた他の五つの都市が重要であると考えた。アムステルダムと北海を短距離で結ぶ北海運河が一八七六年に完成するまで、アムステルダムから北海へはザウデル海(現エイセル湖)を通った。行きはテッセル島で航海の水を補給して、偏西風を利用して一挙に南下した。帰りは、東方から荷を満載した船がアムステルダムに向かう途中、エンクハイゼンとホールンに立ち寄った。これらの港町は、東方から運ばれる物資の買付けの場として繁栄した。この二つの港町に立ち寄った理由の一は、ザウデル海が浅いため、物資を満載した大型船では船底が海底に接触してしまい、アムステルダムの港までたどり着けなかったことがあげられる。私たちはかつての東インド会社の拠点都市の一つ、ホールンの重要性を考え、アムステルダムとの関係を読み解くことをも意図し、調査に臨んだ。一七世紀の黄金期を迎える以前と以後では、アムステルダムの都市形成が大きく異なる。一七世紀以降、アムステルダムは幾何学的な都市へと発展していく。一方、ホールンは今でも一七世紀の港と広場の素朴な関係を示す都市形態を保っている。この対比も目にとどめてみたかった。
(注1)東インド会社(V O C )
連合王国東インド会社(Vereenighde Oost Indische Compagnie )1602年設立
地中海の交易都市・ヴェネツィア
ヴェネツィアでは、広場と教会が居住区の単位となっている。そして都市として成熟していく過程で、舟運と結びついて中心的な役割を果たす三つの場所と中心軸ができた。一つは、経済・商業活動の中心リアルト地区で、早くから市場が置かれた。東方貿易で繁栄する十二、三世紀には、東西世界を結ぶ金融の中心として重要性をもった。二つ目の場所は、海の表玄関サン・マルコ広場である。この広場に政治、宗教、文化の機能が集中する。三つ目は、海洋国家ヴェネツィアを支えた造船所アルセナーレである。そして、ヴェネツィアを貫くカナル・グランデは、サン・マルコとリアルトを結びつけ、運河の両岸に商人貴族の商館が建ち並ぶ「水の都」の象徴的な空間軸をつくりだす。この都市の構造は本誌第五号を参考にしていただきたい。
今回の調査では、観光化したこれら地域をあえて避け、カナル・グランデに直接面してさりげなく存在する小広場をもつ一画と、舟運が今も活きている運河に面する広場、そして庶民的な生活空間が広がる小運河沿いを選んだ。これらを調査すれば、生活という立場から、運河と町並みがどのような関係で成り立ってきたのかを探れるのではないかと目論んだのである。
ヴェネツィアの広場空間
ヴェネツィアというとまず誰もが訪れるのがサン・マルコ広場だろう。この広場はヴェネツィアの海の表玄関である。ヴェネツィアには共和国が計画的につくった公共性の強い広場として、サン・マルコ広場と、リアルト市場の中のサン・ジャコモ・ディ・リアルト広場がある。いずれも回廊で囲われているところに特徴がある。
時間にゆとりのある旅行者は、メインストリートや路地を歩き廻り、教会を核とした個性豊かなカンポ(広場)に出会うだろう。その数は七十以上もある。これらのカンポは、旅行者も気軽に通り抜けできる開放的な雰囲気を持つが、住民の生活と密接に結びつきながら長い年月をかけてつくられた場所である。
また、カンポの他にも、人目につきにくいカンピエッロ(小広場)と呼ばれる小広場も点在している。カンピエッロは、ヴェネツィアが観光都市としてだけでなく、現在でも生活の空間として息づいていることの証である。華やかなサン・マルコ広場やカンポ、そしてカンピエッロといった様々な広場の中から、今回は、そのうち舟運と深く結びついたカンポとカンピエッロを調査した。
住民と観光客が交差するサンティ・アポストリ広場
サンティ・アポストリ運河は、リアルト橋から近い距離に位置していることもあり、重要な幹線運河として古くから舟運が活発であった。その運河と結びついて、十三世紀に広場としての形態を整えはじめた。一階が運河に直接面した建物には、大部分が船から直接入れる入口がある。また、運河に面した一階部分を歩行者が自由に通行できるように「ポルティコ」という柱廊(地上部分を公共の通路として開放しているアーケード状のもの)にした十三世紀の建物カ・ファリエールが注目される。岸には三つの船着場がとられ、現在も使われている。広場には、観光客を対象とした土産物屋が並んでいるが、生活必需品を売る店も多く、住民がこの広場をよく使っていることがわかる。
このサンティ・アポストリ広場では船着場や広場を囲む店舗や住宅群、運河沿いのポルティコ、運河に架かる橋など、要素が立体的に交錯している。舟運機能だけでなく、都市の多機能が広場空間に重層的に凝縮されているのである。ヴェネツィアの住民が水と深く結びつきながらつくりあげてきた空間の一つの形を見ることができる。
広場の北側には、サンティ・アポストリ教会の鐘楼が堂々とそびえている。この鐘楼は、地域住民の精神的な柱であるばかりか、広場周辺のランドマーク的な役割も持っており、調査隊から離れてしまい迷宮都市に途方に暮れている時など、自分の居場所を教えてくれる格好の目標となってくれた。
広場の中央には、雨水を溜める貯水槽がある。運河の水は飲み水として利用できないこともあって、貯水槽に溜まった雨水が周辺住民の生活を支える重要な飲料水となっていた。ヴェネツィアの広場には、必ずこのような貯水槽が設けられ、かつてはそこに婦人たちの井戸端会議が見られた。
公共性の強い広場に面した建物は、一階部分を店舗や倉庫にし、二階部分から上を住宅にしている。一方広場から一歩プライベート性の高い路地に入ると、住居専用の建物に変わる。こうして広場周辺では公私の住み分けをもった住宅環境をつくりだしている。
レオン・ビアンコのコルテ
橋を渡らずにポルティコをさらに奥へと進むと、プライベート性の強いレオン・ビアンコのコルテ(共有の庭)に出る。もともとカナル・グランデに面するビザンチン様式の有名な商館カ・ダ・モストの裏側にとられたコルテにあたる。周りには住宅が並び、サンティ・アポストリ広場とは対照的に、人影もなくひっそりとしてる。このコルテに入る入口部分には、ブラーノ島で見られるゲートのようなアーチが施され、外部からの侵入を緩やかに排する空間の工夫がされている。
商館の奥側にこうして庭をつくるのはヴェネツィアの古い形式で、十三世紀頃に建てられた建物には多くみられた。その後ゴシック期に建築技術が発達してくると、建物の内部にコルテを設けるようになり、裏庭は次第につくられなくなる。現在では、商館の裏庭という性質は薄れ、小さな広場を囲む建物の住人のちょっとした共有空間となっている。
カンピエッロ
サンティ・アポストリ広場の次は、カンピエッロ(小広場)を見てみよう。私達は、リアルト橋に程近いサン・ジョヴァンニ・グリゾストモ地区を調査した。カナル・グランデに面する小広場カンピエッロ・デル・レメールは、入口部分が極端に狭く、一見行き止まりのような路地なので、島のメインストリートを歩いていても、教区教会堂の脇からのその存在に気づくことはない。
狭い路地を右に左に折れ曲がり、トンネルを抜けると小広場にでる。眼前には、カナル・グランデとリアルト市場の建物が広がり、驚くほどの開放感を味わうことができる。
カナル・グランデに正面を向けた建物は、十三世紀のビザンチン様式のアーチをもち(写真右下)、当時の主屋であることがわかる。その玄関は二階部分にあり、階段を上ってアプローチする。階段を使った華やかな空間の演出は、当時ここがカナル・グランデに面する一等地であり、商人貴族の館として建てられたことを物語っている。
このカンピエッロは、もともと個人の館へ入る表玄関の役割を持つ私的空間であった。物資の荷揚げに加え、主人や来訪者が船で出入りする場としても使われていた。奥の建物には住居空間のほかに、食料等の保管庫、倉庫が併設されていた。広場の中央に残っているビザンチン様式の井戸(貯水槽)も当時の趣を今に伝えている。
カナル・グランデに面して前庭のように小広場をとるのは、一つの古い形式である。その後水際に直接商館が並ぶ形式が登場し、この形式は唯一ここだけに残っている。
内陸とラグーナを結ぶシーレ川を下る
私達はイタリアの内陸にあるトレヴィーゾという町からブラーノ島まで、船でシーレ川を下る旅にでた。
水辺の風景の変化を眺めていると、岸辺の違いに気がつく。町から町へ船が移動する間には、鬱蒼とした森やトウモロコシ畑も見ることができる。自然のまま残されているもの、農地が侵食されないように土手が築かれているもの、そして町の近くに見られる石やコンクリートで護岸が整備されているものの三タイプがーレ川を下って最初に目にした町は、カサーレ・スル・シーレである。船からは、教会がまっ先に視界に飛び込んでくる。船長の話によると、この教会はかつて川側に正面が向けられていたというが、現在は道路側に正面入口がつけ替えられてしまった。教会が川側に顔を持つていたことは、いかに舟運が重要であったかを教えてくれる。教会を核として成立した水辺の町には、川を行き来する船乗りたちが休憩するレストランやホテルの機能も備わっていた。
シーレ川沿いには、舟運・産業に関連する施設だけでなく、ヴィッラ(別荘)が見られる。船から見える十五世紀のヴィッラ・バルバロ= ガッビアネッリや十七世紀のヴィッラ・ベンボ= トルツォ、十八世紀のヴィッラ・ファニオ= チェルヴェッリーニなどの別荘は、ヴェネツィアの貴族のためにつくられた。川辺の別荘は、文化が栄えたルネサンスからバロックの時代のヴェネツィアの建築様式で建てられている。建物の正面はいずれも川に向けられており、航行する人々を意識してデザインされている。
ラグーナが近くなると比較的大きな町が見え、閘門がラグーナとシーレ川を隔てている。閘門は川の水のレベル差を調節する装置であるが、通船をコントロールする役割も担っていた。この町には船の修理工場がある。船が運行する場所には舟運関連の施設が欠かせないことがわかる。
ラグーナの原型の町ブラーノ島
ブラーノ島は、ヴェネツィアから約六・五キロ、船でラグーナを小一時間揺られた場所にある。ブラーノは、小規模ながらもレース編みの島として昔からヨーロッパ各地にその名前を広めてきた。レース編みは女性の仕事で、島の男性は主に漁師としてラグーナに出ていく。
この島の特徴は、家ごとに異なる鮮やかな色で塗られた壁にある。この島に降り立つと、赤や緑、黄色に塗られた家はイタリア特有の突き抜けんばかりの青空に映え、まるでおもちゃ箱をひっくり返したように楽しげな風景をつくりだしている。
私たちは、つい鮮やかな色の家々に眼を奪われてしまうが、運河の両側に沿って建物が並び、ほぼ等間隔に奥へ路地が入り込む形態はヴェネツィアの都市発展の初期段階を暗示すると言えなくもない。ブラーノは、ヴェネツィアをはじめとするラグーナの島々の中でもっともプリミティブな町の構造を残す、小粒ながらも重要な島なのである。
島内には三本の運河が通っている。島の中央を蛇行する運河の両側には道が付けられ、途中からは広い道となって島の核である教会まで延びている。この運河と道がブラーノ島の骨格をなす軸となり、それらに沿って密度高く建物が連続したファサードをつくりだしている。運河沿いには、今ではレース編みの店や土産物屋などの店舗が軒を連ねている。教会に伸びる道には、レストランやカフェが並び、目抜き通りとして島の人々や観光客でにぎわっている。
建物が連続して町並みを形成するメインストリートでは、極彩色のファサードが特に効果を発揮し、人々のにぎわいを楽しく演出しているように見える。このような場所では、建物のファサードの連続性を損なわないように、景観の配慮がされている。裏手の広場に通じる路地の入口部分に、建物の入口と同じ大きさのアーチをつくっているのである。それによって、公共性の強いメインストリートとプライベート性の強い奥の空間との住み分けを巧みに行っている。調査のために、アーチを潜り、トンネルの暗がりを進むと、プライベートな領域に踏み込むような感じを受ける。
トンネルを抜けると、メインストリートのにぎわいとは対照的に、静かな空気が流れていた。地区の玄関的な意味を持つトンネル、その先に延びる路地、奥に広がる広場は、セットとなって周辺住民の共有空間をつくりだしている。調査中も、家の前の広場で魚を焼いたり、掃除に余念のない主婦、椅子を路地において休んでいる老人の姿を見かけた。玄関と広場との間にはほとんど段差がないので、主婦が家の前の路地や広場を同じモップで清掃している姿を目にする。
ブラーノの広場は、家のリビングやキッチンの拡張空間として使用していて、生活と密接に結びついた空間をつくりだしている。住民の広場の共有意識は、住宅の使い方にも現れている。ヴェネツィアの住宅では一階部分を倉庫や店舗にし、メインフロアが二階以上にあるのが一般的である。だが、ブラーノでは一階部分をメインフロアとして使用する特徴がある。住宅には台所の炉の出っ張りがある。その炉が一階部分から突き出していることから、一階部分がメインフロアであることがわかる。ブラーノの住宅は、壁の色を除けば数少ない住宅のデザイン要素が煙突であり、広場空間を巧みに演出している。
島の南側にもメインの運河から分岐した運河がある。その運河の南面には建物があまり建っておらず、運河に開かれるようにして空地が幾つもある。地元住民達の裏庭的な役割を担っているようだ。その空地を利用して、魚や野菜の青空市場が開かれる。商品が売れてしまうと、何も無かったようにもと空地にもどってしまう簡易な市場だ。この運河の先には、周辺住民のための小規模な教会が建っている。
ブラーノ島の中心にある運河から南の方へ歩いてきたが、外に行くほど住宅の密度が低くなる。この外へ広がるように発展していった都市の形成プロセスは、ヴェネツィアとよく似ている。だが、海側にまでファサードを形成するヴェネツィアに対し、小さな漁師の町であり続けたブラーノは海側に町並みを形成することはなかった。この島はプリミティブな形態を保ち続けて今日に至っている。
A 島の北側に位置するAでは、メインストリート沿いに建物が連続して建っている。路地を抜けて海の方へ向か うと、建物が徐々にまばらに分布しはじめ、メイン運河から外へと発展してきた過程がよくわかる。メインストリートへと続く路地を歩くと、住宅の壁面が連続する途中にアーチ上のトンネルがあり、さらに路地を奥へ引き込んでいるのを目にできる。集住し、高度利用する徹底した空間づくりの知恵を見てとれる。A地区の住宅の規模は他の地区と比べて若干大きく、比較的ゆったりとした居住空間となっている。特に海に近いフェンスに囲まれた住宅は、規模が大きい。庭には多くの木が植えられ、緑豊かな印象を与える。ブラーノ島のなかでも高級住宅地に属すと思われる。 車が存在しないブラーノ島では、船が生活には欠かせない。移動・運搬、そしてもちろん漁のための足なのである。海辺付近は運河沿いと比べると静かだが、この場所に限っては、外からの観光客を乗せた大型船の船着場や船のガソリンスタンド、造船所が隣接し、船の往来も多く、舟運と深く結びついた活気ある場所となっている。
B 島の中心に位置するBは、他の地区と比べると、家の区割りが細分化している。メインの運河に近い方では、三層の住宅が隙間なく建てられ、高密化している。人口密度が低いブラーノでは、基本的にひとつの建物に一世帯が住む。だがBにだけは、珍しく集合住宅も存在する。この地区を足がかりに、ブラーノが発展していったことが推測できる。 メインの通りから、路地を抜けて住宅に囲まれた広場に出る。中央には水飲み場があって、暑さでカラカラに乾いた石畳に清涼感を与えている。夏の暑さのせいか広場周辺に人の姿はない。だが、路地や広場には自転車や椅子、干した洗濯物がひるがえり、生活の匂いがあふれだしている。 C 島の南側に位置するCでは、運河沿いに連続して建物が並ぶものの、他の地区のように、路地を引き込むことはあまりない。その代わりに、海に面して一面に広がる芝生の空地がある。日向ぼっこをする住民や漁のための網を干す漁師の姿が見られ、島内の裏庭的性格を持っていることがわかる。木々が植えられた広い空地は、同時に島の住民がくつろげる空間でもある。
Cに面する運河沿いは、観光客の数も減り、町並みも静かな佇まいを見せている。運河沿いのレストランも、ゆったりと落ち着いた雰囲気を漂わせている。このレストランは、運河沿いの歩道いっぱいにテーブルを並べ、オープンテラスとなっている。人通りの少ないこの地区だからこそ出来ることであろう。夏の日差しのなか運河とそこに揺れる小さな漁船を見ながらの食事もきっと気持ち良いに違いない。
漁港の町として生き続けるキオッジア
キオッジアは、ヴェネツィアから南西に約三十キロ、陸地に張り付くようにラグーナにせりだしている。この町は、ヴェネツィアと同じく活気のある「水の都」であるが、日本からの観光客がこの町を訪れることはあまりない。キオッジアでは今でも漁業が活発である。周辺の広い運河沿いには、中規模の漁船が停泊し、今もイタリア国内における漁業の中心基地の一つに位置付けられている。
キオッジアの漁業の歴史は古く、五世紀に蛮族の侵攻から逃れてきた人々が住み着いた時に始まった。キオッジアが本格的な漁業の町になるのは、この辺り一帯で伝染病や飢饉が広まり、大きな被害を受けた十五、六世紀頃からである。それ以降、ヴェネツィアや内陸の町に魚を供給することで都市の再生を図ったといわれる。十四世紀にヴェネツィアとジェノヴァの戦いの舞台となったキオッジア(注2)は、古くから地中海の重要な位置にあり、常に周囲の国々の支配下にあったが、漁業基地としての重要性が都市の自立性を高めていったことは確かだ。現在でも七月には魚祝祭(サグラ・デル・ペッシェ)が行われ、海の幸の豊漁を願って船の行列が繰出す。漁業とともに歩んできた都市の一端がこの祭に感じられる。
(注2)キオッジア
キオッジアの戦いの名前で知られている。1380年、ヴェネツィアはジェノヴァを打ち負かし、アドリア海と地中海の制海権を握り、以後の繁栄の歴史的契機となった。
キオッジアの都市構造
迷宮的な都市であるヴェネツィアやブラーノと異なり、キオッジアは規則正しく櫛形に構成されている。南北に延びる広場のような大通りと、それに平行に流れる三本の運河が基本的な骨格をつくる。それに対して垂直に、東西に細い路地が通って全体を構成しているので、一見明快に見える。だが、一歩路地の中に足を踏み入れると、ポルティコを持つ建物が所々に張り出し、迷宮的な空間を生んでいる。
南北に流れる三本の運河のうち、町の両端にあるロンバルド運河とサン・ドメニコ運河には中型漁船が停泊している。これらの運河沿いには、漁業に関係する機能や造船所、倉庫が集中している。中央のヴェーナ運河は、小型船が停泊しているだけで漁業との関係が薄らいでいるが、町の中央を通るポポロ大通りと共に商業機能は今も集中している。
キオッジアに入るポポロ大通りの入口には、十一世紀にすでに町の一番重要な教会であった「ドゥオモ」が建っている。さらに通りを進むと、1392年に建てられたゴシック様式のサン・マルティーノ教会が見えてくる。東側には、運河と通りに挟まれるようにして、十三世紀頃の建築である市庁舎が姿を現す。古い魚市場も、ヴェーナ運河沿いにある。卸の市場は町の外側のサン・ドメニコ運河沿いに移っているが、現在もこの市場は小売の機能を持っている。公共的な建物が並ぶ中心地に魚市場があることは、漁業が都市の中心であったことを想像させる。一三二二年に建てられた柱廊のあるゴシック様式の穀物倉庫、バロック様式のサンタンドレア教会もこの通りの東側沿いに建てられている。公共施設が建ち並ぶ対岸、運河に沿った道には多くの路上マーケットが立ち、買い物客でごった返している。現在のヴェーナ運河のにぎわい振りを見ていると、漁を終え、その収穫物をのせた漁船が数多くラグーナからヴェーナ運河に入り、魚市場周辺に集まっていたかつての光景が蘇りそうだ。
キオッジアの建築タイプ
キオッジアで注目すべき点はポルティコである。ポルティコが付く建物の形態の一つとしては、ヴェネツィアでは水際につくられているものがあり、それがこのキオッジアにも存在したのである。一階をポルティコとし、上階に部屋を張り出すことで、土地を高度利用することができた。キオッジアでは、庶民住宅にまでこうしたポルティコを多く用いながら、高密に集住していった。この形式はブラーノにはあまり見られない。
二階建ての住宅が中心のブラーノ、三、四階の住宅が一般的なヴェネツィアに対し、キオッジアは五、六階建ての住宅で、しかもほとんどが集合住宅である。一階部分は倉庫や仕事場として利用され、生活空間は二階より上である。二階から煙突が出ていることからも、二階部分に台所や生活の場があることがわかるが、これはヴェネツィアと同じ風景である。ポルティコの下は、自転車やバイク、車の駐車スペースとして使われている。本土に近いため、ラグーナの島としては珍しく車社会が入り込んでいる。
キオッジアの商業ゾーンには、公共建築を始め立派な建物が建てられている。その高さはほとんどが三階におさえられ、ヴェネツィアのカナル・グランデ沿いに見られる三列構成の住宅とよく似た様式をもつ。これらの町並みからも、キオッジアの顔としてこの商業ゾーンが形成されていったことが見て取れる。
北ヨーロッパの交易都市アムステルダムとホールン
これまで、地中海貿易の中心地として十二、三世紀の中世にすでに栄華を極めたヴェネツィアを探ってきた。次に目を転じるのは、北ヨーロッパの交易拠点として十七世紀に栄華を誇ったオランダのアムステルダムである。
アムステルダムはライン川の支流であるアムステル川の河口に位置する。低湿地帯であるが、大国の仏・独・英の三カ国に囲まれ、スカンジナビア半島、バルト海沿岸地方にも近い。舟運が主な物流手段であった時代、アムステルダム、アントウェルペン、ロッテルダム等のネーデルラントの諸都市は、イベリア半島などを加えた西部ヨーロッパの中心となり得る地理的な好条件にあった。
アントウェルペンは、十五世紀半ばから約一世紀、世界最大の港町であり続けた。しかし、ネーデルラントとスペインとの八十年戦争(1568〜1648)が始まると、アントウェルペンはスペインの完全な支配下に置かれ、自由な港としての機能を失ってしまう。1500年にはホラント州の有力都市になっていたアムステルダムであったが、1579年にホラント州を含む北部七州がユトレヒト同盟を結び、81年にスペインに対し独立を宣言した。1609年にはスペインと十二年間の休戦協定が結ばれ、オランダ共和国が誕生し、実質的な独立を勝ち取った。この過程で、アントウェルペンの約二万人の市民は、経営、貿易といった様々なノウハウを伴ってアムステルダムに移ったのである。
オランダは、1602年に東インド貿易を行う特許会社を設立する。東インド会社が設立された直接の要因は、塩を買っていたポルトガルと交戦状態になり、塩を買えなくなったことにある。東インド会社が最も輸入したものは、塩と利潤をあげたコショウである。塩はニシンなどの漬け物のために、コショウは物を保存したり薬品に使うために輸入した。当時、東インド会社のオランダ国内のオフィスは六ケ所。アムステルダム、エンクハウゼン、デルフト、ホールン、ロッテルダム、ゼーランド(今のミデルブルフ)に置かれた。中でも取り引きの規模はアムステルダムが最大であった。
東インド会社による貿易は、アムステルダムに巨万の富をもたらし、十六世紀末から目覚ましい都市発展をとげる。1550年には、三万人であった人口が、1597年から1625年のわずかの間に六万人から十二万人と倍になる。逆にアントウェルペンの人口は五万人も減少する。1662年には二十万人にまで膨れ上がり、アムステルダムは都市を拡大していった。都市の発展は、同時に運河網が整備されていく歴史でもある。旧市街の外側に運河に囲まれた街区を幾何学模様のように拡大し、次々に運河をつくっていく。十七世紀のアムステルダムは、「水の都」となっていったのである。
都市の拡大に伴って、港湾機能は十七世紀までに「の」の字を描きながら都市の外側に移動していく。初めはダム広場に面した入り江(今のダムラック)を中心に立地していた。次に東インド会社成立後、都市西部の臨海部に港湾機能は移る。そして、アジアでの貿易が軌道に乗ると、西部から東部の臨海部へと拡大し、港湾機能の中心が移っていく。北海運河が十一年の歳月をかけて1876年に完成すると、再び西部の臨海部が脚光を浴び、大規模な近代港湾施設がつくられ、今日に至っている。
アムステルダムの運河を巡る
アムステルダムは町を歩く以上に、水の上から楽しませてくれる町だ。そこで、船を一隻チャーターして、アムステルダムの運河を巡ることにした。
船によるの運河紀行は、アムステルダムの西部、「ヨルダン地区」と呼ばれている場所からスタートした。十七世紀の初めに開発されたこの地区は、町の西部の三日月型をした地域で、ちょうど人口が急増し始めたころに開発された。隣接する東側の比較的高級な住宅街が形成された地区と比べると、道や運河の通し方が異なる。ヨルダン地区の街区の割り方は、農業開発で区画割りされた形状のまま斜めに道路が通っている。オランダはポルダー(Polder 、排水新開地)の名が付けられているように地盤が低い。人口の急増で都市計画による開発が追いつかず、ヨルダン地区は地盤が低いまま開発されることになった。
アムステル川にでると、はね橋と水門が両側に見えてくる。「マヘレのはね橋」は、1671年に建造され、アムステルダムに残る唯一の木造のはね橋である。この橋は毎晩ライトアップされ、昼とはまた違った趣きを見せる。アムステル水門は、アムステル川につくられた最大の水門で、1929年から電動で開閉している。アムステルダムには、海と接する川や運河には必ず閘門が設けられていた。低地につくられたアムステルダムでは、満潮時には海より低くなるため、水位をコントロールするのに水門が必要だった。そして船の航行を常に可能にするために閘門が設けられた。水門は同時に水位差を使って水の流れをつくり、運河の水質を保つ役割も持っていた。
アムステル川を下り、ヘーレン運河を通って港の方へ進む。大きな船はここを通り、アムステル川を遡る。この辺りは今でもオースタードックと呼ばれ、舟運に関連する東インド会社の施設が集中していた。造船所、ザイル・ロープ工場、倉庫などの建物が繁栄の威容を示す、アムステルダム最初の工業地域でもある。現在の国立海洋博物館は、海軍倉庫を改装して再利用された建物である。近くには東インド会社が所有していた外洋帆船・アムステルダム号が停泊している。船はこのドックから再び町の中へ入っていく。近くに水利管理の施設(水位調節の指令室)であるモンテルバーンス・タワーがある。オランダの基準水位は、現在市庁舎の中にあるシリンダーで確認することができる。基準水位を超えれば、アムステルダムの町は水に浸かってしまう。アムステルダムにとって、水利管理は今も昔も都市の生死を左右するのである。
再び港の方へ出ると、近くにはムント塔(「ムント」とは「硬貨」という意味)が見える。ムント塔は十五世紀後半に建てられた城壁の一部で、見張り塔の役目をしていた。フランス軍がアムステルダムを占領した際、1672〜1673年の間にここで貨幣が鋳造されたことからこの名が付いた。塔の奥には運河沿いに設けられた花のマーケット、「シンへルの花市」が見える。色とりどりの花々が並び、華やかな雰囲気に包まれている。
船はいよいよ町の最も古い場所へと入って行く。漁村としてスタートした頃からあった運河を通ると、建物が直接運河から建ち上がっている。アムステルダムといえば、運河沿いに必ず道が付けられていると思われがちである。だが、古い時代の建物は、ヴェネツィアのカナル・グランデ沿いのパラッツオのように、船が直接横付けできたのである。古い運河沿いには船着き場も所々設けられていて、現在はテーブルが置かれカフェのオープンテラスに変わっているものもある。
古い運河を抜けると、正面にアムステルダム中央駅が正面に見えてくる。右手には「涙の塔」が姿を現す。船乗りの妻たちが無事を祈り涙を流して船を見送ったことから、この名が付いたという。アムステルダム駅の辺りは、もともと防波堤(柵)がつくられていた。大きな船はここで停泊して荷を積み替え、荷は小さな船で運河を巡った。海に近いこの辺りには、宿屋の数も多かった。建物の一階が飲み屋で、二階より上の階が宿となっていた。
アムステルダム駅の前を通り、船は旧証券取引所の方に舵をとった。ダムラックと呼ばれる運河は、もともとダム広場まで延びており、一番最初に港として使っていた入り江である。ダム広場と駅をつなぐ一帯は、現在でも最もにぎわいのある場所で、十七世紀の頃はダム広場には計量所があり、取引が行われていた。それは、税関のようなもので、ここで通行税も取っていた。市場も開かれていた広場には、市庁舎(今の王宮)も面していた。オランダの広場の一般的な特徴として、教会が中心ではなく、市庁舎や計量所が広場の中心となっている。残念ながら計量所はナポレオンの支配時(1806〜1848)に取り壊されてしまった。
駅から西の方へ進み、アムステルダムで最も古い水門(1400年代)を抜けると、倉庫街へと入る。このブラウヴェル運河(「醸造業者の運河」という意味)一帯の倉庫群には、主にビールが納められていた。昔はビールが船乗りにとって保存できる重要な飲料水であったために、舟運で栄えたアムステルダムではビールの倉庫街が町並みをつくりだすほどであった。現在はギャラリーや住宅に転用されているが、倉庫という遺産をオリジナルの状態で残すために外観は保存されている。
アムステルダムの町の発展を物語るのに欠かせない古い倉庫は、現在およそ六〜七百棟が残されていて、そのほとんどが運河沿いにある。一般的な倉庫は、間口が五〜八メートルで、住宅とほぼ同じで、奥行きが約三十メートルである。大きいものになると、二つ分を合わせて約十五メートルの間口の建物もある。倉庫の上部は、ほとんどがビンの注ぎ口のような形をしており、船で運ばれた荷物は、建物の中央部にある大きな開口部から、上にある滑車を使って出し入れされていた。
運河には、ハウスボートと呼ばれる船で優雅に生活している家族も多い。水に住む権利を持ち、水道やガスを引いている。かつての日本の水上生活者を想像してはだめで、彼らは船のデッキに椅子を出して本を読んだり、日光浴をしたりと楽しげに過ごしている。私たちが乗っていた船のキャプテンと水上で生活している人たちは友達らしく、通り過ぎるたびに挨拶をかわしていく。
交易都市の面影を残すホールン
アムステルダムの都市空間の魅力にふれたところで、東インド会社(VOC )のオフィスが置かれていたもう一つの町ホールンを紹介したい。ホールンの目の前に広がるエイセル湖は、かつてのザウデル海と呼ばれる北海に通じる海であった。その海から、東方貿易で得た物資がホールンの港に運ばれていたのである。今は港がヨットハーバーとなり、レジャーと観光の都市となっている。ここでも私たちはエイセル湖から町の全容を見ることにした。
湖面から町を眺めると、まっ先に目に飛び込んで来るのがホールン・タワーだ。荒海を渡ってきた昔の船乗りたちは、砂岩でできたこのタワーを目指して港に入って来たのだろう。砂岩に太陽の光があたると灯台の明かりのように光を放ち、その輝きに導かれて船が港に入って来た。今のエイセル湖はレジャーを楽しむ人たちの船でいっぱいである。沖に出て船のエンジンを止めると、一気に静けさが私たちを包み込む。ゆっくりと時間が流れ始め、贅沢な気分を味わうことができた。現在レストランとして使われているホールン・タワーのまわりには、大勢の人たちが繰り出しているのが船上から見える。桟橋付近で釣りを楽しむおじさんの姿も見られる。にぎわいのなかに、どことなく安らぎとゆとりとを感じさせる。
ホールンの初期の発展段階は、アムステルダムと同じく入り江を港として利用していた。港近くは浅瀬だったので、沖には荷を下ろすための堤防(デイク)がつくられていた。船はデイクに停泊し、荷を積み替えて小さな船で港に運ばれた。そして、港や運河沿いにある倉庫に運び込まれた。東インド会社が設立してから、ホールンも都市を発展させ、港も入り江から海の方へ拡大していった。その時、要塞(城壁)としての外堀と内堀がつくられていった。その後の1510〜1515年には、外堀が内堀に代わり、その外側に新しい外堀と城壁がつくられる。この時期、急速な都市の拡大からも、貿易による莫大な資産がホールンに流れ込んでいたことがわかる。
要塞に沿うように掘られた外堀や運河の水は淡水である。ホールンの人たちは、はじめ川や運河の水を上水や雑用水として使っていたので、三ケ所に「オーフェルトーネ」(オランダ語で「引っ張る」という意味)と呼ばれる施設をつくった。海水より淡水の運河の方を高くするために大掛かりな施設をつくったのである。これを使うことで海からやって来た船を淡水の運河に引き上げ、運河沿いの倉庫に物資を運ぶことができた。その動力は風車や馬、そして人間だった。人力で動かすものは車輪のなかに人間が入って回した。
都市内部にある運河沿いの倉庫で現在も残っているのは、東インド会社の倉庫である。その一つが、ホールン市長の自邸になっている。当時は、インドネシアや長崎まで運ぶ輸出用の荷や貿易で運ばれてきた荷が納められていた。全長は五十メートルもあり、その半分の二五メートルを住宅として使っていると市長は話してくれた。倉庫の内部は現在住宅用に改装されてしまったので、滑車も外されて倉庫としての機能は失っている。市長は日本びいきなのか、家の中は和をテーマにしたインテリアで彩られていた。
東インド会社で栄えた頃、穀類はオランダが世界から輸入し、ヨーロッパ全域に供給していた。石はスウェーデンやドイツ、スイスから輸入している。木材はノルウェーから輸入され、主にホールンに集められた。ホールンの港には、巨大な貯木場があり、造船所は海から見て右側にあり、船のメンテナンスの役割ももっていた。
舟運で栄えたホールンには、かつて船乗りのための宿泊施設が多くつくられていた。町の中に入るタワー(城門)の周辺に宿泊施設はあった。その他にも、町外れ、港のあたり、現在のホールン駅など、計五ケ所に集中して設けられていた。一ケ所につき七〜八軒の宿があり、それらは下が飲み屋で、その上が宿という形式がとられた。これは、アムステルダムと同じだ。これらの宿は、船乗りたちは逃げられないよう、閉じ込めるられるようにそこに集められ、船が出るまで待機するために使われたのである。今でも建物は残っているが、現在はその多くがカフェとして使われている。
湖から戻り、多くのヨットが停泊する入り江の奥に進むと、水門が見えて来た。この水門は手動式で、船を見るなりおじさんがハンドルを回して水門を開けてくれた。ヨットの小さな旅を終え、いよいよ陸上での本格的な調査の開始である。
赤の広場から町を歩く
船を降りた私たちは、初期の港の名残りを残す運河から、町の中心である広場へと向かった。かつての港からは細い道を抜けて広場に出られる。この道を港から荷揚げされたチーズ、魚、りんごなどの物資が、中心の広場に持ち込まれて取引されていた。現在この道は、人通りもまばらであるが、かつては町にとって重要な道だったのである。細い道をさらに進むと、市庁舎が目に飛び込んでくる。広場の右手には計量所が見える。昔と変らない空間体験を私たちができるのも、古い町並みが残るホールンだからこそである。
町が発展する段階で、まず尾根道(堤防)と港へ行く道の交差する場所に、人々が集まる広場がつくられた。広場には市庁舎や計量所などの行政機関が集中し、まさしく町の中心をなしていた。レンガを敷き詰められたこの赤の広場(Rodesteen 、「赤い石」という意味)には、赤レンガがあり、死刑がここで行われていたことの証を今も伝えている。
市庁舎は現在博物館となっているが、建物は当時のままの姿で広場に顔を向けている。広場では定期的に市場が開かれ、いつも活気に満ちあふれている。私たちが訪れた時には、ちょうど車の市が開かれており、多くの人が広場に集まってきていた。広場のにぎわいはイヴェントの時だけではない。普段の時でも、広場はオープンカフェでくつろぐ人たち、立ち話をする婦人たちや遊ぶ子供たちの姿があり、いつも楽し気な雰囲気が漂っている。ベルギー産の砂岩でつくられた計量所は、当時の面影を残しながらカフェに姿を変えている。室内には当時使っていた秤がインテリアとして飾られ、計量所であったことをさり気なく来訪者に伝えている。この建物は、交易によって得た収益で、1608〜9年に建築家ヘンドリック・デ・ケイゼルによって新しく建て替えられたものである。
広場からは放射状にいくつもの道が走っている。このことからも赤の広場がいかに町の中心であったがわかる。その通りの一つが教会通りである。その名の通り教会があるのだが、現在は驚いたことにベビー用品や家具を売るショッピングセンターとアパートになっている。しかも信者が増えればまたもとに戻せるように、内装は教会そのままにされているのは、なんと柔軟な発想なのだろうか。この通りには、茶、タバコ、香料、コーヒーなどを売る店があり、東インド会社時代からの結びつきの強さを伝えている。
ホールンには、交易で活躍した商人たちの住宅が十七世紀そのままの姿で町並みを形成している。
最も栄えた十七世紀、ホールンには約二万人が暮らしていた。北海運河が開削されたこともあり、その後繁栄は続かなかった。1900年頃には、およそ一万人に減少する。
通りのなかには、運河を埋め立ててつくられたものがある。十三世紀頃のホールンはまだ運河の水を飲料水としていたが、人口が増えるにつれて運河は上水の他に下水機能も同時に持つようになり、運河の埋め立てが進む。運河から放たれる悪臭のために、住民たちが自ら資金を出して埋めたこともあった。運河を埋め立てる時は、完全に埋めてしまうのではなく、運河にフタをするように埋め立てる。ヘリッツランド通りはその一例である。下水路となった運河が海に出る所に風車が置かれ、その動力で水を汲み上げて汚水を海へ流していた。フタをされた運河は、時には消火用の水としても使われていた。
川や運河の水を飲料水として使えなくなったホールンでは、雨水を地下に溜めてそれをろ過してポンプ(井戸)で汲む方法が採用されていった。金持ちは個人で井戸を持つことができたが、一般の住民は教会や市役所にあった共同井戸を利用した。現在は下水や上水工事の時に取り払われてしまったものがが多いが、丹念に見ていくと所々に井戸の名残りがある。水と戦いながら、強かに水と関係を深めていったホールンの人たちの歴史が、井戸の痕跡から伝わってくる。
ヴェネツィアとアムステルダムから何を読むか
かつて舟運で栄えた日本の都市は、海や川からの視線を意識した豊かな表情をすっかり失っている。江戸時代、これらの都市の最も活気に満ちた場所は水辺にあった。だが日本では、水際が単一の用途として利用される傾向が強く、物揚場がつくられ、蔵が建ち並んだ。ヴェネツィアやアムステルダムのように、運河の側に広場、美しい邸宅・住宅、物揚場、市場など多様な用途の建物が建ち並ぶ華やいだ空間をつくることはなかった。近代に入り交通モードの主流が舟運から陸上に代わると、日本のように単一用途として水際が利用されていた都市では水辺の価値が忘れられた。水際空間の多くが新しい機能に置き換えられ、あるいは見捨てられたのである。
私たちは三年間、舟運で栄えた日本の都市を調査してきたが、そのほとんどが水辺の表情を失っていることに驚かされた。水際は、都市と海や川との関係を断ち切るかのように高い護岸で覆われている。このような状況をいかにして乗り越えることができるか。それをテーマに「水の都」として生き続けるヴェネツィアとアムステルダムを中心に調査を行った。
ヴェネツィアでは、現在でも歩く以外、人や物の移動は船である。水と深く結びついたこの歴史都市は、今も健在である。ヴェネツィアは完全に観光の町となったかのように思われがちだが、今回の調査で実は生活に密着した舟運機能がしぶとく生き続けていることがわかった。ヴェネツィアの「水の都」としての深みはそれによって維持されている。
早朝から日が沈むまで調査していると、運河から生活物資が次々と運ばれ、住民の足として水上バスやゴンドラの渡しが活躍している場面に出合う。車社会を排除し続けたからこそ、ゆったりとした生活が持続できているように見える。ヴェネツィアに車を持ち込み、道路を広げ、橋を架け替えようとは、もはや誰も思わない。むしろ、この町の水辺空間の豊かさを世界の色々な都市が、そのウォーターフロント開発に取り入れようとしているし、ヴェネツィアに習って、旧市街をできるだけ歩行者空間化しようという動きを活発に見せているのである。
ヴェネツィアは舟運で栄えた都市であるが、日本のように運河沿いに蔵や倉庫が林立することはなかった。水辺が港湾機能を持ちながら、運河と一体となった魅力的な生活空間がつくられた。カナル・グランデ沿いに華麗なパラッツォが並ぶ都市景観は、数世紀の間、都市の文化を表現し続けてきた。そればかりではなく、私たちが調査した広場には、運河と結びついた空間の演出と都市の機能を読み取ることができた。運河沿いのポルティコは、単に通り抜けできる水際の通路というだけではない。機能的要請から生まれたこのポルティコが、広場を囲む壁面に絶妙の変化を与えている。そしてヴェネツィアは、先人が積み重ねてきた都市文化の厚味を生活の場として大切にしてきたからこそ、いつまでも「水の都」としての輝きを失わないのである。
一方、アムステルダムは、都市の発展とともに港湾機能が都市の外側へ移された。その結果、舟運と深く結びついて成立していた運河や建築は本来の機能を失うことになった。にもかかわらず、アムステルダムの運河や建築のほとんどは黄金の十七世紀の姿を今もとどめている。
運河は、観光船ばかりでなく、地元の人や学生たちが運転するモーターボートが行き交い、結婚披露パーティーや船上でピアノを弾くパフォーマンスも水辺の洒落れた雰囲気を生んでいる。思い思いに運河の使い方を楽しんでいる姿には、水との深刻な戦いを克服するだけでなく、楽しみに転化するしなやかさを感じる。アムステルダムでは車が多く見られるが、それを上回るほど船の数が多い。不動産屋の店先は、クルーザーやヨットの売買広告でにぎわっている。運河沿いにはハウスボートがそこかしこにあり、水上での生活を楽しんでいる。
十九世紀以前に開発されたアムステルダムの旧市街には、新しい建築を見かけることはあまりない。アムステルダム市が都市景観を保存するために、特例を除いて建て替えが許されていないからだ。とはいえ、建物がかつてのままの機能を維持し続けているわけではない。私たちが調査したホテルは元々倉庫機能を備えた住宅であったし、古い倉庫群の多くは住宅やオフィス、店舗などに転用され外観だけが保存されているのである。アムステルダムの古い町並みは、決して古臭さを感じさせない。むしろ現代的な意味を付加されて、活き活きとした表情を見せている。しかも、古い建物にとられたレストランやカフェは、運河沿いにオープンテラスをつくり水辺との関係を深めている。
建物の外観を活かして用途を転用する考えは、日本でも個々の建築に少しずつ見られるようになったが、失われた舟運を現代的な機能や意味に置き替えて水辺空間を再生する動きは見られない。舟運とともに存在した運河や町並みが、柔軟な発想で新たな「都市の水の文化」の舞台となることを、アムステルダムの姿から感じ取れるのである。
私たちは、身近かな交通手段として船を考えなくなってしまった。同時に、水際が物流空間に特化された場所から抜け出せないまま今日まで至っている。これら二つの問題は、舟運で栄えた都市に共通する。目先の利便性だけでつくられる都市空間がいかに退屈で魅力のないものであるかが、ヴェネツィア、アムステルダムと日本の現状を比較することでより鮮明に見えてくる。近代の日本人は水との戦いから水を制御することに専念しすぎ、水と楽しむことをすっかり忘れていた。ヴェネツィアやアムステルダムから、水と戦いながらも水と楽しむ環境をつくるという知恵や発想を私たちも学ぶ必要がある。
監修:陣内秀信、岡本哲志
執筆:陣内秀信、岡本哲志、難波勉、岩井桃子、小田知彦、降屋守
図版作成:難波勉、岩井桃子、小田知彦、降屋守
フィールドワークレポートI
ミツカングループ本社
田口 英昭
オランダ/アムステルダム・ホールン 〜生まれ変わった運河〜
陣内研究チームのロケルートを巡りながら、「街の感じ」をつかんでいく。思ったより幅広な運河が幾重にも市内を貫き、並木映る水面をバカンスの観光客を乗せた遊覧船が行き交う。岸辺のオープンカフェではたくさんの人たちが夏の太陽と水辺の光景を楽しんでいる。まさに「北のヴェネツィア」、「水の都」である。そんな雰囲気にひたってバカンスモードでふらふらと街を歩いていると、時折、猛スピードの路面電車、車、自転車に冷やりとさせられる。
運河沿いには狭い間口の三〜五階建ての建物が等間隔でずらりと並んでいる。どの建物もその最上部に荷物を運び上げるための滑車を取り付けるフックがあり、上部ほど道路や運河側にせせり出ていているので荷を揚げるには勝手が良さそうに思える。その建築年代によって異なるという屋根飾りや、窓やその扉が一見単調な風景の中に適度な遊びを作り出す。部分的な補修は繰り返されているものの十七、八世紀の建物である。厳しい文化財保護政策によって維持されている景観なのである。
翌日から本格的な「水」と都市・機能に関する勉強と実地調査が始まった。歴史博物館ではアムステルダムの起源から街の形成・発達の歴史を勉強した。ヴェネツィアもそうであるだろうが、アムステルダムも「水」が都市の存亡に関わるものであることを改めて認識し、その克服の歴史に脱帽した。
オランダはライン川河口のデルタ地帯に位置し、街は海面すれすれまたはそれ以下という特殊な条件のために独特の発達を遂げた。即ち街の形成・発展は水を治めることから始まったのである。「アムステルダム」は「ロッテルダム」などの他の都市の名前と同様に、アムステル川河口部にダム(堰)を造ったことからそう呼ばれるようになった。川を堰きとめ、運河を掘削し、水門を設けることで、潮位の変化に応じて堤防内集落への浸水を防ぎあるいは余剰水を排水して集落を守ったのである。さらにヴェネツィア→アントワープ→アムステルダムへと富が移動し、十七世紀、オランダ東インド会社の外洋貿易が最盛期を迎えると、その立地と運河機能が舟運と結びついて街は更に発展した。その富がさらなる干拓地の、排水技術が高度化すると排水地の造成を生み国土を築いたのである。
運河を船で巡り、跳ね上げ橋や水門に舟運最盛期の面影を見ることができた。しかし現在の運河に舟運の面影は少ない。むしろ大都市の人々に潤いを与えるもの(「親水」)として運河が現代に機能していることを痛感した。結婚披露パーティーの船が行ったり、ピアノと奏者を乗せた船が追いぬいたりしていく。運河は日常生活に新たな「場」を提供することで再び現代に生まれ変わったのである。
オランダでは面白い話をたくさん聞いた。そのうちの印象深いものをあげると・・・。
ヨーロッパの建物は本来は木造で、アムステルダムでは十五世紀の大火の結果、類焼を防ぐために木造建築を禁止して煉瓦造りの今の姿があるのだという。住宅の家賃は部屋の敷地面積ではなく空間体積が単位となるそうである。ビールは船乗りの水代わり(腐らない)に造られたという。確かに街のペンキ塗りはハイネケン片手に仕事をしていた(酒ではないはずだ)。オランダの都市計画は八十年先まで考えるそうである。現地建築家曰く「水の色で水質を判断しがちだが、アムステルダムの運河の水(黄色がかっている)は非常にきれいである」そうだ。などなど…。
オランダの街を歩いて私が最も注意を引かれたことは、日常生活のあらゆる場でのバランス感覚とセンスの良さである。例えば、壁に掛ける絵画のセンスと同時に決して壁を絵で埋め尽くすことの無いバランス感覚。街の風景や部屋は、華美でもなく質素でもなく、過剰でもなく不足でもない。かといって適度な遊び心と潤いを忘れない。どこからこのセンスを身につけたのだろうかと帰国後もずっと気になっていた。それがある時、低地オランダ人の感覚を「地」と「水」の彼らにとっての等価性をもって説明した仮説を目にして、はっとせずにはいられなかった。さらに、「地」と「水」の微妙なバランスを治めて暮らしを造ってきたバランス感覚とその克服の歴史が、センスと合理性を導いたのであろうか。「水」のもつ偉大な影響力をこんなところでも思い知らされた次第である。
イタリア/ヴェネツィア 〜活きている運河〜
異国の見知らぬ街へ入り込むとき、その印象はいつも鮮烈である。そのアプローチが船によるものであったならばそれはなんと特別なものか!。太い杭によって示されたラグーン(潟)内の航路を、沖の海上に浮かぶベネツィア本島に向けまっしぐらに水上タクシーが進む。近づくと、建物に打ち寄せる水がそう見せるのか古い建造物の群れがそう見せるのか、ベネツィアは海に横たわる巨大な生物のようであった。運河を体内に向け入っていくと、しばらくして「食道(大運河)」に出る。老体といえど「胃腸」はすこぶる健康なようで、リアルト橋には観光客があふれ、ヒト・モノがどんどん行き交い、まだまだいくらでも飲みこまんとする活気が伝わってくる。
ヴェネツィアは運河が今も活きていた。陸上には手押し車が通るくらいの路地しかなく、車は基本的に存在しない。物品の大量配送は船で縦横無尽に張り巡らされた運河を通って行われる。十四〜五世紀にヴェネツィアが最も栄えたであろう頃と同じ機能で運河は活きているのである。
いつも子供の明快な表現には驚かされるが、先日、小学校六年生の女の子にヴェネツィアの写真を見せながら思い出話をしていたときのこと。運河や路地の写真をみせながら上述したように説明していると、不思議そうな顔で「(運河が)日本なら裏側なのに変なの」といった。まさにヴェネツィアでは運河は「表通り」であって、現在の日本における道路なのである。彼女にとっての川や水路が「裏側」のものであることは至極当然のことなのである。しかしながら、その「裏側」という表現には、半田運河を岸辺から眺めてみた時感じることのように、関わりの薄くなってしまった遠い存在という意味やその他のマイナスなイメージが含まれているようでならなかった。
ヴェネツィアの都市の形成の歴史は古く、大陸から他民族の侵入によって逃れてきた人々がラグーン内の島々に移り住んだことから始まったとされる。浅い海ではあるが、常に侵食の危険にさらされ、アムステルダムと同じく都市の形成は「水」との戦いの歴史であったことが想像できる。
しかし、ヴェネツィアはアムステルダムと違って、その得意な立地性からモータリゼーションの影響が小さく、街はヒューマンスケールのまま維持された。現にその「迷宮」を歩いていると、不便さ、無駄さに逆にヒトのスケールやペースを思い出させてくれるような暖かみを感じ、不思議とまた来ようと思ってしまうのであった。
水と心のつながりを洞察・調査
私が今回のフィールドワーク体験を通して最も痛烈に感じたこと。それは、実際に街に出て自分の目で見、足で歩き、人々の息遣いと街の空気を感じることがこの研究活動において如何に大切かということである。出発前にアムステルダム、ヴェネツィアの街や運河、水との関わりの歴史についていくらか本を読み、写真を見た。機上ではこれから目の当たりにするであろう都市の姿を思い浮かべ、アムステルダム、ヴェネツィア、半田の「運河」の共通性や相違点、その決定要因について思い巡らし、見てくるポイントを考えた。しかし、一歩町に入って運河を目の前にした時、実物は想像をはるかに超越していて一瞬にして頭が真っ白になってしまった。
「ボクハナニヲシニキタノダロウ?」。
だが、後で思ったことだがこれで良かったのだと思う。
「運河」はアムステルダムでもヴェネツィアでもその機能は異なっているものの、共通してあまりにも人々の日常生活の中に溶け込んでしまっていた。言い換えれば、「運河」や「水の機能」だけを簡単に取り出すことなどできなかった。つまり、人々の価値観や生活習慣に基づく本質的な「心と水の繋がり」についての洞察の無いまま、無理矢理「水」だけを取り出して比較・議論しても無意味であると直感した。
今回訪ねたアムステルダム、ヴェネツィアはどちらも特殊な「水」環境を長い歴史の克服の歴史を通して発展し、現在に至った「水の都」である。その「水」との深い精神的繋がりが、現代においても運河を活かしつづけることができた要因であるように思う。半田や日本の他の運河や水辺を考える場合、それぞれの都市に異なる歴史的背景から生まれた様々な形態があるように、他の都市の事例を表面的に当てはめるだけでは意味をなさないであろう。生活する人々の歴史的背景や価値観、伝統と未来への意志に裏打ちされた、子孫へと繋いで行けるものでなくてはならないと思う。これには時間をかけた詳細な調査と議論の果てに未来への提言があるのだと感じた。
フィールドワークレポートII
ミツカングループ本社
遠山 明裕
オランダ・アムステルダムでは、歴史的な倉庫街がe ‐ビジネスのオフィスや建築家・芸術家向けのソーホーとして積極的に再開発、活用されており、市内の各所で運河の改修・復旧工事や、古い建築物のリニューアルなど多くの工事が活発に行われているのが目についた。
建物の外観変更を市条例で規制しながらも、景観保護や保存だけを目的とするのでなく、時代環境にあった用途へとリニューアルし、使っていくことで経済活力の創出を図っていこうとしている。健全な経済活動と歴史文化との両立を図るバランス感覚には、成熟都市ならではの「したたかさ」を感じた。
「水や自然環境との共生と調和」を図るうえで、都市生活において何を選択し、何に妥協してきたのか。
人口七十万人を擁し、オランダ有数の経済都市であるアムステルダム。十二〜十三世紀に栄えた都市であり、今なお、世界的な芸術・観光都市であるヴェネツィア。両者のスタンスには違いはあるが、どちらも都市形成のルーツが運河と水であることを踏まえ、運河や水辺の空間を都市資源として活用している。
アムステルダムの運河では、元来の機能である舟運機能は既に失われており、現在の水上空間は、観光客用の遊覧船や水上カフェ、ボートハウスと呼ばれる富裕層の水上生活者向けのものとなっている。
舟運がすたれ、地下鉄やトリム(市電)で都市生活の足を整備した後も、いたずらに運河を暗渠化せず、街に残すことによって、都市生活と親水空間としての運河の共存を図り、水辺の景観を生かした街造り、再開発を成立可能にしている。
一方、ヴェネツィアでは、運河、舟運が今なお、街や生活に欠かせない機能として存在している。市民は、日々の利便性と折り合いをつけつつ、水と共生し、市場や広場を中心にコミュニケーション密度の高い、潤いある生活を営んでいる様子が感じとれた。
ヴェネツィアが人を惹きつける理由は、決して優れた景観や歴史的建築だけではないと思う。人々が生活を営む場として、水辺空間が持つコミュニティ機能の質の豊かさが感じられること。水が歴史とともに育んだ市場や広場、運河・船運を街の優れた要素として大切にしながら、生活に不可欠な機能として、より一層活用していこうとする暮しざま。地理的特殊性と歴史文化なくしては成り立たない水上都市における水辺の空間を、都市機能の中心に位置づけることで街としての差別性を選びとっている価値観。これらの複合体として、街が醸し出すヴェネツィアならではの雰囲気に親しみと魅力を覚えるからではないだろうか。
都市の求める差別化目的のおきかたによっては、水辺の空間・機能を残しながら、いかに活用するかがより重要な命題となり、単なる合理性や効率は下位に退けられるという取捨選択の価値判断基準の多様性を日本、オランダ、イタリア都市の比較を通じ、学べたことは収穫であった。
サウンド・スケープ
ヴェネツィアの橋は、タイコ橋であるため、街には自動車は見当たらない。自転車でさえも広場で遊ぶ、幼児用車が見られる位である。街に車がないことで、車を気にせず、安心して歩けることもさることながら、感覚をいかに豊かにしてくれるか再認識させられた。
陣内先生から「『音』について注意してごらん」と言われてみると、車の排気音がない代わり、耳に入ってくるのは、教会の鐘の音、市場やメインストリートのざわめき、ゴンドラ乗りの客寄せの声、広場や橋で挨拶を交わす人々の声である。
夜、食事の帰り、運河沿いの道を歩く時に聞こえてくるのは、石畳を刻む足音と岸を洗う波の音。朝、ジュデッカ運河沿いに建つペンションの窓から入ってくるのは、教会の鐘の音やロープで繋留された船が杭とこすれ、優しくきしむ音やカモメの声など、まさに、癒し系の音色ばかりであった。見えない音が作り出す風景のことを「サウンドスケープ」と呼ぶそうで、目に見える風景(ランドスケープ)とともに、ヴェネツィアの個性を形づくるものとなっている。
アムステルダム
アムステルダムは、十四〜十七世紀にかけ拡大、発達した都市である。
デンハーグが政治・司法・行政機能の中心であるのに対し、アムステルダムは経済の街である。主要な河川や運河を中心に、非常に計画だてて都市形成が行われ、近代都市計画の元祖といわれる。また、堀割や運河を中心に街が形成されている点から、大阪や東京とも同じ骨格を持つ都市といわれている。運河、運河沿いの道路、建物から構成される市街は、並木道などもあり、非常にアメニティに配慮された都市空間であり、十五〜十七世紀という時代を考えると、その先進性には驚かされる。
倉庫やカフェの建物には、建築年度が記された版がはめ込まれており、一目で建築年代がわかる。(「ANNO1640」なら1640年に建てられたというように)。
アムステルダムでも1600年代始めの建物が残っている例は、少ないとのことであった。
運河沿いの道に面したレンガ建築は、大火災後に防火目的で市条例により、従来の木造建物から政策的に誘導されたものである。
もともと、アムステルダムでは、所得格差により居住エリアを分ける考え方はなく、豪商の館と船乗りの宿場や借家が交互に並んでいた。レンガ化政策の背景には、建築コストの高いレンガ建てとすることで貧困層を中心部から締め出そうとする影の目的もあったと聞いた。その結果、アムステルダムの中心部は豪商など富裕層の住むレンガ造りの街となり、労働者は、対岸のザーンダムに移り、木造建築の街に住むようになった。
住宅や倉庫の建築材料として広く活用されたレンガは、地質上、砂岩などの石材が採れないオランダに適した材料である。豪商の商館や教会など建築コストが豊富にかけられる石造りの建築には、輸入石材が使われている。
レンブラントの妻が埋葬されている旧教会はゴシック様式の荘厳なタワーをもつ教会建築である。中でも目を引くのは、木造の梁で支えられた天井である。石の塔で外部から屋根を支えるのでなく、木の梁で内部から支える構造となっている。ゴシック建築というと天空を目指してそびえたつ尖った石造りの塔をイメージするが、イタリア、オランダのゴシック建築は、フランス・ドイツとは異なり、内部から梁で支える構造から、地に足がついた安定的な印象を与えるという。
倉庫は三階〜四階建てであり、保管品の特性に応じて貯蔵される階が定められていた。一階はビールなどの飲料。二階、三階が織物や陶器など、屋根裏には穀物が保管された。オランダでは、航海中にも保存できる飲料用水とするため、穀類を輸入し、ビールを醸造していたという。
倉庫内の階段は、狭く急勾配なため、荷物の搬入は、建屋の最上階に取り付けられた滑車が活用された。滑車は、倉庫が集合住宅に転用された現代も、引越しの時に活用されるという。興味深かったのは、近代建築の集合住宅にも、装飾として滑車をかける杭がつけられ、周囲の倉庫街との調和を図る工夫がみられることである。住宅用の土地面積が限られているアムステルダムでは、天井の高さが住宅の質やステイタスを表わす基準となり、借家の家賃も、平米数でなく、容積=立米で決められているという。
調査のメンバーは、みんな「面白そうだ!見てやろう」、「どうして?どうなってるんだろう」という好奇心・探求心に溢れており、「好きなこと、自分がやりたいこと」へこだわり、調査や行動に落とし込んでいく姿勢―この楽しさにはついつい引き込まれてしまった。