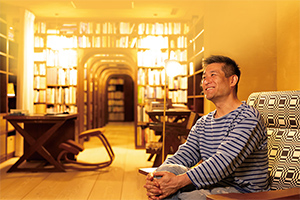機関誌『水の文化』79号

【災害史】
先人たちは災害にどう立ち向かったのか?
――江戸時代の村と農民にみる復興のあり方
私たちが暮らすこの国は、昔から幾度となく大きな自然災害に見舞われてきました。先人たちはどのようにして復興に取り組んだのでしょうか。江戸時代の災害からの復旧と復興をつぶさに検証し、江戸時代の人たちが個々の家まかせにせず、村全体として挑んだことを解き明かす『日本人は災害からどう復興したか――江戸時代の災害記録に見る「村の力」』を上梓した渡辺尚志さんに、江戸時代の災害復興についてお聞きしました。

天保の飢饉で飢えた人びとを救済している御救小屋(おすくいごや)。
御救小屋は飢饉や災害で家や食を失った人びとを救済するために設けられた臨時の施設
渡辺崋山『荒歳流民救恤図(こうさい りゅうみん きゅうじゅつ ず)』,刊,天保9 [1838] 国立国会図書館蔵
-

-
インタビュー
松戸市立博物館 館長
一橋大学名誉教授
渡辺 尚志(わたなべ たかし)さん -
1957年東京都生まれ。1988年東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学。博士(文学)。専攻は日本近世史、村落史。2022年から現職。『日本人は災害からどう復興したか―江戸時代の災害記録に見る「村の力」』『浅間山大噴火』『百姓たちの水資源戦争』『海に生きた百姓たち』など著書多数。
人災でもあった江戸時代の災害
江戸時代の激甚災害には、地震、津波、噴火、洪水、飢饉(ききん)が挙げられます。自然災害ではありませんが、江戸や大坂などの大都市では大火もしばしば起きました。江戸時代の災害には2つの特徴があります。1つは「単発ではなく複合的に起きること」、もう1つは「天災であると同時に人災であること」です。
1783年(天明3)に起きた浅間山噴火では、広範囲に火山灰や砂が降ったので農作物と耕地が失われ、結果として飢饉が拡大しました。地震が起きると津波がくるように、複数の災害が連続的かつ複合的に起きたのです。
江戸時代も後半になると大名たちはおしなべて財政難に陥ります。年貢米を担保に江戸や大坂の大商人からお金を借りるケースが多く、その年がたとえ凶作でも年貢米で支払うため領内は食糧不足となり飢饉が起きました。大名は幕府からの自立性が高く、藩は半ば独立国家のようでしたから、隣の大名の領地が飢饉になったとき、交通を遮断して穀物を外に出さない「穀留(こくどめ)」を行ないます。領内が飢えなければよいというこうした政策によって、飢饉がより拡大することもありました。
さらに農業に関して言えば、江戸時代は中世までに比べると耕地が格段に広がった時期です。大河川の川沿いまで開拓したので生産量こそ増えましたが、そうした場所は洪水が起きると被害を受けやすい。また、江戸時代の物流は舟運が軸でしたので、江戸や大坂など近世の大都市は大河川の河口部や海沿いにあった。それは経済発展にとっては合理的ですが、同時に洪水や津波に対するリスクを高めることでもあります。
開発や産業の発展は、平常時は人びとの暮らしを豊かにしますが、裏を返せば災害のリスクを高めることにもなるのです。江戸時代の災害は、人災としての側面も大きかったといえます。
地域の有力者たちが果たした復興の役割
災害からの復旧と復興はいつの時代でも困難なものです。現代では「自助」「共助」「公助」の組み合わせが重要といわれていますが、江戸時代は公助の役割が格段に低かった時代でもありました。
情報インフラが発達していないので、地方で大災害が起きても江戸に伝わるまでタイムラグがあるうえ、どの程度の被害なのか実情もはっきり伝わらないため、どう救済していいかわからない。ですので藩や幕府は救済はするけれど、民間任せの面が強かったのです。
公助が期待できない社会だったがゆえに、自助と共助の果たす役割が重要でした。特に共助で大きな力を発揮していたのが村の有力百姓たちです。彼らは2つの役割を担っていました。
1つは「被災者を直接救済すること」です。有力百姓は最初にその土地に入って村を開いた人の家系であることが多いため、もっとも条件のよいところに屋敷を構え、水がこんこんと湧き出る村いちばんの井戸を敷地内にもっていたりします。地震や津波などの大災害で井戸が使えなくなった時には、自分の家の井戸を村人に解放するといった形で救済していました。
もう1つの役割は「災害の実態を記録して後世に伝えること」。江戸時代になると庶民も災害の記録を文章で残すようになりますが、ふだんから本を読み、字を書くのに慣れている地域の有力者の方が情報をより多く残しています。そのなかには防災意識の芽生えと受けとれるものもありました。
川越藩(現・埼玉県)で名主を務めた奥貫友山(おくぬきゆうざん)は18世紀前半の洪水を「大水記(おおみずき)」(寛保3年[1743]成立)として記します。地域の有力者である友山の村は荒川の西岸のすぐそばにありました。「大水記」には「洪水などの災害時には泥水が井戸に流れ込むので、あらかじめ井戸水を汲み置くべきだ」といった防災マニュアルのような記述があります。
また、備前国(現・岡山県)の判頭(五人組の筆頭)だった平松勇之介は、「洪水(こうずい)心得方(こころえかた)」(嘉永5年[1852]成立)を著し、「家を建て直す際には敷地を高くする」「米や麦の俵は重いので事前に家の二階や土蔵に収納しておくこと」など洪水の教訓を書き残しています。
そのほかにも食糧が不足した時に備えて「この草は食べられる」「この木の皮はこうやって剥(は)いでこう加工すれば食べられる」など救荒食に関する知恵を記した人もいました。
しかし、こうした記録があるという事実は、裏を返せばどれほどひどい災害でも時間が経てば忘れられていく証でもあるわけです。
ちなみに友山は親戚や村人のみならず見ず知らずの人にも食糧を与えました。それはすばらしいことですが、私有財産には限りがあります。友山はのちに莫大な借財を抱えることになるのです。
村の共同性を強めたのは「水」
公助が弱く、自助にも限界があった江戸時代に、村人たちが大災害に遭ってもそれなりに復興していけたのは共助の力が大きかったからです。共助の主体は村でした。
1783年の浅間山噴火でもっとも大きな被害を受けたのは上野国(こうづけのくに)の鎌原村(かんばらむら)(現・群馬県吾妻郡嬬恋村)です。村人の8割以上が亡くなり、耕地の9割以上が火砕流に埋まってしまいます。復興に努めて田畑はどうにか耕せる状態になりましたが、耕す人がいません。そこで生存者全員で相談して、被災前の田畑の所有権は白紙に戻し、開発可能な耕地は生存者で均等に分けて作付けしていくと決めました。それが復興にもっとも効率的で早道だったのですね。
こうした災害時に発揮される村の力の根底には、ふだんから村人たちが強く結びついていたことがあります。「災害が起きたから協力しよう」と突然言い出してもうまくいかないでしょう。
村人たちの日常的なつながりの大きな要因は「水」でした。江戸時代の農業の基幹は水田稲作なので、水が必要なわけです。用水路やそこを流れる水は村全体の共有物ですからメンテナンスは必須です。今でもそうですが、村では年に一度は全戸総出で用水路の泥さらいをしたり、水の流れを阻害する木の枝を伐採するといった共同作業を行なっています。
田に水を引く際にも村人同士の綿密な話し合いが必要でした。江戸時代の技術力では田一枚一枚に水を直接引き入れることは難しい。下の図のように、比較的高い場所にあるAさんの田に用水路から水を引き入れ、いっぱいになったら畔(あぜ)に設けた水路やトンネルですぐ下のBさんの田に水を送っていました。これは「田越(こ)し灌漑(かんがい)」と呼ばれ、広く用いられていました。
田越し灌漑の場合、Bさんが一人で田植えの日を決められません。Aさんの田からいつ水が来るかによって日どりが変わってくるからです。そこで隣り合った田の持ち主が全員で相談して農作業の日どりを決めておく必要がありました。
このように村人たちが日ごろから水を介してつながりを深めていたからこそ、復興に際しても力を発揮することができたのです。
いざというときに生きる「つながり」
ところが、大災害の場合は村全体が大きな被害を受けているので、たとえ立派な有力者がいても、いかに共同の力が強くても、村内だけで復興するのは難しいです。
そこで生きてくるのは、日ごろのネットワークです。被害が少なかったよその村の有力者からお金を借りて村人の救済にあてるといったことが可能でした。それは村同士のつながりだけではなく、都市部の商人との間でも同じで、余った穀物を米屋に売っていたつながりがあれば、仮に洪水で村の田が全滅してもその米屋から米を買うこともできます。村と村、村と都市部で日常的かつ経済的なつながりをもっておけば災害時に生きてくる。この世はいつでも持ちつ持たれつなんですね。
また、地域の有力者同士は婚姻関係を結んで親戚になっている場合も多いですし、経済的に余裕があるので余暇に俳諧を楽しむといった文化的な活動もしていて、ふだんからさまざまな形でつながっていました。
もちろんこれらの関係は災害のためにつくっているわけではありませんが、人的なつながりの輪を広げておくことは、救済の手助けを受けるときに作用します。これは有力者に限った話ではなく、村人も同じで、洪水で床上浸水になったら一時的にどこかへ避難しなければなりませんから、ほかの村にいる親戚などを頼るわけです。見ず知らずの家に突然行って「しばらく置いてください」と言っても無理ですからね。
日常的な人のつながりが災害対応時にも重要なのは、江戸時代の事例から言えることです。
災害対策から生まれた地域の自治や公共性
江戸時代の災害対策から生まれた地域的な自治や公共性をもっともよく表しているのは、飢饉に備えて食糧などを蓄えておく「備荒貯蓄(びこうちょちく)」です。人びとの間に防災意識が芽生え、災害を想定してあらかじめ食糧を備蓄しておかなければいけないという発想が出てきます。個人や村で備えるだけでなく、複数の村々が共同で穀物を供出して備蓄することが行なわれるようになりました。その穀物を、中心的な村に蔵を建てて蓄えたり、同じ領主の村同士で協力したりする備荒貯蓄は、地域自治、地方自治の現れです。
村人だけではなく、領主も穀物を供出するケースもみられました。それは公共性の一つの現れと言っていいと思います。ただし、領主が財政難で供出量がわずかな場合は民間の負担が重くなります。そこから幕府や大名が中心的存在として備荒貯蓄を制度化し責任をもって運用しなければうまくいかない――という考えが民間から出てきて、近代以降は政府や地方自治体が公助を充実させる方向へと進んでいます。
復興を果たすうえで村の力が大きかったのは事実ですが、村には地主がいれば小作人もいますし、お金を貸す有力者がいればお金を借りる貧しい人もいるわけで、すべてうまくいっていたわけではなく矛盾もありました。それも含めて江戸時代の人たちが何を考えて、どう工夫して、どこまで到達して、どういう限界や課題があったのかを押さえたうえで、今にどうつながっているのかを理解する。歴史を学ぶ意義はそこにあります。
今は公助が江戸時代よりも充実している分、共助の大切さが忘れられている感は否めません。江戸時代の歴史から私たちが学ぶべきことは、日常のさまざまなつながりが、いざという時に役に立つという不変の事実だと思います。
(2025年5月20日取材)