機関誌『水の文化』79号

【人とのつながり】
「余剰」を交換し合える社会へ
──災害時にも大切な「顔が見える関係」
コミュニティデザインという分野を広く知らしめた山崎亮さんがこの道に進んだのは、阪神・淡路大震災での体験が大きなきっかけだったそうです。コミュニティに分け入り、たくさんの人びとの話に耳を傾けながら活動している山崎さんは、災害時の備えについてどのように考えているのでしょうか。
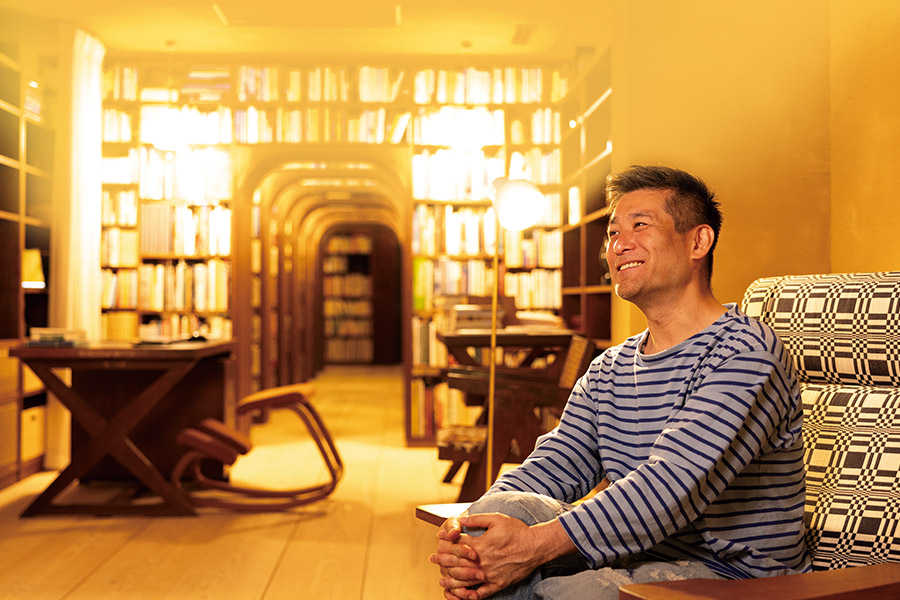
-
インタビュー
コミュニティデザイナー
関西学院大学建築学部 教授
山崎 亮(やまざき りょう)さん -
1973年愛知県生まれ。大阪府立大学農学部にて増田昇に師事(緑地計画工学専攻)。メルボルン工科大学環境デザイン学部にてジョン・バージェスに師事(ランドスケープアーキテクチュア専攻)。大阪府立大学大学院(地域生態工学専攻)修了後、SEN環境計画室勤務。2005年にstudio-Lを設立。地域の課題を、地域に住む人たちが解決するためのコミュニティデザインに携わる。
水を備蓄するのは誰のため?
「災害のために備えましょう」。そう促されてペットボトルの水をたくさん用意するのは、あなた個人が助かるためだけにやっているのでしょうか? みんながそれを常に考えられるような社会になるといいなと思っています。
個人主義的に「水を用意しておく=自助」と考えれば「隣近所がどうであれ、自分だけは助かるために備える」となります。水をはじめ備蓄用品を売る側も「あなたと大切な家族を守るために」と呼びかけるので、そう思い込まされているだけかもしれません。
印象的な話があります。東日本大震災のとき、避難所となっていた体育館で「私は大丈夫ですから、ほかの人のところに行ってください」と言う人が多かったそうです。私だったら大きな被害を受けてそう言えるかどうかわかりません。
自分が助かるためではなく、助けが必要な人に手を差し伸べてもらうために備えておく──この感覚は、個人主義的な思考回路からは生まれません。少し余分に水を準備しておけば、たまたま水を用意していなかった人に「よかったらどうぞ」と渡すことができます。それは自助でありながら、自助を超えた共助にもつながる。とても大切な思想だと思います。
人が抱える欲求を二つに分けて考える
「私は大丈夫。備えはしておいたから」と言えるようになるには、「個人」と「社会」の関係を考えることが一つの道標です。
私たちは資本主義と社会主義を対峙する概念と捉えがちですが、資本と社会は対義語ではありません。これを読み替えると、根底にあるのは個人と社会です。まず個人がいて、その個人が複数になって形成される社会がある。個人と社会のバランスがとれている状態がもっとも好ましいはずです。
ところが大量消費を前提とした今の社会では個人を、正確に言うと個人の欲求を煽るばかりです。そうした方が商品やサービスは売れますからね。人間の欲求に限りはないのだといわんばかりに、あれも買え、これも買えと私たちは常に煽られつづけています。
ところがイギリスの経済学者、ケインズは、人間の欲求は一つではなくて二つに分けられると定義しました。一つは衣食住に代表される「それがないと生きていけない」絶対的な欲求です。もう一つは高級車やブランド品など「所有していると他者に優越感を抱ける」相対的な欲求です。
絶対的な欲求を「第一の欲求」、相対的な欲求を「第二の欲求」とします。私たちはこの二つの欲求を混ぜ合わせて自分の欲求だと思い込んでいるので、まずは生きていくために必要な第一の欲求がどこまでなのかを考えてみましょう。きっと「ここまでは必要。だけどもうこのブランド品はいらない」と見極められるはず。すると、今までは第二の欲求に費やしていた部分が空きます。この空きが「余剰」です。
余剰にはモノを買うお金のような目に見えるものと、時間や知識、経験など目に見えないものがあります。こうした自分の余剰を、親しい人やご近所さん、肌が合う仲間など面識のある人たちに使ってみてはどうでしょう。個人的に満足するけれど上限のない第二の欲求に費やすよりも、人生が豊かになる気がします。
見返りを求めるわけではありませんが、仮に自分が仕事を失ったら力になってくれるでしょうし、それこそ災害が起きたときには「あの人いないよね?」「探しに行こう!」となるはずです。
みんなが余剰を出し合う「面識経済」
自分と面識のある人たちが自らの余剰を差し出し、受けとり合う生活を想像すると愉(たの)しくなりますよね。私は、そうした面識関係=顔が見える関係にある人たちでつながって行なう経済活動を「面識経済」と呼んでいます。
例えば、道路に面した畑地で見かける野菜の無人販売所。この始まりも余剰を元とする面識経済だったと想像します。想像というのはその歴史を詳らかにした人がいないからですが、例えば白菜が豊作で食べきれないけど農家の知り合いもみんな豊作だし、でもどこかに白菜を欲しい人がいるかもしれない、と台を置いて「ご自由にお取りください」と札を立てた。そこへ農家の親戚もいない人が通りがかり「あら、助かる!」と持って帰った。もらいっぱなしは気が引けるから何かお礼を持って行く──。もともとは無人販売ではなく無人配布所だったんだろうと思います。
10人から20人くらいで小さな面識経済圏はつくれますが、さすがに生活全体を賄うのは無理なので、面識経済比率を少しずつ上げていく。それは災害時に助け合える関係を築くことでもあります。
コミュニティが希薄な都市部でもできること
都市部は、中山間地域や離島に比べ人間関係が希薄なのは否めません。しかし、新たにコミュニティをつくる方法はあります。
社会学では地縁をもとに生活全般でつながっていくものをコミュニティ、共通した興味でつながるものをアソシエーションと使い分けてきました。私は前者を「地縁型コミュニティ」、後者を「興味型コミュニティ」と言い換えています。都市部で地縁型は難しいので、サッカーや料理、カメラなど共通の趣味をもつ人が集まる興味型コミュニティを目指すのが現実的でしょう。興味ごとに30人から300人くらいの仲間と多層的につながっておくことは可能です。
起きてはほしくないですが、災害を機につながりを結び直すこともあるはずです。大学三年生のときに阪神・淡路大震災が起きて、緑地を軸とする都市計画を専攻していた私は、建物の判定調査のために被害の大きな地域に入りました。地図に全壊を示す赤鉛筆しか使わない状況で心が折れかけていたとき、川辺に集まった被災者同士が励まし合っている場面に出会いました。途方に暮れるような状況でも、人と人がつながっているのを見て温かい気持ちになったこの経験が、のちにコミュニティデザインに携わるようになったきっかけです。
経済成長一辺倒の時流に逆らうようですが、一度立ち止まって自分のなかの欲求と向き合ってほしい。そうして見出した余剰を周りの人に差し出せば、愉しく笑って過ごせる日常、そして災害に遭ってもなんとかなる関係を築くことができると思っています。
(2025年6月2日取材)





