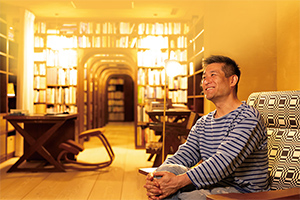機関誌『水の文化』79号

【文化をつくる】
ふだんから備えたい心と水
-
編集部
いつどこで起きるかわからない激甚災害に対して、ふだんからどう備えたらよいのか──それを水が絡むテーマごとに探った特集「備えは日常のなかにある」。皆さんはどう受けとられたでしょうか? 編集部が今号の特集を振り返ります。
ふだんできないことは災害時にもできない
今号の取材を振り返ると、大きく二つのことに気づく。
一つは、お会いしたほぼすべての人たちから「日常」という言葉を聞いたこと。もう一つは、大きな災害が起きたときに大事だとよくいわれる「自助・共助・公助」の境目がよくわからなくなったことだ。まずは日常の方から考えたい。
日常は、ふだん、平生(へいぜい)、常日頃だ。災害時は日常が非日常となるので特別なことと思いがちだが、災害への備えは日常のなかにあると教えられた。
震災が起きるたびに報じられるのが避難所のトイレ問題だ。NPO法人 日本トイレ研究所の加藤篤さんはさまざまなシンポジウムや講演会でトイレの重要性を訴えている。加藤さんは「私たちがメディアに取り上げられるのは災害時が多いので、むしろ注目されたくないんです」と苦笑する。携帯トイレが災害時になぜ有効なのか、被災地におけるトイレの実態などをきめ細かに教えてくれた。マンホールトイレも万能ではなく、タイプによっては下水道本管が壊れていたら使えないし、水源が必要なケースもあることなども知った。
特に携帯トイレはきちんと扱えるように練習しておきたい。切羽詰まった状態ではまず失敗する。日常で試しておくべきだろう。
「日常を楽しみながらの防災」を発信しつづけるのは、国際災害レスキューナースの辻直美さん。お子さんが幼い頃、散歩しながら避難所や避難場所への道のりを確認していたそうだ。「道の狭さや勾配など地図ではわからないことが把握できますよ」と言う。辻さんに「避難所と避難場所の違い、わかりますか?」と聞かれ、恥ずかしながら答えられなかった。
指定避難所に行っても人がいっぱいで入りきらなければ、自力で別の指定避難所へ向かうしかない。これも辻さんに教えていただいたこと。どういう災害が起きたらどこへ避難するのかを常日頃から確認し、歩いておくことは大切だ。
また、家庭風呂が普及する前は日常的に使われていた銭湯が、いざというときの避難所となっていることは意外だった。避難所としての条件を満たす銭湯と行政が防災協定を結び、ふだんから防災や観光関連のイベントなどで連携しているからこそ、取材対応もスムーズだったのかと腑に落ちた。
銭湯だけでなく、例えば友好姉妹都市が防災協定を結ぶ例は多く、食糧や飲料水の提供、職員の派遣といった災害対応を想定している。姉妹都市が夏祭りなどで互いに出店し合うのは、いざというときの関係づくりの側面もある。
ふだんから取り組んでいなければ、大混乱する災害時にはなおさら何もできないのだ。
自助・共助・公助の境目はなくていい?
次に「自助・共助・公助」を考えたい。自助は一人ひとりが自ら取り組むこと、共助は近隣に暮らす人たちが一緒に取り組むこと、公助は国や自治体などが取り組むことで、災害時はその連携が大事だといわれる。三つの輪が連携する図もよく見かける。
ところが、取材をするなかで、その範囲があいまいになっていく。例えば自助。この言葉を額面通りに受けとれば、「自分が困らないように水や食料を備えておくこと」となるが、山崎亮さんがインタビューの冒頭で「それは自分だけが助かるためだけにやっていることなのか」と問うたように、自助でありながら共助にもつながっている。自分が備えておけば「私は大丈夫。助けが必要な人のところに行ってください」と言える。
また、共助と公助も混じり合っている。自治会長が伊勢湾台風で被災した経験から「井戸を掘ろう」と強く主張して生まれた防災井戸「蔵清水(くらしみず)の井戸」。三重県名張市の蔵持市民センターを訪ねると、面食らうほど多くの人たちが待っていた。自治会の方々と蔵持市民センターの職員は想定できたが、名張市役所の職員がいたのは予想外だった。お話を聞くと、蔵清水の井戸は名張市の呼びかけに蔵持地区が提案し、交付金で設置したものだった。
また、石川県珠洲市(すずし)の馬緤町(まつなぎまち)で自主避難所として使われていた珠洲市自然休養村センターを訪ねたときも、全員が地元の人なのかと思いきや、ボランティアとして遠方から来て長期滞在している人もいた。
自助は考え方次第で共助にもなる。そして、蔵清水の井戸のように、共助も公助(公)との連携があるからこそ、市内の小学生全員が訪ねる機会をみんなでつくることができる。日常で持ちつ持たれつの関係にあるのだったら、ことさら災害時にだけ自助・共助・公助を強調しなくてもよいのではないか……。
そんなことを考え、足りない要素があるのは承知のうえで、自助・共助・公助のあり方を図式化したので見ていただきたい。(下図)
都市部のコミュニティは古くて新しい課題
災害時の自助・共助・公助を考えた場合、そのパワーバランスも考慮すべき点の一つだ。
藩が独立国のようだった江戸時代は公助が弱く、自助と共助が頼みの綱で、村と村の有力者が復旧・復興に取り組んだことは、渡辺尚志さんが詳らかにした。しかし、共助が強くなりすぎたがゆえの悲劇もあった。江戸時代に飢饉(ききん)が頻発した地域では、食べものを盗むなど悪さをした人を領主や代官の裁定を待たずに村で始末した事例がある。仮に現代で共同体がもつ一種の危うさが発露しそうになったら、抑止するのは公助(公)だろう。
また、今も昔もなんらかの理由で地域になじめない人は一定数いる。そこは公助(公)が手を差し伸べるべきところだ。
一都三県(東京、神奈川、千葉、埼玉)に人口の約3割にあたる3680万9387人(総務省「令和6年住民基本台帳人口・世帯数」)が住むように、今の都市部は過密だ。しかも共助が成り立ちにくい。大都市で人と人がどうつながっていくかは古くて新しい課題として今もある。山崎亮さんが言うように、都市部で地縁型コミュニティは難しいが、興味型コミュニティなら可能かもしれない。また、地域防災のシンボルとして何を持ち出せるか。かつては「水」が村人たちを結んでいたが、今は井戸や銭湯が可能性を秘めていると思う。
大規模災害から考えるこれからの社会と水
自助・共助・公助をことさら強調しなくても、と言いながら逆説的なことを述べるが、災害への備えを水について見た場合、やはり公助(公)の役目は大きい。
激甚災害において毎回起きる混乱の原因がどこにあるのかを鋭く指摘した菅野拓さんは、被災地のインフラに関して「高度経済成長型」の復旧は見直すべきだと語った。特に上下水道という水に関するインフラは、人口減少が進む現状では水道料金の値上げという形で跳ね返ってくる。ただでさえ復旧・復興で苦しんでいる被災住民の負担を、さらに重くする。
珠洲市馬緤町の区長、吉國國彦さんは『水の文化』の取材に応じた理由をこう語った。
「幸い私たちの地域にはがけ崩れを防ぐために敷設された深井戸からの水がありました。飲める水です。しかしきれいな水は限りがあります。私たちの経験を伝えることで、皆さんの街が災害に遭ったとき、『水がどこにあって、どういう使い方ができるか』を考えるきっかけになればと思ったのです」
国土交通省が能登半島で予定する小規模分散型水循環システムの実証事業は、取材時にはまだ具体化していなかった。「私たちは地震で断水し、復旧してすぐに9月の豪雨でまた断水しました。でも深井戸の水があったので困らなかった。その水を活かした小規模な水道システムを構築できないかと提案しました」と吉國さんは言う。
大規模な自然災害が起きたからこそ発せられた菅野さんや吉國さんの提案が見過ごされるようなことがあれば、あまりにももったいない。
また、「天災は忘れられたる頃来る」で知られる地球物理学者で随筆家の寺田寅彦は、「津浪と人間」(1933年)でこう記している。
「しかし困ったことには「自然」は過去の習慣に忠実である。地震や津浪は新思想の流行などには委細かまわず、頑固に、保守的に執念深くやって来るのである。」
いつの世も人は物事を忘れがちだから江戸時代の人たちは災害の実態を後世のために書き残した。江戸時代に弱かった公助も、今は行政と民間支援団体が平時からつながることで災害時に力を発揮することがわかってきた。逆に共助は地縁が薄れ弱まっているが、自助は共助につながるし、興味型のコミュニティならつくれそうだ。人とかかわるのがちょっと苦手ならば、近所の人に挨拶することから始めればいい。
寺田が言うように、災害が過去の習慣に忠実ならば、私たちも水や食料の備蓄、人とつながることを習慣づけるのはどうだろう。仮に災害が起きたとしても家族やご近所、仲間を助けられるし、災害がこなければ自分の暮らしが楽しく充実したものになるのだから。