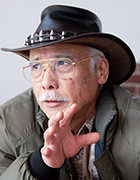機関誌『水の文化』53号
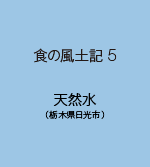
冬の結晶を夏にいただく
日光 天然の氷

天然の氷を削ったかき氷は、ふわふわ感たっぷり。地元産の「とちおとめ」を使った手づくりシロップも絶品(日光霧降高原「チロリン村」)
水と風土が織りなす食文化の今を訪ねる「食の風土記」。今回は、厳寒期に水を溜め、天候と気温を見ながら凍らせる「天然氷」です。戦前まで重宝された天然氷も、電気冷蔵庫が普及してからは全国で廃業が相次ぎ、今では希少な存在となりました。豊かな森が育んだ水を用いた日光の「天然の氷」は、どのようにつくられ、保管されているのでしょうか。
日光の氷は大切な食文化
「ヴィーン、キリキリキリ……」という耳慣れない音が響く。1月下旬の栃木県日光市。住宅街を抜けた川べりの池では、雪が舞うなか天然氷の「切り出し」が行なわれていた。
池に張った氷の上で男性が特製の動力カッターを操り氷を切り出す。それを一つずつ竹で組んだレールに乗せ、氷室(ひむろ)まで滑らせていく。運び込まれた氷はきれいに並べられ、杉の大鋸屑(おがくず)がたっぷりかけられる。
ここには「四代目徳次郎」こと山本雄一郎さんが、先代から受け継いだ氷池(こおりいけ)と氷室がある。水は500mほど遡った場所の湧水を導水管で引き入れる。冬は日があたらず、冷気だけで凍らせるには絶好の場所だ。市内で観光施設を営む山本さんが氷づくりを始めたのは10年前。自身の施設で提供するかき氷用に天然氷を仕入れていたが、卸業者から「氷づくりをやめるらしい」と聞いた。山本さんは一面識もない先代に「手伝いますから続けてくれませんか?」と掛け合ったが首を縦に振らない。「私がつくるので教えてください」と頼んでも断られる。あきらめきれず翌朝から氷室に毎日通い、「これは先代だけのものではない。日光の大切な食文化です」と食い下がり、とうとう継承を許された。2007年(平成19)の冬に教えを乞い、翌年から「四代目徳次郎」と名乗って出荷しはじめた。
天候を予測して「凍らせどき」を探る
清少納言の『枕草子』にかき氷の記述があるように、氷は遅くとも平安時代にはつくられていた。日光は冬こそ寒いものの、東北や日本海側ほど雪が降らないので氷づくりに適しているが、本格化したのは明治期後半。産地としては後発だが、この地には外国人向けの民宿からスタートした「日光金谷ホテル」(創業明治6年)などがあり冷凍・冷蔵設備が必要だった。最盛期には十数軒の氷室があり、地元のみならず東京などへも貨車で運ばれていた。
四代目は、例年11月初旬から氷池の清掃など準備を始め、12月〜2月で氷をつくる。厚さ15cmを目安に切り出すが、通常は2回、多くても3回しか切り出せない。ただ池に水を入れただけでは、質のよい「硬い氷」にならないからだ。
普段は池を凍らせないために常に水を引き入れて表層を波立たせておき、よい氷がつくれそうだと判断したときに水を止める。大事なのは温度と凍り方。表面の氷が硬くなければ、その下も硬くならない。
「氷は夜に育つので、そのときの温度が大切です。凍るのに時間がかかりすぎると柔らかい氷になってしまうし、急激に凍っても柔らかくなってしまう」と四代目は言う。氷点下7〜8度の寒さが数日続くのが氷づくりに適しているが、予想外に気温が下がらない、あるいは逆に下がりすぎた場合はできた氷を割り捨て、次のチャンスを窺う。だから一冬に2、3回しかつくれないし、天候の予測も重要だ。天気予報の精度は高まっているものの、四代目は「先代の予測の方がよく当たるよ」と笑う。
「あの山(赤薙山[あかなぎさん])を見てください。稜線に雲がかかっているでしょ? 雲がのんびり流れているのでよい氷はできません。いろいろなことを先代に教わりました」
氷づくりで伝える昔の知恵と工夫
天候の予測と同様に、氷を保管する氷室にも先人の知恵がつまっている。気温が上がると氷は表面から溶け、にじみ出たその水分が温まり、さらに氷を溶かしてしまう。そこで日光杉の大鋸屑を入れるのだ。大鋸屑は表面に溶けた水分を吸ってゆっくり発散させ、壁と床の杉材が受け止めるため、1年以上保管できる。また、氷を守る大鋸屑は、逆に氷で冷やされるため腐らないという補完関係にある。氷室で今使っている大鋸屑は50〜60年前のもの。「大鋸屑は氷にくっついて外に出た分を補給するだけです」と四代目は語る。
切り出した氷を滑らせるレールに日光の孟宗竹(もうそうちく)を使うのは、毎年地元から調達すれば竹林は人の手が入り、荒れることはないからだ。四代目は「滑らせるときに竹の節がブレーキ代わりにもなる。そうした昔の知恵を少しでも残していきたい」と言う。
「いい氷をつくるには、水がよくなければいけない。その水は森が育んでいる」と考える四代目を中心に、「森と水の会」という団体も立ち上げ、森の保全に着手している。
先人の知恵と工夫がぎっしり詰まった日光の「天然の氷」。硬い氷だからこそのふわふわ感をこの夏、どこかで味わいたい。
(2015年12月22日取材)