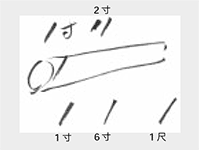機関誌『水の文化』4号
木場に受け継がれる川並の心意気

東京江東区内の木場公園のイベント池で、日頃の成果を披露する「角乗り保存会」の皆さん。 多くの若者が、江戸の伝統を継承しようと集まってくる。
「木場の『角乗り保存会』が往時の川並の角乗りを披露した」という記事が毎年夏に見られます。保存会が江東区の木場公園で各乗りの技を披露したり、技を伝承する為に角乗り指導を行っているのです。東京の下町・木場はすでに「新木場」に移転し、流通形態の変化により、木場の文化を背負っていた「川並」という職業もなくなってしまいました。元川並鳶そして「角乗り保存会」の会長として、若い世代の方々に角乗りの技を伝え続けている川藤健司さんに、木場に息づいていた「水都の文化」について伺いました。
-

-
川藤 健司 (かわとう けんじ)さん
-
川並鳶特有の細い股引きと、七枚小鉤(こはぜ)足袋をはき、腹がけ半纏姿のいなせな川藤会長。 昭和18年、東京木場で生まれる。幼少の頃より父の家業である川並の修行を始め、昭和36年から、本格的に川並の世界に。現在、(株)川勝代表取締役会長。「東京木場角乗り保存会」会長。
木場は木材を中心につくられた町
――川藤さんは、現在「角乗り保存会」の会長をしておられるわけですが、ご自身も川並でいらしたとうかがいました。どのような経緯でこの道に入られたのでしょうか。
川籐 私の親父が川並(注1)で、この木場で生まれ育った人間でして、親父が初代、私が二代目ということです。親父は明治生まれのいわゆる頑固親父、竹を割ったような性格の人でしたね。まあ、物心ついて十歳ぐらいから夏休みや春休みといった学校が休みの度に、遊びがてらに親父の手伝いをやらされました。その経験が川並の第一歩でしたね。本格的に親父の跡を継いだのが、1961(昭和36)年。この年から川並の世界に入るわけですが、角乗りとのつきあいもこの時からです。
――角乗りについてうかがう前に、川並がどんな仕事をしていたのかについて教えてください。
川籐 川並を語るには、木場という場所がどんな所だったのかを抜きにしては語れません。小唄の文句にありますが、木場は橋と堀の町、「木の香ゆかしき深川の」と続くんですね。橋がたくさんあるということは、川がたくさんあるから。橋を渡って木場、深川に入ると、木の香りがプーンとする。そのものずばり、もく(木)の場所「木場」なんです。
その木場は、材木屋、川並、筏師(注2)、木挽き(注3)、荷揚げ人足(注4)の町でもありました。例えば、荷揚げ人足。伝馬船で材木(製品になったもの)を運んでくると、堀に面した岸壁に横付けにする。各材木屋の堀に面した所には、荷揚げ用の取り入れ口が切ってあります。伝馬船からそこへ「あいび板」と呼ぶ足場板を渡すんですが、幅一尺、長さ三尺三寸の板をまともに渡すと坂になっちゃうでしょ(注5)。人力で運び上げるわけだから、あんまり坂になっちゃうときついんですよ。それで、岸壁の取り入れ口を荷揚げ用に、伝馬船よりも少し低くした場所を作っておくんです。そうすれば勾配ができて材木が取り入れやすくなる。このように、木場の町はすべて木材の商いを中心にして、考え抜いて作られていたんです。
(注1)川並
木場で原木を仕分け、検品する川並鳶のこと。
(注2)筏師
原木をまとめて筏に組み、運ぶ職業。
(注3)木挽き
製材職人。今でも最高級の丸太は、手作業で挽くという。
(注4)荷揚げ人足
堀に面した材木倉庫に横付けされた舟から、人力で材木を運び上げる人足。
(注5)
一尺は約30.3センチ。一寸は一尺の十分の一。
川並の仕事は木材のディスプレイ師
川並の仕事と筏師の仕事との違いをお話ししましょう。本船や帆船で運ばれてきた原木が東京湾に着くと、荷主が自分の買った原木を筏に組んで貯木場に持ってくるんですが、その仕事をするのが筏師。筏師は貯木場で大まかな仕分けをして、原木を再び筏に組み直します。東京湾に着く原木は、商社や木場の大問屋が山で買い入れたもの。原木はその後、一次問屋、二次問屋を渡って、製材所で製品になりますが、川並は製品になるまでの道筋で発生する、細々こまごました仕事を受け持ちます。
――具体的には、どのような作業なのでしょうか。
川籐 簡単に言えば、ディスプレイの仕事かなあ。きれいに陳列して見栄えを良くしたり、検尺といって石数(注6)を確認したり、等級(質)を整えたり。要するに、手間をかけることで付加価値を付けて高く売れるようにしたんです。靴屋で言えば、筏師はできた靴をまとめて何足も売る卸売り業。川並は一足づつ売る小売業にあたりますね。ただ小売りと言っても、二次問屋から三次問屋へというようにどんどん細かい商いになっていくんです。
例えば私が、Aという二次問屋の出入りの川並だったとします。原木問屋から仕入れた丸太は、石数で買い上げて堀まで運んできます。それを一本一本測り直して、浮かんでいる丸太にガリ引き(注7)で正しい寸法を印つけしてやる。おもしろいことに一〜三寸は一〜三本引っ掻くんですが、四寸は四か4と書き、五寸は×(バツ)、六寸は一寸と同じで一本なんですね。見りゃわかるというか、一寸と六寸を間違えるわけがないんですよ。一尺も一本です。
同じようなことですが、よく親父から「サシは杖にしとけよ」と言われたものです。検尺は差し金を使って測るんですが、目で測れということです。目で間違いなく測れるようになれば、差し金を当てるのはただ確認だけになるんですね。それを差し金に頼るから数字を読み違えることになる。要は、それを戒める言葉です。
検尺するのは確認の意味もありますが、まとめ買いをした丸太は、細かく測ると合計した石数が上がるんですね。そうすると例えば百万円で仕入れたものが百十万円になって、我々の手間賃が出る。出入りの川並としてAの旦那の役に立つというわけです。さて検尺が終わると、次の買い手に渡すのにきれいに並べ変えてやる。太いのと細いのがばらばらに並んでいる筏っていうのは見栄えが悪いってんで、両端に細い丸太を、中央に太い丸太を並べて蒲鉾型に作るんです。そうしてできた筏を、今度はBという三次問屋の川並が検品するんです。丸太の直径が百分〈ぶ〉(一尺)で長さ十尺が一石。丸太の状態でその見当をつけるんですが、それが九十七分しかなかったとする。分切れ(ぶぎれ)と言うんですが、そういうのを見つけると「おい、これは切れるじゃねえか」と指摘されるんです。Aの川並としては、危ないのを覚悟の上で目一杯測るわけですよ。ある程度利益は出ているのですから、そこで赤伝が切られてもAの旦那の損にはならない。かえって「うちの川並は、俺のために頑張ってくれた」ということになる。顔が立つということです。逆にBの川並が分切れに気付けば「さすがうちの川並だ」ということでBの旦那に顔が立つ。だから、どの川並も目一杯で木を測る。当然、川並同士で、分切れで言い争いになることもありますよ。
わたしゃ健司ですから「ケンぼう」と呼ばれてたんですけど、「おいケンぼう。切れる(分切れている)じゃないか」と言われる。「おじさん、どこが切れるんだよ」というと、「おまえ強情はるんじゃないよ。切れてんじゃねぇか。」こっちは、差し金を引っかける所にゴミで厚みをのせて木をひっかけてるから「切れてないじゃないか」と。すると「おいケンちゃんよー。俺は何十年もやってるんだよ。この仕事をよー。」俺も強情だから「おじさん何言ってんだよ。年のこと言うなら、おじさん、俺はお袋の股から差し金もってオギャーと生まれてきたんだよ」って言うとおじさんが、「いや。参った。お前には参った」となるわけですよ(笑)。そして「おじさん、借りとくよ。次の時返すよ」となるわけ。そして、今度相手がそのおじさんの時は、逆にうんと甘く測ってやるわけですよ。「今日のところは、貸しといてやるぜ」と言い、受けるほうも「この借りは、次に返すよ」っていうんで、持ちつ持たれつだったんです。
(注6)石数
体積の単位。材木の場合、一石は十立方尺を表し、約.○二八立法メートル。
(注7)ガリ引き
丸太を引っ掻いて、字を書く道具。彫刻刀のような形状をしている。
川並は水都江戸にしかいなかった
――江戸に限らず、木場のように木材を商っていた地方都市にも、川並という職業はあったのでしょうか。
川籐 これが江戸だけなんですね。不思議なことに。木場というのは、もく(木)の場所「木場」だから、江戸に限らないわけです。江戸深川の木場は、徳川幕府による築城を中心とした町作りから、木材市場が活況を呈したのが始まり。だから木場も川並も、寛永年間から約四百年の歴史があります。木場の中心となっている深川は、深川という人が埋め立てた干拓地。寛永18(1641)年の大火の後、材木置き場は火災をおこす恐れがあるからと、御用材木商人を移転させた町外れの河口が今の深川です。ここに独自の情緒や人情が発達して、他の地域には見られない川並という仕事の需要を生んだのでしょう。
――川藤さんが本格的に川並となられた、昭和三十六年頃には、川並の親方のは何人ぐらいいらしたんでしょうか。
川籐 確かな数字ではありませんが、親方は二十人ぐらいいたと思います。その下にそれぞれ十人ぐらいの若い衆がついていましたから、全部で二百人はいたのでしょう。まあ、丸太を川に並べて点呼取ったから川並なんだよ。
角乗り川並の「遊び」が「トレーニングの場粋の見せ場」に
――川並と角乗りとはどういう経緯でつながってくるんでしょうか。
川籐 慶長年間から、約四百年になろうかというのが角乗りの歴史です。江戸という所は、江戸城の築城のために、全国からいろいろな職人が集まってきた場所です。当時は遊びがあまりない時代ですよね。職人には娯楽というものがなかった。角乗りというのは、川並という職業の人間が、余技、娯楽として編み出したのが始まりです。仕事の合間に、丸太を回してみる。ところが、丸太じゃ簡単でおもしろくない。こういう余技というのは難しいほうが楽しいんです。ツガ材は角材で来ましたから、今度は角材を回してみる。角材というのは、水面に対して斜めになって浮くんです。それを回すには、角材の角の所に足の土踏まずを引っかけていく。足の裏を載せるのだって、面が四つしかないんです。それに比べると丸太は、足を引っかける所も載せる所も無数にある。それで、難しい角乗りを夢中になって練習して、回せるようになると下駄を履いてみたり、身近にある扇子や番傘を持ってみたりと、次々に難しい技に挑戦していったんです。角乗りというのは、川並の余技、娯楽であると同時に、身のこなしを洗練させて、身軽に仕事ができるようにするトレーニングでもあったのです。それでそれらのすべての技を結集したのが、三宝乗りです。
――ここに川藤さんが、三宝乗りを披露されている写真がありますが。
川籐 ああ、これは明治百年の記念の時の写真だから、1968(昭和43)年かな。角材の上に三宝を三段重ねにして、高い下駄を履き、扇子を持って演じる。しかも、登場のときには、三宝の上にあぐらをかいて突き出してもらって出てくるんです。あぐらからスッと立つと、野原に一本の杉が立っているように見えるんですね。そこでやはり深川らしく、粋な口上が入る。「野中の一本杉でござい」と言うと、パッと立つわけです。それから義経の八艘飛び、鵜の餌拾いと続いて、三宝をばらして角材の上に飛び降りて回すんですが、そこでも「これより器ばらしでございます。通称獅子の子落とし、親獅子が子獅子を谷底に突き落とすように見えましたらご喝采」と口上が入ります。今も、三宝乗りができるように、会員には、全部教えています。
『木場角乗り保存会』
――現在、東京木場角乗り保存会には、何人ぐらい所属していらっしゃるんですか。
川籐 会員は二十五名です。木場の角乗りは、1952(昭和28)年に東京都指定無形民俗文化財に指定されました。新木場への移転ということもあって、ここが木場だったというものが何も残っていない。そんな状況に義憤を感じて、保存会に入る深川生まれの若者も多いんです。木場の情緒がなくなってきたということは、川がなくなり、堀もなくなり、橋もなくなって、筏も浮いていない状況になり、ここが木場だったということを表すものが一つもない。角乗りは、そういう意味から江戸文化、江戸の水の文化の継承でもあります。
――川藤さんが川並になられた頃は、まだまだ盛んな時代だった。
川籐 ええ。この写真で私の後ろに座っている人は、副会長の中村喜三郎さんという人で、私にとってお師匠さんですよ。私が角乗りの世界に入った時に、この中村さんから「お前は川並の伜だし、お前の親父に俺は世話になっている。お前は将来、角乗り保存会の会長にならなくちゃならない人間なんだから、しっかりやってくれ」と言われました。中村さんはその時分、この三宝乗りをやっていたんです。それで「お前もこれができるようになって、いずれ会長になってくれよ」とずいぶん叩き込まれました。
――最近の保存会の様子は、いかがですか。
川籐 乗るのは速く上達するけれど、色気がないね。先程の服装だって、そんな細い股引きを穿くのは粋を気取ってのことでしょう。やはり昔は遊ぶ所でも色街があって、自然と身についたものなんだけれど、だんだんそういうわけにもいかないものね。本来、芸を磨いて、木の知識もあって、色気もなくちゃ川並は一人前じゃなかったんだから。鳶口(注8)を使える人もいなくなったしね。筏を重ねて置くと場所を取らないから、組んだ筏の上に丸太を引き上げて二重、三重にするんだけれど、丸太に鳶口を打たないで人が打った鳶口の鉤の上に誤って鳶口を打っちゃう。するとすかさず「バカヤロー、お灸据えるんじゃないよ」と怒鳴られたもんです。昔は、二言目にはバカヤロー。でもそれが愛情表現だったんだよ。木場、深川、川並といえば、やはり八幡様のお祭り。富岡八幡のお祭りがなければ、話が始まらないんだよ。そして八幡様のお祭りは、水掛け祭り。ここでもやはり、木場は水とは切っても切れない縁があるんだ。
(注8)鳶口
丸太を引き寄せるのに使われる、竹竿の先に鉤の手が付いた道具。