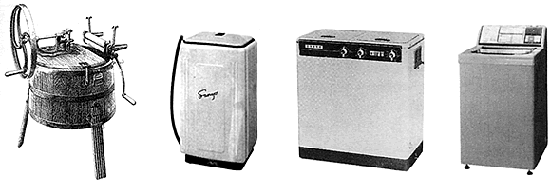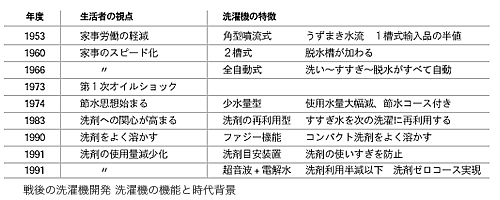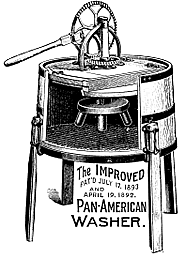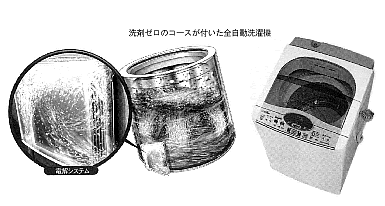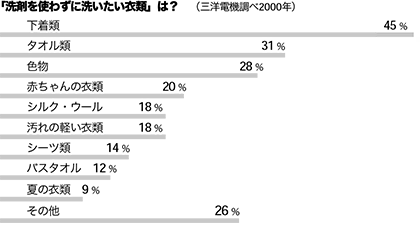機関誌『水の文化』11号
土地の文化を知らないと洗濯機は作れない洗濯機の商品開発と消費者のライフスタイル
-

-
画家
寺田 實 (てらだ みのる)さん -
1946年滋賀県大津市生まれ。 大津中央高校卒業。三洋電機(株)で洗濯機の商品企画に従事。日本初のホームランドリーの企画やコインランドリー導入を実現、日本電気工業会洗濯機委員会委員長や三洋電機(株)営業企画部長を歴任。1999年に画家として独立、毎日新聞にスケッチ&エッセイを連載。著書多数。
昭和28年は電化元年
ーー今日は銀座のギャラリーで画家である寺田さんにお話を伺うわけですが、もう一つの顔でもある洗濯機の商品企画マンとしての経験から、その開発黎明期の話をうかがえますでしょうか。
1962年(昭和37年)の春、1槽式洗濯機の梱包作業をしたのが、私と洗濯機との長いつきあいの始まりです。それから組み立てラインで働き、営業部門に移動、商品企画課に28年間いました。いわば、日本の洗濯機の普及、発展のすべてを見せてもらったというわけです。52歳で退職し、現在は絵を本業にしています。
世界で初めて洗濯機が作られたのは1845年のアメリカで、手動式のハンドルを手に持って左右に揺り動かす方式のものでした。このかき混ぜる方式(撹拌式)が、長らく採用され続けることになります。50年後の1905年に初めて、電動洗濯機ができました。
日本では1922年(大正11年)に、三井物産がアメリカから電気洗濯機を輸入したのが最初と言われ、国産1号機は1930年(昭和5年)に東芝から発売されましたが、一般家庭への普及には程遠い存在でした。
一般家庭に普及したのは、戦後、1953年(昭和28年)8月に、渦巻き水流を起こしてスピーディーに洗う「噴流式」と呼ばれる洗濯機が発売されたことによります。
これを機に、故大宅壮一氏が「電化元年」と命名した年。冷蔵庫、洗濯機、テレビが三種の神器と呼ばれ、日本の電化生活の幕が開けられました。大卒の初任給が1万円の時代に、1万8500円の角型噴流式の洗濯機は、主婦の家事労働の軽減化が図れることから、人気の商品となったのです。当時は、まだ匁(もんめ)の時代でした。今は、容量をキログラムで表示しているでしょう。それが、匁だったんですから。
続いて1960年(昭和35年)には、日本初の2槽式洗濯機が発売されました。これは「洗い、すすぎ」と「脱水」が同時進行できる商品として、大ヒットしました。1槽式からの買い替えが促進され、1966年(昭和41年)に全自動式が登場するまで、日本の洗濯機の主流となりました。
正確に覚えてはいないのですが、かつて、上野動物園にいた象の花子さんがタライに載っている広告があり、「主婦が1年に洗う汚れものの量は、象1頭洗う労力に匹敵する」ということを訴えるものでした。しかし、私が販売の現場で痛感したのは、洗濯機に対する贅沢感がなかなか払拭できないという消費者感覚でした。もうひとつ足かせになったのは、生地が傷むのではないか、という不安です。
同じような抵抗感は、2槽式から全自動への移行期にも見られ、水をたくさん使うのではないか、騒音がうるさい、生地が傷む、というようなことを言われました。結局それらを一つひとつの誤解を解いて受け入れてもらうことでしか、一般への普及はありえないというのが、現場から見ていた私の実感です。つまり販売拡張のため、消費者の頭の中にいる「悪魔」を取り払う役割を担っていたというわけです。
人が参画する要素を持った家電、洗濯機
洗濯機は、もともと人間が手でしていた作業を機械化したものですから、洗濯のプロである主婦層を相手にしなくてはならない。相手は洗濯のプロ。そこが、メーカー主導で開発が進められたビデオやテレビとは決定的に違います。
家事が嫌いな人でも、よく晴れた日に洗濯をして、庭に乾したときの爽快感は感じることでしょう。「洗濯」という作業には、一人一人にある種の思い入れがあり、洗濯機にも同様の充足感を満足させることが要求されたということです。充足感を満足させるという点では、2槽式のほうが全自動式より優れていたということができます。実際、全自動式のように、使う側の人間が作業にまったく参画できないスタイルの洗濯機は、2槽式に比べ普及に時間がかかりました。
15年ほど前にシカゴで主婦を30〜40名集めて消費者調査を行いました。そこで出された意見を集約して作れば理想の洗濯機ができるだろうと考えたのです。アメリカで意気込んで発売したのですが、全然売れませんでした。ユーザーの意見を尊重しすぎると、特長のある商品づくりができない。つまり、平均的なものには、消費者は魅力を感じないのです。
同じことは日本の専門機関の研究にもいえることで、データを鵜呑みにできません。やはり商品企画は、難しい仕事ですね。常に消費者の要望と時代背景を察知する先見の明が求められ、設計・技術、営業・企画、デザイン、販売、お客様クレームといった、全社あげての商品開発が、新しい商品の提案へとつながっていきます。消費者のニーズを単に反映させるのではなく、さらにこちらが消費者に一歩進んだ提案を行わなくてはならないのです。
汚れが軽度になってきた
当初は利便性追及で始まった商品開発も、1973年(昭和48年)の第一次オイルショックで、洗剤不足の不安を経験し、洗剤供給の安定、洗剤の少量化、ひいては環境面への配慮など、多様な視点が求められるようになりました。
また、共稼ぎの家族が集合住宅で夜に洗濯しても騒音が生じない商品がヒットするなど、ライフスタイルの変化にも敏感でしたね。洗濯機についている糸屑フィルターもほんの些細なものですが、これがないと洗濯物は糸屑だらけになってしまう。これは、森さんという設計課長が日本で初めて開発したものです。
渇水が深刻だった夏を経験してからは、節水型の洗濯機が開発されました。2槽式では通常200リットル前後の水が消費されていましたが、オイルショックをきっかけに資源全般への関心が高まり、少量の水で洗濯できる機器の開発が急務になり、全自動式で100リットル前後で洗える商品が開発されました。
また洗剤の発達や変化についても気を付けなければなりません。洗濯用の合成洗剤も一昔前までは大箱でしたよね。コンパクト洗剤が出回るようになったのも、洗剤メーカーの配送コストの問題です。それまでふわっと溶けやすい洗剤だったのが、ぎゅっと濃縮されて溶けにくいものに変化してしまう。それで困るのは、溶け残った洗剤が全自動式の洗濯機の内槽と外槽の間に溜まって、洗濯物を逆汚染することです。この洗剤をいかに効率的に溶かすかということを追及することも大切です。
最近では汚れの質が変化し、かつては「汚れたから洗濯する」、という考え方が、「着たから洗濯する」に変わってきています。昔のように農作業や泥んこ遊びで衣服が汚れるということは、ほとんどなくなってきています。せいぜいが、「汗をかいた」といった程度の汚れです。2001年8月に世界で初めて発売された、洗剤を使わずに洗う洗濯機の登場は、まさにこのような「軽度の汚れ」の時代の申し子ではないでしょうか。電解水の力と超音波洗浄方式を用いて汚れを落とす仕組みですが、汗を落として衣服を清潔に保とうという考え方なら、充分な能力を持っています。無駄に洗剤を使って、河川を汚染する心配もない、究極の環境配慮型です。
洗濯文化と洗濯機文化の関係
家電メーカーとしては、海外への輸出も積極的に行おうと当然考えたわけですが、こと洗濯機に関しては、どうもそれが難しい。つまり、洗う文化が、国によってこれほど差があるものだとは、想像もしていませんでした。ですから洗濯機への要求も、国によって事細かに違ってきます。
日本では古くから洗濯の記述が見られます。『古事記』にも『今昔物語』にも『徒然草』にも登場します。日本で、洗濯は、元来衣服についた邪気を払い、神に近づく「潔斎」、「みそぎ」の発想が根底にあると考えられています。ですから毎月決まった日には、そこら辺を浮遊する霊が乾し物に取り付くから、洗濯はしないという俗信までありました。
日本の特殊性としては、何よりも水が豊富にあったということがあると思います。このため、日本の洗濯は水をたっぷり使った「流しすすぎ」が主流でした。角型噴流式の洗濯機も、その日本人の感性に合致した商品といえるでしょう。2槽式の洗濯機で流しすすぎをしていくと、汚れていた水がだんだん澄んだきれいな水になってきて、汚れが落ちてきれいになったという説得力につながります。
後に全自動の節水型が登場して、中間脱水を行うようになります。洗った後の洗剤の泡を脱水で落とし、水をちょろちょろと入れてまた脱水、これの繰り返しで洗剤を落としていくやり方ですが、流しすすぎと同じ効果を少ない水で行っていると消費者は頭では分かっていても、感性としては納得してもらえない。ですから、洗い上がった洗濯物に鼻をくっつけて、
「あら、洗剤の匂いが残ってる。やっぱりまだすすぎが充分じゃないんだワ」という話になるんです。
また、水の性質の違いも、洗濯の仕方を決定する際の大事な要素となります。日本では軟水ですが、ヨーロッパ等では硬水が主流。水を豊富に使える日本では圧倒的にうず巻式ですが、ヨーロッパでは、主としてドラム型です。ドラム型は、大変時間がかかるのですが、少ない水で、生地を傷めないで洗うことができます。石鹸を溶けやすくするためにお湯を用い、少ない水量で洗います。また住居が石造りのため、多少騒音がしても構わないというスタイルの洗い方に落ち着くのです。
では、アメリカはどうか。アメリカは基本的に容量が大きくなくてはならない。棒が付いている撹拌式で、大物を時間をかけて傷めずに洗う、というスタイルになります。
「乾かす」の導入
乾すという感覚も、これまた違ってきます。一般的に日照時間が短い北ヨーロッパでは、「人の目に触れる場所に洗濯物を乾すのはけしからん」という風潮が主流です。日本も、徐々にそうなってきています。ベランダに洗濯物を干すことを禁止するマンションとかが出てきているようですから。
ホームランドリーのヒットは、そういう風潮が日本にも浸透してきたことがきっかけとなったと思います。ホームランドリーという名前は1979年(昭和54年)、私が命名しました。下が洗濯機、上が乾燥機というものです。乾燥機の販売も、やはり贅沢感を払拭するのに時間がかかりましたが、「乾す所がない」、「乾す時間がない」というライフスタイルの家庭には爆発的に浸透していきました。もちろん時間がかかり電気代がかさむ、洗濯物が縮むといった乾燥機の欠点の克服がなされた上での話です。
コインランドリーのアイディアも僕が打ち出しました。ずいぶん銭湯などに通って、置かせてもらいましたよ。昭和46年のことです。その時には、こんなものは普及するはずがないと言われていましたが、今では全国に1万店強のコインランドリーがあります。銭湯の片隅にひっそりあったコインランドリーですが、今では車で乗り付ける郊外型にシフトしつつあります。こう考えると、洗濯に対する日本人の感覚も隔世の感がありますね。
土地の文化を知る
洗濯文化の違いというのは、風土、生活習慣、水の需給事情、湿度、家屋の構造等など、多岐に渡ります。しかし、日本の洗濯機が海外で売れない最大の原因は、価格が高く、小さいこと。日本と違って海外のメーカーは、いったん金型を作ったら20〜30年は変えないのです。ずっと同じ金型を使います。そのためもあってか、海外製品はものすごく安価で、大型の商品ができます。置く場所には困らないし、日本のように住宅が密集していなければ、騒音がしても気にならない。洗濯機の開発も、やはり日本では微に入り細にうがつことが求められているんだなあ、と思いますよ。
そのことを証明する例として、イタリアのファブアーノという紙の産地で有名な所があります。そこにあるメーカーは、世界の洗濯機をOEMで生産、つまり自社の名前を出さずに、他の会社の名前で何社もの商品を委託製造している会社なのです。ヨーロッパを中心に世界各国から受注して、実に大量の洗濯機がここで生産されているわけです。OEMという委託生産体制を取るメリットは、自社で作るよりコストが抑えられるからです。僕が企業人だった頃、洗い、すすぎ、脱水、乾燥までできる洗濯機を作る企画が持ち上がり、このメーカーを訪ねました。新製品の製造には、生産用の金型やライン設備などに膨大な資金が必要となります。それを、世界の洗濯機を集中して作っているこのイタリアのメーカーに生産してもらえれば、かなりコストを節約できるのではないかと考えたわけです。
ところが予想に反して、まったく使いものになりませんでした。一番問題になったのは、振動です。結局、日本から防振機構を持って行き付けたりしました。つまり海外から日本に逆輸入しても、「そのまま」では売れないのです。それだけ日本の消費者は、製品への要求度が厳しいということです。
日本電機工業会洗濯機専門委員長時代には、台北、北京、香港、マニラ、バンコク、クアラルンプール、ロンドン、ローマ、パリ、ハンブルグ、ロサンゼルス、シカゴ、オタワの個人の住宅を3年半ぐらいかけて訪問し、徹底的に現状を調べさせてもらいました。
そこでわかったことは、何か。それは、「その国の文化を知らなくては、洗濯機は作れない」ということです。これほど輸出入の動きが少ない家電は、他にはありません。
洗剤とは、切っても切れない間柄
ーー洗濯と洗剤は切っても切れない縁でつながっていると思いますが、相互開発の協調態勢はあったのでしょうか。
いやあ、まったくそんなものはないですね。食器洗い乾燥機の場合は機械が売れないと洗剤も出ない、ということで比較的仲が良いようですが、洗濯機に関してはまったくそういうことはありません。
洗剤を使って洗濯するようになったのは、近代のことです。日本で石鹸が登場するのは、室町時代にポルトガルの宣教師が「シャボン」石鹸を持って渡来したのが始め。しかし、石鹸の存在や使用は一部の特権階級に限られ、一般消費者に普及したのは明治10年以降のことです。それ以前には、ワラ灰(灰汁)や米の研ぎ汁といった自然系のものが使われていました。普通の汚れというのは、時間をおかなければほとんど水洗いで落ちるものです。ですから、こういった自然系の洗剤を使っているうちは、琵琶湖のような閉鎖性水域での富栄養化もあまり問題にならなかったのだと思います。
僕は生まれも育ちも琵琶湖湖畔。今となっては信じられませんが、僕が子供の頃は、琵琶湖の水でお茶を入れて飲んだんですよ。それが「琵琶湖の水は汚い」というのが定説になってしまって、悔しくなって市民運動に参加するようになりました。
先ほどコンパクト洗剤の話をしましたが、洗剤を入れる順番を考えたり、お湯を使ったりと、洗剤を溶けやすくするための啓蒙を行いました。消費者には「洗剤を多く使えば、汚れがよく落ちる」といった誤解も潜在的にあったため、これを改めるためにも、コンパクト洗剤を溶けやすくする機能や、洗剤量目安付き商品の開発も行われましたね。
洗濯機を通して
ーー半世紀の日本の洗濯機の変遷のうち、約40年に渡って関わってこられた寺田さんは、今後、洗濯機に何を期待しますか。
「傷めず早く洗う」というのが、洗濯機一号機の使命でした。それが、「傷めず静かに大量なものを早く洗う」になって、やがて「ランニングコストを安く」という条件が加えられました。今後は、それにプラスして「乾燥までできること」という要素が要求されるようになると思います。
皆さんご記憶と思いますが、以前は洗濯機は庭にありました。これはやはり、洗濯機がたらいの延長と捉えられていたことの表れでしょうね。家屋の内側に入ってきたのは、この20〜30年のことです。しかし、これだけ多様な事柄が要求される家電製品が、雨ざらしで屋外に置かれるのですから、耐久性の面でも大きな開発努力が要求されたのです。
日本人の洗濯観も、「汚れたから洗う」から「着たから洗う」になり、汚れの程度は軽度になっているにもかかわらず、洗濯回数は増えました。昔のように着たきり雀ではないので、洗濯物の量も圧倒的に多くなっています。このようなライフスタイルの変化に合わせて、メーカーはますます努力することが問われていくでしょう。
でも自分が売っていたのに、このようなことを言うと何ですが、腰をかがめて、たらいに向かい、自分の手で洗って、絞る。しわを伸ばしてパンパンとはたいて、物干竿に乾す。お日さまの匂いがする乾いた洗濯物を取り込んで、きちんと畳み、家族のそれぞれの引出しに直す充足感。こういったものは、洗濯機が進化すればするほど失われて、家事文化、洗濯文化が次世代に継承されないようで、ちょっと哀しくなりますね。
僕は、洗濯機も洗濯文化の一翼を担う存在だと想っています。せっかく「充足感を共有できる家電」という使命を受けて、洗濯機が開発され続けてきたのですから、その経験を大切にしてほしい。そして、洗濯が文化として現代まで継承されてきたように、次世代にも伝えられるものでありたいと思います。洗濯は水が命、みずみずしさを失わない商品開発を期待しています。