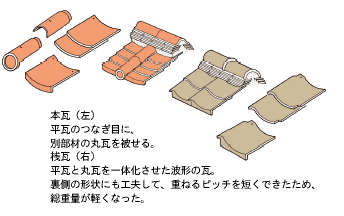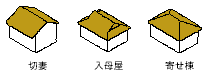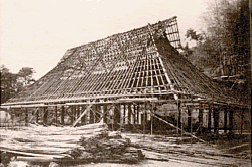機関誌『水の文化』17号
屋根から雨に思いを馳せる 雨をしのぐ屋根 外に誇る屋根
-

-
京都工芸繊維大学教授
石田 潤一郎 (いしだ じゅんいちろう)さん -
1952年生まれ。 京都大学大学院工学研究科博士課程修了。滋賀県立大学助教授を経て、現職。 著書に『屋根の話』(鹿島出版会、1990)、『スレートと金属屋根』(INAX 1992)他。
屋根材は地域固有の素材で
日本では、雨露をしのぐということが住宅の最大の要件です。原始住居では屋根と壁は一体で、寒さをしのぐというウェイトが高かった。縄文時代までは現代よりも寒かったのでしょう。旧石器時代は葉っぱがついたままの生木で作ったシェルターのような住居です。
一方で、屋根を葺く材料も問題です。日本の場合ですと茅などの草と樹皮から始まって、今日まで残っているものは茅葺き、板葺き、檜皮(ひわだ)葺き、そして瓦の4種類に集約されます。北方民族ですと、鮭の皮を剥ぎ、それを屋根の上に張りつける例もあります。さらには、割った石板(スレート)で葺く地域もあります。葺き材は、大量にしかもコンスタントに供給されるものでないとなりません。日々傷んでいくものですから、簡単かつ大量に身のまわりでとれる材料に限定されてきます。
茅葺き屋根のはじめというと、登呂遺跡のような住居を思い浮かべますが、実際は茅の上に土を盛っていたのではないかということが、考古学の分野で指摘されているようです。浅間山の麓に「日本のポンペイ」といわれている村があります。紀元6世紀ぐらいに浅間山の噴火で全村燃えた所ですが、発掘された火山灰の下の潰れた家を見ると、屋根の上に、火山灰ではない土が盛ってある。ですから、骨組みを組んだ上に薄く草を葺き、土を塗り固めていたようなのです。雨で溶けないか心配になりますが、固めるとそうでもないようです。
日本の場合は雪国でも、勾配を急にして雪を落とす一般的なパターンと、板葺きを石で押さえ、ひたすら雪を溜めて耐える新潟県に見られるようなパターンがあります。後者ですと半端にずり落ちて屋根が傷むのが1番困るそうです。農家は基本的には茅葺きになります。茅で葺く場合は、地域の入会地に茅野を作って茅を育て、みんなで使う。葺き替えのときも協力して、今年はAさんの家、来年はBさん、とみんなで協働する。「結(ゆい)」といわれる制度で、これは全国的にみられます。
ですから、町の中心部になると茅の供給ができなくなる。また、瓦も桟瓦(さんがわら)が発明される以前の本瓦は重量があって、骨組みを頑丈に作らねばならず、お金のない人は瓦が使えませんでした。したがって、そういう所は板葺きになり、昔の「洛中洛外図」などを見ると、京都では、板の上に竹の網のようなものを載せて押さえたりしていたわけです。
珍しい所では、長崎県の対馬に、石置き屋根というのがあります。あれは、倉庫を頑丈に作ろうという時に、平たい石が簡単に手に入るためによく使われる。そういう局地的に、ある場所だけで大量に供給される材料があると、それを使うことがあるわけです。
蛎殻(かきがら)葺き
ただ、おもしろい葺き材もあったようです。東京では蛎殻葺きというのがありました。日本橋に蛎殻町という地名も残っています。単なる蛎殻ではなく化石の蛎殻で屋根を葺いたといいます。江戸は非常に火事の多い町で、桟瓦が普及する前は、お金のない人は瓦が使えないわけです。このため、都心でも板葺きや茅葺きが多く、すぐ火事になる。幕府はそれを何とかしなくてはならなかった。
瓦を葺けと指示しても、みんな言うことを聞かない。それで、火の粉が飛んできてもすぐには燃えないようにと、板葺きの上に蛎殻を葺き並べるよう18世紀の初めごろお触れ書きが出ます。この屋根は、ちょっと雨風が吹くと蛎殻がずり落ちるので、軒先に貝殻止めの横木「貝留め」を張ったそうです。
蛎殻屋根はある時期流行ったようですが、軽く葺ける桟瓦が大津で開発されたため、ぱたっとなくなってしまいます。1730年前後の江戸では武家、町家とも多く蛎殻屋根だったと言われていますが、16年間の推進政策が終わると、お金のある人は桟瓦にするし、お金のない人はまた元の板葺きに戻ってしまった。こうして、江戸の町では屋根材が一定でないという特異な状況が現れます。
京都や大坂は桟瓦が大変早く普及したので、上方から江戸に行くと、ばらばらな屋根の街並みが非常に奇異に見えたらしいですね。
―― 住み手は、葺き替えの寿命を何年くらいと想定したのですか。
気候条件によるのですが、茅ですと25年から30年。大分県では茅は40年、麦わら15年、稲わら7年と言われているそうです。みなさん、沖縄は赤い瓦にシーサーが載っている屋根を想像するかもしれませんが、薩摩藩が茅葺き以外認めなかったため、明治後期までは茅葺きでした。ところが、沖縄の茅は寿命が短く、だいたい4、5年と言われています。寒い所で育った茅のほうが寿命が長いのです。
葺き替えというと我々は、すぐに白川村の総葺き替えみたいなものをイメージしますし、文化財だと補助金がついたときにまとまって行うわけですが、現実には、表面の一番傷むところだけ替えるとか、北側の陽があたらないところが腐るからそこだけ替えるというような、挿し茅という形で、常にちょっとずつ替えているというようなことだったらしいですね。檜皮で30年~40年ぐらい、板葺きはもう少し寿命が短いと思います。
屋根の形を決めるもの
竪穴住居では屋根が地面に接しており、時代が下るにしたがい屋根が持ち上げられていき、立ち上がる。そうなると、柱の上にいかに斜めの屋根部材を組み立て、載せるかが重要な要素となります。ある傾斜を持った面を、どのようにつくるかが家づくりの出発点だったと思います。いわば建築技術の一つの成果、エッセンスが屋根の骨組みに表れています。
降雨量と、降るのが雨か雪かによっても、屋根の形状は違ってきます。ヨーロッパでは、アルプスの北と南とで画然と違っています。北は雪が滑落しやすいように急勾配になり、スレート屋根が使われます。スレートは硯石と同じ材質ですから割り肌は滑らかで、雪が降ってもすぐ落ちます。ドイツでは、スレート屋根が多いですね。
それがイタリア、スペインになると雨だけですし、雨量も少ないですから、スペイン瓦という円形を並べたような瓦葺きになり勾配が緩い。一尺いって三寸上がるというぐらいの勾配です。イタリアの町を塔の上から見下ろすと、赤茶色の屋根瓦が一面に張り付いたように広がっていますが、同じ葺き材の屋根が同じような勾配で使われることが多いということがわかります。スペインは半円形断面、イタリアは平面的な瓦ですが、いずれも都市全体が統一されていて、景観上大きな要素になっているのは、皆さんご存じのとおりです。
日本では桟瓦葺きが江戸時代の半ば以降に普及しますが、これにも地域差がある。京都のように比較的強風が少なく、横殴りの雨が降らない所ですと、屋根勾配が緩くなります。下から雨が吹き上げられないので、毛細管現象で中へ水が侵入しないため、緩くしても構わないからです。
要するに屋根は傾斜が緩ければ緩いほど、屋根の懐が小さくなって小屋組みに使う木材が短くて済むということがあり、経済的にはできたら平べったくしたいのです。日本で1番屋根が緩いのが、京都の山科だといわれています。普通の京都の町屋で、おおよそ十尺いって四寸か四寸五分上がる勾配です。関西は割合平べったく、そこへ細い棟瓦が載るという華奢な感じに仕上げます。
これが関東に行きますと、例えば川越の土蔵造りは五寸から六寸という、お寺に近いような急な屋根になり、重たく感じます。このように、関東では屋根が立ってきますから、屋根の面が目立ちます。それに見合うように、棟瓦の積み上げも、段数を多くして、重々しく見せるというデザインになってきます。ですから、雨の降り方の差、雨量と風の強さがデザイン全体に及んでいるとも言えるのではないでしょうか。
さらに、瓦ではなく、茅ですと話が違ってきます。茅葺きでは傾斜が緩いと水が漏ってしまうので、ほとんど45度前後、緩くても38度程度。それより緩くなると水が漏るし、60度以上立ててしまうと、今度は葺く時に危険で仕方がない。白川郷あたりは、多分限界でしょうね。勾配が急なところは、雪対策のため、あるいは屋根裏部屋を養蚕に使うといった、室内用途からの要請もあると思います。
― 勾配ではなく、屋根の形状はどういう要因が影響しますか。
例外もありますが、定説として言われているのが、寄せ棟は竪穴式住居系、切り妻は高床式住居系という分類です。竪穴住居の屋根は、周りから枝などを取り囲むように立て掛けたので寄せ棟風になりました。多少煙出しの穴を開けたりして入母屋的にも見えますが、基本的には寄せ棟です。こうして日本の土着の形式として寄せ棟屋根が出発し、入母屋にも発展していきました。ここに入母屋民家の骨組み写真があります。入母屋の民家 垂木の並び方がよくわかる。『物語/ものの建築史‐屋根のはなし』(鹿島出版会1990)よりいかにも四方から集め寄せ掛けた形になっていて、竪穴式住居がまわりから木を差し掛け、屋根を組んでいた名残りであろうといわれているわけです。
これらの民家とは別系統で、神社仏閣建築があります。見た目は同じ入母屋でも寺院建築の場合、寄せ棟から変化した民家における入母屋とは、構造も違うものです。寺院建築は、中国からいわば先端技術として伝わってきました。そこでは、入母屋、寄せ棟、切り妻がセットで導入されますが、入母屋は2階建ての大規模な建物に用いられ、寄せ棟は平屋、そして切り妻は付属的な施設のものでした。つまり、入母屋がもっとも格が高かったわけです。寺院建築の入母屋屋根の発生は、おそらく切妻屋根の妻側に庇を伸ばしたものです。ここで庇というのは軒を覆うだけの短いものではなく、建物の構成要素として重要なものでした。古代から鎌倉時代までは、いったん「身舎(もや)」と呼ばれる中心構造体を建て、もっと広くする必要があるときに庇を延ばしていました。京都御所の紫宸殿を見ますと、屋根の面に段差がついています。この段差が最初の構造体の庇から新たに延ばした庇に切り替わる境界なのです。もちろん、今の御所の紫宸殿は、最初から一体で造られていますが、発展の過程を示しているわけです。
ですから、大陸からの技術が使えるような支配者階級が切妻、入母屋系の屋根で、寝殿造りは、入母屋になります。
町並みの屋根
室町時代までの屋根は、かなりばらばらでしたが、江戸時代になると幕府が派手なデザインを禁じます。町並みというのは、今は民家が並んでる景観という意味ですが、昔は人並みの並みでして、みんなと同じようなレベルにそろえようというのが町並みという意味でした。その中で、同じ屋根勾配で、同じ材料で、同じ屋根の家をそろえるということが固まってくるわけです。
それでも、屋根のデザイン的な美しさには、やはり意識しただろうと思います。成文化されたルールはありませんが、何か突飛なことをすると人から何か言われるとか、役人がやってきて「やめろ」と言うとか、そういうことはあったらしい。とにかく統一をとって、ある整然とした美しさを求めたのではないかという気はします。
― 滋賀県の高島町などでは、瓦の古い町並みが残っていて印象に残りますね。
実はあのあたりの瓦葺き集落も、昭和40年ぐらいまでは茅葺きだったところが大半なのです。
普通の農村や街道町ですと、戦後まで茅葺きで、それがどうも高度成長期になるころに一斉に変わったようです。茅葺きは、結で維持している部分がありますから、一斉に崩れるという面がある。葺き替える金がないとか、年寄りで息子が継がないという家が茅葺きをトタンで覆い、あとはもう将棋倒しのように変わってしまう。
それでも昭和40年代までは、まだ意識していたのか、あるいは技術的な幅も狭かったからか、ある種の統一された形式の屋根が残っていました。しかし、それからさらに40年経った現在では、選択肢が多過ぎて、選ぶほうでもそれが面白くて、ばらばらになっていくという背景がありますね。我々が屋根を調べる際にも、苦労します。村の屋根がいつ変わった、というようなことは史料には出てきませんから、結局現地に話を聞きに行くしかありません。おじいさん、おばあさんをつかまえて訊くと、「これは何年に、何とかという屋根屋が売りつけにまわったんだ」ということを話してくれます。
高度成長期の時代は、やはり、茅はちょっと貧乏くさいという意識があった。今でこそ素敵で残さなくてはという思いが生じていますが、当時はとにかく瓦のほうが格好いいという風潮です。瓦は手間もかからないし、雨漏りもしない。それでみんながどんどん変えていってしまったということがあります。
茅場も意識がちょっとでも薄れたりすると、維持されなくなるし、結(ゆい)も崩壊してしまうのです。
サスティナブルな屋根のデザイン
屋根の形状や材質は、これまでの述べてきたように地域性が高く、どういう屋根を美しいと感じるかには個人差があります。しかし日本に限って言えば、茅や瓦になれ親しんだ感性から美しいと感じる要素は、分節された茅や瓦のような素材が、繰り返されるところにあると思っています。
ツルンとしたトタンにペラペラした印象を持つのは茅や瓦のイミテーションとして使うからであって、近代建築を進めたミース・ファン・デル・ローエやル・コルビジェのように素材の持つ機能を生かした使い方をすれば、日本人にも美しいと感じられるかもしれません。そういう意味では、屋根も建築もこれからどんどん変化があって当然でしょう。
京町家の再生に携わっている人の話を聞きますと、冷房も暖房もがんがん入れないととても住んではいられないそうです。そういう視点で短期的に見ると、必ずしも環境に優しい建築とも言いがたい。京町家は奥に庭があるうなぎの寝床のような形で、前と後ろが通風できることでかろうじて維持できているという極めてパッシブな建物です。高いマンションが建つと、途端に日当たりが悪くなり風が吹かなくなるから、逆に言うと住み手は周囲の都市環境に対して神経質にならざるを得ないですし、いわゆる炭坑のカナリア役のような建物なのです。だからこそ、広い意味から言えばやはりサスティナブルデザインと言えるでしょう。
トータルとしてみると、やっぱり環境に寄与する部分というのが相当あるな、という印象があります。エネルギー消費型でない京町家をいかに作るかということも非常に大変ではあるし、それが町家ブームみたいな言われ方でしか語られないのは残念ですが、かなり射程距離の長い話だと思います。
屋根というのはデザイン性だけでなく機能が重視される箇所ですから、材料とか形状はその土地の自然環境、あるいは材料供給など、純物理的な要因で規定される部分があり、まさに建築物と外界との接点であり、せめぎ合う場所なわけです。
だから、環境に優しい1種類の屋根が決まっているのではなく、屋根というのは、環境に対する自らの姿勢を決める要素だというふうに思います。つまり屋根を考えることで、外とどう向かい合うのかという自分の姿勢を、はっきりと固めることができるということです。
それは、必然的に、雨にどう対していくのかということにもつながってくるわけです。