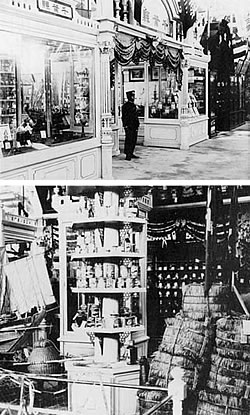機関誌『水の文化』25号
船主・商人ネットワークの水産資源へのインパクト
三陸水産資源盛衰史

岩船郡村上三面川鮭浚之図 (財)村上城跡保存育英会所蔵 写真提供:新潟県立歴史博物館
-

-
東京農工大学大学院共生科学技術研究部助教授
高橋 美貴 (たかはし よしたか)さん -
1966年生まれ。 東北大学大学院文学研究科国史学専攻博士後期課程修了。 主な著書に『近世漁業社会史の研究-近代前期漁業政策の展開と成り立ち-』(清文堂出版1995)他。
交易と資源の関係
私は、学生時代から三陸や新潟の鮭漁の歴史などを調査してきました。資源管理という観点から見ると、これらの地域では18世紀初頭と18世紀後半から19世紀初めにに大きな変化がありました。
18世紀から19世紀にかけて、全国的に塩引き鮭が広く消費されるようになるようです。ただ、これは全国規模で長期的な動きとしては推測できるのですが、個々には多様な状況があります。例えば、越後の村上藩(新潟県)では下級武士・青砥武平次(あおとぶへいじ)の提言によって鮭の「種川制度」が導入されます。種川というのは川の中洲に鮭が産卵する条件に合うようにバイパスした川をつくり、そこで自然産卵させて鮭の回帰を狙ったものでした。漁業資源の保全制度としては画期的なものですが、ここで増産された塩引き鮭がどこに流通したのかはよくわからない。しかも村上藩の史料を見ると、村上に蝦夷地産の秋あじ(秋鮭)が入荷されています。地元に秋あじが入っているにもかかわらず、三面川でわざわざ鮭資源の増産をしなくてはならない必然性がよくわからないんです。でも、その増産された鮭が売れているのは確かです。おそらく都市部ではなく、内陸農村部などに向けて出荷されているのではないかと思います。つまり、今まで水産物をあまり食べていなかったような場所にまで流通するようになり、消費量が増えたのではないかと推測しています。
種川制度が導入されたころに村上藩が力を入れていたのは、生糸、煙草、陶磁器生産、漆などの殖産興業でした。明らかに食生活、住生活にかかわるような物産です。その市場のひとつとして狙っていたのは、おそらく内陸の農村部でしょう。逆に、この時期には、漆器、陶磁器、水産物の消費の拡大が内陸部であったのではないかと推測しています。
考えてみれば、豪農の文化活動が活発化するのもこのころですね。
食生活史研究は都市が中心で、農村のことはあまりわかっていません。行事食はある程度わかっていますが、これにも鮑(あわび)やスルメなどの海産物が多くなっていくようです。こうした食習慣も18世紀後半から19世紀にかけて活発になってきたのではないかと思います。
村上藩と同様の動きは三陸にも見られ、市場との関係を考えるならば、そうした水産資源と物流(海運、河川舟運、陸運)が促進した交易圏拡大を見ないとならないでしょうね。
三陸鮭の商品変動
では、三陸の鮭はどうだったのでしょうか。
江戸時代後期、17世紀後半から18世紀初めというと、南部藩などが藩営として、江戸に向けて水産物を大量に出荷した時期です。南部藩の農業生産量は大きくない。そこで、林業や漁業などの自然生産物を商人に請け負わせて捕らせ、それを大量に江戸に出荷させ、その運上金を吸い上げるという仕組みで藩営をしていました。
鮭漁も、こうした動きと連動して、17世紀末から18世紀初頭にかけて、出荷量がすさまじい勢いで増える時期があります。わずか10年で漁獲量が2倍になるというペースです。捕った鮭は、盛岡城下町にも出荷されるのですが、多くは江戸に運ばれていたようです。
ところが、その後の18世紀初め、たった5年程の間に鮭の生産量が三分の一に急落するのです。南部藩は困り、大混乱に陥ります。
なぜ生産量が落ちたのでしょうか。
私は捕りすぎの影響と考えたのですが、生態学者に言わせると、鮭は資源変動が大きい種で、そう単純な話ではないらしい。また、前近代社会の人間が自然に与えるインパクトなどはたかが知れていて、鮭の資源量が左右されるほどの影響は有り得ないだろうというのです。
原因ははっきりと特定できません。ただ面白いのは、三陸の場合、それを契機として、鮭の資源保全慣行に気を配るようになるということです。鮭は夜に遡上するので、「夜は漁をしない」とか、「朝の2時間だけしか漁を許さない」という漁業規制の慣行が南部藩ではでき上がってくる。宮古(岩手県)の津軽石川でそのような慣行が導入されるのが1749年(寛延2)以前であることもわかっています。
それ以降も、南部藩領から鮭が江戸に出荷され続けますが、目立つ商品ではなくなっていきます。それと前後して伸びてくるのが蝦夷地産の鮭でした。
南部藩は18世紀後半になると、他の水産物を江戸向けの主力商品として出すようになります。例えば鮭がダメになったころから、漁の遠洋化が始まり、鰹(かつお)を捕るようになります。18世紀後半には鮪(まぐろ)も捕るし、魚肥生産のために鰯(いわし)の生産量も拡大していきます。この中でも大きい位置を占めるのは鰹と鰯でした。
つまり、資源量や江戸市場での消費量などに応じて、漁獲される魚種が変わり、加工方法も変っていくわけです。
鰹節の加工技術は紀州から
鰹生産の拡大は、18世紀初頭に始まります。鰹の一本釣り漁法や鰹節の加工法はもともと三陸にはありません。紀州漁師を呼び寄せて、入ってくるんですね。現代でも三陸には、「紀州から漁師を呼び寄せて鰹漁を導入した」という伝えの残る家が残っています。そういう家が紀州漁師を雇って地元漁師に技術を伝え、急速に鰹漁が広まっていきます。尾州(尾張)からも来ていますね。捕った鰹は、塩鰹や鰹節に加工されました。
こうした紀州漁師は出稼ぎの寄留者が多いのですが、紀州出身だという家伝を持つお宅が三陸には今でもあることから、そのままいついてしまった人も多いのかもしれません。
紀州漁師が鰹節の製法を伝えるまで、三陸では鰹の加工品は塩鰹が中心だったようです。塩鰹は、樽の中に、腹わたを抜き塩をまぶした鰹を重ねてつくったもので、保存がいい上、にじみ出た漬け汁は調味料にもなりました。
それに対して、鰹節は加工に大変手間がかかる産品でした。鰹節は、鰹をまず三枚におろし、それを熱湯で約1時間煮熟(しゃじゅく)します(生利節(なまりぶし))。次に、乾燥した楢(なら)やクヌギ、桜などの堅木を炉で燃やし、その中で生利節を1時間ほど焙乾(ばいかん)して水分を抜きます。さらに鰹の生肉をすり込んで外形を整え、もう一度焙乾し、2〜3日間日干しします(荒節、鬼節)。その後、表面の油分などを包丁で削り(裸節)、木箱に詰め、温度25〜28度、相対湿度75〜85%の室(むろ)に2週間ほど入れて青カビを生やします。カビを払い、室に入れる作業をカビが生えなくなるまで続けて完成品となり、完成には3〜4ヶ月かかるといわれています。
塩鰹と違って、鰹節製造には煮熟と焙乾するのに火を使います。ですから、「紀州漁師を呼び寄せると薪を大量に使うので、薪の値段が上がるからやめてくれ」という要望が地元から出されたという文書も残っています。
もちろん鰹節を製造するようになってからも、三陸では塩鰹生産が続きます。
なぜなら、江戸市場で鰹節といえば結局、紀州や土佐ブランドであって、三陸ものはそれには勝てない。手間をかけ、燃料を注ぎ込んでまでつくる見返りがなかったということらしいのです。
一方、塩鰹ですと、江戸では師走贈答用の塩引き鮭の廉価版としての需要があった。師走になると新巻鮭を買う感覚ですね。塩引き鮭の代用品として、塩鰹は大量の需要があったのです。ですから1年を通じて、というよりは、11月ごろに集中的に出荷されているんですよ。夏から秋に鰹を捕って塩鰹に加工し、11月に送ります。
つまり、鮭の漁獲量が減少して、価格でも蝦夷地産の鮭に負けてしまった。そこで鰹を捕って、付加価値の高い鰹節で勝負しようと思ったけれど、結果として鰹節の出荷量は微々たるものだった。しかし贈答用の塩引き鮭の廉価代用品として、塩鰹の大量需要があった。塩鰹の送り先は主に江戸ですが、江戸時代の後期になると内陸部の農村地帯が多少のゆとりを持つようになって、その需要先の一つとなっていったのかも知れません。もちろん、江戸という都市生活者の増加も、塩鰹の需要を押し上げていたことは間違いないでしょう。
大船渡の船主で、商人であり漁家でもあった千田(ちだ)家(前項参照)も、このような鰹漁とその加工生産を行なって、それを江戸に盛んに出荷していました。千田家の勢力が伸びてくるのも、三陸地方で鰹の生産量が拡大してくる時代と重なるのではないかというのが、私の持っているイメージで、今後古文書の調査が進めば、解明されていくでしょう。
俵物の世界
千田家の場合、鰹の加工品以外にも、中国向け輸出品を集荷していたことがわかっています。いわゆる俵物です。
俵物というのは煎海鼠(いりこ)(干しナマコ)、干し鮑、フカノヒレなどの海産物の干物を俵に詰めて輸送したところからつけられた名前で、江戸時代の長崎貿易の重要な輸出品でもあります。
一つは干し鮑。海士(あま)の生産力は高く、深く潜るので取り尽くすぐらいだったようです。三陸には、海士の集落がいくつかあるんですね。近代になると、観光用に女性の海女に変わってきますが、もともとは女性は潜りません。男海士です。例えば吉里吉里(きりきり)村の前川家ではそういう海士連中を呼び寄せて、漁場の近傍に泊まらせて、鮑を大量に捕り、干し鮑を生産しました。
千田家ですと、伊達藩の俵物集荷の元締めになっていますので、地域の集荷拠点の位置を占めている家だったと思います。
長崎に幕府が設置した「長崎俵物会所」は、中国への日本側の集荷の窓口です。そこが地域の拠点になるような商人に、俵物の集荷を任せるのです。
長崎俵物会所が、藩を飛び越えて直接各地の巨大商人を把握・集荷しようとするシステムを組み立てようとする時期があるんですが、これを俵物直仕入れ制といいます。しかし、結局はうまくいきませんでした。その理由としては、幕府=長崎会所が輸出差額を大きくするために、俵物を買い叩いたからと考えられます。意外なことに、鮑だけではなくナマコの国内市場もあったようで、漁師たちは長崎会所に卸さずに、横流しが横行したらしいのです。
それで、18世紀の後半から、藩が俵物の集荷を請け負うようになりました。藩に強制することで、藩の責任で領内から俵物をかき集めるようなシステムにしたのです。集荷を押しつけられた藩には新たな責任が押しつけられたということになります。
請負商人の世界
沿岸部の諸藩では、漁業から税収を確保するために、しばしば漁場の請負制が採用されていました。請負制というのは藩側にものすごく都合のよいシステムです。漁師一人ひとりがどれぐらい魚を捕ったかという把握は非常に難しいし、漁獲量は年ごとに増減する。そういうところから、どのように税金を吸い上げるか、どうやって農業のように安定的に税金を吸い上げるかを考えたとき、一番いいのは商人に「この漁場、いくらで請け負うか?」と入札させることです。商人としては一発勝負で、安く入札して漁獲量が上がれば大儲けですし、その逆なら家が潰れるかもしれない。そういう選択をさせる。他方、商人としても「ここで捕れたものは、他には売るな」ということを、藩の命令として漁師に強制できる。
鮭の場合は河口付近や川で捕れるのでどういう生産をしたかはあまり問題ではなくて、江戸に送って、差引勘定で黒字ならよいという経営であったと考えられます。
しかし、これが鰹や鮪になると、遠洋に出ていく必要が生じ、資金調達から始めなければならない。つまり、生産と商売を始めるのに資本がいるし、水主(かこ)を雇わなければならないので、請負ではなく漁業の実態を把握している必要があります。水主の家族構成をきちんと把握して、住む小屋も与えました。家が断絶したりすると、そこに別の水主の子どもを連れてきて家を存続させるというようなこともしていました。
こういう漁場の請負という形は、蝦夷地の開発でも使われています。
蝦夷地では、江戸や関西の商人が請負で入っていって、河川での鮭の集荷を行なう「場所請負制」というシステムを採っていました。松前藩などはもともと耕地が少ないので、家臣たちにアイヌの人たちとの交易権や、後には漁業の水産物の集荷権を給付しました。家臣は、それを商人に請負わせて請負金をもらい、経営は商人に任せていました。商人は、倭人(本州の人間)漁師を連れてきたり、場合によってはアイヌの人たちをかなり酷使して鮭生産をしました。この商人で有名なのは栖原(すはら)家で、江戸商人ですが、もともとの出身は紀州です。
水産資源の国際商品化
私は最近、江戸から明治時代にかけての漁業政策に関心を持っています。明治維新後、岩手も新潟も、そして明治政府も水産資源問題を強烈に意識するのです。1880年代から90年代のことです。内務省や農商務省は「このままいくと日本の水産資源はどんどん減る。資源繁殖に努力しないといけない」といっています。具体化を命令された結果、岩手県などでは、資源保全システムや慣行探しにやっきになります。そこで出てきた「夜は鮭をとらない」などの過去の慣行がそのまま法令化されていきました。
水産物が激減するような現象が実際にあったかというと、一部を除いてはどうも見られない。それにもかかわらずそうした動きが出てくるのは、1880年(明治13)にベルリンで万国漁業博覧会が開催されたことに端を発します。日本政府は漁業政策の視察としてヨーロッパに役人を派遣しています。その視察団が欧米列強の漁業政策の様子を見て、「文明国の人間は資源に優しい」という論理を組み立てたのです。
そのときの報告には、「有害過酷な漁具・漁法を放棄せよ」とあり、「寛大優良な漁業を目指し、乱獲につながる漁業を規制しよう」という流れになりました。
林野庁(当時の農商務省)も当時ヨーロッパに視察団を派遣しており「森林資源の保全」を言い出します。このように資源を人工的に増やそうという発想は、林業も漁業も根っこは同じところにありました。
この時期の北米、イギリス、ドイツなど欧米諸国では、日本では顕著でなかった水産資源の減少が、実際に問題になっていたのです。背後には産業革命があり、人口増加もあって水産物の消費量が急速に増え、それと並行して工場廃水による水質汚染も進んだ。その中で、欧米諸国で唱えられたのが「資源繁殖」というスローガンだったんですね。
一見、先進的に見えるかもしれませんが、彼らの目的は自然保護ではなく、資源量を増やしたいということです。
万国漁業博覧会がきっかけとなって、当時、日本でも水産物が国際商品として意識され始めました。万国漁業博覧会には、日本からもニシンや鮭が塩漬けで出品されました。この流れで商業捕鯨も起きてきますし、魚油が欧米向けの最大の商品になります。
しかし、欧米にこれらを運ぶには、赤道を越えなくてはなりません。傷まないように塩漬けを持っていったけれど、途中で多くがダメになったなどということが起こります。そこで缶詰が積極的に求められるようになってきます。北海道開拓使にも1877年官営缶詰工場が設立され、鮭・鱒(ます)の缶詰がつくられ始めます。缶詰が定着するのは日露戦争のころで、軍用食として利用されたり、日露戦争後の北洋漁業の発展で鮭、鱒、カニの缶詰が企業化されるようになります。
このころ、日本では不評の紅鮭がヨーロッパでは好評だったことから、紅鮭缶詰工場を建設し輸出したのが、後の日魯漁業(現・株式会社ニチロ)創業者の一人で、箱館の奥筋廻船船主の次男に生まれた平塚常治郎だったというのは、水産資源の商品化における船主・商人の役割を考える上で示唆的です。
商業ネットワークの形成は、生産・貯蔵技術の革新、海産物資源の保全、輸送技術の進歩と、密接にかかわっていたのです。