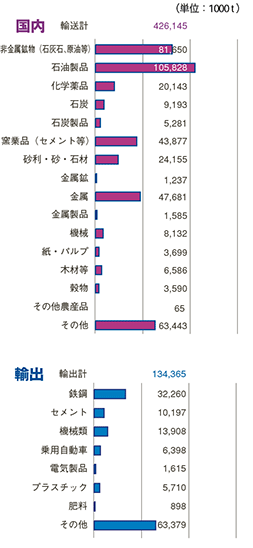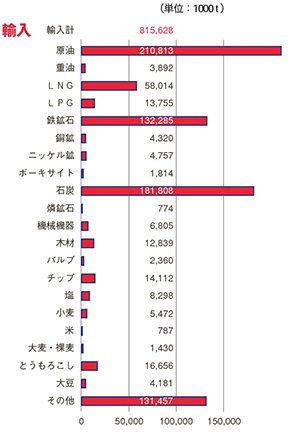機関誌『水の文化』25号
舟運気分
-
編集部
舟運が支えた江戸庶民の繁栄
モノ・人・情報が生産地と消費場所を行き来する。このこと自体は今も昔も変わらない。ただ江戸時代には、千石船を使用した廻船が、物流モードに大きな役割を果たしていた。舟運の発展のお蔭で、江戸初期に比べ大量のモノが広範囲に普及することになり、大衆品が生まれ、庶民の文化が花開く一助になったことは想像に難くない。
この時代を支えたのが、多様な顔を持った商人たちだった。大規模な廻船問屋あり、海産物加工を行ない千石船船主でもあった商人あり、水軍から始まり江戸に出て今日まで続いている企業あり、地縁、血縁、職業縁で生きた商人ありで、実にバラエティに富んでいる。
舟運の時代は、商人が縦横無尽に活躍した世の中であり、港は商人と庶民をつなぐ場、つまりは市場でもあった。多様な商人とそれを支える商業活動が経済発展の原動力だったのだ。
バラエティに富む舟運時代の商人像
江戸時代の舟運文化は、単に「歴史的遺産」に過ぎないのだろうか。
千田家のような商人の存在は、地元民の雇用を確保し、地域の暮らしを豊かに保つという、過疎地の「まちおこし」を彷彿とさせる。「漁業資源」「人的資源」「山林資源」といった多様な資源を維持しながら生産と取引を行なう、いわば「守りながら開発する」という方法は、現代の地域経営にも応用できる知恵とイメージを提供している。
紀州商人のように舟運を縦横に駆使しながら市場を読み、自らの業態を変化させながら、時代に即応してきた姿からは「継続は力」という商いの基本を教えられる。ベンチャー精神旺盛な商人たちは、顧客の知らない新商品を供給することで、新たな販路を開拓し、新たな商組織の実現を果たしている。
20世紀前半を生きたオーストリア の経済学者シュンペーターが、「新結合こそが経済発展を生む」と記したのは、まさにこのようなとらわれのない商人の姿勢であり、今後の社会を読み解く羅針盤となるだろう。
環境問題を重視した21世紀の経済発展に、商人たちがどのような新結合をもたらしてくれるのだろうかと、楽しみになるというものだ。
環境モーダルシフト
物流の主流が船から鉄道、そしてトラック輸送に転換し、「陸の道」の行きすぎが「まちのありかたを変えた」ということは、今日よく言われていることだ。
そんな中、日本の大手自動車メーカーが、2006年(平成18)10月から愛知県と岩手県間の部品輸送を、それまでのトラックから鉄道に切り替えた。持続可能な循環社会の構築に向け、環境対策に貢献するのがその理由という。
二酸化炭素排出量を減らすために、自動車中心の物流から鉄道や船にシフトすること、つまり「環境を意識したモーダルシフト(輸送方法の転換)」が企業ベースで実践されるようになったという喜ばしいニュースである。
このような「モーダルシフト」は、以前であれば効率化が主流とされていたことを思うと、企業が目先の利益やコスト計算では、もはやその役割を果たせないところまできているという証しともいえよう。
1tの貨物を1km運ぶ場合の二酸化炭素排出量を比較すると、船は自動車の四分の一、鉄道だと八分の一だという。1997年(平成9)に締結された京都議定書において、日本は2010年までに二酸化炭素の排出量を1990年(平成2)と比べて6%削減することになっている。モーダルシフトは、真っ先に成し遂げねばならない必須課題なのである。
舟運は今でも日本の大動脈
では、現代の舟運は衰退しているのだろうか。
確かに物流のモードが、鉄道やトラック輸送を主流とするようになり、特に内陸輸送を担ってきた河川舟運は大幅に減少した。しかし、長距離大量輸送に適した物品について見ると、依然として舟運が主流である。現在、日本の内・外航海では鉄鋼、機械類、石油製品といった原料品や車を含めた機械類が運ばれており、舟運は今でも日本経済を支えている大動脈ということができる。
生活にかかわるものも同様だ。例えば「衣」。綿花はアメリカやオーストラリア、麻は中国やフィリピン、合成繊維の原料となる石油は中東から運ばれてくる。
「食」はどうかというと、小麦粉の6割弱はアメリカから、エビはインドネシアやタイ、牛肉はオーストラリアやアメリカなどから運ばれてくる。
いわば現代の「ものづくり」「食糧産業」にかかわる企業は、舟運によって支えられていると言っても過言ではなく、その商圏は地球上すべてに広がっている。
運ばなくてはならないモノ
そもそも、物流がスピードを求めて舟運から鉄道やトラックにモーダルシフトした責任は、私たち消費者にある。江戸時代後半から各地で特産品がつくられるようになり、年貢用の米をよそから買って納めても採算が取れる世の中になった。その背景には物流システムの発達がある。当然、自給自足は成り立たなくなる。結果として他の地域との依存関係が強まり、物流はいっそうの重要性を増した。
伊丹や灘の新酒を競争で江戸に運んだ「千石船」は、西宮〜品川沖間を3日で来た。いうなれば航空機でボジョレーヌーヴォーを日本に持ってくるようなもの。こうした「遊び」が単調な毎日に楽しみを与え、働く原動力になったことは江戸も現代も変わりがないようだ。江戸っ子も、ジェット機があったら灘の新酒を運びたい、と思ったに違いない。逆に言えば、江戸時代にあって千石船はジェット機だったのである。
現代の舟運から見え隠れするのも、同様な構造だ。一国で完結できる存在は有り得ない以上、他国との依存関係を良好に維持することは国際社会で生きていく上で有効だが、今の日本の現状は、まったくの他国任せで危うい綱渡りのように見える。
欲望には限度が必要だ。「急がないものはゆっくり運ぶ」という選択肢を私たちが選ぶことが、「ゆっくり運ぶものを増やす」流通の仕組みを変えることに結びつく。もう一歩進めて考えてみれば「その荷物は、本当に運ばなくてはならないのか」と、立ち止まって考えてみることも必要だ。原油をジェット機で運ぶことがナンセンスであるように、舟運でしかなし得ないことがある以上、「運ぶこと」それ自体の是非を問う姿勢も大切ではないだろうか。
商社に代表されるような現代の商人に、そのような物流の再編成を要求できるかどうかは、まさにわたしたち消費者の選択にかかっているのだ。
見えない舟運
河川の舟運が減ったことが、21世紀の流通における「舟運の衰退」という誤解を生んだことは否めない。それにしても、江戸時代の舟運文化と現代を生きる私たちの間に、これほど大きな隔たりができてしまったのはなぜなのだろう。
かつての舟運は帆船であるがゆえに季節に左右され、特に日本海側では冬はオフシーズンを余儀なくされた。したがって運べる季節に運べるものしか、商品となり得なかったのである。ところが動力の導入で、帆船では不可能だったことが可能になった。それに伴い、商品からも季節感は消えていった。
日本橋界隈で取り扱うモノが、米や塩という江戸庶民の台所に直結する産品から、小麦粉、砂糖、繊維などにシフトしていったことも、まちから庶民の息遣いを失わせていった一因となった。こうした原材料は製品をつくるために使われることが主であり、庶民の暮らしには間接的なかかわりしか持たないようになったからである。
商いの規模が大きくなれば、河岸で現物を並べていた商いのスタイルから、倉庫に眠る商品を伝票だけでやり取りする商いへとシフトするようになる。そのため、一大コンツェルンに成長した商社が一体何を商っているのか、パッと見にはまるでわからないという現象が引き起こされるのである。
こうした過程で、庶民と直結した舟運のリアリティは、徐々に薄れていったのだ。
私たちが抱く暮らしの中の欲望に、ある程度の節度を持つことが、舟運に再びリアリティを取り戻し、環境を意識したモーダルシフトの段階に留まらず、「運ばなくてもいいモノは運ばない」ことを決意する追い風となるに違いない。