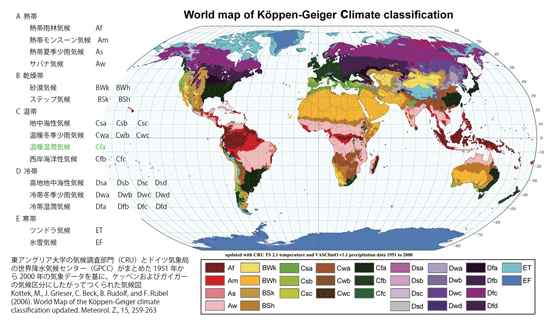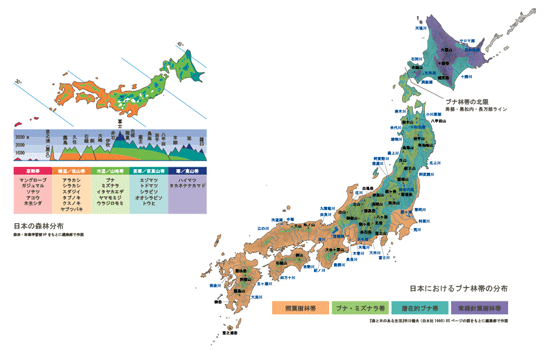機関誌『水の文化』34号
ブナ林帯文化論の復権
照葉樹林文化で日本人の深層心理を解き起こす文化論が一世を風靡した時代がありました。 長野県小布施に生まれ育った市川健夫さんは、日本列島は照葉樹林文化一辺倒ではないと、ブナ林帯文化論を説きました。風土の目利きが説得力を持つのは、人の暮らしが自然と密接にかかわっていたからです。 文化の多様性と森としての機能の再発見をうながす、市川さんから学びます。
-

-
地理学・地誌学専攻 理学博士
市川 健夫 (いちかわ たけお)さん -
1927年長野県生まれ。1948年東京高等師範学校を卒業。東京学芸大学を経て、信州短期大学学長、東京学芸大学名誉教授。長野県立歴史館館長などを歴任。
主な著書に『日本のブナ帯文化』(朝倉書店 1984)、『森と木のある生活』(白水社 1992)、『風土発見の旅』(古今書院 1995)、『青潮文化』(古今書院 1997)ほか
モンスーン的風土
日本列島は東アジアの東の端にあります。海洋の影響をまともに受け、夏が雨季、冬が乾季となるモンスーン的な風土です。
しかし、気候学者のウラジミール・P・ケッペン(注1)は、日本の気候をCfa(湿潤温暖気候)と表現しています。
Cは最寒月の平均気温がマイナス3℃から18℃の温帯気候を意味し、fは乾季がなく降雨が一年中あるという意、aは最暖月の平均気温が22℃以上あることを示しています。
日本海側には、青潮(あおしお・対馬海流)の影響で本来乾燥しているはずの北西季節風が水分をたっぷり吸収し、脊梁(せきりょう)山脈にぶつかって大量の降雪をもたらします。太平洋側にも、ときおり通過する温帯低気圧が、雪や雨をもたらします。
こうした要因で、ケッペンがCfaと表わしたように、日本には厳密な意味での乾季がないのです。
このような気候条件と肥沃な森林褐色土は、日本の森林を極めて豊かに育みました。加えて熱帯とは異なり、森林の復元力が強いことも、特筆すべき特徴です。
この豊かな森林資源と生活が密接に結びついていたことが、我が国の歴史にはよく表われています。
縄文時代には、森によって育まれた野生動物や野鳥は、狩猟民にとって大切な蛋白源でしたし、森林土壌を有効に利用する焼畑耕作によって、食糧栽培も営まれていました。
大陸から稲作が伝わってからは、豊かな森林によって涵養されている水資源は、生命維持に重大な意味を持つようになります。畜産の比重が低かった我が国において、灌漑用水から供給される天然肥料分が、2000年以上にわたる稲作の栽培を支えてきたのです。
木の実や漆や木蝋(もくろう)の採取といった森の恵みの利用、馬産や養蜂といった空間の利用は、持続的な利用を可能にする見識によって維持されてきました。高度経済成長と、それに伴って起こったエネルギー革命が、そんな森林と人々の暮らしを分断してしまったのは、大変残念なことです。
(注1)ウラジミール・ピーター・ケッペン (Wladimir Peter Koppen1846〜1940年)
ドイツの気候学者、また植物学者。両親はドイツ人であるが、ロシアのサンクトペテルブルクに生まれた。ドイツ学派の気候学の大成者として著名であり、ケッペンの考案したケッペンの気候区分は、改良を加えられながら現在も広く使われている。
ケッペンの気候区分
1923年、植生分布に注目して考案された。気温と降水量などの変数から単純な計算で決定される。
気候帯ー気候区ー月平均気温をそれぞれ記号化し、その組み合わせにより、気候区分を表すもの。
1.気候帯
赤道から極地に向けて5つの気候帯に分類し、最初の大文字で表記する。
A(熱帯) B(乾燥帯) C(温帯) D (冷帯) E(寒帯)
2.気候区-1
2文字目の大文字は、区域を表す。
W(砂漠) S(ステップ) T(ツンドラ) F(氷点下)
3.気候区-2
2文字目の小文字は湿度によって分けた区域を表す。
s(夏乾燥) w(冬乾燥) f(湿潤) 注:気候帯によって基準値は異なる
4.気温区分
3文字目の小文字は平均気温によって分けた区域を表す。
aー最暖月が22℃以上
bー最暖月が10〜22℃未満、かつ月平均気温10℃以上の月が4カ月以上
cー最暖月が10〜22℃未満、かつ月平均気温10℃以上の月が3カ月以下、
かつ最寒月がマイナス38℃以上、マイナス3℃未満
dー最暖月が10〜22℃未満、かつ月平均気温10℃以上の月が3カ月以下、
かつ最寒月がマイナス38℃未満、マイナス3℃未満
hー年平均気温が18℃以上、
kー年平均気温が18℃未満
照葉樹林文化論
今日では、日本民族の基層文化に、照葉樹林文化があることが知られています。この概念に学問的な定義を与えたのは『栽培植物と農耕の起源』(1966岩波書店)を著わした中尾佐助です。
ヒマラヤ地域から華中・華南、日本列島に至る照葉樹林帯という生態系に共通する基層文化が、照葉樹林文化複合です。ここには水稲栽培を基本とする国家観、宗教観がありました。
稲作を中心とした照葉樹林文化国家であった大和朝廷の支配によって、北九州、瀬戸内、近畿地方の中央低地、濃尾平野、福井平野、加賀平野などには条里制の水田が広く分布していきました。条里制の遺構水田は、律令国家にとって権力の物質基盤であったわけです。
実は東南アジアや南アジア諸国では、気候的には二期作が可能であるにもかかわらず、雨季のみの一期作に留まっている水田が少なくありません。これは充分な灌漑施設がなく、多くを天水に頼っているからに他なりません。
一方我が国において「旱魃(かんばつ)に凶作なし」と言われるのは、灌漑施設が発達し、徹底的なまでに稲作を実現してきた背景があるからです。
森林は、水田の主要な肥料分である刈敷(かりしき)の供給源でもありました。
中世に入ると、新しい作物として綿花栽培が導入されました。綿は無霜期間が210日以上ないと成熟しない亜熱帯作物のため、照葉樹林の森林限界以北では栽培できません。また、非常に肥料を必要とする植物で、干鰯(ほしか)などの魚肥が流通するようになったのは、地力を必要とする綿花栽培のためでした。
1858年(安政5)施行した安政の開国以来、伝統的な照葉樹林文化複合は解体していきます。その後、綿花や菜種栽培は減少しますが、生糸輸出の増加により、蚕糸業という新たな照葉樹林文化が形成されていきました。
画一視することの過ち
照葉樹林の生育には、温量指数(注2)の暖かさの指数が85〜180℃で寒さの指数がマイナス10℃以上あることが必要です。
私が住む長野県北部の場合、暖かさの指数が100℃、寒さの指数がマイナス16℃となっており、照葉樹林は生育できません。ですから私は、照葉樹林文化論に対して、日本においてもブナ林帯文化があるのではないか、と提唱したのです。
水稲は夏作物ですから、短期間であっても夏の高温によって生育できますが、永年作物である茶は冬の寒さで凍害を受けます。
ところが晩秋から大量に雪が降って根雪になる地域では、積雪に守られて茶の木が枯れることはありません。北緯40度を超える秋田県能代市で、茶が生産できるのは、1m以上にもなる積雪のお陰です。
明治政府が殖産興業政策として行なったサトウキビ栽培は、こうした植生を無視した政策で失敗してしまいました。1953年(昭和28)に東北地方で起きた大冷害における被害も同様です。
こうした例は、日本を画一的に照葉樹林帯に属すると誤解した過ちで、風土を無視した農政の失敗です。ブナ林帯では照葉樹林文化が風土に合わないことは当たり前のことなのです。
(注2)温量指数
生態学者の吉良竜夫が提唱した、植生の変化と気温との相関関係を表わすための指標。暖かさの指数と寒さの指数があり、合わせて温量指数と呼ばれる。
具体的には、各月の平均気温と5℃との差を累積して平均気温が5℃より高い月の累積が暖かさの指数であり、5℃より低い月の累積が寒さの指数である。
ブナ林帯文化の再考
私は1950年代(昭和25〜)から、日本における高冷地と寒冷地研究を続けていますが、これらの地域は森林植生の上ではブナ林帯になっています。日本では辺境の地と見なされてきましたが、世界的に見たらけっして厳しい酷寒の地ではありません。かえって真夏でも冷涼で、快適に過ごせる居住環境といえるでしょう。
しかし、そこにはブナ林帯の風土を知って、適切な対応をする知恵が必要です。
例えば、「西の牛に東の馬」と言われるように、東日本で馬が卓越したのには理由があります。
気候が冷涼な地域が多いために、馬のほうが<糞畜>として優れているからです。馬の厩肥の発酵温度は牛よりも6℃も高いのです。
耕地面積が広く田植えの適期が短期間である東日本では、脚の速い馬が重宝されました。
加えて反芻動物でないため、飼料の熱効率が低く、牛に比べて30%多くのエネルギーを要する馬は、農地開発が遅れたために粗飼料の供給地が豊富に残っていた東日本のほうが適していたのです。
ブナ林帯で風土認識を改めたいものの筆頭に、住宅があります。兼好法師が「住まいは夏をもって宗とすべし」と『徒然草』で述べたのは、照葉樹林帯での話です。
第二次大戦前、当時の植民地であった樺太(現・サハリン)に住んだ日本人とロシア人の燃料消費量は36対1だったそうです。バラックのような小屋とルンペンストーブ対イズバ建築(丸太を横積みした校倉構法の民家)とペチカの違いが、燃料消費に格差を生んだだけではなく、住人の健康や生命にも多大な影響を及ぼしました。
最近ではやっと日本でも二重窓が普及してきましたが、これだけでもエネルギーの節約に大いに貢献できます。
入母屋造りの住宅は、気候が温暖な近畿地方の中央部で発達した様式です。寺院に多く、格式が高いとされるために、経済的に余裕のある人が入母屋造りの家を建てたがりますが、寒冷で雪が多いブナ林帯で採用するものではありません。
このように森林と生活の深い結びつきにも、風土に根ざした理由があるのだということを、みなさんが覚えておいてくださるように願っています。
焼畑耕作の消滅
かつての武蔵野台地や房総半島、三浦半島といった関東平野には、広い照葉樹林帯がありました。しかし、それらは焼畑耕作によって消失します。雑木林と呼ばれているコナラ・クヌギや赤松の林は、焼畑の跡地にできた二次林です。
焼畑耕作も西日本の照葉樹林帯と東日本のブナ林帯では、やり方が違います。
照葉樹林帯では、冬のうちに森林を伐採し、春先に野火をつけて焼き、すぐに種を蒔くので、焼き払った初年度から粟・黍(きび)などが栽培できます。
ところがブナ林帯では雪が深く春の種蒔きに間に合わないため、梅雨明けしたあとに火を入れます。ですから初年度の穀作は蕎麦(そば)ぐらいしか蒔けないのです。日本で蕎麦食が東日本に偏在しているのは、こうした焼畑耕作と関連があったと考えられます。
焼畑は4〜6年間輪作を繰り返してから放棄され、森林に転用されました。栽培されたのは、蕎麦、粟、大豆、荏胡麻(えごま)、里芋、赤蕪、あずきなどで、これらは典型的な焼畑作物です。
1960年代(昭和35〜)の拡大造林によって、こうした切替畑に杉・檜(ひのき)が植林されるようになりました。これらは野火を入れたあと1年間おいただけで、切替畑に使われずに直ちに植林されるようになった。そこで造林は急ピッチで進みましたが、新たな焼畑用地がなくなった1970年代(昭和45〜)後半から一気に過疎化が進みました。
景観的な美しさだけでなく
武蔵野などに残った二次林は、西日本にはあまり見られない平地林です。狭い沖積平野しか持たない我が国において、特に西日本では早くから水田として開発され尽くしたために、平地林は残されなかったと考えることができます。
東海地方には牧ノ原・磐田原・三方ヶ原という「遠州の三大原野」が残されていましたが、その多くは明治になって開拓され農地に変わってしまいました。
そういう状況の中で関東平野に平地林が残ったのは、強酸性で痩せた火山灰質の土壌ゆえに、水田ではなく畑作が多く、有機質の堆肥を必要としたからだと思われます。
山付きの農村なら、山間部で刈敷も得られますが、洪積台地が広がるという地形的な条件ですから、平地林を入会で使って落葉を施肥としたのでしょう。
関東平野ではそのような平地林を「山」と呼びます。鹿児島県大隅半島のシラス台地でも同様です。「おじいさんが山に柴刈りに」の山は薪を取る農用林野のことで、山地のことではないことがわかります。
今でも、「山」の自然保護に熱心な生態学者までが雑木林と呼んではばかりません。
20世紀初頭は日本に産業革命が勃興した時代で、自然主義文学が開花しました。『武蔵野』(民友社1901)で国木田独歩が、また『自然と人生』(国民新聞1900)で徳富蘆花が、雑木林の美しさを述べています。
しかし、生産の傍観者であった都市民は「山」が農用林野であった記憶を持っておらず、平地林を美しい自然だと認識したものの、農業生産の場であるととらえることができませんでした。
日本人はまず水稲栽培を基本とする照葉樹林文化複合に基層文化の源を求め、ブナ林帯の持つ独自性を見失いました。次に拡大造林で培われた人工林を美林として尊重して、経済的価値の低い広葉樹林を雑木林として蔑視してきました。
こうした認識は、森林と人の暮らしが稀薄になっているからであり、大変残念なことです。かつての密接なかかわりを掘り起こし、時代を経て形が変わっても、その関係性を守り続ける大切さを伝えていきたいものです。
森と林のニュアンス
英語では森と林をそれぞれforestとwood、ドイツ語でForstとWald、フランス語でforetとboisと使い分けしています。
日本語でも森と林という語がありますが、違いについてはあまり意識されていません。本来、林とは用材・薪炭・落葉などを得るためにつくられたもので、直接的な経済性を目的としない場合は森と呼ばれています。寺社や公園、屋敷森などがそれにあたります。
私たちはとかく林にばかり目を向けがちでしたが、公共的な働きを持つ森にも、もっと意識を向ける時代になっているように思います。
世界遺産になった白神山地のように、東日本には、幸いにして残されたブナ林があります。それらを次世代に守り伝えるには、経済性といった単一の価値観にとらわれていてはなりません。森林の持つ、森としての機能を積極的に見出していくことも、これからは大切なことでしょう。