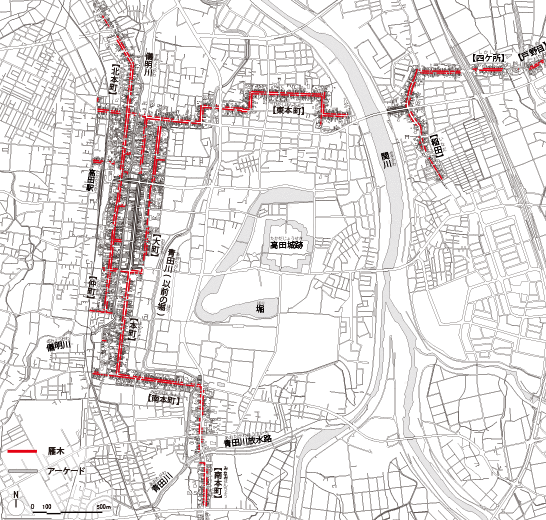機関誌『水の文化』45号
雪都・上越高田の宝物
日本一の雁木通り

建築家の目線からまちづくりにかかわり続けている関由有子さん。いったん外に出た関さんが見出す雪都・上越高田ならではの魅力。そこには人の暮らしとかかわっているからこそ輝く資源が息づいていました。
-

-
一級建築士 あわゆき組代表
関 由有子(せき ゆうこ)さん -
1956年、新潟市上越市生まれ。京都大学工学部建築学科卒業後、建築設計事務所へ就職。フィンランドの家具に出合い、ものづくりの力に触発されてフィンランドに留学。約3年間、木工・家具製作の専門学校に通う。1997年に帰国後は、上越市でせきゆうこ設計室を開設。森林・林業ボランティア活動から始まる地域材の活用提案と、「雪国・越後高田」の歴史的建造物を活かしたまちづくり活動にかかわっている。
主な著書・論文に、月刊『地域開発』特集ローカルデザインから地域の未来を考える(共著/日本地域開発センター 2013年11月号)、月刊『ゆきのまち通信』105号 上越市高田「雁木の街」夢をかたちに… 雁木と町家でまちを楽しむ(企画集団ぷりずむ 2006)
雁木(がんぎ)は雪国の知恵の結晶
雁木というのは、主屋から張り出す軒や差し掛ける庇(ひさし)のことです。往来の多い街道筋や、多くの人が集う商家などが連続するまち並みにつくられました。上越地域が発祥ともいわれ、高田の現存する雁木の総延長は約16km。日本一の長さです。
「この下に高田あり」と言われたほどの豪雪地帯。それで主屋の前面に庇を張り出して、歩く空間を確保したのが雁木です。
屋根から落ちた雪や降る雪が溜まれば、往来は通れなくなります。周りが雪に覆われても、雁木の下はトンネルのようにぽっかり空いています。そんな雁木の下の細い道を人が歩いている写真も残されていて、それを見ると「ああ、本当に役立ってきたんだなあ」と思います。雁木は、雪国ならではの知恵の結晶なのです。昔は水道や電話線も雁木の下に埋まっていました。メンテナンスするにも便利ですから。さすがに水道は道路内に移りましたが、電話線はまだ雁木下にある所も残っています。
しかし、明治に入ってから火事の延焼を恐れたことから、新潟県は雁木廃止令を出しました。新潟市は雪が少ないから高田とは事情が違うこともあって、ほかの地域ではどんどん壊されていきました。それでも高田では雁木を残してきたのですね。
小学校でも雁木のある昔の雪国の暮らしを教えていますが、昔に比べたら雪が少なくなって、雁木に対する感謝の気持ちも薄れてきました。「高田は雁木があるから発展しない」とか「車を停めるのに邪魔だ」と厄介者扱いされた時期もあります。
そうなってくると、雁木が特別のもので素晴らしい雪国の知恵なんだ、という思いも薄れます。そもそも高田の人にとってはあまりにも日常なので、わざわざ注目することもない存在だったのでしょう。
しかし、平成に入ったころからは「もうスクラップ&ビルドのまちづくりではダメだ」ということに気づいてきました。京都や金沢などの特別な古都でなくとも、高田のような地方都市にも、ようやくそういう思いが浸透してきたのです。
高田人気質
興味深いことに、雁木はそれ自体もその下の通路も、個人の所有です。つまり、自分の土地を歩道として公に提供して、歩く人のためにわざわざ私費を投じて庇をかけているのです。それは江戸時代から現在まで変わらずに続く伝統。高田の人の助け合い精神というか鷹揚さを感じさせられますね。さすがに固定資産税は免除されていますが、特別な恩恵があるわけではないのに守られ続けてきたのです。
今、新築中の歯医者さんも雁木をつくっていますが、絶対につくらなくてはいけないという条例があるわけではありません。ただ、上越市は2004年(平成16)4月から〈雁木整備事業補助金〉制度を始めて後押ししています。
雁木は個人の資産だから、それに市が公金を投入するには、市民が納得するようにコンセンサスを取る必要があります。それで上越市ではどれぐらいの雁木が残されているかといった調査を行ない、アンケートをまとめました。その結果を受けて、強制力はありませんがガイドラインが定められました。
そのガイドラインに則った雁木をつくる場合には、7割を補助(限度額は間口1mにつき11万9千円)するというのが〈雁木整備事業補助金〉制度です。
また、雁木は各家が個々につくったので床の高さがまちまちでバリアフリーの観点からも問題があるということで、段差解消工事にも6割の補助(限度額は間口1mにつき1万8千円)が出ます。
始まった当初は「補助金が出るといったって、今さら雁木なんて」という雰囲気でしたけれど、一昨年ぐらいから弾みがついてきて、4月に受付開始するとあっという間に予算枠が一杯になってしまうほど、利用者が増えました。
そもそも雁木のある場所を、どうこうするつもりはないのです。だって、自分の家だけ、もとの雁木の所にはみ出すことなんてできないでしょう。
一時は家の建て替えのときに雁木をつくらない家が増え、少し下げて駐車スペースをとる例が多くなりました。家が連なるまち並みは、壁面線が概ねそろうことで美しく見えるのですから、こういうのは困った現象です。今まで歯抜け状態になってデコボコだった壁面線が、雁木復活でそろっていけば、うれしいことです。
こういう補助金で復活した雁木が連なるまち並みを見て、みんな、「ああ、やっぱりいいな」と思ったのでしょう。それで「じゃあ、うちも建て替えても雁木をつくろう」という気持ちになってきたようです。
豪雪地帯 上越高田
高田という地名はあちこちにありますが、ここは越後の高田。人が住む平野としては、例がないほどの豪雪地帯です。そもそも、江戸時代前にはここには小さな村があっただけでした。直江津の海辺にあった福島城に入った松平忠輝が、菩提が原(高田城敷地の古名)に新たに城を築き、城下町をつくったのです。
これには諸説ありますが、上越市学芸員の中西聡さんは「その背景には平和がある」と書かれています。すでに戦国の世ではなく、占いで城の位置を決めたというのです。地図に福島城と高田城完成までの陣頭指揮を執った御仮屋と高田城の3点をプロットすると、南北ライン上に等間隔(2里)できれいに並びます。つまり、人為的に決められた場所だというのです。そこが実は豪雪の地で、のちのまちづくりに苦労することになるのですが。
屋根の雪下ろしは大仕事ですから、落雪、消雪、融雪といろいろと考えられてきましたが、落雪は敷地が広くないと問題です。隣地に雪が落ちないように、あとから鉄骨造の柵を建てた例もあります。また、屋根から落ちると硬い圧雪になり、なかなか融けにくいので処理が大変です。
消雪パイプを屋根に上げて温水を散布すると、押し入れにカビが発生したり、湿気がこもる恐れがあります。結局、雪の重さに耐えるように主屋をしっかりつくり、こまめに雪下ろしするのが一番確かな方法かもしれません。中越地震のときに、地震の規模に比べて倒壊家屋が少なかったのは、屋根雪を考えた頑丈な造りだったから、というのも一因です。
主屋はがっちりとした造りだから、そうそう建て替えるものではありません。しかし雁木は簡易な構造ですし、主屋の雪を受け止めて壊れもします。意外と直さなくてはならないもの。だから雁木はそれ自体が文化財で新しくしてはいけない、というものではありません。モノが文化財なのではなく、システム自体が文化財ですね。雁木は、豪雪の高田で生まれた雪と共生する知恵なのです。
あわゆき組の誕生
雁木の残るまち並みや町家というと建物に目がいってしまいがちですが、大切なのは人がどう暮らしているか、コミュニティの在り方はどうか。いくらモノが残っても、人がいなくてはまち(都市)とはいえません。
私は建築家ですが、建築が人の暮らしや生き方に与える影響の大きさを考えてきました。「町家を生かして何かできないか」と考えたのが、〈あわゆき組〉の出発点です。
高田の町家の保存と活性化が話題になり始めた2003年(平成15)末から、大町5丁目から本町7丁目の住民と、まちづくりに関心のある人が町家に集い、率直な意見を交換する中で、町家公開(オープン町家)の試みが始まりました。
「こんなに古き良きものが残されているのに、それを生かさないのはもったいない」「時流に流されて、どこにでもある地方都市に変わり果ててからでは手遅れ」「ここに暮らしている私たち自身が誇りに思うまちを、子どもたちに伝えたい」。そんな想いが実を結び、2004年(平成16)秋、「城下町高田・花ロード」というイベントで〈あわゆき組〉が誕生しました。
寺町のまち歩きをしてみて、お茶を飲む所がないことがわかって「甘味処をやろう」ということに。旧・麻糸商の〈高野商店〉をお借りして甘味処〈あわゆき亭〉を開店し、着物姿で大勢のお客様に町家の雰囲気を味わっていただきました。
2005年(平成17)2月には〈あわゆき道中〉と題して、懐かしい角巻(かくまき)と雪下駄姿で雁木のまちを練り歩きました。角巻というのは雪国の防寒具。誰も着なくなって押入の奥に仕舞われていた角巻を、県内一円から寄付していただきました。
雁木の調査に通ってきていた新潟大学の学生さんたちも応援してくれました。あわゆき組に若い男子が多いのは、こういう人たちがその後も高田にかかわってくれたからです。建築や都市計画はモノだけ調べてもダメだということが、調査しながら地元の人と触れ合うことでわかってもらえたのかな、と思います。あわゆき道中で、彼らはトンビ(インバネスコート。日本では男性の和装用コートとして用いられた)や黒いマントを着ます。
観光は目的ではなく手段。あわゆき組の活動が外から人を呼び込むことで、コミュニティがつながり、ここに住む人が暮らしやすくなるとうれしいですね。
高田だからできること
高田は江戸時代から水田耕作が経済基盤であり、工場の少ない町でした。それで明治の末に陸軍を誘致したけれど、それも一時のこと。戦後引き揚げてきた人たちが寺町に住み始めたから、寺町なのにアパートがあったりして雑然としている。ありのままの高田は、そんな歴史を持つまちです。
駅前の雁木アーケードは道路拡幅の再開発でつくられたのですが、できたあとにバブルが弾けて、今は「本物の雁木のまち並みを残せばよかった」という反省の声も聞かれます。
ヨーロッパには、木造建築をリノベーションしながら長く使う伝統があります。それは血縁で残せないものは社会が残す、という思想があるから。建物が個人の私有財産としてだけではなく次世代に引き継がれるのは、そういう意識が強いからです。
高田でも調べてみると、景気が良くなった職人が同じ町内で大きな家に移り住んだりしていました。日本にもステップアップ住み替えがあったのですね。こういう考えが定着すれば建物メンテナンスの意義が高まるし、軒を出して建物が傷まないように気を配ります。また、木造は実はメンテナンスしやすいことにも気づきます。地元上越の杉の価値も高まるでしょう。
高田にはスキーを日本で最初に伝えたレルヒ(注1)さんや高田瞽女(注2)の歴史もあります。あわゆき道中では、瞽女唄を継承している月岡祐紀子さんに来ていただき、三味線を弾きながら瞽女唄の門付をして歩いたり、スキー汁(注3)を振る舞ったりして、忘れられかけた高田の歴史を楽しみながら掘り起こしています。
まち(都市)は、人が訪れて人々が交流することから素晴らしさが広がっていくものです。そんなまちの素晴らしさと心地良さは、自然や人とのつながりを大切にしてきた雪国の人々の歴史に支えられています。
中心市街地がカラッポになってしまう前に、まち歩きの楽しさやコンパクトシティの便利さを見直し、歴史あるまちの魅力を多くの人々に実感してほしいと願って始めたあわゆき組の活動。年々、注目度がアップして、仲間も増え、当初の願いがかなえられつつあるようです。
(注1)テオドール・フォン・レルヒ(Theodor Edler von Lerch 1869〜1945)
オーストリア=ハンガリー帝国の軍人。1911年(明治44)高田第13師団を訪問して、日本に初めてスキー技術を伝え指導に当たった。
(注2)高田瞽女(たかだごぜ)
厳格な師弟序列の下で三味線と唄を習い覚え、1年の大半を巡業の旅に費やした目の不自由な女性を瞽女という。娯楽の少なかった昭和初期までは、毎年瞽女の唄を待ちわびる村々があった。地主などの裕福な家が常宿となることで、瞽女たちは門付けの長旅をこなした。祝儀には現金のほか、米や豆、野菜などの農産物、真綿や和紙をもらうこともあったという。瞽女の活動は日本各地にわたるが、新潟県はその一大拠点で長岡と高田には大組織があった。
(注3)スキー汁
明治時代、上越高田にスキーが伝えられたことからつくられた一連のもの(スキー民謡、スキー正宗、スキーせんべい、スキー小唄など)の一つ。盛んに行なわれたスキー演習の際に食事としてつくられた肉入りの味噌汁が発祥とされている。サツマイモとスキー板に見立てて短冊形に切った大根、ウサギの肉が入るが、現在は豚肉で代用される。1998年(平成10)、長野冬季オリンピックに連動して始まったレルヒ祭をきっかけに、まちづくり事業として、スキー汁の宣伝・普及活動が進められている。
(取材:2013年2月10日)