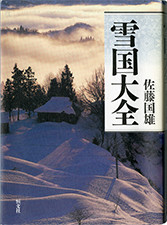機関誌『水の文化』45号
雪国の生活をたどる
-

-
古賀河川図書館長
水・河川・湖沼関係文献研究会
古賀 邦雄(こが くにお)さん -
1967年西南学院大学卒業
水資源開発公団(現・独立行政法人水資源機構)に入社
30年間にわたり水・河川・湖沼関係文献を収集
2001年退職し現在、日本河川協会、ふくおかの川と水の会に所属
2008年5月に収集した書籍を所蔵する「古賀河川図書館」を開設
雪国の悲劇
平成25年3月2日、北海道紋別郡湧別町の猛吹雪の中で、父親が9歳の娘を護るために、自分の服を着せ、自らの命をかけて娘の体を温め続けた。翌朝父親が娘を抱いたまま倒れているのが発見された。父親は凍死、娘は凍傷を負っていたが助かった。《父一人子一人の子を雪中に存(ながら)えさせし父の体温》(池上晴夫)の歌が、3月25日の朝日新聞朝日歌壇に掲載されていた。まさしく、父親の体温が娘の命を救った。
冬期北半球では、西北の風が吹く。シベリアから冷たい風が日本へ向かって吹いてくる。この風は、シベリアと日本の間にある日本海の水蒸気を運び、それが日本の中央を縦走する山脈に当たったときに雪となって落ちてゆく。この時期は大体1月から2月にかけてであって、換言すると、冬期の季節風の最も旺盛な時期に日本海側に大雪が降る。大雪に苦しめられるのは、新潟、富山、石川、山形、長野などをはじめとして、北海道、青森、秋田、岩手などに及んでいると、雪の結晶の研究者・中谷宇吉郎著『雪』(岩波文庫 1994)に述べている。
柏原辰吉著『北海道の自然 雪を知る』(北海道新聞社 1993)を開いてみる。魚のえいの形に似た北海道の中央を、北から南に連なる北見・日高の両山脈、これにより北海道の冬の天気は見事に西と東に分けられる。日本海側の留萌の1月の日照時間は51時間(1日になおすと1.6時間)、太平洋側の釧路では172時間と、3倍以上の日照に恵まれる。釧路の一冬の降雪量の合計は148cm、留萌では479cmと、これも3倍となる。天塩山地や暑寒別岳付近の積雪は4〜5mに達することがあり、春の雪解け水は100km2当たり約2億m3の水が流れ出す。北海道の河川は4月から5月にかけて最も流量が多くなる。山の雪が天然のダムとか、白い石炭といわれるゆえんである。
酒井與喜夫著『カマキリは大雪を知っていた 大地からの天気信号を聴く』(農山漁村文化協会 2003)には、カマキリが高い所に産卵すると大雪になることを約40年間にわたって、立証した。カマキリの産卵が始まるのは初雪の降る90日前後、雪に埋もれないようにうまく越冬し、春を迎える。大雪のときは杉など高い所に産卵場所を選んでいる。それは、平年積雪の3倍の高さであるという。面白い民間研究者の記録である。雪崩のよる雪国の悲劇はあとをたたない。特に豪雪のときには雪国では雪崩が起こり、人命が失われている。若林隆三著『雪崩の掟』(信濃毎日新聞社 2007)は、世界及び日本の雪崩現象をとらえ、その対策を教えてくれる。
鈴木牧之(ぼくし)と柳田国男
昭和25年ごろの我が家は、雨が降れば天井から水が落ちてきて、あるだけの洗面器を並べたが、江戸期においても雪漏れ水のために同じことを行なっていたことを知り、驚いた。鈴木牧之編撰『北越雪譜』(岩波書店 1991)は、越後塩沢の著者(1770年〜1842年)が豪雪地帯で暮らす人々の習俗を綴った江戸期の出版物の復刻である。家内の氷柱の項目で、「春も稍深くなれば雪も日あたりは解あるひは焚火の所雪早く解るにいたりて、かの屋根の損じたる処木羽の下たをくぐりてなどして雪水漏ゆゑ、夜中にわかに畳をとりのけ樋鉢のるゐあるかぎりをならべて漏をうくる」とあり、「漏は次第にこほりて、座敷の内にいくすぢ大なる氷柱を見る時あり。是暖国の人に見せたくぞおもはる」あわてて、畳を上げている光景は滑稽でもあり、なお、部屋の中に氷柱が張るのもまた滑稽に映る。
もう一つ、斎の神の祭りを挙げてみる。「吾が国正月十五日に斎の神のまつりといふは所謂左義長なり。正月かざりたるものをあつめて燃やす。小地谷といふ所人家千戸よきとちなり、これをまつるにその町々におのおの毎年さだめの場所ありてその所の雪をふみかため、さしわたし三間ばかりめぐらしたる高さ六七尺の円き壇を雪にて作り、これに二処の上り階を作る、これを雪にてする」と事細かに綴る。他にも「雪蟄(ゆきこもり)」、「熊人を助」、「越後縮」、「鮭の洲走り」、「餅花」などが雪国風土記を現わす。
昭和16年ごろの秋田地方における雪国の生活を捉えた柳田国男・三木茂著『雪国の民俗(復刻版)』(日本図書センター 2012)がある。坊主頭には手ぬぐいをしばり、編み笠を覆い、草履をまとっている。農に従う、激しい風土の中で、土に生きる人たちが描きだされている。農村歳時記では、大正月お飾り、トシナ、秋田萬歳、カンモチ、ナマハゲ、ボンデン、出稼ぎ、天神祭、早苗振り、鹿島さま、盆の市、雀追ひ、籾摺り、田舎芝居、薪とり、年の市、餅つきを捉え、衣食住と民具では、アネコモッぺ、輪髪、分け髪、トンビ、カクマキ、ケラ、キダラ、ホシモチの飾り、箱電車、煙だし、飯櫃と箱膳、カヤギザラと岩七輪、ドジョウド、そして信仰・まじなひでは、小祠、虫送り、エモナガシ、犬コ、百萬遍の綱、ナナクラヨセ、薬師の絵馬、庚申講を映し出す。
このような雪国の生活を柳田国男は、「雪国の分散せぬ冬の家庭には、単なる安静とか平和とかいふもの以上に、無言の愛情の調和が醸し出されて居たのであった。祖父に赤い鼻緒の草履をこしらえてもらって居る悦びなど小さなことだが一生覚えて居る女が多かった。それと同じことを今一段と念入りに心を籠めて、年をとってから男にして返そうとすることが、永い世代に亙って一家の繋がりを引きしめて居たのである」と、指摘する。しかし、雪国の生活もまた時代と共に変化する。
雪国の生活
山川肇著『雪ぐにの人生―風土を生きる―』(農山漁村文化協会 1986)から、その変遷を追って見る。昭和21年の第1次農地改革、次いで第2次改革で、不在地主制は否定され、耕作権が物権化され、小作料が金納化され、農地の移動が制限された。暦が新暦に変わった。旧暦は農事暦で、特に雪国の地方では、旧暦が便利であった。独立農民のモラールは高まり、農業生産力は高まり、60年代の高度成長で農業の機械化が進む。次は、燃料革命である。集落共同で伐採し、細分した木を沢におろし、雪を利用して雪そりで運び、各戸で薪にした。これが石油に変わった。そして、農耕馬が姿を消し、馬力が耕運機に変わった。旧暦がなくなり、農耕馬が消え、薪による燃料が変わり、雪国の暮らしのサイクルが大きく変わった。秋田地方に残っている犬こまつり、かまくら、竹打ちも観光行事に変わり、そこには生活がないという。また、雪国の住宅建築にも変化を受ける。
雪の社会的な追求者である高橋喜平著『雪国の人びと』(創樹社 1979)は、昭和28年に発行されたもので、好評なので新版となった書である。この書で「雪と文学」について、次のように語っている。雪の文学は、詩の形式によるものが多いとあり、その理由は「雪が人の心を揺さぶるのは光の諧調によるものであって、雪から光を除けば残るものは石ころ同様の単なる個体でしかありえない。つまり雪は光の強弱と陰影を巧みに利用して自らの美貌を強調している。その美しさつきない余韻を持っているために、人々が雪から受ける感動を表現するには、詩がもっとも適当な役目をもっている」という。
日本列島が高度成長に向かい、雪国が大きく変貌していく。その変貌について、昭和一桁生まれの新聞記者が雪国をくまなく歩いたルポ、佐藤国雄著『雪国大全』(恒文社 2001)は、鈴木牧之の『北越雪譜』を超える書といえる。三八豪雪をきっかけに、雪を宿命と諦めていた住民の意識が大きく変わった。戦争に多くの兵士を送り出し、戦後の立て直しに米や野菜の食料をはじめエネルギー源の水力発電、さらに労働力としての団地づくりや新幹線、高速道路建設工事などの出稼ぎ、みんな日本海側の雪国の人びとが支えてきたのである。それを雪国の政治家たちが中心となって、「表日本」との生活格差、その矛盾を訴え、積雪関連の法律が成立し、大型機械力が導入され、国道や幹線道路の無雪化が実現、屋根の雪下ろしに関する克雪住宅も開発されるようになった。かつて「雪地獄」と嘆き、諦めていた雪国にも新時代が到来した。
この書の内容は、冬への序曲、雪による災害、住まいと雪下ろし、雪と道路、鉄路を守る、民俗と暮らし、雪国の伝統行事、出稼ぎと花嫁、雪の恵み、スキー今昔、文学と雪を捉える。雪はマイナス面ばかりではない。雪の恵みは、空気を清浄にしてくれる。気分を爽やかに、山の雪が河川の源を養う。そりで重いものを運ぶ、野菜穀物を優しく包んで寒気から守る。地中からの水分の蒸発を抑える。雪は豊年を約束、雪明りが冬の夜を明るくする、詩人や画家の良いモチーフになると雪国を賛美している。吉野正敏編著『雪と生活』(大明堂 1988)では、雪の積極利用として、降雪による無塵を利用した小千谷の縮、銘酒「越の寒梅」、「麒麟山」、「太平山」、秋田の「いぶりガッコ」、青菜漬け、野沢菜漬け、そしてハム、ソーセージなども雪国でなくてはならない食料である。
雪の歌
雪国の昔話を一つ挙げるとすれば、岩崎京子/文、井上洋介/絵『かさこじぞう』(ポプラ社 2006)であろう。大晦日、貧乏なじいさんが、吹雪の中、町へ五つのかさこを売りに出かけますが一つも売れなく、帰りに六つの雪の中の地蔵様が寒かろうと、五つ地蔵様にかさをかぶせ、一つには、じいさんのつぎはぎだらけの手ぬぐいをかぶせて家に戻ります。その夜、六人の地蔵様がじいさんの家に、米の餅、粟の餅のたわら、それにみそだる、ニンジン、ごんぼう、お飾りの松をもってきました。じいさまとばあさまは良いお正月をむかえることができました。
このお話には、お地蔵様に対する優しい心が貫かれ、その優しさが爺様と婆様へ返ってきている。雪には人と人との優しさをつなげる効用があるようだ。太宰治は「こな雪 つぶ雪 わた雪 みず雪 かた雪 ざらめ雪 こおり雪」と、七つ雪を表現。これを演歌歌手新沼謙治が「津軽恋女」で歌って全国的にヒットした。雪に関する2編の詩を挙げて終わりたい。
「雪」
太郎を眠らせ、太郎の屋根に雪ふりつむ。
次郎を眠らせ、次郎の屋根に雪ふりつむ。(三好達治)
「積もった雪」
上の雪 さむかろうな つめたい月がさしていて
下の雪 重かろうな 何百人ものせていて
中の雪 さみしかろうな 空も地面もみえないで(金子みすゞ)