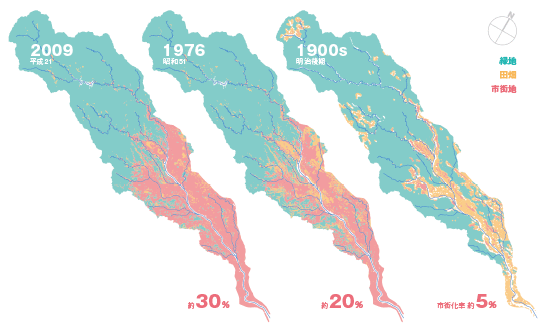機関誌『水の文化』48号
治水哲学を涵養するもの

九州地方最大の河川である筑後川。別名 筑紫次郎とも呼ばれ、坂東太郎(利根川)と四国三郎(吉野川)と並び称される大河であると同時に、暴れ川でもある。
高橋裕さんは東京大学第二工学部土木工学科のご出身。第二工学部は、戦時中の工学者・技術者養成を目的として、1942年(昭和17)から1951年(昭和26)までのわずか10年間存在した学部です。本郷の第一工学部と比べて、教官は他組織での実務経験者が多く、自主独立の気風があったといいます。高橋さんはここを河川哲学構築の出発点として、全国の川や水害発生現場に足を運びつつ、領域を超えた交流の中で、総合治水の重要性を訴え続けてきました。技術だけに偏らない治水哲学を、と次世代に引き継ぐべき想いを語っていただきました。
-

-
東京大学名誉教授
高橋 裕(たかはし ゆたか)さん -
1927年静岡県生まれ。1950年東京大学第二工学部土木工学科卒業。1955年東京大学大学院(旧制)研究奨学生課程修了。1968年から1987年東京大学教授。1987年から1998年芝浦工業大学教授。国際連合大学上席学術顧問、河川審議会委員、水資源開発審議会会長、中央環境審議会委員、東京都総合開発審議会会長、ユネスコIHP政府間理事会政府代表、世界水会議理事などを歴任。『河川工学』は土木学会出版文化賞を受賞。
主な著書に、『国土の変貌と水害』(岩波書店 1971)、『都市と水』(岩波書店 1988)、『河川工学』(東大出版会 1990/新版2008)、『社会を映す川』(山海堂 2007)、『川と国土の危機−水害と社会 』(岩波書店 2012)、『土木技術者の気概−廣井勇とその弟子たち』(鹿島出版会 2014)ほか
災害リスクを抱えた日本
日本の戦後は大規模水害とともに幕開けしました。
終戦の年、1945年(昭和20)9月の枕崎台風は、死者・行方不明者約4000人、全壊家屋5万5000戸以上という直接被害だけでなく、米の収穫時と重なったことで日本の食糧事情悪化に拍車をかけました。
1947年(昭和22)にはカスリン台風が利根川を破堤させ、5日後にその氾濫流が南下して、東京東部が水没。1945年から1959年(昭和34)までの戦後15年間、日本では大水害が頻発し、ほとんど毎年1000人を超す水害犠牲者が出ていたのです。
温帯地域に位置する先進国の首都が、こんなにも自然災害にさらされているのは特殊なことです。
伊勢湾台風に見舞われた1959年(昭和34)、私は留学先のフランスでその報に接しました。それまで日本の治水対策、水害の実態を現地で話すたびに、「先進国である日本で毎年1000人もの人が水害で亡くなるなんて信じられない。高橋の話は大袈裟なのではないか」と疑われていましたが、伊勢湾台風の被害が報道されて、やっと私の話が本当だと理解してもらえたほどです。
島国である日本は、近代的発展を主として沿岸地域の開発によって成し遂げてきました。臨海に工業と人口を集中させた結果、津波や高潮に対する危険度は非常に高くなりました。
治水対策が功を奏し、1982年(昭和57)に長崎市とその周辺で299人の死者を出して以降、日本では死者100人を超した水害はありませんでした。そのため、日本人の災害に対する感覚も鈍くなっています。しかし日本列島では地震や火山噴火のリスクも高く、阪神淡路大震災や東日本大震災、また近年多発する土石流によって、再び大規模災害多発地帯の様相を呈しています。日本がヨーロッパ諸国とは違う地質、地形、気候風土であることを再確認する時期にきています。
資源調査会に鍛えられる
敗戦直後の日本は国土が荒廃し、衣食住とも極度に不足していました。
「日本は資源がない国だ」というおおかたの認識を覆し、「日本には水と土地が豊富にある。それを有効に開発すべき」と言って日本の将来に希望を与える発言をしたのがGHQ(連合国最高司令官総司令部)天然資源局技術顧問として来日中のエドワード・A・アッカーマン博士でした。
当時外務省調査局部員だった大来佐武郎(おおきた さぶろう)さんたちがアッカーマン博士と研究会を重ね、1947年(昭和22)12月に、資源の総合的計画的利用のために資源委員会が設立され、事務局長に安藝皎一(あき こういち)先生(1902〜1985年 当時は内務省土木試験所長)が就任されました。資源委員会はその後、資源調査会と改名しています。
私は治山治水部会に大学院生時代から専門委員としてかかわらせていただくようになり、その後委員として1991年(平成3)まで35年間、資源調査会のお世話になりました。
戦後15年は大型水害が頻発していましたから、災害復旧費や治山治水費は膨張の一途でした。治水投資の妥当性について建設省(当時)以外からの意見も必要と、大蔵省(当時)から強い要望が出されました。そのためか治山治水部会には土木工学者や建設省関係者のみならず、地理学、農業水利学、林学、経済学といった多彩な分野から個性的な専門家が顔をそろえました。自由闊達な学際的な会議からは、日本復興に向けた各委員の熱意を感じたものです。
1953年(昭和28)から3年間の筑後川水害調査を皮切りに、以降3年ずつ特定の河川を対象に現地調査を続けたことも、狭義の河川工学を越えた広い視野を養うのに役立ちました。ここでの経験と学際的な交流が私の河川哲学を鍛えてくれたと感謝しています。
ピーク流量増加の仮説
今から61年前、1953年(昭和28)6月25日から29日までの5日間に、筑後川流域は未曾有の梅雨の大雨に見舞われ、北九州一帯が大洪水となって死者行方不明者1000人超、全半壊流失家屋4万5000戸となる大被害となりました。資源調査会治山治水部会の最初の現地調査は、この筑後川水害の検証から始まりました。
当時は飛行機や新幹線の時代ではありませんでしたから、水害発生直後、東京大学大学院生であった私は東京から久留米まで24時間以上かかって、何回も現地に入りました。
この水害に遡ること6年前、1947年(昭和22)のカスリン台風のときの利根川の洪水流量は、1万7000m3/s(前橋の八斗島量水標から栗橋に至る流量)で、利根川における有史以来の最大流量を記録しています。
利根川の洪水流量の推移を調べてみると、1896年(明治29)は5300m3/s、1910年(明治43)は6960m3/s、1935年(昭和10)は9030m3/sと更新され、カスリン台風時には明治大洪水の3倍にもなっていました。たとえ想定外の豪雨だったとしても、明治期と比べて3倍も降ってはいないでしょう。どこの川でも同じ傾向が出ていましたから、私は明治以来の河川工事が洪水のピーク流量を増加させたのではないか、という仮説を立てていました。
ところが利根川には長期観測データが少なく、比べようがないのです。5年や10年の観測データからでは違いは導き出せません。そう思っているときに、筑後川で未曾有の大水害が起こりました。
調査出発前に指導教官の安藝皎一先生から「筑後川洪水の出足は、きっと早くなっているだろう。洪水流量も明治、大正期よりも大きくなっているという仮説に立って検証してはどうか」というアドバイスをもらいました。
継続観測の価値
私は、『新河川学』〈野満隆治(のみつ りゅうじ)・瀬野錦蔵 共著/地人書館 1959〉に上野巳熊(みくま)さんという方が長らく水文観測をしていることが紹介されていたのを読んで、林野庁小国試験地の上野さんを訪ねることにしました。
小国試験地はかつての森林測候所で、1914年(大正3)以来の時間雨量が正確に記録保存されていました。開設以来観測してきた上野さんは、上流(大山川流域小国町及び玖珠川流域の森町)の雨量と下流(久留米の瀬下)の洪水位との関係を統計的に分析し、上流の雨量から下流の洪水位を事前に予測するという日本最初の洪水予報を導き出しました。「豪雨時の雨量と流量の関係を究めたい」という科学的好奇心から出た分析結果でしたが、本業の林業試験場の仕事とは関係ないと上司の叱責を買ったそうです。
上野さんが参考にした瀬下量水標にも、流量記録を取り続けた人がいました。瀬下量水標には1885年(明治18)から67年間取り続けた365日24時間水位記録67冊が、量水番の倉庫に大切に保存されていました。
祖父の代から「明治天皇のご命令だから何ごとにもまして大事な仕事だ」と言って、河川敷に自費で小屋を建て、そこに寝泊まりして1時間ごとに量水標記録を読んでいたそうです。内務省からの任命でしたから、明治天皇のご命令、となったのでしょう。
孫であるその人が観測を始めて20年の間、記録を見に来たのは私が初めて。誰も見に来ずとも、真面目に観測を続けてこられた量水番ご家族のお蔭で、私は仮説を立証することができました。
河川工事が起こす副作用
洪水を素早く流すために連続堤防を築いたことで、従来あふれていた洪水の流れが河道に集められてあふれなくなったのですから、中下流部の洪水流量が増大するのは当然です。
明治以来の洪水対策が結果的に中下流部の洪水のピーク流量を大きくし水害リスクを高めることになったことは、今となっては常識になっていますが、当時はそんな仮説を立てる者はいませんでしたから、建設省(当時)の一部の幹部は大変機嫌を悪くしました。私は河川工事が悪かったとは一言も言っていないのに、批判されたと思われたのでしょう。
川は大工事を施すと河道の形態が大きく変わって、しばしばマイナスの副作用を生じます。要は、その認識を持つことが大切です。
水害が裁判になる時代
高度経済成長期に入り都市の水需要が増え、水不足が深刻な問題となり、筑後川上流にも筑後川の治水と日田市の下流への利水、水力発電を目的とした松原ダム・下筌(しもうけ)ダムが計画されました。
当時は開発一辺倒で「ダム反対は非国民」とまで言われる時代でしたが、小国町の大地主である室原知幸さんは、下流への利益のみを追求して地元を省みない開発一辺倒なやり方に異議を唱え、東京地裁に提訴。私は下筌ダム訴訟で原告側鑑定人を引き受けましたが、「国立大学の教授が国策に反対する側につくことはけしからん」という考えが大勢を占めている時代でした。
室原さんはダムサイトに〈蜂の巣城〉を築き、1958年(昭和33)から1971年(昭和46)まで13年間にわたる反対運動の先頭に立ちました。「公共事業は法に叶い、理に叶い、情に叶わなければならない」という名言を残し、〈水源地域対策特別措置法〉成立のきっかけをつくった人物です。
水害訴訟は1970年前後から多発しますが、それは60年代に入って住民意識が変化し「水害は行政の責任」という考えが広まった結果です。新潟県北部〜山形県豪雨による羽越水害(1967年〈昭和42〉)を皮切りに、大阪・寝屋川氾濫による大東水害(1972年〈昭和47〉)、多摩川水害(1974年〈昭和49〉)など、全国で訴訟が起こされました。
私は多摩川水害訴訟で原告、被告の共同推薦で法廷に立つなど、多くの水害訴訟にかかわりました。研究者として科学的見地に立って裁判にかかわったことで、河川の見方が鍛えられたと思います。
水害は社会現象
水害は、被災地域の開発、土地利用と密接な関係にあります。
1958年(昭和33)の狩野川台風では、東京の人口が急に増え、洪水を受け止めてくれていた田畑などが失われたことで、多くの新興住宅が浸水被害を被りました。都市水害の走りといわれています。
1959年(昭和34)の伊勢湾台風では、農地が工場に変わるなど土地利用が急変し、地下水の過剰揚水が地盤沈下の原因になり、さらに大径木のラワン材が海岸堤防を乗り越えて人や家屋に当たって被害を大きくしました。増大した木材需要からフィリピンのラワン材を大量に輸入して、貯木場に収まりきれない分を仮の貯木場に置いていたのです。
狩野川台風にしろ伊勢湾台風にしろ、あと10年早くきていたら、これほどの被害は起きなかった。つまり、水害の規模は降雨や台風の規模だけに左右されるわけではなく、土地利用が大きく影響を及ぼしているのです。それを単に自然現象が原因だと言ってしまったら、有効な対策を立てることはできません。
都市計画を行なう側が水害との関係を充分に認識し、危険地域では地下室建設を制限したり、ピロティ式住宅(1階部分を柱だけの空間にした住宅)を推進するなど減災に務める責任があります。
土地だけでなく、川の利用履歴を知ることも、減災のために有効です。例えば一級水系利根川の支流である小貝川は、古くから洪水の多い川として知られていますが、江戸時代には用水河川でした。水を取りやすくするため河床を高くしていましたが、裏返せばあふれやすいということです。江戸時代にはそれをわかっていたから、周囲の土地利用もそれに応じたものになっていたのです。
被害がなぜ生じたかは、想定外の降雨や自然現象だけが要因ではありません。なぜそこに人が住み家屋が建っていたか、再び被害を生じさせないためにはどうしたらいいかという点に言及してこそ、災害の専門家としての役割が果たせると思います。
水害発生リスクの変化
河川改修事業の効果で大水害は相当程度和らげられ、ダム建設によって水不足が解消されましたが、1970年代後半から人工化された河川の環境悪化が問題視されるようになりました。
ダムや堰の影響で土砂の動きも変わり、下流や河口への土砂の流れは減り、建設ブームを支える川砂の乱掘などにより、河床は不安定になりました。大水害頻発時代は海岸への流出土砂に苦しめられましたが、最近は逆に土砂流出が減少し、河口部周辺の海岸決壊を招いています。
また、都市化の進行は、都市の水循環を変化(都市域における浸透量の減少、豪雨の河道への直進による洪水流量の増加など)させました。
都市の中小河川の流出率(河川流出量と降水量の比)はいよいよ増加し、いわゆる都市型水害が全国の多くの新興住宅地に蔓延しましたが、これは無秩序な宅地開発が原因の一つなので、従来の河道改修のみでは完全に防ぐことはできません。
現在、河川整備計画が直面している難問は、気候変動に対する治水計画、それと深く関係している海岸保全計画、森林及び水源地計画です。
2007年(平成19)のIPCC(気候変動に関する政府間パネル)報告によれば、将来、豪雨頻度が増し、大型台風の襲来や海面の上昇(21世紀末までに最大59cm)も予測されています。
2004年(平成16)は、死者224人、行方不明者16人という甚大な被害が出た年となりました。この年に発生した台風29個の内、10個も上陸したのがその原因です。これは地球温暖化による気候変動、特に海水面の上昇の影響とも思われます。
またゲリラ豪雨と呼ばれる局地的大雨には、気候変動だけでなく、都市化によるヒートアイランド現象の影響もあります。台風の頻発などによって水害のリスクが増えるだけでなく、水源地域の人口減少に伴って、今までの治水政策の変更も必要となります。
治水政策の転換を
治水安全度の低下は、多くの日本の河川において確実に進行しつつあります。日本の重要河川の治水目標は、過去100年の洪水資料に基づき、200年に1回の確率の大洪水に堪えることを目標としています。しかし、その確率洪水の計算を最近20年間の洪水流量記録に基づいて再計算すると、治水安全度は、従来計画のおおむね半分にまで落ちています。
治水安全度の低下を補うには、従来の河川改修やダム計画だけでは不可能で、治水政策を思い切って転換する必要があります。
例えば、大洪水の対策には、氾濫危険区域の開発規制と大洪水時の浸水補償を考慮した一時的氾濫遊水地の設定など、水害に強いまちづくりを行なうことが有効でしょう。今まで河道内に押し込めることを目標としていた洪水流の一部を、河道外へあふれさせることを含む治水策です。
また、海面上昇による津波・高潮危険度増加に対しては、長期構想を立て沿海部における土地利用を見直し、重点的に守るべき地域とそうでない地域とに分けて効率化を図らなければ、すべての土地を守ることは難しいでしょう。
日本の多くの海岸堤防は、1959年(昭和34)の伊勢湾台風以後に建設され強化されたので、そろそろ更新期を迎えるタイミングです。そこでまずは補修時に堤防高を逐次嵩上げして、海面上昇に備えます。
これらの施策は今までの治水対策とは異質であり、土地利用の改変を含むので、従来の行政のしくみや既存の手続きでは実施することは難しく、新たな法体系、行政手法が求められます。ともかく、島国である日本にとって、22世紀までも続く海面上昇は由々しき大事であることを、政治家も行政もしっかりと認識し、長期的視野に立って対策を樹立すべきです。
治水哲学を磨く
気候変動という新たな課題は、私たちに治水対策、沿海域対策の大きな転換を求めています。
戦後の食住不足の時代には、連続堤防を築いて中小洪水を防ぎ周辺地域を開発することが、その時代の要求でした。しかし時代は移り、社会的要求も変化しています。
河川の在り方も、それに応じて変化するのが当然で、どのような治水対策をとるかは、河川技術者の哲学に左右されます。
『技術生活より』を著し、土木界の哲学的先達だった直木倫太郎さん(1876〜1943年)は、「『人』あっての『技術』、『人格』あっての『事業』であり、その『人格』の向上を計らないで独り『技術』の力のみを欲するのは困難である」とその技術哲学を発信しました。
私自身、学際的な交流や地域の歴史や土地利用形態について学ぶことで、少々の治水哲学を磨いたと自覚しています。
日本はアジア・モンスーン地域に属し、稲作を中心とした土地利用で森林や沿岸域の管理を行ない、技術だけに偏らない治水哲学を培ってきました。今一度、日本固有の土地利用を見直し、新たな技術を加味した治水哲学を構築したいものです。
(取材:2014年6月12日)