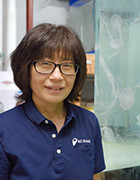機関誌『水の文化』51号
水中を浮遊するクラゲに癒される

真昼の空の満月のようなミズクラゲ。成体は傘の直径が15〜30cmくらいになる
水中でふわりふわりと泳ぐクラゲが「癒される生きもの」として人気を集めている。得体のしれない姿であり、しかも毒をもっているので苦手な人もいるはずだが、いまや全国各地の水族館がクラゲの飼育・展示に力を入れている。クラゲの何が私たちの心を癒すのか。クラゲ展示の先駆けとして知られる新江ノ島水族館(神奈川県藤沢市片瀬海岸)を訪ね、人気の理由を探った。
-
新江ノ島水族館
クラゲの飼育展示に先駆けた水族館
目の前が相模湾の砂浜。夏ともなれば海の家で賑わう。潮風の心地よい絶好の場所に新江ノ島水族館は位置している。
日本全国に水族館は数あれど、ここはクラゲの飼育と展示にいち早く着手したことで名高い。1954年(昭和29)、旧江の島水族館オープンと同時にクラゲは水槽にいた。「初代館長が生物の進化・系統の学問的な観点からクラゲは外せないと考えたのと、葉山の御用邸に近いことも理由の一つです」と話すのは、学芸員でクラゲの飼育技師、足立文(あや)さん。クラゲの研究者でもあった昭和天皇は、御静養の折、しばしば水族館まで足を延ばされたという。
1973年(昭和48)、人工飼育の難しいミズクラゲの一生を水槽内で再現することに成功し、常設展示が可能になった。さまざまなクラゲを飼育し繁殖する試行錯誤を積み重ねた結果、1988年(昭和63)には世界初のクラゲ専門展示館「クラゲファンタジーホール」を開設。1993年(平成5)、長年にわたる飼育繁殖の功績が認められ、日本動物園水族館協会から海産無脊椎動物では初めての古賀賞(注)を授与された。
2004年(平成16)に新江ノ島水族館(愛称「えのすい」)としてリニューアル後もクラゲファンタジーホールは幻想的な癒しの空間として人気を集めている。
(注)古賀賞
希少動物の繁殖に功績のあった動物園や水族館に対して贈られる国内最高の賞。日本動物園水族館協会の育ての親、上野動物園初代園長・古賀忠道博士の業績を記念して1986年(昭和61)に制定された。
変幻自在に浮遊する多種多彩なやわらかさ
絡んだクモの糸のような触手を水槽いっぱいにゆっくり広げるサムクラゲ。鮮やかな赤い触手をひたすら長く伸ばし、ゆるやかに漂うアカクラゲ。優雅にたなびく口腕が天女の羽衣を想わせるインドネシアンシーネットル。その名のとおり紫の縞模様がきれいで、米西海岸産なのに蛇の目傘そっくりのパープルストライプドジェリー。
ふわふわとたゆたうのもいれば、ぴょこぴょこ向きを変えるのも、ゆらゆら流れてゆくのもいる。赤、桃、橙、黄、紫――変幻自在に浮遊する無色透明な〈やわらかさ〉に多種多彩な〈差し色〉が入った自然の見事な造形には恐れ入るしかない。
ぼーっと見ているだけで、水に漂うクラゲの優雅でゆるやかなリズムに引き込まれ、せわしなさに磨り減り尖っていた心の角が丸くなる。水のなかで奏でられる形と色と動きのシンフォニーは、いつまで眺めていても飽きない。「リピーターのお客さまも多い」(足立さん)のがうなずける。
旧江の島水族館の時代、1997年(平成9)に初めて癒しをテーマにしたイベント展示「クラゲのリラクゼーション」を開催した。その後、全国の水族館の定番的なテーマ設定となる〈クラゲ=癒し〉の先駆けも「えのすい」だった。
「クラゲのゆったりしたリズム」と「すりガラスのような、やさしい透明感」がクラゲの魅力だと足立さんは考えている。
だから、エンターテインメントに走った過剰な装飾はしない。「光の演出も、あくまでクラゲ本来の美しい色を際立たせるためのものです」(足立さん)。
丸みを帯びたデザインが和やかさを感じさせることから、クラゲファンタジーホールの水槽の窓や解説パネルの四隅の角は丸くしてある。2013年(平成25)に登場した球型水槽「クラゲプラネット(海月の惑星)」も、より美しく癒されるクラゲ展示を追求したものだ。
おなじみの姿は一時期で、
脳も心臓もなく生きている
10分間のクラゲショー「海月(くらげ)の宇宙(そら)」が始まった。壁と天井にプロジェクションマッピング(CGによる特殊効果の視覚演出)で江ノ島の海の動画が映し出される。気がつけばクラゲファンタジーホールはクラゲの傘を模したドーム状。「クラゲは人よりも魚よりも恐竜よりもはるか昔、地球に誕生しました。特別なところに棲んでいる生きものではありません。江の島のまわりにもたくさんのクラゲがいます」のナレーションとともに、周囲の海面がせり上がる。巨大なクラゲの体内に抱かれた観客を海中へと誘う趣向だ。
ミズクラゲの一生が再現された。よく知られた容姿で海を漂うのは、ほんの一時期にすぎない。卵から孵った幼生は岩などにくっつき、小さなイソギンチャクに似た姿になる。やがて体がくびれ、皿を重ねたような形に変わって、その一枚一枚が離れて浮遊し、おなじみの格好のちびクラゲへ。
観客から「ああやって生まれるんだ! すごいすごい、初めて見た!」と感嘆の声がもれた。クラゲには脳も心臓もない、というのにもびっくり。
「神経と筋肉と消化器官と生殖器官だけのシンプルな生きものです。エサを追いかけて捕まえるなど複雑な動きをする生物は神経中枢で命令を出す脳が必要ですが、クラゲは基本的に水の流れに身を任せ、まわりのプランクトンや稚魚を食べていればいい。反射だけで動いている生きものなんです」と、後で足立さんがくわしく教えてくれた。
クラゲファンタジーホールでクラゲに興味をもったら、隣の展示「クラゲサイエンス」で生態を知ることができる。「えのすい」に行けば最大50種類のクラゲに出会う。
クラゲの生態はまだよくわかっていないことも多く、生理化学的な有効成分も研究されているという。
毒があって嫌われやすいが、
癒される人もまた多い
クラゲの一生は種類によって数週間から数年までまちまち。足立さんによれば、飼育するには「底へ沈まないように水の流れをつくるのと、濾過層から汚水と一緒に吸い込まれないようにすること」が肝心で、なかなかにコツがいる。クラゲは傘の内側に水を抱き込み、その水をジェット噴射のように押し出すことで推進力を生み出しているのだが、泳ぐ力は弱い。多くは水の流れが止まると、ただぷかぷか浮かんでいるだけか、底に沈んでしまう。
飼育が面倒なので他の魚と違って扱う卸売業者も少なく、採集するか他の水族館から譲り受けることが多い。大きいもので触手の長さが50mにも達するカツオノエボシは採集も飼育も難しい。「南から強い風が吹いてくると海岸に打ち上がるので、いそいそと出かけていきます」と足立さん。ただし打ち上げられて死んでも、触手にある刺胞の強力な毒針はしばらく効力があるので、素人は見つけても触らないようくれぐれもご注意を。
「えのすい」では毎月9日、展示飼育スタッフとともに近くの漁港でクラゲを調査・採集する「えのすいクラゲの日」を設けている。季節や天候によっては1時間あまりで10種類ものクラゲを見つけられるという。
クラゲは毒針をもつ「刺胞動物」に属し、イソギンチャクやサンゴの仲間。触手にエサが触れると、刺胞を発射して毒で弱らせ、触手から口腕を伝って真ん中の口、胃腔へとエサを送って消化し、不要なカスをまた口から出す。
つまりクラゲの毒はエサを食べて生きるために必要なものなのだが「刺されると痛くて怖い、気持ち悪い」とクラゲを忌み嫌う人も少なくない。
「水族館で〈好きな生きもの〉のアンケートを取るとイルカやペンギンがトップで、クラゲは人気がありません。ところが〈癒される生きもの〉だと上位にくる」(足立さん)という。
かつて研究者との共同研究では、さまざまな測定やアンケート調査から、クラゲの癒し効果の有効性が示唆された。最近では、〈癒される生きもの〉として観賞用「クラゲ飼育セット」も市販されるようになった。動物園と水族館の文化は西洋が発祥だが、ことクラゲの飼育展示に関しては「えのすい」をはじめ日本の水族館が世界の先頭を切り、海外にも影響を及ぼしているという。
生命の源としての水に一番近い生きもの
足立さんは大学で生物の研究をしているときから「よくわからない不思議な海の生きものが好き」だった。その代表選手がクラゲ。「毒があって怖いとか気持ち悪いという先入観を取り払って、こんな生きものも海にはいるんだ! という気づきの窓口になってもらいたい」との思いでクラゲの飼育展示に取り組む。
「海月の宇宙」のナレーションで、ハタと膝を打つところがあった。
「浮遊するクラゲたちに囲まれていると、ふと時間と空間の感覚があいまいになることがあります。宇宙の塵から地球が生まれ、その地球で生命が誕生しました。クラゲを見ていると不思議な感覚になるのは、命のもとがふわふわと宇宙空間を漂っていたころの、遠い昔の記憶のせいなのかもしれません」
クラゲの身体成分の大半は水。死ぬと溶けて海水に戻る。クラゲは原初の地球で生命が誕生した母なる海の記憶の遺伝子も呼び覚ますようだ。水面に浮かぶ姿を上から見ても癒されないのに、水中で漂う姿は人を癒す。クラゲとは、実に不思議な生きものである。
(2015年8月10日取材)