機関誌『水の文化』61号
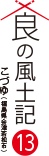
舟運と文化の蓄積がもたらした こづゆ

会津地方でハレの日に食される「こづゆ」
水と風土が織りなす食文化の今を訪ねる「食の風土記」。今回は、福島県会津若松市の郷土料理「こづゆ」です。ホタテの貝柱を使ったこづゆには、舟運と会津の風土が大きく関係していました。
阿賀川を遡り運ばれた海産物
うまみたっぷりのホタテの貝柱でだしをとり、里芋やにんじん、糸こんにゃくなどを盛り込んだ薄味のお吸い物を、浅めの会津塗の器でいただく。福島県会津地方で江戸時代からごちそうとして食べられてきた「こづゆ」は滋味深く、口にするとほっとする。
磐梯山(ばんだいさん)を含む奥羽山脈や越後山脈に囲まれた雪国の会津では、阿賀川(あががわ)(注1)や只見川(ただみがわ)を遡上するサケやマスが人々の重要なたんぱく源だった。流通網が発達していなかった時代、新鮮な海産物の入手は難しく、北前船によって北海道から新潟港を経由して運ばれる乾物が中心で、身欠(みが)きニシンや棒鱈、こづゆの具材として欠かせないホタテの貝柱などが入ってきた。そのため会津では生の魚介ではなく、乾物を用いた料理がハレの日のごちそうとして食べられるようになった。
乾物は、会津にどのように届けられたのだろう?2010年まで福島県立博物館で民俗分野の学芸員を務めた佐々木長生(たけお)さんに尋ねた。
「新潟港に入った乾物類は、平田舟(ひらたぶね)に積み替えられると阿賀川を遡り、会津藩の西の玄関口として栄えた川湊、津川(注2)まで運ばれました」
新潟から津川までは流れも穏やかで早くから舟運が行なわれていたが、津川より上流の塩川湊までは激流で、特に徳沢と上野尻(かみのじり)間の「銚子の口」は難所のため、越後街道を陸送せざるを得なかった。
「舟が通れないところでは『中追馬(なかおいば)』といって、馬の背に荷物を載せて運びました。空(から)になった舟は舟引が綱で引いて川を上ったのです」と佐々木さんは話す。
そして流れが穏やかになると再び舟に積まれ阿賀川を遡り、塩川湊へ。そこで乾物は荷揚げされ、人の背で会津の各地へ届けられた。
(注1)阿賀川
福島・新潟県を流れる一級河川。福島・栃木県境の荒海山が源流で、会津盆地で猪苗代湖を源流とする日橋(にっぱし)川と合流。さらに尾瀬に源を発する只見川とも合流し、新潟県に入ると「阿賀野川」と名を変え、日本海に注ぐ。
(注2)津川
津川町は新潟県東蒲原郡にあった町。2005年の町村合併で消滅した。現在は新潟県に属するが、古くは会津藩の領地で、舟運で栄えた。
お腹いっぱいになるまで何杯でも
こづゆの発祥にはいくつか解釈がある。中国から伝わった精進料理が会津藩の武家料理となり庶民の間に広まった説。また、江戸時代初期、大晦日や正月の初市などでお神酒と一緒にふるまわれたが、必ず里芋が入っていたことから、里芋を重んじる日本古来の習慣(注3)が根底にあるという説も。
「貝柱は高級品ですから、昔はこづゆに使う貝柱の数がもてなしの度合いを表していたんです。あそこの家は貝柱がたくさん入っていたのに、ここの家は少ないなーって。おもしろいよね」
そう言って笑うのは、会津居酒屋「籠太(かごた)」の店主で、会津郷土料理研究会を主宰する鈴木真也(しんや)さんだ。籠太で、鈴木さんにこづゆのつくり方を見せてもらった。
使う具材は貝柱、里芋、にんじん、キクラゲ、糸こんにゃく、白玉麩、季節の青味(今回は水菜)の7種。奇数で縁起がよいためだ。籠太では最初に日高昆布とかつおぶしでだしをとり、一口大に刻んで下ゆでした具材、貝柱および貝柱を戻した汁を加え、酒と塩としょうゆで味を調える。「つくり方はシンプルですが、具材を戻す、里芋のぬめりを取るために下ゆでした野菜を洗う工程などは手間がかかります」と鈴木さん。
できあがったこづゆは、元は吸い物の蓋として使われていた、小ぶりで浅めの専用椀に盛られる。これはお代わりを当然としており、「お腹いっぱいになるまで何杯でもどうぞ」という会津のおもてなしの心が込められている。こづゆなら祝い事などの正式な席でお代わりをしても失礼にあたらない。
(注3)里芋を重んじる日本古来の習慣
里芋は古くから農耕儀礼や儀礼食に用いられ、稲の伝播より古いとも推定される。また、正月に餅を食べずに里芋を食べる地域も各地にあり、「芋正月」などと呼ばれる。
今でもこづゆは家庭料理の定番
意外なことに、会津では正月におせち料理を食べる習慣がない。鈴木さんが子どものころの主な正月料理といえば、サメの煮つけ、サケの粕煮、ニシンの昆布巻き、豆数の子などに加え、大鍋につくったこづゆを毎日のように食べていたそうだ。今でも正月はもちろん、冠婚葬祭、子どもが帰省したときなど特別な日にこづゆをつくる家庭は多い。
「私が郷土料理の研究を始めた理由の一つは、こづゆがなくなることが嫌だったから。つくる手間を面倒だと思えば、こづゆは家庭から消えてしまいます」と鈴木さん。
鈴木さんの開く料理教室では、こづゆの回は通常よりも参加者が増える人気ぶりという。
一方、材料をレトルトのパックにまとめた「こづゆセット」も会津のスーパーや土産物店で販売されている。鈴木さんは「手軽で便利だけど、やっぱり家庭の味がいちばん。昔はこづゆができなきゃ嫁じゃない!なんて言われたけどね」と笑う。ちなみに、会津には「ざくざく煮」というこづゆに似た郷土料理もあるが、鈴木さんいわく「貝柱ではなくサケのアラを使うこと、大根が入っている点が違う」とのこと。
文化が蓄積する会津特有の風土
「会津」という地名の由来が、日本最古の歴史書『古事記』にあると佐々木さんが教えてくれた。8世紀の崇神(すじん)天皇の時代、諸国平定のための任務を終えた大毘古命(おおひこのみこと)と建沼河別命(たけぬなかわわけのみこと)が出会った場所が「相津」と呼ばれ、のちに「会津」になったという。
佐々木さんによると、神々が出会う場所、つまり文化が合流する場所が会津であり、阿賀川や只見川は文化の通り道なのだ。
「会津は、周囲を山に囲まれた盆地で、しかも豪雪地帯ですから文化が入りづらい。けれど、いったん入ったものは通過せずに留まり、共存していく特色があります。例えば正月には棒鱈を食べるなど、ほかの地域ではすでになくなってしまった習俗が、会津には今も残っていたりするのです」
和船と人が運び、外の文化を留めるという会津特有の風土のなかで根づいたこづゆ。これからもこづゆが継承されていく未来を願う。
こづゆのつくり方
取材協力:会津居酒屋「籠太」
福島県会津若松市栄町8-49
Tel.0242-32-5380 (17:00〜23:00/日曜休[不定期])
(2018年12月13日取材)

















