機関誌『水の文化』72号
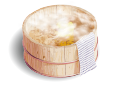
【過去に縛られない未来】
〈第三世代〉が重ねる試行錯誤
──「地域の力」で知名度上げた黒川温泉
かつて「半農半営」の湯治場だった熊本県の黒川温泉。交通の便が悪く、同じ阿蘇地域にある杖立(つえたて)温泉や内牧(うちのまき)温泉と比べても無名だった。ところが一人のカリスマに影響を受け、景観などを含めて「黒川らしさ」を演出すると、全国屈指の人気温泉地となる。そこに至る創意工夫、そしてそれを土台としながらも現状に甘んじることなく新たな魅力を積み重ねようとする若い世代に焦点を当てる。

黒川温泉の名を広めた「山の宿 新明館」の後藤哲也さんが設計した風呂。日本の温泉は10種の泉質が定められているが、
黒川温泉には「単純温泉」「塩化物泉」「炭酸水素塩泉」「硫酸塩泉」「含鉄泉」「酸性泉」「硫黄泉」の7種がある
一つの旅館のような山間の温泉地
熊本空港から車で1時間強、阿蘇・外輪山の北方に位置する黒川温泉を訪れた。泉源が豊富で、一つの温泉地に7種の異なる泉質が存在する全国でも珍しいスポットだ。
せっかくなので、黒川温泉名物の湯めぐりを体験することにした。旅館組合・風の舎で「入湯手形」を買うと、26軒ある旅館のなかから好みの露天風呂を3カ所選んで入浴できる。温泉の効能を見比べて、どの露天風呂にしようかと迷うのが楽しい。旅館に入って入湯手形を見せると、宿泊客でなくてもとても温かく迎えてくれる。
黒川温泉の中心部は、30分もあれば歩いて回れるコンパクトな大きさ。素朴な田舎の風景以外、特別に目を引くものはないが、温泉のはしごをして小路を行ったり来たりするうちに、懐かしい故郷にいるような愛着を感じはじめる。次にまた来たら、「お帰りなさい」と言ってもらえそうなこの雰囲気こそ、黒川温泉の魅力なのかもしれない。
江戸時代から湯治場として知られていた集落に、組合組織として黒川温泉観光旅館協同組合が設立されたのは1961年(昭和36)だった。しかし、黒川温泉が全国区で有名になったのはここ数十年のことで、それ以前は訪れる観光客も少なく、地図に名前すら載っていないような山奥のさびれた温泉地だった。
そんな黒川温泉が変わるきっかけとなったのが、後に観光のカリスマとして名を遺す「山の宿 新明館(しんめいかん)」の後藤哲也さんだ。若いころから独学で観光を学び、「来る人を驚かせる温泉をつくりたい」と自らノミをふるって敷地内の岩山を削り、10年かけて洞窟風呂を完成させた。また、田舎らしい風景にこだわり、宿の周りにわざわざ山の雑木を移植する。周囲の目は冷ややかだったが、この洞窟風呂が口コミで話題となり、新明館は1970年代、閑古鳥の鳴く黒川温泉で唯一、客足の途絶えない宿となった。
1980年代になると、第二世代と呼ばれる青年部の若者たちが、後藤さんのアドバイスのもと、黒川温泉の変革に乗り出す。それぞれの宿が趣向を凝らした露天風呂を新設し、「露天風呂の黒川温泉」を打ち出したが、敷地の制約でどうしても露天風呂がつくれない旅館が2軒あった。そこで、この2軒の宿泊客も露天風呂を楽しめるように「入湯手形」を発案。それが「黒川温泉一(いち)旅館」という地域理念につながっていった。
第二世代がつくった素朴な景観
浴衣を着たカップルや親子づれが、田の原川に架かる丸鈴橋の上で足を止め、景色を楽しんでいる。黒川温泉の街並みは、どこを歩いても緑が多く、まるで山の風景を切り取った絵のようだ。実はこれらの木々はすべて地域の人の手で植栽されたものだと聞いて驚いた。
「今の黒川温泉の世界観は、第二世代の先輩方が苦労してつくり出したものです」と、黒川温泉観光旅館協同組合事務局長の北山元(はじめ)さん。
1986年(昭和61)、第二世代が中心となって旅館組合の組織を再編し、黒川温泉の景観づくりを本格的に開始。上の世代の猛反発を受けながらも、乱立していた派手な看板を撤去して、統一デザインの共同看板を導入。近隣の裏山にある雑木を、あえて不揃いなまま植栽し、あたかもそこに昔から自然に生えていたような木立を形成した。こうして一つひとつ手をかけ、素朴ながら美しい、黒川温泉ならではの景観をつくり上げていったのだ。
秘湯ブームもあり、入湯手形がメディアでもたびたび取り上げられると、「露天風呂の黒川温泉」の名は全国に知れ渡り、多くの観光客が訪れるようになった。ピークの2003年(平成15)には宿泊者数40万人、推定入込客数120万人を記録。入湯手形の販売数も最大で約22万枚となった。
「黒川の旅館組合は、入湯手形の事業収益を柱に運営されています。国や自治体の補助金に頼らず、経済的に自立しているからこそ、主体的に自由な活動ができるのが強みです」と北山さんは言う。
第三世代を突き動かす将来への不安
今、黒川温泉を担っているのは、30代から40代の第三世代。その中心人物の一人である老舗旅館「御客屋(おきゃくや)」代表取締役の北里有紀(きたざと ゆうき)さんは1998年(平成10)、21歳の時に黒川へ戻り家業に入った。同時期に同級生たちが続々と地元に戻ってきて、皆で集まることが増え、青年部の地域活動が活発になっていく。
若い力に期待した第二世代は、早い段階で旅館組合の役職を第三世代の若者たちへ譲り渡す。北里さんは2011年(平成23)に初めて組合の理事の職につき、2015年(平成27)に理事長に選任される。
「このころ、黒川は賑わっているようでしたが、実際には客足にかげりが見えはじめていました。若い仲間たちの『何かやってやろう』という勢いの裏には、黒川温泉はこのままで生き残れるのかという、将来への漠然とした不安がありました」と北里さんは当時の心境を明かす。
特にその危機感を強くしたのが、2016年(平成28)の熊本地震だった。旅館の被害は小さかったものの、道路の寸断や風評被害などもあり、観光客が一時期途絶えてしまった。旅館経営にとっても痛手だったが、組合の理事長だった北里さんは、地域の業者への支払いが激減していることに衝撃を受けた。
「観光業には衣食住のすべてが含まれていて、その先にはさまざまな取引先があります。もし旅館がなくなったら、5年後、10年後にこの地域の人びとの暮らしはどうなるのか。自分たちは地域経済を支えているのだと、責任を痛感しました」
黒川らしさとは変わりつづけること
黒川温泉を次の世代へ引き継いでいくためには、世の中の変化に合わせ、旅館のあり方もまた変えていかなければならない。黒川温泉だからこそ打ち出せる価値とは何か考え、導き出した一つの答えが「食」を軸とした地域の循環システムだ。
「地域の環境や経済のサステナビリティと、食を通じた一人ひとりの健康や幸福。この両者を横断して満足させることができるような循環のしくみを、黒川温泉から発信していきたい」と言う北里さん。
黒川温泉は2030年ビジョンとして、「日本の里山の豊かさが循環する温泉地」を目指すことを宣言した。具体的な取り組みとして、旅館で出る食品残さ(生ごみ)からつくった堆肥で野菜を育て、旅館の料理として提供する「黒川温泉一帯地域コンポストプロジェクト」や、地元産のあか牛を地元で消費することで阿蘇の草原を保全し、地域の畜産と農業の循環を守る「あか牛つぐもプロジェクト」など新しい試みも動きはじめている。
もう一つ、力を入れているのが人材育成だ。黒川温泉の旅館従業員は、20代、30代の若者が多い。
「旅館業は、キャリアパスが描きにくく、残念ながら離職率が高い業種です。とにかく宿にとって一番大切なのは人材です。『地域が人をつくり、人が宿をつくる』という信条のもと、私たちは各旅館任せにするのではなく、地域としてキャリアサポートをしています」と北里さん。
次世代リーダーを育成する「黒川塾」は、各旅館従業員の若手リーダー候補を対象に、地域のことを深く学びながら、仕事のなかで自らありたい姿を見いだすための研修プログラム。今年3年目に入っている。
もちろんうまくいくことばかりではない。例えば、外部の人との関係を拡大したいと考え、地域づくりへの貢献に応じて特典を付与する「第二村民構想」を打ち立てたが、人の思いをルール化するのは難しく、この制度は休止した。
「ほかにも、消えていったプロジェクトはいくつもあります。でも頭で考えてできない理由を並べるより、とにかくやってみて、そこから柔軟に次の方向を見極めるのが、黒川らしいやり方だと思っています」
この北里さんの言葉のように、若い世代が変化を恐れずに挑戦しつづける黒川温泉。観光カリスマ・後藤哲也さんの精神を受け継いだその姿勢に、これからの温泉地の可能性を見た気がした。
(2022年9月4~5日取材)




















