機関誌『水の文化』72号
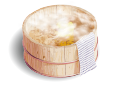
文化をつくる
日本の温泉文化は発展途上
──私たちの欲求が温泉を変える


-
編集部
知っているようで実は知らない
温泉の成分が付着して石化している湯口からとぽとぽと湯が流れ込む。それを横目にわが身を湯船に浸すと、じわっと体に温泉が染み入る――。何とも言えないひと時である。
日本人は温泉が大好きだといわれる。今回の特集では、温泉が人を癒し、惹きつける根源的な力について、温泉に一家言(いっかげん)もつさまざまな分野の方々にお話を聞き、またいくつかの温泉場を巡って考えた。
「ゆったり浸かって『湯治』」では温泉がもつ効能を、「見て歩いて温泉街」では時代の流れと変遷を、「過去に縛られない未来」では有名な温泉地で若い世代が新しい価値をどうつくろうとしているのかに着目した。
その過程で感じたのは、私たちは温泉について実はあまりよく知らないということ。25度以上ならば温泉、25度未満なら冷鉱泉と呼ぶこともそうだし、温泉の成分は未来永劫同じではなく、今は「塩化物泉」だったとしても塩化物イオンの濃度が薄まれば「単純温泉」に切り替わることもある。温泉には水道水と同じように消毒のために塩素や銀イオンを加えているし、湯の花が発生しにくくなる薬剤を入れるケースもある。
温泉地についても同じである。温泉地の在り様は時代とともに大きく変わっているけれど、それはそのときどきの私たち人間の欲求が色濃く反映された結果なのだ。
その一方で、温泉という存在がもつ神秘性や人びとを惹きつける強い磁力は昔から変わらないし、そこには水も深くかかわっていることを改めて知った。
大衆の欲求を受けとめ変わりつづける温泉地
過去に遡ると、温泉地は人びとが病や傷を癒やす湯治場だった。その後の街道整備、鉄道敷設、自家用車の普及で、温泉地は徐々にレジャー的要素を帯びていく。人が押し寄せるので旅館を大型化し、サービスも新たに考えた。すべては、あれがやりたい、これもしたいという人びとの欲望をかなえるためだった。
バブル経済のころ、温泉地では会合と称する宴会が毎晩盛大に開かれた。温泉はもはやそっちのけで、飲めや歌えの大宴会場と化していた。今では考えにくいこの状況は、わずか30年ほど前のこと。団体旅行から個人旅行へと人びとのニーズが変わり、すたれた温泉地はあるけれど、ちゃんと対応した温泉地もある。
時代によって変化を求められても、過去に縛られて新たに挑めないものが多いこの社会で、温泉地はそのつど挑んでかたちを変え、残ってきた。温泉にはそれだけの力があり、また日本人の温泉に対する深い愛情があったからなのかもしれない。
温泉地を成り立たせる「温泉」と「水」
地中から温かい水=温泉が湧き出る。これは人間が窺い知ることができない地球活動によるものであり、だからこそ弘法大師や行基など高僧による開湯伝説という物語が各地に生まれた。燃料が薪や炭しかなく湯を沸かすのが大変だった時代、勝手に湧き出る温泉は貴重だったから地域の財産として大切にされた。
日本は温泉資源に恵まれている。深く掘れば出る、のだ。
1988年(昭和63)から1989年(平成元)にかけて全国3000超の市町村に一律1億円が交付された。これは当時の竹下登内閣による地方創生政策「ふるさと創生事業」で、使い道は自由だったため、温泉掘削に取り組む自治体も多かった。1993年(平成5)に明らかになったのは、1億円を用いて温泉を掘った自治体は252市町村あり、掘削中を除く215市町村が温泉を掘り当てたという事実だ。
ところが、その後のメンテナンス費用が重くのしかかる。平成の大合併後に事業が見直され、閉鎖されたところも多い。特に日帰り入浴のみの温泉にその傾向が強い。付け焼刃では続けられなかったのだろう。
その点、昔からの温泉地は「融通」し合うのでやはり強い。城崎(きのさき)温泉は湧出量に恵まれていないがゆえに、3つの源泉を1カ所に集めて配湯する集中管理方式で運営している。箱根町の塔之澤(とうのさわ)温泉も旅館同士で融通し合って営業していると聞いた。
一方、温泉地は温泉だけでも成り立たない。「水」が大事なのだ。塔之澤温泉「福住楼(ふくずみろう)」五代目の澤村吉之さんが話してくれたように、温泉宿では熱い源泉を適温にするために加える水、そして宿泊客が飲んだり洗面に使う水、さらに調理用の水も必要だ。また、温泉水を調査・研究している人のなかには、温泉の成分もさることながら、温泉に加える水が重要だと主張する人もいる。
温泉と水。この二つがあるからこそ温泉地が成り立っており、しかも温泉の質に水が大きな影響を及ぼす可能性があるという視点は、今回の取材で学んだことの一つだ。
温泉地を支えるさまざまな商い
「湯治場」。この言葉は昭和を生きた人間にとって甘美に響く。古き良き日本をイメージさせるからだ。
ここに2枚の古写真がある。いずれも大正時代から昭和初期のものだ。新潟県の栃尾又(とちおまた)温泉で、江戸時代からの湯治文化を継承する自在館からお借りした。
1枚目は中央に三味線を弾きながら唄をうたっている女性がいて、周りの人はそれを見つめている。三味線を弾いているのは「瞽女(ごぜ)」だそうだ。瞽女とは江戸時代から昭和初期ごろまで三味線を手に、語りものやはやり唄をうたって旅をして歩いた目の不自由な女性たちのこと。新潟県は瞽女の一大拠点だった。
もう1枚は、地べたに並んだ野菜を湯治客が品定めしている様子を写したもの。かつて湯治客は米やみそ、漬物などを持ち込んで、野菜などは露店で買い込んで自炊した。地元の農家にとっては、数少ない現金収入の手段だったに違いない。
このように、温泉場には昔からその地域を支える小さな経済が回っていた。箱根の塔之澤温泉では別の商売で成功した人が温泉宿を始めるケースがあった。黒川温泉の御客屋(おきゃくや)七代目の北里有紀さんは、コロナ禍で客足が途絶えたとき、宿に出入りする地域の業者への支払う金額が一桁減っているのを見て「自分たちは地域経済を支えていたのだ」と責任の重さに愕然としたと話していた。
城崎温泉で旅館の浴衣を着て共同湯(外湯)に浸かり、ほてった体を冷ましながら商店街をぶらぶら歩き、昼はソフトクリームを、夜は地ビールを買い求め、大谿川(おおたにがわ)のほとりのベンチで味わったのは至福の時間だった。それも温泉宿が自分たちだけで客を囲い込まないように内湯を小さく小さくつくり、できるだけ外湯を使うようにそっと促しているからだ。
自分だけ栄えても仕方がない。その精神は、生き馬の目を抜くような今の社会のなかでとても大きな意味をもつのではないか。
温泉がもつ類まれなる力
さてこれからである。湯治場が短期の観光温泉地となり、旅館が大型化して内湯が増え、人びとが外に繰り出さなくなり、周辺の飲食店が地盤沈下した結果、温泉街としての魅力が損なわれる……。その悪循環がようやく断ち切れそうな気配がする。
温泉地が大衆の欲求によって形を変えてくれるのならば、私たちがこれから温泉と温泉地をどう考え、何を望むかが重要になるだろう。
近年、温泉に関しては「源泉かけ流し」がキーワードとなっている。ついつい「ここの温泉、源泉かけ流しなんだって!」と喜んでしまうが、温泉を地域の資源と考えた場合、果たしてそれはよいことなのだろうかと考え込んでしまう。
地球上のあらゆる資源は有限であることを突きつけられている現代、温泉もまた有限であることを忘れてはいけないと思う。実際に泉質が変わってしまって「温泉」の看板を下ろさなければいけなくなった温泉宿もあるし、ある日突然温泉が枯れたケースもあるのだから、過度に使わないように、やたらと掘らないようにしないといけないだろう。
古くから保養や療養に用いられてきた温泉の価値は、現代でも変わらない。温泉のもつ成分や入浴による温熱作用、周辺の自然や環境などが総合的にはたらき、療養効果があることは単なる迷信ではなく、公にも認められていることだ。
人びとを惹きつける力をもった温泉は、地球がもたらす奇跡ともいえる存在なのである。
この国の温泉文化はまだ発展途上
そんな堅苦しいことを抜きにしても、温泉は楽しい。都市近郊に増えている温泉センターも捨てがたい。近所に手足を伸ばしてのびのび入れる温泉があるのは幸せだ。しかし、温泉には転地療養という効果もあるようだから、できれば遠出してみよう。酸ヶ湯温泉のように周辺の山を登ってもいいし、渓流釣りなど趣味を楽しんでもいい。そしてその土地の温泉に浸かる。その間、スマートフォンやパソコンをできるだけ触らないようにすれば、まさに極上のデジタルデトックスだ。
人の少ない温泉地に一人で行く「ソロ温泉」も興味深い。温泉にそっと浸かって自分と向き合うのは、ストレスフルな現代における湯治といえる。人と話したくなったら、湯船で一緒になった人に声をかければいい。地元の人であれば「いいお湯ですね」と泉質にふれてみる。旅人っぽい雰囲気だったら「山登りですか?」とか「どちらから?」だけでいい。話が弾めば楽しいし、弾まなくてもひと時のことだからさほど気にならないだろう。温泉地では他人に深入りしない、少しドライなくらいの関係がちょうどいい。
もともと温泉にはさまざまな楽しみがあったはず。それがここ数十年で「稼ぐ」ために特化したことで、温泉のもつ本来の楽しみを狭めてしまった面があるのかもしれない。かつて文豪が温泉宿に逗留して作品を書いたのは、現代のワーケーションに近い行為だ。
これからの温泉、そして温泉地はさらに多様化するのではないか。集客力に優れた大型ホテルがひしめく温泉地もあれば、泉質を大事にした小さな宿が数軒集まるだけの温泉地もいい。オーベルジュのような料理をセールスポイントにした一軒家的な温泉宿も注目されつつあり、すべての部屋に内湯があるホテルもある。インバウンドに特化した温泉地だってあり得るだろう。外国人観光客は長期滞在が基本なので徐々に日本食に飽き、夕食は外で済ませる傾向が強いと取材で聞いた。とすれば地域全体で取り組めば新たな商機がある。温泉地が「十湯十色」の様相を呈する。そんな未来を夢描く。
地下で起きた現象から湧き出る温泉に浸かり、湯気と熱い湯に愉悦を感じながら、自分は温泉に何を求めているのか、どんな温泉地だったらまた来ようと思うのか、海外から来た人は温泉のどんな点に興味をもつのか――思いを巡らせたい。
日本の温泉文化はまだまだ発展途上。「これから」をつくるのは、今を生きる私たちだ。








