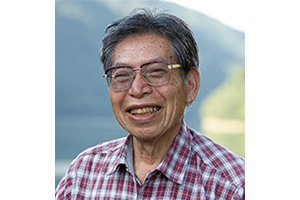機関誌『水の文化』73号

【詠む】
気づきを重ね、丁寧に生きる
──俳句と水と我が暮らし
「五七五」という十七音だけで個人がささやかな情感を詠(よ)む俳句。日本独特の短詩だが、身近なようで実は知らないことも多いのではないか。学生たちにアニメやポップスを用いて「俳句学」を講義する新鋭の俳句研究者、青木亮人(まこと)さんに、俳句の歴史やその魅力、水との関係性などを聞いた。
-

-
インタビュー
愛媛大学教育学部 准教授
青木 亮人(あおき まこと)さん -
1974年北海道小樽市生まれ。同志社大学文学部文化学科国文学専攻卒業、同大学院修了。博士(国文学)。専門は近現代俳句。『NHK出版 学びのきほん―教養としての俳句』『その眼、俳人につき』『近代俳句の諸相』など著書多数。2023年1月、『愛媛 文学の面影』三部作が第38回愛媛出版文化賞部門賞を受賞。
芭蕉や子規によって一変した価値観
俳句の源は鎌倉時代に流行した「連歌(れんが)」です。連歌は五七五七七のリズムで和歌を詠んでいた貴族たちのプライベートでの遊びから生まれたと言われています。Aさんが五七五を詠んだらBさんが七七を詠むという漫才の掛け合いのように、お酒を飲みながら楽しんでいた。それがAさん、Bさんの後にCさんが五七五を詠んで、Dさんが七七でこたえる……その繰り返しが連歌と呼ばれるようになりました。室町時代には連歌も貴族が公の場で詠むべき詩歌(しいか)と位置づけられ、戦国武将も連歌を詠むようになったのです。
ところが、そのうち「こうあるべき」と硬直化してしまったため連歌は魅力を失っていきます。江戸時代に連歌は定着したものの、独創的な作品は生まれにくい状況でした。代わって台頭したのが、「俳諧(はいかい)」です。連歌が身分の高い人のたしなみとなる一方、庶民は笑いや下ネタなど俗な事柄を詠って楽しむようになります。それを連歌と区別するために俳諧連歌と呼んでいたのが、略して俳諧と言われるようになりました。
俳諧を楽しんでいた層から登場したのが松尾芭蕉です。芭蕉は見事な俳諧作品を数多く生み出すと同時に、「五月雨を集めて早し最上川」など五七五で完結する「発句(ほっく)」を個人制作として詠んでいます。芭蕉以降の俳諧は和歌や連歌を超えて江戸期の庶民が親しむ詩歌となり、「俳聖」と呼ばれた芭蕉を尊敬する歌人として与謝蕪村や小林一茶などが生まれます。
実は、俳諧も連歌と同じように型にはまっていくのです。芭蕉を尊ぶあまりに斬新な作品が生まれにくく、個人の発句よりも集団で制作する俳諧の方が重んじられていた。明治時代になり正岡子規が彗星のように現れ、「個人が詠む五七五で完結する発句こそ文学である」と主張し、発句を「俳句」と称するようになりました。
子規が登場することで今でいう俳句、五七五の十七音で完結する詩歌が成立します。子規は、明治期に渡来した西洋流の芸術観で俳諧をとらえ直し、「私」という個人の実感を詠う俳句こそ文学と考えたのです。
俳句を詠むと高まる暮らしの「解像度」
俳句の魅力をひと言で表すならば「短いこと」。俳句は、五七五の十七音に、春夏秋冬を感じさせる季語を入れると体裁は整う。季節感と自分の周りの出来事を詠むと作品になるので、他の芸術と比べて達成感が早く得られます。
ただし、いざ詠もうとすると使える文字数が少なすぎて、思ったことがうまく表現できない。そういう難しさも抱えています。
また、俳句には季語のない無季(むき)俳句もありますが、基本的に季語を入れることを推奨していますので、「自分にとって春とはどういう季節なのか」と季節感をあらためて考えるきっかけになります。
春の代表的な花は桜ですが、「梅の後は桜」ではなく、梅の後には桃があり、さらに雪柳、連翹(れんぎょう)、木蓮(もくれん)などがあり、それらが少しずつ重なりながら咲く。雨も同様で、春雨があり、夏に突然降るのは夕立で、秋の霧雨や冬の時雨(しぐれ)もあるわけです。季節の移ろいも夏から急に秋になるのではなく、夏の残暑を感じさせる秋があれば、冬が間近に迫った秋もあります。
いざ季語を使おうとすると、草花や食べものや行事といったふだんは見過ごしていたことへの認識が求められることに気づきます。季節に限らず、いつも歩いている道、庭に咲いている花、空を飛ぶ鳥、あるいはよくすれ違う近所の人、職場の仲間たちなど自分の生活にかかわるすべてのことに対する認識がこまやかになる、つまり暮らしにかかわる「解像度」が高まるのではないかと思います。俳句を通じて認識が豊かになり、感覚も磨かれていく。それもまた俳句の大きな魅力です。
ふと立ち止まって自分を知るきっかけに
「水」は日本人の生活すべてにかかわるものですので、俳句でも広く詠まれています。大きく分けると二つあって、一つが「季節感を伴って詠まれる水」。春の水、秋の水というように四季の移ろいとして詠まれることが多いと思います。
もう一つは「生活にかかわる水」。水を使うことが多い料理や間接的に水がかかわる田んぼなども詠まれます。日本は川が多く海に囲まれていますし、北国なら雪も水にかかわります。雪解(ゆきどけ)は春の季語で、雪解け水が集まって流れる様を雪解川(ゆきげがわ)と表現したりします。
四季でもっとも水を欲する季節は夏なので、夏の季語には水にまつわるものが多いです。ここで水にちなんだ句を二つ紹介します。
水澄むやとんぼうの影ゆくばかり
星野立子
「水澄む」は秋の季語です。夏は水が濁りがちですが、気温が下がると水も澄む。そこに秋の気配を感じるんですね。澄んだ水の上を飛ぶ複数のトンボをじっと見ている。そういう情景が目に浮かびます。
水筒に清水しづかに入りのぼる
篠原 梵
水筒に湧水を汲んでいて、水が増えてくる様子を入りのぼると表現している。夏の水の冷たさ、きらきらとした夏の光の眩しさが感じられます。作者の子どものような眼差しも窺えます。
いずれの句も劇的な瞬間があるわけではなく、ほんとうに何気ない瞬間を詠んでいます。俳句とは、人生の意義を鮮やかに照らすというよりも、ごく平凡な風景のなかに佇む自分を知るきっかけになるものかもしれません。
俳句を通じて関心を抱くのは川なのか空なのか木々なのかといった、いつもは意識しない自身の感性に気づく瞬間があるはずです。その気づきの積み重ねによって、何に対しても丁寧に、見て接して感じて言葉を遣い、日々生きるようになるのではないでしょうか。俳句とはそういうものだと私は考えています。
(2023年1月21日/リモートインタビュー)