機関誌『水の文化』73号
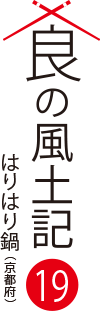
京水菜でいただく はりはり鍋
水と風土が織りなす食文化の今を訪ねる「食の風土記」。今回は、京野菜の「水菜」を用いた関西の冬の風物詩「はりはり鍋」です。

京都原産の伝統野菜・京水菜を用いた「はりはり鍋」
地下水で育まれた京都原産の「京水菜」
寒さに強く、冬に収穫時期を迎える水菜。今でこそ全国のスーパーマーケットに並んでいるが、原産は京都で、冬の到来を告げる京野菜として「京水菜」と呼ばれ親しまれてきた。京菜(きょうな)とも呼ばれる。京野菜の記録は、古いもので16世紀(室町後期~安土桃山時代)にまで遡る。
「生育に十分な水を必要とする水菜が京都で栽培されるようになったのは、豊かな水のおかげです」
そう教えてくれたのは、京都府立大学 京都和食文化研究センターの佐藤洋一郎さん。桂川や鴨川など大きな川が何本か流れる京都は、北の方で降る雨や雪の影響で、地下には琵琶湖の8割に匹敵するほどの水が溜まっているといわれる。地下水が豊富なのである。
特に東側は砂礫(されき)質。浅い地層から良質の水が得られるため、今もまちの至るところに井戸がある。そのため京水菜や賀茂なす、九条ねぎといった京野菜の栽培、豆腐の製造など、水の恩恵を受けた産業や文化が古くから発達した。
庶民に親しまれる「はりはり鍋」
旬の京水菜を楽しむ名物料理が「はりはり鍋」だ。材料は基本的に肉、京水菜、和風だし汁の3つ。はりはり鍋は大阪のある飲食店が考案したとされる。名の由来は、水菜のシャキシャキとした触感を「ハリハリ」と表現したこと。かつてはくじら肉を入れていたが、今は豚肉など他の肉を使うことも増えている。佐藤さんは、はりはり鍋が京都で食されるようになったのは半世紀ほど前ではないかと推測する。
「私は幼少期を大阪で過ごしましたが、家ですき焼きといえばはりはり鍋で、当時は〈くじらのすき焼き〉と呼んでいました。水菜もくじら肉も安かったので、経済的だったのでしょう。今ははりはり鍋というと高級なイメージもありますが、昔は庶民の食べものでした」と佐藤さんは言う。
京水菜を用いたはりはり鍋を提供する「おばんざい 和さび」を訪ねた。和さびのはりはり鍋は、だし汁に京水菜や油揚げ、豆腐などを入れて味わう。水菜本来のシャキッとした食感をそのまま楽しむなら、だし汁にサッとくぐらせるくらいがベストだそうだ。
「はりはり鍋はお酒を飲んだ後のシメの一品として人気です。年配の人には馴染み深い料理ですが、今の若い人は知らない人も多いんです。むしろ京都以外に住む人たちの方がよく知っています」と、店主の寺井友一さんは話す。
伝統野菜を味わって未来につなぐ食文化
ビタミンやミネラル、食物繊維も豊富な京水菜は、栽培技術が発達する前は冬場の貴重な青物野菜だった。今はサラダで味わうことも多いが、本来は煮たり炊いたりして食べるものだと佐藤さんは言う。そういった意味でもはりはり鍋は、京水菜を味わうにはおすすめの料理だそうだ。
「京水菜をはじめとする日本各地に残る伝統的な野菜を食すことは、日本古来の食文化を守ることにつながります。現代の人びとは伝統野菜をあまり食べなくなっていますが、ぜひ京水菜以外の京野菜もいろいろなレシピで試してみてください。そして、それぞれの家庭で自分たちの味を見つけて、次世代につないでいく。それが、ひいては大きな課題になっている日本の食糧自給率を高めることにもつながるのです」
京水菜という伝統野菜を用いたはりはり鍋を通じて、これからの食のあり方も改めて考えたい。
はりはり鍋の下ごしらえ
取材協力:おばんざい 和さび
京都市北区紫野宮東町10-3 ルモン紫野
Tel.075-441-8388 営業時間17時~22時(月曜定休)
(2023年1月13日取材)






![[1]水菜をきれいに洗ったら、4〜5cm幅の食べやすい大きさに切る。1人分の目安は約2株](../../img/kikanshi/no73/13/img06.jpg)
![[2]油揚げはほどよく焦げ目がつくくらいにバーナーで炙ることで、香ばしさとうま味が出る。炙ったら幅2cmほどに切る。1人分の目安は1枚](../../img/kikanshi/no73/13/img07.jpg)
![[3]豆腐を切る。1人分の目安は1/4丁](../../img/kikanshi/no73/13/img08.jpg)
![[4]好みで鶏肉や豚肉などの肉、香りづけにゆずの皮などを盛りつけて完成(写真は約3人分)。家庭で楽しむ場合、だしは市販の和風だしを準備すればOK](../../img/kikanshi/no73/13/img09.jpg)



