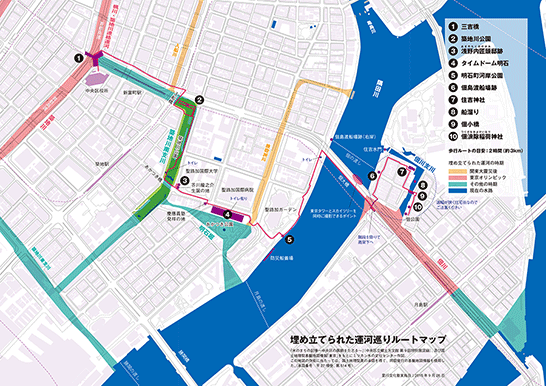自分でも開催!
自分でも開催! 里川文化塾 新富町から佃島の埋め立てられた運河を巡る
〈水の都〉と呼ばれた江戸・東京。網の目のように運河や水路が張り巡らされ、物資の輸送に水運が使われていましたが、陸上交通の発達に伴い、しだいに姿を消していきました。しかし、都道や首都高になってもかつての運河の姿がわかる「三吉橋」からの眺め、川床を活用して公園となった「築地川公園」など、今でも運河の跡をたどることができます。また、「住吉神社」の裏手には、現在も部分的に江戸時代から続く運河が残る佃川支川があり、埋め立てられずに残っている運河を見ることができます。さらに、明石町一帯は多くの史跡が残り、江戸時代から連綿と続く〈水の記憶〉だけでなく、水辺とともに生きたかつての人々の暮らしぶりまで思いめぐらすことができるプログラムです。
里川文化塾開催当日のレポートはこちら
第20回里川文化塾 埋め立てられた運河から水の記憶をだどる
実施概要
- フィールド
- 東京都中央区
- ルート
- 三吉橋〜中央区内のフィールドワーク〜佃公園
- 歩行目安
- 2時間(約3km)
- 最寄り駅
-
【出発地点】三吉橋
新富町駅(東京メトロ有楽町線)から 徒歩1分
築地駅(東京メトロ日比谷線)から 徒歩5分
【終着地点】佃公園
月島駅(東京メトロ有楽町線)まで 徒歩5分
センターからのアドバイス
- 中央区にはたくさんの文化財や碑が残っています。ゆっくり探索すれば新鮮な驚きや楽しい発見があるかもしれません。
- タイムドーム明石では中央区の歴史や文化の展示もご覧いただけます。(有料)
- 佃地区は住宅密集地を歩く場所が多いので、周囲に配慮して歩きましょう。
- 個人宅の撮影はご遠慮ください。
- 歩きやすい服装および履きなれた靴(スニーカー、ジョギングシューズ、トレッキングシューズなど)で回られることをお勧めします。
関連情報
URL
開催レポート「第20回里川文化塾 埋め立てられた運河から水の記憶をだどる」
http://www.mizu.gr.jp/bunkajuku/houkoku/020_20150926_mizunokioku.html
「川がない橋が秘めた東京の履歴」(機関誌『水の文化』47号)
http://www.mizu.gr.jp/kikanshi/no47.html#08
「商人の港、日本橋界隈」(機関誌『水の文化』25号)
http://www.mizu.gr.jp/kikanshi/no25.html#03
タイムドーム明石(中央区立郷土天文館)
"http://www.city.chuo.lg.jp/bunka/timedomeakashi/