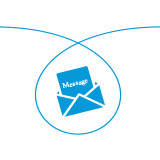里川文化塾
第1回里川文化塾 府中用水ワークショップ

里山や里海だけではなく、暮らしとかかわるすべての水循環の経路を私たちのセンターでは「里川」と呼んでいます。いろいろな里川を発見しその価値を身近に感じたい! ということで、第1回の里川文化塾に選んだフィールドは府中用水(東京都)です。
開催概要
- 日時
- 2011年9月11日(日) 10:00〜16:30
- 会場
- 府中用水・くにたち郷土文化館
- 主催
- ミツカン水の文化センター
- 共催
-
くにたち郷土文化館
http://www.kuzaidan.com/province/
- 参加者数
- 19名
-

-
講師
くにたち郷土文化館学芸員
齊藤 友里加 さいとう ゆりか -
プログラム
府中用水と生き物と農業の関係
知ってましたか?
府中用水を歩いてみる
印象に残ったことを
地図に書き込んでみた
再度、府中用水へ
最後に意見交換
江戸時代からの旧家をリフォームしたコミュニティスペース「やぼろじ」で意見交換。地図に観察内容や意見を記入し、「100年後の府中用水」について意見交換を行ないました。
「このままの姿で残ってほしい」というのが、参加者全員の意見。
しかし、一方では、「農業者が減って維持が不可能になるのでは?」、「企業が進出した土地では、用水が暗渠化している」「用水の用途を変えるのは簡単ではない」など、いくつもの意見が出されました。
府中用水を"使う"ことが、結果として府中用水を"守る"ことにつながるわけですが、立場によって異なる考えを、いかに調整していったらいいかという課題が残ります。里川の可能性とともに、実現への課題を実感する学びのときとなりました。
資料
-
- どっこい用水は生きている ~都市農業と生き物たち~ (くにたち郷土文化館 企画展冊子)
-
- 里山だいすきガイドブック (くにたち郷土文化館 ミュージアムグッズ)