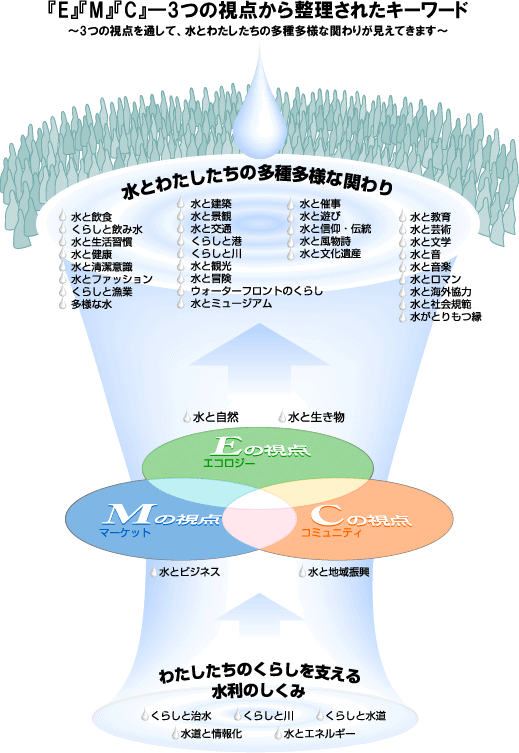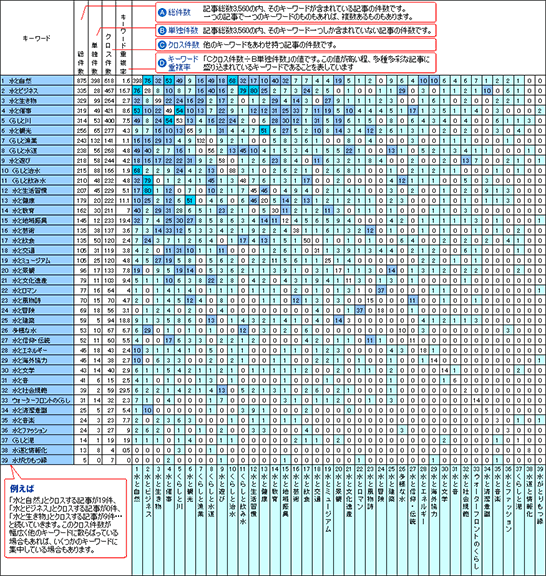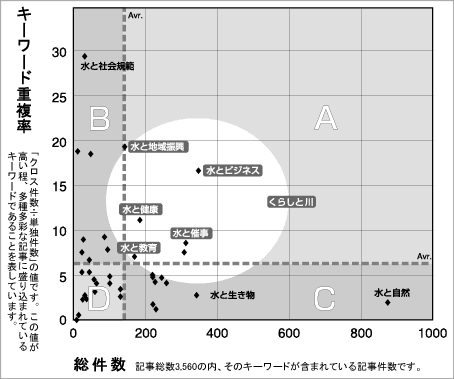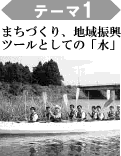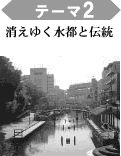機関誌『水の文化』4号
くらしと水の多様な関係
-
編集部
ミツカン水の文化センターは「水の文化」に関わる多面的な研究活動を行い、その成果を広く公開し、活動を展開することで、水に関する意識の向上を図ると共に、新しい“人と水とのつきあい方”の提案を通して、人々の豊かなくらしの創造に貢献していくことを目的に、1999年1月に設立されました。
昨年は、富山和子氏(立正大学教授・日本福祉大学客員教授)と共に「水の文化とは何か」を問う研究取材を連続実施し、既に「ため池文化(香川)融通の智恵」「日本の浦島、中国の浦島(丹後半島)」「有明海とアオ(淡水)の世界(佐賀)」を公開して、各地域の水の文化に関わる興味深い歴史、事実、智恵、考え方、などを紹介して参りました。
さらに、陣内秀信氏(法政大学教授)とは「舟運から都市の水の文化を探る」をテーマに、日本および海外各地域でのフィールドワークを展開中です。こちらは、郷土史、建築史、物流史、都市史、河川史、などの領域を越え、「水の文化」をキーワードとした都市の特性を描き出し、さらに新たな提案を行おうとするものです。
そして今回の特集は、当センターとして実施した「くらしと水の多様な関係」調査結果の一端です。
わたしたちのねらいは、日本各地での生活における“人と水とのつきあい方”に関する“知恵”を調べ、公開し、共有していくことで、皆様のくらしのお役に立てていただくことにあります。そのために、現在、何が議論され、何が注目され、何が求められているのかを体系的に整理していくことが必要だと考えました。とくに今回は“生活者の身近なくらし”を通して、昨今の「水」に関わるさまざまな話題が新聞記事上でどのように扱われ、どのようなテーマに基づいて紹介されているのか体系的に整理しました。さらにその上で、どのような活動が成されてきたのか、いろいろな事例を紹介したいと思います。
水とつきあっていくための「レシピ集」として、本特集におつきあい下さい
調査の方法とキーワード一覧
■過去5年間の新聞記事の傾向をデータベース化
1995年12月〜1999年4月までの主要新聞(朝日、毎日、読売、日経、日経産業の各紙)から、「水に関わる記事」を抽出しました。記事は全部で7,644件。その中から、“身近な水とくらし”に関わる記事のみを選り分け、3,560件(記事総数)に集約しました。次に、それらの記事にキーワードをつけ、分類しデータベース化しました。そしてこのキーワード毎におおよその傾向を読みとり、いくつかのトピックスをご紹介しようというのが、今回の調査です。
■主要テーマは“身近な水とくらし”
今回は、“身近な水とくらし”にスポットを当ててみました。水に関わる記事は数え切れないほどあります。しかし、水とのつきあいは、人・場所・目的などでそれぞれ異なります。個人・集団でも、もちろん異なります。水とのつきあいとは、結局、水が様々な局面で果たしている、人々にとっての役割ともいえるでしょう。
「水」についての大きな問題−誰にとっても重要な問題は、連日紙面を賑わせます。ダイオキシンや環境ホルモン、酸性雨…。河口堰や干拓地埋め立てなどの公共事業…。こうした“当然考えねばならない問題”の一方で、個々人やある集団などにとって“水の役割”が、どのように広がっているのかを明らかにしたい。この点を重視して記事を選んでみました。主要新聞から選んでいますので、主に都市部の人々に軸足を置いて、くらしにとっての身近な水の役割を描く結果となっています。
■分類のためのキーワード
下の表は、記事の分類に使用したキーワードの一覧表です。ある1ヶ月間をサンプルにとり、おおよその作業用の分類キーワードを設定して、それに、修正を加えていきました。
このキーワードは、「図書館十進分類法」のように、整然と階層的に整理されているわけではありません。むしろ、いろいろなキーワードの“重なり”が出やすいように設定したものです。このキーワードの重なり具合全体を見ると、新聞報道におけるキーワードのもつ意味の重層性や、キーワード同士のつながりが浮かび上がってきます。
キーワード一覧
| キーワード(五十音順) | 記事の掲載内容例 |
|---|---|
| ウォーターフロントのくらし | 臨海都市、海岸 |
| くらしと川 | 川、流域 |
| くらしと漁業 | 漁業、養殖、漁村保全、漁師 |
| くらしと水道 | 上下水道、井戸、水源涵養林、雨水利用 |
| くらしと治水 | ダム、堰、河川修復 |
| くらしと飲み水 | 浄水器、水質浄化、魔法瓶、雨水利用、ミネラルウォーター |
| くらしと港 | 港町、ヒットソング |
| 多様な水 | 深層水、イオン水、水の栄養 |
| 水がとりもつ縁 | 漂流物、雪などを通しての交流 |
| 水と遊び | 釣り、ヨット・カヌー等、海水浴、潮干狩り、スポーツ、テーマパーク、水遊び |
| 水とエネルギー | 発電、節電 |
| 水と生き物 | 魚、昆虫など水と生き物、水と生き物によるまちづくり |
| 水と飲食 | 酢、酒、寿司、茶、ミネラルウォーター |
| 水と音 | 水琴窟、漏水、鳴き砂 |
| 水と音楽 | ヒットソング、音楽 |
| 水と海外協力 | 水質浄化・淡水化等産業協力、NPOなど多様な団体の海外協力 |
| 水と観光 | 流氷、潮干狩り、温泉、川床、クルーズ、水晶の洞窟、氷筍、雪の大谷 |
| 水と教育 | 自然の教育力、環境教育、資格(ビオトープ管理士、気象予報士)、マナー教育 |
| 水と景観 | 親水空間、景観、公園、景勝地、噴水 |
| 水と芸術 | 絵画、写真、水中写真、演劇、彫刻、オブジェ、染め物 |
| 水と健康 | 温泉、治療、癒し、プール、スポーツ |
| 水と建築 | 庭園、都市空間、噴水、雨水利用、実験住宅、橋 |
| 水と交通 | くらしと舟運、河川舟運、災害時の代替輸送、船、運河、航路 |
| 水と催事 | イベント、シンポジウム、祭礼、スポーツイベント、懸賞催事 |
| 水と社会規範 | マナー、慣行、法律 |
| 水と自然 | 環境保護一般、森林保全 |
| 水と信仰・伝統 | 宗教行事、祭礼、婚礼、沐浴 |
| 水道と情報化 | 下水道管の利用、2000年問題 |
| 水と生活習慣 | 入浴、トイレ、洗濯、銭湯 |
| 水と清潔意識 | トイレ(蛇口、洗浄便座) |
| 水と地域振興 | 水を利用した地域おこし、まちづくり |
| 水とビジネス | 商品、開発、サービス業(銭湯など) |
| 水と風物詩 | 灯篭流し、笹舟、祭、川床、ひな流し、山開き、漁解禁 |
| 水と文化遺産 | 建築遺産、遺構、史料、無形文化財、自然遺産 |
| 水と文学 | 文学、俳句、川柳、活字資料 |
| 水とファッション | 容器のデザイン(飲料水、酒)、つけ涙、化粧 |
| 水と冒険 | 雪原、カヌー、ヨット、丸木船、水泳、海底調査 |
| 水とミュージアム | 水族館、様々な水を題材にした博物館 |
| 水とロマン | 探検、文学、旅行、漂流物 |
整理のための3つの視点
■Ecology・Market・Community−「水」は三つの視点からとらえられている
新聞記事とキーワードを眺めてみると、記事の書き手・読み手はおおよそ三つの視点から情報を解釈していることがわかります。第一は、生態学的(Ecology)な視点から水を見る見方です。人を含めたすべての動植物の生態上のバランスを重視し、生物多様性を損なわない環境を第一に考える視点です。本特集では“『E』の視点”と呼びます。第二は、ビジネス機会として水を捉える見方です。生産者としての利益追求、消費者としての満足感充足を第一に考える立場です。この見方を市場(Market)からの立場として“『M』の視点”と呼びます。そして、第三は、地域にとって水が果たす役割を重視する見方です。地域全体の福利等を第一に考える視点です。これをコミュニティ(Community)重視の立場として“『C』の視点”と呼びます。新聞記事は“くらしを支える水利のしくみ”を前提に置きながら、これら三つの視点をミックスさせながら書かれ、読まれているようです。
例えば、次の記事はどうでしょうか。
「水環境関心あるが‥‥」 87%合成洗剤使う/都民アンケート
川や海は汚したくないが、便利な合成洗剤はやめられない?−「水環境と消費生活」をテーマにした東京都消費者生活センターの都民アンケートで、こんな消費者像が明らかになった。東京の川や海の水質について、九割以上の人が「大変関心がある」「少しは関心がある」と答えた。半面、ほとんどの人が、天然の石けんに比べて分解が遅い合成洗剤を使っていると回答。理由(複数回答)はいずれも「使いやすい」が八割弱。(96/9/28日経)
新聞記事検索でわかる傾向
〜過去5年間の新聞記事から〜
記事の内容から、それぞれ記事ごとにキーワードをつけました。一つの記事で一つのキーワードのものもあれば、三つも四つもキーワードがつけられた記事もあります。下表は各キーワードにあてはまる記事の件数を表した、クロス集計表です
 「水と自然」というキーワードを例にとると「総件数875」とあります。この「総件数」は、記事総数3,560件の内、「水と自然」というキーワードが含まれている記事が875件あったことを示しています。この875件の中には「水と自然」というキーワード一つしかつけられていない場合もあれば、それ以外のキーワードもつけられている場合もあります。各キーワードは、総件数の多い順に上から下に並べられています。
「水と自然」というキーワードを例にとると「総件数875」とあります。この「総件数」は、記事総数3,560件の内、「水と自然」というキーワードが含まれている記事が875件あったことを示しています。この875件の中には「水と自然」というキーワード一つしかつけられていない場合もあれば、それ以外のキーワードもつけられている場合もあります。各キーワードは、総件数の多い順に上から下に並べられています。
 「単独件数」は、「水と自然」というキーワードのみに分類された記事の件数です。
「単独件数」は、「水と自然」というキーワードのみに分類された記事の件数です。
 「クロス件数」は、一つの記事の中で他のキーワードをあわせ持つ記事の件数です。各キーワードの行の件数の合計から単独件数を引いたものです。
「クロス件数」は、一つの記事の中で他のキーワードをあわせ持つ記事の件数です。各キーワードの行の件数の合計から単独件数を引いたものです。
 「キーワード重複率」は、「クロス件数÷単独件数」です。率が高い程、いろいろな記事に盛り込まれているキーワードであることを表しています。
「キーワード重複率」は、「クロス件数÷単独件数」です。率が高い程、いろいろな記事に盛り込まれているキーワードであることを表しています。
例えば、縦軸No.10の「くらしと治水」と横軸No.20の「水と景観」、両方のキーワードをあわせ持った記事は6件あったということになります
キーワードの重なりを示す クロス集計表(対象行列)
調査結果概要
クロス集計表から、いろいろなことが分かります。
■「水と自然」が圧倒的
単独件数・クロス件数共に群を抜いた高さです。それだけ環境問題に対する、一般的な意識が定着してきている証拠といえるでしょう。と同時に、他のキーワードと重なりながら、様々なエコロジカルな意味を派生させているようです。
■「水とビジネス」の意外な件数の多さ
「水と自然」「水と生き物」といった内容の記事とともに、「水とビジネス」に関する記事が第二位となっています。中でも「くらしと飲み水」 「水と生活習慣」とのクロス数が高くなっています。水に対する様々なリスク意識(防災、健康、環境…)がビジネスチャンスを生み、それに対する商品・サービス開発がニュースとなっているようです。
■「水」は地域づくり・まちづくりの貴重なツール
「水と自然」「水と地域振興」など、水が地域づくりやまちづくりの上で、様々なツールとして人々を結びつける役割を果たしていることがわかります。水に関係する催事、遊び、環境教育などの記事を追うと、さらにそれがよく分かります。
■キーワード重複率と総件数でグラフをつくる
下のグラフは、縦軸がキーワード重複率、横軸が総件数を表しています。そして、それぞれの平均値から点線を引き、グラフをABCDの四つのブロックに分けたものです。
- Aブロック:総件数、キーワード重複率共に高い→そのキーワードに当てはまる記事件数が多く、多くの記事にそのキーワ−ドが盛り込まれている。
- Bブロック:総件数は低いがキーワード重複率が高い→当てはまる記事件数は少ないが、そのキーワードはいろいろな記事に盛り込まれている。
- Cブロック:総件数は高いが、キーワード重複率が低い→当てはまる記事の件数は多いが、それ単独で使われる場合が多い。
- Dブロック:総件数、キーワード重複率共に低い→当てはまる記事の件数が少なく、他のキーワードとの結びつきもあまりない。
■浮かび上がる6つのキーワード
上のグラフを見ると、たとえば「水と自然」というキーワードは圧倒的に総件数が多いのですが、キーワード重複率はそれほど大きくないためCブロックに位置しています。総件数が多ければキーワード重複率がある程度低くなるのはやむをえませんが、やはり他のキーワードとあまり結びつかずに単独で、多数の記事が書かれていることをうかがわせます。
一方、「水と社会規範」というキーワードはBブロックに位置しています。キーワード重複率が高く、様々なキーワードと結びつきながら多種多彩な記事があるのですが、その件数は少ないのです。
そこで、記事の件数が多く、しかも様々な記事に盛り込まれているキーワード。ここに注目することができるでしょう。Aブロックに位置する6つのキーワード―「水とビジネス」「水と催事」「くらしと川」「水と健康」「水と教育」「水と地域振興」―です。これらのキーワードは多層的な意味をもち、社会からも注目されているといえそうです。
■6つのテーマに注目!
「水とビジネス」「水と催事」「くらしと川」「水と健康」「水と教育」「水と地域振興」の記事全体を眺めてみると、それぞれよく取り上げられるテーマがあることがわかります。
例えば、「水とビジネス」や「水と健康」では、飲料水に関するビジネスの記事が目立ちます。また、「水と催事」「くらしと川」「水と教育」「水と地域振興」等では、水を活用した様々な地域振興の取り組みや、環境教育、水に関するレジャーに関する記事が目をひきます。
一方、これらキーワードの周辺にも、失われていく“水に関する伝統”を現在に甦らせたり受け継いだりすることで、まちづくりに活かしていくという「水都の過去」に関する記事や、下水道や河川を新時代の都市基盤として活用しようという、「都市の未来」をうかがわせる記事も注目されました。
そこで今回は、左記の六つのテーマを選んで、関係者のインタビューや過去の記事の趨勢を集めてみました。