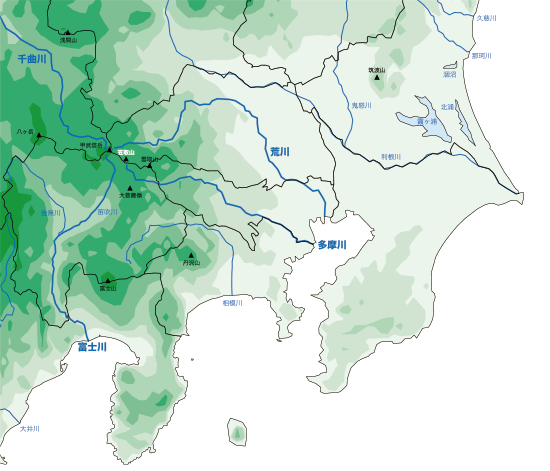機関誌『水の文化』18号
水源涵養と林業経営をめぐる森林思想史 溜める水と使う水
-

-
日本獣医畜産大学非常勤講師
泉 桂子 (いずみ けいこ)さん -
1996年東京大学農学部卒業。 2001年東京大学大学院農学生命科学研究科博士課程修了。 著書に『近代水源林の誕生とその軌跡−森林と都市の環境史−』(東京大学出版会、2004)がある。
水源林研究に入ったきっかけ
水源林というのは、森林の持つ「水源涵養機能」を人間が積極的に利用して、適正な河川流量及び水質を得ることを目的として維持されている森林です。「水源涵養機能」は、洪水緩和機能、渇水緩和機能、水質浄化機能の3つのサブ機能に分けて論じられるのが一般的です。
現在、水源林そのものに対する関心は高まっていますが、いったい水源林というものが歴史的にどのようにして生まれ、管理されてきたのかということを、きちんと調べて議論の土台をつくりたいと思ったのが、東京や山梨の水源林を調べようと思いたったきっかけです。
実家が山梨県の兼業農家で、母が農作物を相手に働く姿を見て育ちました。生態系のベースには植物があって、人間は自然の構成要因の一つにしか過ぎないという思いを抱いて、環境問題に関心を高めていきました。
林学の分野では予定調和的な考え方がありまして、人工林を整備すれば自ずと水源涵養機能も良くなるし、国土の荒廃も防げると、自明の理として言われていました。しかし、1992年(平成4)の地球サミットで森林原則声明が出され、森林の持つ多様な機能と、維持可能な発展を総合的に検討すべきと、森林をめぐる問題意識が日本でも変わり始めました。
題材に採った東京都の水源林ですが、東京と山梨にまたがって、面積2万1600haに及びます。量的に見ても、歴史の長さから見ても、全国的に類を見ない水源林です。
東京では奥多摩町、山梨県では塩山市、小菅村、丹波山村で、いくつかのエリアに分かれます。
明治時代の多摩川 水源涵養と伐採、伐流との衝突
水源林という言葉ですが、近世では「水の目林」といって、農業用水の源となる森林を守らなくてはならないといわれていました。水源林のルーツの一つでしょう。821年(弘仁12)の大政官符令にも、「水源の森林を繁茂させるべし」という一文があります。
水源林の歴史は、水道利用する下流の人々と、森林の位置する地元の人々の間の歴史として見ることができます。
まず明治時代から見ていきましょう。青梅地方は東京近郊に立地する足場丸太の一大産地でした。明治中期になると、青梅丸太が有名になります。その丸太は、江戸時代には多摩川を筏流しで運ばれていました。
三多摩地域(北多摩、南多摩、西多摩で、現在の東京・多摩地域)は、明治26年に東京府に移管されるまで神奈川県に編入されていました。神奈川県は小径丸太の産出を奨励していたのですが、1889年(明治22)になると、「東京市の上水道の水源でこのような丸太生産をしていてよいのか」という声が挙がります。「多摩川上流で水量が減少しているらしいが、水源森林を乱伐していることが原因ではないか。市としては近代水道を敷設することもあり、森林乱伐をやめさせ、森林を買い入れてはどうか」と、東京市会で建白書が提出されます。この建白書は、関係者の大きな関心を呼びました。
その2年後の1891年(明治24)になると、神奈川県の西多摩郡長・郡民の双方が、現在の日の出町あたりの森林を伐採したいという希望を神奈川県に申し出ます。この森林は1887年(明治20)に神奈川県が水源涵養林に指定し、伐採や土地の掘り返しを禁じ、希望があれば県の許可が必要であると規制していたのです。地元の要望に対して、神奈川県はこの申し出を許可します。ここであらためて東京市民と神奈川県の間で衝突が起きるわけです。
この衝突は言い換えれば水源利用と森林伐採の衝突です。しかしよく見ると、筏流しと上水利用という衝突も垣間見えます。多摩川というのは、飲用水利用と筏流し(筏流(ばつりゅう))が衝突した唯一の例と言われています。羽村取水堰等いくつかの堰で、農業用水や上水供給のために取水すると、本流の水量は減少してしまうのですが、それが筏流しにとっては大きな支障となります。1880年(明治13)に木材業者が筏師組合を組織し、神奈川県知事に筏流の許可を求める運動を行っています。
1889年(明治22)に甲武鉄道(現在のJR中央線の前身)が開通し、木材、薪、炭や、八王子や多摩地域の製糸、生糸といった産品が、鉄道で東京まで運ばれるようになります。その結果、筏流は廃れていき、板束と平板は1900年(明治33)の筏流を最後に、以後鉄道がそれを代替するという形で、衝突は自然解消します。
水源地を管轄したいという東京府の渇望
当時から、東京府が多摩川を水源地として重視していたことは明らかです。
東京府としては、多摩川の水源と森林の状態を把握する必要がありました。とは言っても今と違って、上空から森林の状態を見ることはできません。実際に森林がどのような状態になっているかは、山に分け入って調べなければなりませんでした。そこで、東京府の担当者が神奈川県の山奥まで探検に行き、「水干(みずひ)」と呼ばれる多摩川の水源地(現在の塩山市)を突き止め、「武蔵国玉川泉源巡検記」という報告書を著しました。1880年(明治13)のことです。
1890年(明治23)にパーマー等の意見を参考に作られた「東京市区上水設計第2報告書」でも、多摩川が水源地として重要ということが出てきます。この報告書に東京市では水源涵養の1条を加えることを議決し、上流の水源林をきちんと管理することも明文化されています。
東京府は1892年(明治25)に三多摩を神奈川県から編入させてほしいと申し出、翌年に実施されますが、その理由の一つには、東京府が自分の水源である多摩川を管轄下に置いておきたいという意図がありました。
また、三多摩地方は自由民権運動の盛んな地でしたので、それを首都東京で管轄しておきたいという意志もありました。これで西多摩は東京府になったのですが、神奈川県時代とは異なり自由に森林を伐ることができなくなりましたので、地元の人には反発もありました。
1899年(明治32)になると東京に近代水道が通水するのですが、翌年に奥多摩の日原でフランスの企業が民有林を伐採しようとし、東京市議会で取り上げられ大問題となります。また、このころの山梨県下の森林の状態はどうだったかといえば、製糸工場がどんどん建てられ、動力源に蒸気機関が導入され、燃料は豊富な森林資源が用いらるという具合で、森林は荒廃していきました。そこでまず、東京府が水源林を買い取り、管理をしました。
はげ山に林業経営のための森林を
1903年(明治36)に、尾崎行雄が東京市長になります。彼は水源管理に大きな関心を持った市長でした。このころになると近代水道にも一応の目途がついたわけですが、水質もあまりよくないし、水量も足りない等、問題点が明らかになってきます。そこで、当時東京府が行っていた水源林管理を、東京市が調査し、水源林を東京市が直接管理するしかないという結論を出します。1911年(明治44)に東京市は東京府から水源林を買い入れることになります。
この決定に大きな足がかりを与えたのは、吉野林業に着目した1909年(明治42)の「臨時水源経営調査委員会報告書」です。その報告書の中で、多摩川は地形も流量も吉野川によく似ているにもかかわらず、なぜ吉野川では林業が興り、多摩川では興らないのか、という問題提起がなされています。吉野川は「其ノ林業ノ盛ンナルカ為ニ、吉野川ノ流レハ、雨後ニモ溷濁セズ、透明ナルコト淵底ノ魚も数フルに堪へ」るほどであったそうで、多摩川もこのようにすべきだということが提言されました。
すでに、1897年(明治30)に河川法、砂防法、森林法の治水三法が成立しており、多摩川上流の荒廃は激しく、はげ山であったことから、吉野林業を模倣する形で東京の森林経営は始まったわけです。
1909年(明治42)から大正初期にかけて、精力的に植林をします。当初計画は毎年500haの森林を植林する計画でした。この数字そのものもかなり無理があると思うのですが、実際には1年あたり350ヘクタールの新植を行いました。戦後の一番多い、拡大造林の時の実績が年200haですから、いかにすごい勢いでの植林だったかがわかります。
これは林業経営の収益も期待できるとして、邁進したわけですね。1921年(大正10)ごろになるとはげ山への植林も一通りすんで、造林のスピードは緩やかになります。それまでは大規模な植林で地元の人に雇用の場を与えてきたのですが、今度は毎年どれくらい、どこの木を伐ってよいかを地元の集落と協議によって決めるようになります。
大正から昭和の初期にかけては、国有林で択伐(たくばつ)が流行ります。ドイツ、スイスなどで択伐が流行し、針葉樹の一斉林が虫害、風害に弱いなどの認識が生まれていました。皆伐(かいばつ)のように木をみんな伐ってしまうのではなく、何本か抜き切りしていくのが択伐で、その後自然の力で森林を世代交代させることを天然更新といいます。そこで、地元の人が択伐をし、伐った木を地元の人に払い下げるという方式をとります。これがなぜ機能したかというと、地元の人々が炭や薪を欲したからです。特に炭焼きが大事な産業で、小さな広葉樹を伐ってもらい、それを炭焼きするということは地元の利益に適うことだったわけです。薪炭材の更新は萌芽(ぼうが=ひこばえ)によってできるため技術的にも比較的容易です。
1933年(昭和8)の東京市の森林経営計画では、樹種混交の森林、針葉樹と広葉樹の混交林をつくっていこうとします。
木材生産機能と水源涵養機能の両方を、発揮させようとしたのでしょうね。
昭和の時代 風致の維持から戦時経済へ
小河内ダム・貯水池の計画が持ち上がるのは1931年(昭和6)ですが、このころになると水源林の風致に対する関心が高まってきます。つまり、奥多摩地方は東京の重要な観光地であるという意識です。小河内貯水池ができれば富士五湖のような観光地になるだろうという声も挙がり、「水源林も風景に配慮しなくてはならない」という考え方が出てきます。
小河内貯水池・ダムは単独の水道局が持っているダムとしては、世界にも類を見ない規模です。着工は1938年(昭和13)、完成は1957年(昭和32)で、戦争から戦後復興の時期に重なる大工事でした。
戦中期間は水源林も木材資源の供給地として乱伐に遭い、薪炭、パルプ、製材品に供されました。特に1939年(昭和14)とその翌年は東京府内では深刻な木炭不足で、切符配給制も導入されました。
この時、間伐材を使ったパルプ生産も行われていますので、明治末期に行った大植林が資源として成熟してきていたわけです。戦前の森林経営は長伐期で、酒の樽などを作っていた吉野林業のやり方に習ったものと思われます。しかしどこでも行われたことですが、1942年(昭和17)には、従来はスギは80年、ヒノキ80年〜100年、カラマツ60年だった伐採予定年齢を、スギは40年、カラマツ50年、ヒノキ60年と引き下げます。それだけ、木材資源が渇望されていたということでしょう。
水源林管理組織も1933年(昭和8)時点では水道局庶務課林務係でしたが、1943年(昭和18)に戦時体制として東京都制が施行されると、経済局に移管されます。「戦争遂行と民政安定のために木材資源を供給せよ」ということです。財産林として森林を見なし、水源涵養林とは言っていられなくなったわけです。
戦後復興から拡大造林へ
戦後は「復興期(1946〜1955)」と「経営の量的拡大期(1956〜1972)」「水源林独自の計画確立期(1973〜2001)」の3期に分かれます。
復興期は帝都復興のための木材供給が水源林の使命になりますが、何と言っても水源林に大きな影響を与えたのは次の「量的拡大期」です。その「量的拡大期」は、いわゆる高度経済成長期で、木材バブルの時代でした。
小河内ダムは1957年(昭和32)に完成しますが、このころには東京都の水需要が急増し、「小河内貯水池だけでは東京の水源にならない」と問題になります。そこで多摩川の他に、水源として新水系を利根川に求めるわけです。ここで多摩川の位置づけが変わります。
1961年(昭和36)に水資源開発促進法、水資源開発公団法が成立します。水資源公団というのは大雑把に言えば東京に水を持ってくるためにできたような組織ですから、ここから利根川水系の開発が始まります。ただ利根川分水で、絶対的な水量不足は解消できたのですが、水利権は多摩川と異なって入り組んでいますし、ダムは公団の持ち物ですから、利根川水系で何かあったときのために多摩川はバックアップの意味を持っていました。量的には少なくても、意味合いは大きいのです。
この時代には木材生産の拡大が声高に叫ばれました。水源涵養機能に適しているといわれた「針広混交多層林」にこだわらなくなりました。
代わって打ち出されたのが、天然林を伐採して人工林にするという「拡大造林」の方針です。そのため、それまで行われてきた天然林の択伐は縮小していきました。
この時期の水道局は択伐に消極的で、地元との合意があるので最小限で行っていました。しかし、燃料革命で薪炭材の市場価値がなくなり、天然更新で薪炭ではない別の用途の木を供給することが求められていたのに、それに応える技術を確立できなかったという背景があります。
この時代の経営計画の特徴は、成長量以上の伐採を計画したことです。何でこんなことがまかり通ったのかというと、「いま造林している針葉樹の成長が早いので、いまたくさん伐っても将来は担保できる」と考えられたのです。これには、自然に対する人間の傲慢さが感じられますね。
古典的林学の基本である、森林の再生可能な範囲での伐採という考え方も、当時は林学の中で「古くさい」と批判を受けていました。1956年(昭和31)には成長量以上の木材を伐らないという立場と、成長量以上の木材を伐る拡大生産の立場とで論争がありました。当時は木材バブルでしたから、ある大新聞の社説に「国有林伐り惜しみ論」というのが載り、「国有林が伐り惜しんでいるから、木材の値段が吊り上がるのだ」という論陣を張ったそうです。そういう狂騒的な世の中でした。
木材生産への要求が高くなる一方、東京都の主たる水源が利根川水系に移行したことで、水源林の水源涵養機能の重要性も薄れたとも考えられます。
水源涵養機能重視への転換
拡大造林の転換点は1972年(昭和47)です。自然保護運動が高まり、日本自然保護協会が水道局に意見書を出します。
「水源林経営は天然林を切り尽くして、治山治水上問題が多い。木材生産と水源涵養は両立しないのではないか」と、痛烈に批判しています。この意見書が出されたのは1966年(昭和42)ですが、一つの有力な意見書でした。東京都も革新都政の中で、自然保護政策を積極的に推し進めます。
1971年(昭和46)には「都民を公害から防衛する計画」を定め、自然を保護し回復することを施策上の重要課題にします。翌72年(昭和47)には、「自然の保護と基本的回復方向」を定めて、残っている自然は強力に保護することになり、水源林は小笠原諸島などと同じように原生保全地域に指定されます。林業経営も自然保護に留意し、開発行為は認めないと明言しています。
この時期の地元との関係もこのような規制により大きく変化します。それまでは立木払い下げで地元との経済関係をつないでいましたが、1971年(昭和46)に入り、地元としても過疎で人手がなくなり、消防や学校の維持管理で金がかかるということで払い下げをやめる代わりに交付金を出す、という大きな曲がり角を迎えます。森林の木材を媒介としない、制度的つながりを地元と結び直すこととなりました。
明治以降一貫して水量の拡大を求めてきた水利用のあり方も変わり、1973年(昭和48)には、「水道需要を抑制する施策」を発表し、水道局自身が水需要を抑制することで需給バランスをとることを明言しました。画期的な出来事だったと思います。
そして80年代から高度浄水処理が取り入れられ、「安全でおいしい水」が求められるようになります。
こうした水道局側の動きに合わせるように水源林も1972年(昭和47)には天然林の伐採は行わない、拡大造林は行わない、人工林伐採も暫時減少させると軌道修正することになりました。
そして改めて「水源林経営の目的は水源涵養機能を発揮させること」と第一に表明します。「土壌の浸透機能、土砂流出防止機能のい森林を造成する」と定め、「木材生産は副次的なものにすぎない」と明文化しました。一時期背後に押しやられていた水源涵養機能がここでまた表舞台に登場することとなりました。
木材生産なき水源涵養林の時代
私は木材生産と水源涵養は歴史的に見る限り両立すると思っています。しかし現在は木材生産の需要が相対的に非常に小さくなっている時代です。でも逆説的に言えば、だからこそ今の状況は利害を離れて森林のことや水のことを考えることができる良い機会ではないですか。長い歴史を振り返っても、こんなことは、かつてなかったわけですから。
水のためにはどうしたらよいか。子供、孫のためにどういう森をつくればよいか、夢を描く絶好のチャンスだと思います。水源涵養税が議論になり、一部で実施されてきているのも、こういう時勢を反映しているのでしょう。ただ税金を徴収するだけでは、水源林に対する関心を呼び起こすことにはつながりません。その税金を誰に、どのように配分するかも難しい問題です。単なる委託に陥らない、下流から上流に何かを還元するという意識がないと水源林を守る上流のインセンティブを高めることにはならないでしょうね。そのためには、源流を見に行くという体験も大切だと思います。
また、東京都の水源林を見ていて思うのですが、人工林の伐期を伸ばすというのは一つの選択だと思います。100年や200年たった人工林というのは見た目は天然林と変わらず、荘厳で神様が宿っている感じすらします。そういう森をつくっていけば、水源涵養機能も高いでしょうし、木材としても価値の高いものとなると思います。長伐期にシフトするという選択肢は検討に値すると思います。ただ人間は100年も生きられませんから、これは個人の力ではどうにもならず、社会的な仕組みが必要になりますね。
最後に、「利用とは何か」という点をお話したいと思います。水は世の中を回っているもので、その輪の中に人間はいるわけです。水を使うときは、上流から水を流してくれる人がいるわけだし、自分が使った廃水も川や海に流れていく。
今までの水資源開発は、使えば使いっぱなしだった気がします。近代水道の歴史もこうして追ってみると量的な拡大の歴史でした。これからは、水利用を「循環の輪」で考えていかなくてはならないでしょうね。