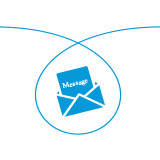機関誌『水の文化』20号
安全は達成されると壊れ始める

-

-
国際基督教大学大学院教授・東京大学名誉教授
村上 陽一郎 (むらかみ よういちろう)さん -
1936年生まれ。東京大学大学院人文科学研究科博士課程修了。専門は科学史、科学哲学。東京大学先端科学技術研究センター長などを歴任。 主な著書に『近代科学と聖俗革命』(新曜社、1982)、『安全学』(青土社、1998)、『安全と安心の科学』(集英社、2005)他。
危険の質が変わってきた
18世紀になると、ヨーロッパでは文明化という考え方が生まれます。文明化とは「インフラストラクチャーを整え都市化する」という意味です。実は日本の江戸は、17世紀末には世界でもっとも人口が多く、上下水道の面からみても、一番インフラストラクチャーが整備された都市ということができました。同時代のヨーロッパでは、汚物を窓から投げ捨てるために、エスコートする男性は道側を歩くのがマナーとされたほどでした。
日本の棚田では落ち穂をついばみにくる小鳥の糞を肥料にしたり、大きな循環の中で、全体的に緩やかな安全対策が取られていたのです。自然災害は天災と見なされ、発生頻度を下げることは不可能で、仕方がない前提として受け入れられてきました。
ところがインフラストラクチャーの考え方が進むにつれ、安全対策も「人間の手で危険を押さえ込む」という意味に変わってきます。つまり、「危険が発生する頻度を減らし(防護)」、「発生時に起きる被害を減らす(緩和)」という二つの面で、徹頭徹尾、人間の技術で危険を押さえ込もうとするようになります。この発想は裏を返せば、「押さえ込むことができないのは、人間の側の失敗である」ということにもつながります。現在の日本人が安全と安心をしきりに言い立てる背景は、ここに端を発していると思います。
しかし皮肉なことに、危険は、技術が進むほど増えていきます。一つには、列車などの人工物が、新たな危険を生み出すからです。その新たな危険を、自動列車停止装置(ATS)のように技術で減らすことができる場合もあります。
もう一つには、技術の進歩で、今まで自然災害としてあきらめていた危険においても、何とか緩和することができるかもしれない可能性が生まれてきました。そうなれば、昔は考えもしなかった「危険を緩和する手だて」を考えるようになり、課題の一つととらえられるようになります。技術が発達した文明社会では、「何が防げて、何が防げないのか」という判断が、最大の課題になるでしょう。
また「安全に対する新しい視点」も要求されるようになりました。人工物は人間が設計・施行し、管理するものです。しかし、人間は全知全能の神ではありませんので、人工物のもたらす危険に対して完璧な防護・緩和の設計を行なうことは不可能です。また人間が管理する限り、必ず人為的なミス(ヒューマンエラー)が起きることは避けられません。
そうは言っても人間が何とかしなければならない以上、100%の安全は不可能としても、その程度を上げていくことに努力していく必要はあります。しかし安全度が上がれば、我々が抱く不安は除かれるのでしょうか? 安心は得られるのでしょうか? これは、社会や文化によって、感じ方にかなり差があります。このような問題が、これまでの安全工学では対応できない領域として浮かび上がってきています。
やはり、文化や社会構造を見据え、人間の心理も見据えた上で、安全という問題を包括的に追求する視点が必要なのではないか。これが、1998年に私が「安全学」という学問を提唱した理由です。
技術が見えない時代
かつて「技術」というものは、我々の生活に密着し、自分たちの目で見ることができました。例えば私が子供のころは、研ぎ屋さんが家にやって来て、預けた包丁を目の前で研いでくれました。鋳掛(いかけ)屋さんは鍋に穴が開いたら、裏打ちや溶接をしてすぐに使えるようにしてくれました。つまり、職人技能的なものは生活技術として、目の前に、目に見える形で存在していたわけですね。
余談ですが、私の家では1970年(昭和45)ごろまで井戸を使っていました。電動ポンプですから、停電になると水まで止まってしまいます。戦後すぐはよく停電したので、本当に困りました。昭和24年ぐらいまでは、一日に数時間しか通電していなかったという時代でしたので、こういうときには、むしろ手動の井戸のほうがよかった。
ところが現代の技術は、ほとんど生活の現場では見ることができません。蛇口をひねれば水が出ますが、水源はどこで、どのように処理された水なのかは、気にしなくてもよい。鍋釜も工場でつくられ、消費財として店で買い、壊れたら捨てる。技術は目に見えなくなり、隠れてしまいました。
「目一杯機械を働かせたら可哀想だ」という感覚が私にはあって、蛇口をきつく締めることにどこかで抵抗があります。温水給湯器も温度を最高に上げるということが、私にはできません。ところが、子供たちの世代になると、クーラーを最低温度にすることなど平気なのです。つまり我々の世代は、温水器の仕組みを知っていて、長い時間フルで使うとどこかが痛むと思うから、八割ぐらいのところで止めておきます。それは、いろいろなタイプの目に見える機械や器具を見てきているからです。でも若い世代は仕組みを知らなくても、ただインプットすればアウトプットするという状況の中で器具を使った経験しかありません。技術が見えないということから生まれる、ここ50年ぐらいの新しい状況です。
技術を見えなくした大きな力はITです。
私はホンダの創業者、本田宗一郎さんと晩年の20年ほど親しくおつき合いいただきましたが、その本田さんが、自分の会社でつくっている車のボンネットを開けてもわからなくなった、とおっしゃったことがあります。この言葉どおり、今の車はボンネットを開けてもまったくわかりません。メカニカルには目に見えるのですが、ITコントロールになるとまったくのブラックボックス。ですから、故障したら、修理するのではなくユニットを取り替えるようになっています。
満足と不足がわからないと安全問題を解きほぐせない
現代社会に生きる人々が抱え込んでいる不安というものは、どういうものなのでしょうか。
今、日本の死亡原因で一番多いのがガン、6位が自殺です。これは重要な社会問題になっています。「職を離れた50歳代の人が経済的不安から自殺することが多い」と報道されます。しかし、「経済的に将来が不安だから自殺する」というのであれば、昭和19年から22年ころに生活していた大人はみんな死んでいたはずです。明日どころか、今晩のごはんが食べられるかどうかわからない。お米がない、卵もない、腐ったようなタラが一週間に一匹配給されるという状況で、どうやって喰っていくか、みんな不安を抱えていたに違いないのです。私の父親、母親もそうでした。だけど、彼らは死にはしなかった。
ということは、いま、主要な収入源が無くなり死を選ぶ人の理由は、実は、「将来の経済的不安」が第一ではないのではないか。むしろ、一番の大きな理由は、今まで享受してきた生活が壊れ、奪われてしまうことへの恐怖、不安ではないのか。いわば「持っていることが奪われてしまうことへの恐怖、不安」です。
しかも、昭和20年当時は皆が同じ経済的不安を抱えていましたが、今は自分だけが失う恐怖と立ち向かわなくてはならない。この違いも、不安を倍加させる大きな要因となっているでしょう。
こう考えていくと不安という概念も、不足とか、満足度とか、もしかしたら幸福度のようなものも考えないと明らかにできないものかもしれません。
ところが、ここでも文明化が問題になります。文明社会というのは我々の欲望を駆り立てて、満足させない社会です。「自動車にこんな付加価値をつけてみました」とか、「テレビが32インチでこんなに美しくなりました」と欲望を駆り立てる。「これで満足していてはだめです。もっと新しい機能や付加価値がついた商品を買ってください」というのが、現代の姿です。どこで満足するのか、何を不足と考えるのか、技術と欲望の追いかけっこのようなものです。
象徴的な話ですが、クローン技術で羊のドリーが誕生した翌日、アメリカの産婦人科の先生のところにある女性から電話がかかってきたそうです。「私たち二人の女性は愛し合っている夫婦です。ドリーの技術を使って、私たちが子供を持てるようになるのはいつでしょうか」と質問したというのです。女性同士が愛し合うことはそんなに珍しいことではないのかもしれないけれど、今の今まで、女性同士で子供を持つということは誰も夢にも思わなかった。それが、ある技術が生まれた瞬間に、その欲望が煽り立てられたというわけです。
このように、「安全と危険」の問題を考えるときには、「満足・不足」という感覚を、「安心・不安」と絡めないと、問題が解きほぐせないと思っています。
ままならない社会なのに自己責任を問われる
イラクの人質事件で、自己責任ということが話題になりましたね。ああいう状況の中で、自分の安全を省みず出かけたことが問題だ、という言い方がされたわけです。裏返せば、人々は、どのような状況でも自分の行動には責任を負うことができると、どこかで思っている節がある。
しかし我々は、安全についても「技術的に保証する」と言われれば、文句なく社会システムに委ねてきたわけです。消防や水道が、そのよい例です。自治体から「水道をつけなさい」といわれ、「確かにポンプの電気代もかさむし、井戸職人もいない。管理にお金もかかる」と、私は井戸を埋めて水道に切り替えました。地方自治体が提供してくれる水の供給に、己を委ねているのです。ということは私は、東京の供水装置が故障したり、災害で動かなくなったときに自分で水を集める手段を放棄した、ということに他ならないのです。
ゴミもそうです。かつては、自分の家で燃やしたり、埋めたりしていたものを、全部地方自治体がやってくれるゴミ処理に委ねています。私は今でも、紙などは家にある小さな焼却炉で燃やしたいと思っていますが、ダイオキシンが出る、煙が迷惑だ、という理由で落ち葉さえ焚けません。
このように文明化が進むと、自分の責任で処理していたことも、必然的に公のシステムやマーケットメカニズムに委ねていくことになります。私は、これを技術の「外化(がいか)」と呼んでいます。
本来身近にあった技術を外に委ねざるをえなくなった社会で、自己責任を問われるということは矛盾しています。では、いったいどこまで自己責任を追及できるのでしょう。ここから先は公共サービスがカバーしてくれるという「摺り合わせ」(インターフェース)が、今のところ、まだ上手にできていません。これは安全学の大事なポイントです。
NPO・NGOの役割
そういう中で、公共サービスでもない、マーケットメカニズムでもない第三者が新しい選択肢として注目されていくでしょう。つまり、NPOないしはNGOがこれからの社会の中で、かなり重要な役割を発揮していくことと思います。小さなことしかできない個人が力を合わせた新しい働きが、可能性として浮かび上がっていると思っています。
NPOやNGO、昔風に言えば隣組でもよいのですが、そういうものが行政と対立したり、単に行政のアシスタントになるのではなく、自分たちも主役の一人だという気持ちで、実際に何ができるかを考える。
私が住んでいる三鷹市は昔からそのような傾向の強い所です。たとえば、コミュニティセンターのような施設は市が造り、管理は地域住民に任せます。「みなさんの好きなように、自由に使ってください」と言われると、住民の側も無責任なことはできませんから、自分たちで責任ある組織をつくってきちんと管理します。実際、防災に関しても連絡網をつくるとか、井戸がどこに残っているとか、どこに逃げればいいかという道路図を、行政とタイアップしながら住民が率先して作っている例もあります。
ネットワークすることで意識が高まってきているし、自分たちにできること、できないことがどれだけあるかがよく話し合われています。行政でないと手が出ないという点は、ちゃんと行政に申し入れるという姿勢が現実に浸透しています。こういう姿を見ると、頼もしく感じます。
安全に慢心せずに言い続ける
安全とは価値であり、その価値は文化と言い換えることもできます。安全文化を打ち立てていくためには、言い続けるしかありません。
企業のトップとこのような話をすると、「安全という概念は消極的だ」とおっしゃる方が多い。「我が社は安全を第一に掲げています、安全こそがわれわれの企業価値です」とは、なかなか言えないとおっしゃる。そういうとき、私は「万が一が千に一つになって何かが起こってしまったとき、払わなければいけない犠牲やコストを考えてください」と言います。今まで安全を考えないがために事故を起こし、企業イメージを失墜させ、天文学的なコストを払った企業が現実に何社もあるからです。
重ねて「安全という価値は、何にもまして、常に追求し続けなければならない最大の価値の一つです。何かが起きてからでは遅いということだけは肝に命じてほしい」と申し上げます。安全であるという現状を維持することが、何ものにもまして価値のあることなのです。やはりそこをわかっていただいて、少しずつでも前進してほしいということが、私が安全学を始めた理由でもあります。安全が当たり前になると慢心しがちですが、その意味でも、言い続けるしかありません。
安全に対しても圧倒的な力を持っている行政や企業に対し、安全を追求するインセンティブを強く持つように警告を発し続けることが、市民が怠らずに続けなくてはならない役割の一つでしょう。
【火災保険の歴史】
火災保険は、中世ヨーロッパ・ドイツでギルドによる相互救済機関として発達し、15世紀には火災を対象としたギルドが多数存在した。
イギリスでは、1666年のロンドン大火の直後に、ニコラス・バーボンという医師が個人で保険経営に乗り出したのが火災保険業の始まりといわれている。1858年にはファイア・オフィス・コミッティーが組織され、料率算定とともに防災活動に乗り出している。
日本では、1887年(明治21)に、東京火災保険会社(安田火災海上保険を経て、現・損保ジャパン)が営業を開始する。保険金受け取り第一号は、1890年(明治23)、東京・浅草で牛肉商を営む井上さん。家屋火災に対して1600円の保険金が支払われた。
当時、火災保険会社が数社できたそうだが、保険会社の体力も低く、利益を安定させるには、多数の契約者を集めねばならないということで、料率競争になったこともあったようだ。リスクに見合わない安い保険料で契約者を集めたため、火災になると払えないという事態もあったようだ。
その後、もっぱら火災のみを対象としていた火災保険も、1959年の伊勢湾台風をきっかけに、風水害も補償する商品に拡大した。一方、高度成長期に入ると火災保険の加入率が飽和状態になってきたため、各社とも補償範囲を広げ商品の充実を図ることになる。例えば、火災の後片付け費用、怪我の治療費用、近所への見舞金などを補償する(費用保険金)商品も現れた。
火事は、日本においては地震と切り離しては考えられない。地震火災の補償は火災保険に含まれていないが、1923年の関東大震災のときに「これだけの損害が出ているのに保険会社は冷たいのではないか」という世論があり、契約者に対して見舞金を払った例がある。
火災保険とは別に、地震保険の必要性については、戦後、地震が起きるたびに話題にのぼった。実現した契機は、1964年(昭和39)の新潟地震である。時の田中角栄大蔵大臣が「国家保険のようなものをつくれ」と大号令をかけ、2年後の1966年(昭和41)に地震保険が設立された。
地震保険は、通常の損害保険とは異なり、1回の地震で支払われる総額上限は現在5兆円と決まっている。関東大震災クラスの地震が起きても支払える額で、1回の地震で750億円までは保険会社が、それを超えると政府も保険金を支払うしくみになっている。
仮に、いま東海地震が起きると、2兆円弱程度の損害が見込まれているが、ちょうど同額程度が準備金で積み立てられており、東海地震が1回起きると、準備金が底をつく勘定だ。ただ、空になっても払わないわけにはいかないので、政府も保険会社も借金をしてでも払うことになる。
このように、火災もかつては、天災と思われていたのだろうが、財産も増え、持ち家率も上がり、保険に対する見方や利用の仕方がどんどん大衆化して根付いていった。それに応じて、保険会社も補償範囲を広げることで顧客のニーズに応えたというのが、日本の損害保険の歴史といえそうである。
(参考:社団法人日本損害保険協会のインタビューより)