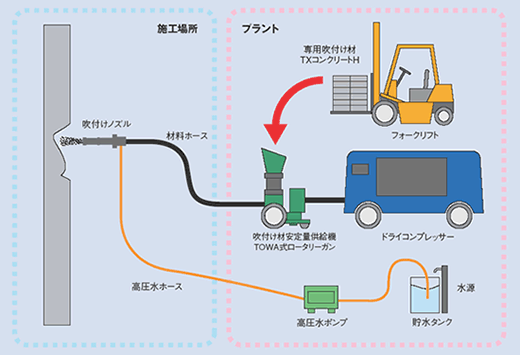機関誌『水の文化』26号
良い建物を都市に残す仕組みとしての
定期借地権と区分所有

上段左:修復後の求道学舎エントランスホール。右側のガラス扉が入り口になり、手前にはスロープが設けられた。 上段右:修復前の入り口は、現在は郵便受けになっている。 下段左:求道学舎裏手側になる敷地内への通用階段。他の三方向はすべて建物に囲まれており、狭い路地を通らなければ学舎棟までたどり着かない、とても立地条件の悪い物件である。 下段右:正面入り口。手前右側が求道会館で、一番奥に見える建物が学舎棟。
1970年代から建て始められた鉄筋コンクリート製高層マンションは、そろそろ建て替え寿命を迎えつつある。 分譲による区分所有という、日本が初めて経験する所有形態での建て替えは、果たして順調に進むのだろうか。 日本では人口減少にかかわらず、都市人口は増えると予想されているが寿命を迎えた建物は、都市の活性化の足かせになりかねない。 建築家として、求道学舎(きゅうどうがくしゃ)の後継者として、「定期所有権」に活路を見出した近角真一さんに「都市の未来像」をうかがった。
-

-
建築家
近角 真一 (ちかずみ しんいち)さん -
1947年北海道生まれ。1971年東京大学工学部建築学科卒業。内井昭蔵建築設計事務所を経て1979年独立。現在、集工舎建築都市デザイン研究所所長。求道会代表として求道会館復原保存、求道学舎リノベーションを主導したほか東本願寺参拝接待所、御影堂阿弥陀堂修復などにも参画している。日本建築学会オープンビルデイング小委員会委員、日本大学芸術学部デザイン学科建築デザインコース非常勤講師、東京藝術大学美術学部建築科非常勤講師。 作品に、武蔵大学、麗澤大学、NEXT21、ふれっくすコート吉田、他。都市開発やプロダクト開発などの仕事も多く手がけている。 著書に『SD別冊25近未来型集合住宅NEXT21』(共著鹿島出版会1994)、『NEXT21その設計スピリッツと居住実験10年の全貌』(共著大阪ガス2005)他。
武田五一の名作建築を修復
今日お話する「求道学舎(きゅうどうがくしゃ)」というのは、私の祖父、近角常観が青年への伝道のためにつくった学生寮です。
近角常観(1870―1941)は、滋賀県の真宗大谷派西源寺に生まれた宗教者で、1899年(明治32)の宗教法案への反対運動の功績として、東本願寺から欧米の宗教制度視察旅行に派遣されました。1902年(明治35)に帰国後、31歳の常観は、青年に浄土真宗の教えを伝えたいと東京・本郷に求道学舎を設立、布教を始めています。粗末な2階建ての家屋でしたが、常観の講演に集まる若者が次第に増え、1915年(大正4)には新たに「求道会館」を建設し、後進の育成に力を注ぎました。1926年(大正15)には求道学舎も建て替えられましたが、どちらも明治、大正期の優れた建築家である武田五一(注1)の建築です。
私は1996年(平成8)から6年間工事をやって、築90年の求道会館の修復を完成させていました。こちらは幸いなことに補助金事業となり、9割を公的な補助金でまかなうことができていました。しかしオープンしてみると、毎年300万円の赤字が出ることがわかったのです。
これは破産どころの話ではなく、直ぐに立ち行かなくなってしまうぞ、と気づき、寄宿舎として建てられた求道学舎を何とかして、その収益を求道会館の運営に回そう、と考えました。1999年(平成11)までは、叔母が求道学舎の舎監をしており、ボロボロながらも何とか機能していたのです。
その時点で求道学舎は築80年で既に相当傷みが激しく、このまま手をこまねいていては崩壊してしまう、というところまできていました。
そこで紆余曲折の末、コーポラティヴ方式で修復することを決め、まずは求道学舎に暮らしたことのある何百人もの方々にダイレクトメールを送ったのです。しかし、若干の反応はあったものの結果としては全滅でした。そのうち新聞で取り上げられるようになると、その度に大勢の方が見学にみえましたが、なかなか契約する人が現れず、
「こんなに確率の悪い募集は初めてだ。価格設定が高すぎたかな」
と、コーディネーターの勧めで価格を下げようという話にまでなったんです。
まあ、あの状態で応募者が決断されるのは、すごく難しかったと思います。なにしろ、本当に廃墟でしたから。ですから途中は「本当にできるのだろうか」と、かなりヒヤヒヤでした。
(注1)武田 五一 (たけだ ごいち 1872ー1938)
備後福山藩(現・広島県福山市)生まれの建築家。京都帝国大学(京都大学)に工学部建築学科を創立した。アール・ヌーボーを日本に紹介した建築家ともいわれ、建築のみならず、テキスタイルデザインなどにも造詣が深い。フランク・ロイド・ライトとも親交があり、国会議事堂建設や法隆寺、平等院などの古建築修復にもかかわった。
コーポラティヴ方式の採用
ところが、私のほうには先程のような事情があって、簡単に値段を下げるわけにはいかなかったんです。ですから価格を下げようと言われても、私も女房も強硬に反対して、このまま売れなくても仕方がないと頑張っていたら、徐々に契約が決まり始めました。最後にだめ押し的に朝日新聞に取り上げられたところ、ばっと埋まってしまいました。そのあとは、ウェイティングリストができたほどでした。
「コーポラティヴ方式でこんなに大勢のウェイティングリストができたのは、初めてです」
とコーディネーターに言われました。
そもそもコーポラティヴ方式でいけると断言したのは、コーディネーターの田村誠邦さん((株)アークブレイン代表・不動産鑑定士)です。ベテランの彼でさえ、ハラハラドキドキの展開だったのです。
しかし、この方式に至るまでは、女房と二人でいろいろな方法を考えました。何人ものデベロッパーを呼んで、私が書いた図面をもとに、幾らで実現できるか値づけをしてもらいましたが、ここの土地は細い路地で三方を取り囲まれていて、重機が入らないので手壊しになってしまう。裏側は崖で道路づけは崖側なので、建設資材もそこからクレーンを使って入れることになる。壊すのも新築するのも高くつき、お話になりませんでした。
次に改修をして賃貸契約にしよう、という計画もありました。何人かの方と計画を練ったのですが、皆さん改修費をかなり安く見積もる傾向にあることがわかりました。ある人の計画などは、「ドアを取り替えて、鍵穴を替えて」とかいうレベルなんです。当時の求道学舎は本当に廃墟という状態でしたから、そんな所を「周りは全然いじらずにドアだけ替えて」などと言う人に事業を任せる気にはなりません。
分譲もダメ、賃貸もダメ、ということになったときに、我々夫婦が思いついたのが「つくば方式(注2)」だったんですね。私たちはつくば方式の住宅にいくらかかかわっていたので、「定借(定期借地権)」でやれば何とかなるんではないか、と考えたのです。ただ、つくば方式というのは普通は新築なんですね。中古のコーポラティヴ方式というのは実例がないんです。
それで断られるかもしれないけれど、という思いでつくば方式のコーディネーターを長くやっておられる田村さんにお願いしたところ、その日のうちに「いける。大丈夫、やりましょう」ということになって、スタートしたのです。
コーポラティヴというシステムが、少し誤解されているようなので申し上げますが、そもそも入居しようという人々が建設組合をつくって、その人々が投資するという仕組みです。それは、我々建築家から見ると、デベロッパーによらない建築づくり、という意味が大変大きい。
普通のマンションをつくるときには、売れなかったときのためにデベロッパーが利益を担保として取っておきます。しかし、コーポラティヴの場合は売れ残る恐れがないため、そのリスク分を負う必要がない。それがコーポラティヴの最大のメリットです。
また、決して彼らが仲良くして、お祭りをして、共同で家づくりをしようというのではないんです。ところが、ここの場合は、もともとの建物があってそれに価値を認めた人たちの集団ですから、結構仲がいい。そういう意味で、似た者同士が集まってくる。イギリスのリースホールド(注4)と同じで建物や環境が気に入って集まってくる。定期借地権付きの区分所有住宅とは、一定期間、そういう生活を買うことなんですよ。そういうモデルとしても、今度のプロジェクトは非常に良かったと思います。建物が生活のイメージを語ってくれている、というのは、普通のコーポラティヴとは少し違うと思います。
今のマンションはデベロッパー主導で規模、間取りから何からすべて決められていて、商品のように売り買いされていますが、そういう流通の仕方は、実は「住まい」という装置には馴染まない。やはり「住まい」は、住む人に合わせて規模や使い方を決めたい。
コーポラティヴというのは、欲望の増幅装置だと言った人がいます。だから最初に提示するモデルには、最低限のものが提示される、という。それに不満があるのはわかっているから、一番安いものを提示して膨らましていく、オプションで個別性を充足させる、というのが通常のやり方だそうです。
しかし、うちでやったのは逆のやり方でした。最初に標準で入れたもののグレードが高く、これ以上の付加仕様はまずはいらない(近角建築設計事務所主宰で、真一さんの奥様であるさんが本プロジェクトのデザインを総括)。だから、皆さん見た瞬間に気に入ってくれました。これは、私の女房が長年戸建て中心に注文住宅を手掛けてきたノウハウで、ユーザー密着型で仕事をしてきた彼女の強みです。最高級品ではないがこれだったら賢いユーザーがOKする、といった選択に外れがないんですね。
よくいわれていることですが、あれもこれも施主の要求を言いなりに聞く、というのは、すごく大変なことなんです。ですから我々が高い水準のものを最初に提示したというのは、そういう大変さをよく知っているんで、むしろ欲望の増幅装置にならない方法を選ぶことが大切だと考えたからです。
これは建築家のおごりかもしれませんが、素人が集まって知恵を出しても、絶対良い建築はできません。コーポラティヴといったときに、誤解されやすいのはここの部分です。それぞれがそれぞれにとって理想の家づくりがしたいだけで、建築全体に目を配ることはできないんです。
(注2)つくば方式
「スケルトン定借(定期借地権)」の通称。つくば市にある旧建設省建築研究所で開発されたことから、こう呼ばれるようになった。契約期間が30年以上の建物譲渡特約付きの定期借地権を応用した「定期借地権住宅」の供給方式のひとつで、入居者は当初30年間は定借の持ち家に住み、31年以降は建物をいったん地主に売却。その売却代金を生かして、安い家賃で継続して住み続けることができる(家賃相殺契約)。建物は耐久性の高いスケルトン(SI)住宅(注3)にするので、入居者は良質な住宅を低価格で購入できる。
(注3)SI (スケルトン・インフィル)
建物のスケルトン(柱・梁などの構造躯体)とインフィル(住戸内の内装・設備など)とを分離した工法による集合住宅。設備や間取りなどの変更が容易にできるだけでなく、通常30年程度の耐用年数とされる基幹配管を外配管にすることにより、配管の修繕を本体から分離して考えることができるというメリットがある。
(注4)リースホールド
イギリスの土地の定期所有権の仕組み。国王や貴族が土地を持っていて、そこに建てた建物を一定期間、一種の債券として売買する。一定期間が経ち価値が0になったときに、土地の所有者は建物に手を入れて、再度リースホールドする。
進んでいる土木の技術
コンクリートの建物を取り壊す一番の理由は、中性化です。コンクリートの寿命は60年といわれていますし、私も学校でそう習いました。
しかし、60年間で寿命がくるというのは実は間違いで、コンクリートはもともとアルカリ性なのですが、時間の経過ととも酸性側に寄っていきます。つまり、中性化です。中性化すると鉄筋が錆びやすくなります。しかし、錆びるためには、水と空気が必要なんです。コンクリートにヒビが入ると侵入した雨水などが鉄筋の近くまでいき、空気も入っていきます。こういう状況になって、初めて鉄筋の腐食が始まって断面がなくなっていく。雨水が錆びを流していくのでどんどん鉄筋は細くなっていくのです。
また、水の出口がないと錆びは膨張を始めてコンクリートを押し開いて「爆裂」する。そのことでますます水と空気が入りやすい環境になります。こうした仕組みでコンクリートは寿命を迎えます。
求道学舎は築80年でしたから100%中性化していました。なおかつ、外側には無数の亀裂が入り、数十カ所で爆裂が起きていた。今までの常識でいえば、完全に寿命がきている。しかし、我々のように「残さざるを得ない」事情を抱えている人間にとっては、何とか残したい。普通の価格的判断からいったら「もう壊したほうがいいですよ」という状態だったと思います。
今回の改修では戸田建設を指名しました。まず求道会館の改修をよくやってくれたということ、それに求道会館も求道学舎も戸田建設の前身である戸田組がやっていたという関係もあります。求道会館からは初代の戸田利兵衛の名前が棟札から出てきているんで、戸田さんとしては逃げられない。求道会館で建築業協会賞も取っており、大変高い評価を受けておられた。
当時の武田五一の設計図に対して、戸田組設計部が鉄筋コンクリートの図面を描いているんですね。強度計算も戸田組がやって武田五一が監修している。戸田の本社に残っている資料は、戦災でほとんど消失してしまったため、私が保管していた図面をお見せしたら大変喜んでくれました。そういう意味で積極的に取り組んでいただきました。
普通は建築家が図面を引いた場合、構造は専門の設計事務所を頼むんですが、今回は戸田建設の構造設計チームに依頼しました。「あなたたちの先輩の仕事に学んで、よろしくお願いします。今でもちゃんと強度が残っている立派な仕事を先輩方がされたのだから、あなたたちもがんばってください」と言って、頼んだのです。
そういう経緯があったためか、戸田建設の技術者の方も思いが強かったのかもしれません。普通だったら「ここと、ここと、ここが爆裂しています。だからダメです」というところが、戸田建設の構造部の人が、「ここと、ここと、ここが爆裂しています。でも、これ以外は大丈夫です」と言うので思わず笑ってしまいました。じゃあ、この悪いところだけ直せばいいんですね、ということになりました。
実際にどうなのか、という検証のために健全だと思われる箇所を試験的にはつり出してみたら、まったく錆びていませんでした。鉄筋の断面も全然減っていない。試しに試験場に持っていって鉄筋を引っ張ってみたんですが、新品とまったく同じ値が得られました。
我々が短い期間に知り得た修復のための知識は、実に多様で、そのどれもが建築の分野で知られていないというのは驚きでした。大変な手間とコストがかかるので、諦めてしまったために継承されなかったことなのかもしれません。選択肢が増えたということは、大変良かったと思います。
建築は機能がすべてではない
コンクリート建築の経年変化によって、これからこうしたケースがどんどん増えると思います。そういう意味からも見学の方はとても多いのです。良くやった、とほめてくださる方もいます。しかし、今回私たちが経験したような知識は、どこでどうやって手に入れればよいのでしょうか。
私には泣く泣く協力してくれる施工業者とか、ただで技術を提供してくれる建築研究所とかいった恵まれた環境があったから、実現できたのだと思います。まあ、オーナー2人が建築家ですから、技術的に乗り越えようとした。そうでない場合は、もっとデベロッパー的な解決を目指すんじゃないでしょうか。
似たような話で、死んだ親父が大切にしていたライカのカメラを、お袋が修理のためにカメラ屋さんに持っていったことがあります。するとニコニコして帰ってきて「こんなに新しい自動式のカメラに交換してくれたよ」と言うんですね。それを聞いて私は愕然としましたね。
この場合は、それまで無用の長物だったカメラが自分でも使える便利なモノと交換してもらったという喜びがあるんですよ。これは機能を問題にしている、ということです。建築の場合は機能もあるんだけれど、それだけじゃあない。建築の良さは、機能を超えているところにある。それなのに、今の建築は機能がなくなると壊されてしまう。それがちょっと悲しいところですね。
たとえばギリシャのパルテノン神殿に機能があるかというと全然ない。では、それが無用の長物かというと、私のような建築家にとっては最高の目標なんです。
求道会館を残そうというときに、
「お前は建築家であって宗教家でもないのに、こんな建物を残すといってどうするつもりなんだ」
と親族にずいぶん批判されました。しかし、なぜ残したいのか、ということをなかなか説明できなかったんです。そういうときに一族の長老であり、常観の愛弟子でもあった叔父が、
「求道会館は、我が師、近角常観の墓だ。墓は壊せない。残すべきだ」
と言ったんです。以来、これを残すということが親族の中できっちり位置づけできたんです。
何に使うか、どんな役に立つかということを話し出すと、議論百出で意志統一が図れなかったんだけれど、あの時代に活躍して死んだ常観の墓だ、だから子孫がこれを守ると言われたときに、私は救われました。それ以来私は「建築の一番理想的な形、究極の姿は墓である」とよく人に言うんです。墓さえ守っていれば、墓が次の世代に語るべきものを持って働きかけていくだろう。
そういう「もの」としての意味というのが、建築の一番深いところにあるんだろうなあ、と思うんですね。
市場経済と区分所有の落とし穴
日本における開発のメカニズムというのは、市場経済で動いていますよね。市場経済というのも、非常に短期的な価値で測られています。しかし土地や建物の流通の在り方というのは、本来こういうスタイルではなかった。たとえば、戦前には東京には大変貸家が多く、地主たちは借家経営するための資産として、まともな家を建てていました。
今は分譲ということが市場をリードしていて、不動産投資の大部分が分譲で占められている。マンションでは区分所有という方式で、建物を分割して所有することが主流になっています。
しかし求道学舎のように期限を区切って、一つの主体が権利を集約して行使するというやり方は、不動産が常に生き長らえるためには絶対必要なんですよ。だからそういうサイクルを持っていない所有の仕組みは、多分長生きしない。ですから区分所有に期限を設けなかったというのが、区分所有法の最大の欠陥です。これは結局、財産権をどんどん小口に分けていって、流動性がなくなる方向にいっているからなのです。
1970年代からマンションが建てられ始めて、30年が経ちました。30年経つと大変なことになる、ということは、みんな何となくわかってきた。少なくても設備は全部ダメらしいぞ、ということは言われ始めています。取り替えるときには、住んでいる人が全員合意してお金を出して直す。それからまた30年経つと今度は駆体が寿命になるらしい。そうなったときに、この国は一体どうなってしまうのか。日常生活の大半の時間を不毛な合意形成のために費やすことになるのでしょうか。
定期借地権は債権ではなく財産
日本の都市部では、地価がすごく上がります。だから修復して残すというよりも、壊して立て直すという方法が取られると思うんです。そのためもあってか、定期借地権というのが財産として非常に低く見られています。借地は所有とは見なされていないのが現状です。
しかし、定期借地権の創設にかかわった稲本洋之助先生(東京大学名誉教授)も「本当は定期所有権としたかった」とおっしゃっていました。
「借地という概念でやってしまったために足踏みしている。でも、その上に区分所有マンションを載せたら、それはもう定期所有権だよなあ」とおっしゃって、建物を上に載せることで期限付き区分所有権が実現できるなら、仕組みとして結構いけるのではないか、と。
現在問題視されている木造住宅密集地域では、土地利用が細分化され、いろんな機能が集まっている。車も入れないし、建て替えもできない。言ってみれば、これを立体化したのがマンションなんです。木造住宅密集地域の何倍もひどいことになっていくのです。
そうした破綻へのスパイラルが底を打って、逆向きになる可能性は、いったいあるのでしょうか。私はその鍵を、今回採用した求道学舎の仕組みが握っているのではないかと思っていますし、今後普及すると思っています。
建物部分は区分所有し、定期借地の上に載っているので期限付き所有権になるわけです。これは所有権ですから財産になります。きちんと評価される。期限付き所有権は使用価値として市場で売買されることが可能です。定期借地権は本来、債権ではなく物権として取り引きできるはずなんです。
現在流通している定期借地権マンションは、期間が終われば建物の寿命もそれまでという考えなので、終了間際には価格が暴落し、環境悪化が懸念されます。しかし求道学舎の方式では、期間が終わって権利者がいなくなったあとも建物は残るという前提です。一つの主体に権利が集約され、中古定借の次のサイクルの権利者を迎えることができます。日本ではこれが中古定借の第1号なので市場性も何もわからないわけですが、最後にババを引く人がいない画期的なシステムだと思います。
今注目されているサスティナブルの問題でも、所有のことはちょっと脇に置かれているように感じます。でも、そこのところを視野に入れないと、1000年も続く都市なんて、想像もできないですよね。
期限付き区分所有権で問われる建物の寿命
30年とか、60年の寿命しかない建物に、100年の定期所有権は設定できません。だから、建物の寿命が短いということが問題になるんですよ。イギリスの例でいえば、建物の寿命は300年とか400年のスケールで考えられているんです。まず、こういう伝統をつくる。でないと、この仕組みは成り立ちません。
求道学舎の場合も中途半端に改修するというのは、一番取ってはいけない選択だったということはわかっていました。たとえば、今1億円かけて直した。もう10年たっていろいろ不具合が出てきたときに、また1億円かかる。でも、そのときにはもうお金は借りられないですよね。そうなると、求道会館の運営に資金を回すという可能性もなくなってしまう。
それで定期借地権を、それもなるべく長い期間を設定しようと考えました。今回は62年という期間を設定したのですが、その間の品質保証をするということを目標にして、修復事業に着手しました。
実は、現在200年建築構想というのが盛んに議論されていて、この6月に発表されるということが新聞に載っていました。やっと政治の世界でもそのことに気づいてくれたか、という気持ちです。
ハウスメーカーは「邸別生産」ということに取り組んでいますが、これはユーザーが自分たちが自由に理想の家をつくることができた、そう思って満足できるシナリオを用意しているんです。
我々が提唱しているSIという仕組みも、SIにすることで欲望をユーザーに全部解放するわけじゃあないんですよ。買いたい人が、「これで本当に自分の理想の家づくりができた」と満足感を得るためにどうしたらいいのかということなんですよ。そのためのソフトの問題なんですよね。
100年後都市に住むことの展望
このままいくと、都市に人が住まなくなってスラム化します。都市がスラム化したからといって郊外に良い新都市ができるわけではなく、スクロール状態にただ広がっていく。発達した交通機関が、スクロール化した都市をつなぎ、なんとなく、焦点のない拡散した都市ができるんじゃないかな。
団塊ジュニアたちがどんどん都心に戻ってきているといわれていますが、そのほとんどが区分所有マンションですから、スラム化が先延ばしにされただけという気がします。SIで物理的に変えるチャンスがあれば、フィジカルな意味ではスラムにはならないと思うんですが、それ以外のものは、おそらく非常にスラム化していくでしょう。
ロンドンの場合も、一時期都心部がスラム化しましたが、少なくとも土地は女王陛下のものでしたから、建物や道路を新たにつくることで、都市が再生し得たわけです。日本はもっと悲惨です。建物だけでなく土地も細分化されているわけですから。
建物だって社会資産として整備すべきだ、という論調が生まれてくれば、社会資産として整備した街区というものに人が住めるようになって、100年の定期借地権をつけた権利が市場で高く売れるんじゃないでしょうか。そういう成功例ができれば、都市も変るはずです。
住宅開発を民間に任せっきりにする風潮は、明治の初年に銀座のレンガ街で実施された計画が悲劇的な結末を迎えたことが一因です。そのため住宅開発には経済原理が優先して、ビジョンが持ち込みにくくなったのかもしれません。
人が住んでこそ、都市なんです。
昔は、商売する人たちは都市に住んでいました。住まいの中でやる商売というのは健全ですよね。今は人は郊外に多く住んでいて、夜になれば、都市は非常に殺伐とした状況になっている。
また、町の人からすごく愛されている建物でも、所有者が壊すと決めたら壊されてしまうんです。みんなのものだと思っていたんだけれど、実は所有者のもので、誰も止められない。本来、都市というのはそういうものじゃないはずです。みんなの気持ちが集約できるような社会システムじゃないと。常に経済原理だけで動いている社会が、良い社会になるはずはありません。
やはり、そこに社会としての歯止めをかけないといけない。改修の度にいつも所有者が負担を担うというわけにはいかないでしょう。残すためには、システムを考えないとね。ただ一方的に残せ、残せというんじゃ、所有者だってつらいですよね。容積ボーナスなんかも、受け継ぐために必要なファンドとして活用すべきです。
六本木の国際文化会館(注5)が残ったのは、空中権を森ビルが買ったからです。そのお金で、国際文化会館を改修したんです。誰もが「これは残したい」と考える建物や環境を残すための社会システムには、当然、こういう発想があっていいんだと思います。
第2、第3の求道会館があったとしても、今のままなら壊されてしまいます。
それにしても100%中性化した建物を修繕して、いくら私や田村さんが大丈夫だと言い、データを開示したからといって、これをこの先62年の定借権を買って、自分の人生をここにかけようとされた方々は、本当に勇気がある。感服します。
(注5)国際文化会館
三菱財閥の岩崎邸跡地にアメリカのロックフェラー財団などからの援助で建てられた文化的学術的交流を目的とした財団。1952年、当時日本の第一線で活躍していた前川國男、坂倉準三、吉村順三という3名の建築家による共同設計。
【コンクリートの中性化に対応する土木の技術】
建築はいよいよダメとなったら壊せばいいが、トンネルとか護岸とか土木事業はそういう訳にはいかない。だから土木事業のために特化して開発されたそういう技術がたくさんあるということを、近角さんは今回の修復事業で知った。「独立行政法人 建築研究所」(元は建設省の管轄。建設の技術においては日本で最高の研究機関)が、近角さんの要望に応えてくれたという。
まずは「アルカリ性回復液」。しかし、表面はアルカリ化するのだけれど、鉄筋に到達させるためには20mmとか30mmとかの深さまで浸透させなくてはならない。そのために片側に電極を置いて、イオンを発生させて引っ張る。土木ではそうやって実践した例がある。そんな大がかりなことは不可能なので、「ポリマーセメントモルタル」をセットで使うことにする。
「ポリマーセメントモルタル」とは、中性のままコンクリートをパックして水と空気の侵入を遮断する、という方法。爆裂した箇所をはつった後に新しい鉄筋を入れて溶接し、その周辺すべてにアルカリ性回復液を染み込ませてから新しいコンクリートを詰めて、壁体ができた後にポリマーセメントモルタルでパックすれば完璧。まあ、歯医者の治療のようなものである。
それともう一つの新兵器が、求道学舎に無数にあった「ジャンカ」対策に活躍した吹きつけコンクリートという技術だ。1階にプラントを置いて、エアーホースでセメントと骨材(砂利)がプレミックスされたものを手元まで送り込む。するとノズルからプレミックスされた粉状の物体が吹き出して、もう1本水道水のホースがきていて、手元の空中で混ざるようになっている。水量は下の機械で適正量になるようにプログラムされていて、2本のホースから吹き出した水とプレミックスされた物体とが空中で混ざってコンクリートになり、ペタッと吹きつける。まさに「水の文化」である。
これは片面に型枠を置いて、反対側からコンクリートを吹きつけるのだが、吹きつけて張りついた瞬間へばりついて、だれてくることがこない。コールドジョイントもできないし、とにかく早い。1人でホースを持ちながら吹きつけていき、左官屋さんが2人で平らにならしていくうちに、見る見るできてしまうそうだ。
ジャンカとは豆板と書き、セメント分が抜けてしまって砂利だけになった部分をいう。ジャンカは、コンクリートと砂利がうまく混ざらないからできる。当時はネコ車で足場の上を渡って持っていったため、1階はよく打てていることが多いが、上の階に行くにつれて、ジャンカが起こりやすい。これは建築当時の技術力からいったら仕方がないことで、生コン車が来てコンクリートを打つ現代とは技術レベルが格段に違うのだそうだ。
上にいくにつれて型枠は開いていってしまうし、コールドジョイントといって、いったん乾いたコンクリートの上に新しいコンクリートが載ったときにうまく混ざらなくて亀裂が生じてしまう。また、当時は長押(なげし)などの仕上げ材を留めるために木レンガという木のかけらを入れていた。木レンガはコンクリートの断面の半分近くまで入っており、それが腐ってそこから雨水が侵入して鉄筋を腐食させていた。また型枠同士をジョイントするのに今は金属を使っているが、当時は木セパ(木製セパレート)という木の桟のようなものを型枠に打ちつけて固定しており、この木セパからも水が入っていた。
ジャンカや爆裂、コールドジョイント、木セパ、木レンガといった悪い箇所をどんどん取ったときは、「鳥かごみたいな鉄筋だけになってしまうのでは」と心配するほどの状態だったそうだ。
「定期借地権」とは
1992年(平成4)8月に施行された新借地借家法にもとづいて、供給側である地主が安心して借地を提供し得る環境を整備し、住宅宅地の供給を目的として生まれた。
この法律は主として土地を貸す側である地主の権利を守るものであり、今までは貸した土地が半永久的に返ってこなかったり、立ち退き料を支払わなければならなかったが、新法では公正証書等にするため期間(50年以上)を限定できる。また、期間の延長はなく契約完了時に土地は確実に返還され、その際地主が立ち退き料を支払う必要はない。
一方、借りる側は、契約時に土地代の20〜30%程度の保証金を支払わなければならないが、土地を購入するよりは資金計画にゆとりができるため、広い土地を借りることができる。契約期間中は相続、転売、賃貸もでき、保証金も契約完了時に全額返還される。ただし、契約完了時には更地にして返還しなければならず、上に建てた物件の解体費用が必要になってくる。当然「借地」なので保証金とは別に地代を払い続けなければならない。
「区分所有権」とは
独立した住居・店舗・事務所または倉庫その他の建物としての用途に供することが可能な、数個の部分で構成された1棟の建物を、各部分ごとに所有すること。
この場合の権利には専有部分と共用部分とがあり、共用部分は原則として区分所有者全員の共有となり、共有持分は各者が所有する専有部分の床面積の割合による。また、区分所有者全員で管理組合を設立し、マンションの管理、運営にあたらなければならず、維持、管理していくための費用を負担する。
さらに経年変化とともにさまざまな修繕や補修の必要が生じるため、屋上の防水塗装のやり直しや、外壁の塗り替えといった大規模な修繕については、別に基金を積み立てておくことが多く、これを一般に「計画修繕積立金」あるいは「大規模修繕積立金」と呼ぶ。毎月積み立てる金額も、原則として共有持分割合によって計算されるが、規約で別に定めることもできる。
なお、2002年の法改正で、集会において区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、建物を取り壊し、かつ建物の敷地もしくはその一部の土地、または建物の敷地の全部、もしくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議をすることができるようになった。