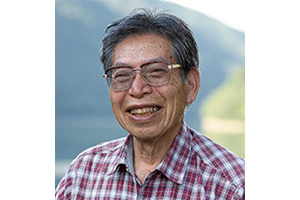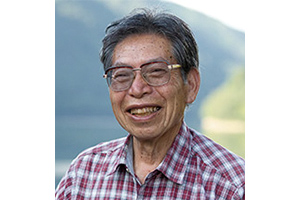機関誌『水の文化』26号
新江戸シナリオの可能性
ポスト温暖化の世紀をクールに
-
編集部
科学的予測とバックキャスティング
「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」の報告がまとめられ、21世紀末の平均気温が1980年から1999年に比べ2.4〜6.4℃上昇する可能性があると、政策策定者向けレポートに盛り込まれた。各国とも1995年の京都議定書の約束を粛々と守らねばならないが、当の日本の温室効果ガス排出量は、基準年の1990年に比べ2005年は8.1%増えた。京都議定書の約束なら6%マイナスにする約束だったのに、である。
このまま温室効果ガスが増えるとどうなるのか。各機関で多くの予測がなされている。IPCC第四次報告による「90年と比べて6.4℃平均気温が上がる」という悲観的予測では「多くの生きものが絶滅する」「食物の採れる量が減る」などショッキングな言葉が並んでいた。これは、過去の趨勢を将来に反映させた科学的予測で、「現状を踏まえた予測 forecasting」だ。
ところが多くの環境団体は、このような予測に危惧を感じ始めている。なぜなら、予測結果というものは、どうしてもその時々の政治経済の影響を受けやすいからだ。事実はどうであれ、「ある業界に甘い」「先進国に都合が良い」などというバイアスがかかる。
そこで、スウェーデンの環境NGOナチュラル・ステップが唱え始めたのが「バックキャスティング(backcasting)」という手法だ。最初に未来の望ましい社会像を定め、それを実現するために、なすべきことを遡って予測しようというものだ。「今できること」から始めることにより、とかく環境目標が達成されずに多くのコストを浪費してしまうことが多い環境予測・対策の分野に、「目標とすべき夢の社会論」を導入しようというわけである。
国立環境研究所を中心につくられた『2050日本低炭素社会シナリオ:温室効果ガス70%削減可能性検討』(2007年2月)も、この手法を使い「CO2を1990年に比べ70%削減する技術的なポテンシャルが存在する」と謳っている。
50年後のあるべき社会をシナリオとして仮定して、それが実現するためのエネルギー選択、効率などを算出したもので、「夢の社会」を導入している点は評価されるものといえる。
100年後の夢
編集部は、温暖化がきっかけとなって、人々が抱く100年後の社会予想・夢に関心を持った。
100年後ともなれば、「科学的な予測の正確さ」よりも、「こうなってほしい夢」のほうに意味がある。
ところが、実際に出回っているいろいろな予測を読むと、数量データの扱いはかなり厳密に行なわれている割りに、社会変動などのシナリオ、つまりソフトな要素はざっぱくな印象を受ける。例えばIPCCで想定されたシナリオも4つの因子、
A「経済高度成長を重視」
B「環境保全を重視」
1「グローバリゼーションが進む」
2「地域化が進む」
を組み合わせたもので、未来予測をするという大雑把なタイプ分けになっている。
このシナリオは、世界中の研究者が個々に行なっていた研究を集め、タイプ分けすることで作成されたそうだから、これでも一歩前進と思わなくてはいけないのだが、それにしても、そのシナリオの実現性や社会とのかかわりが、あまり意識されていないようなのだ。
社会的要因にもできるだけ配慮した予想を行なおうとすれば、夢のもとになる現実社会への洞察の深さがどうしても必要になる。ましてや、バックキャスティングなら、なおさらだ。
江戸社会システムイメージ
そのような思いから、今号では各分野の専門家にそれぞれの立場から未来を予想し、夢を語っていただいた。すると100年後のモデルイメージとして、「江戸時代」を挙げる人が何人もいたのである。
確かに江戸時代は、「循環型社会のモデル」とか「自然と人間がうまく共存していた時代」「分権と自治の時代」として見直されている。しかし一方では、福沢諭吉が「身分制度は親の仇でござる」と述べたような窮屈な世の中でもあった。
人の寿命も短かった。「人生わずか五十年」とうたった織田信長よりも、江戸の庶民はさらに短命だった。宗門改帳のデータから推測すると1600年ごろは30歳程度。ちなみに、平均寿命が50歳を越えたのは、戦後の1947年だった。人口はどうかといえば、1830年の天保年間では約3200万人と推測されている(以上は鬼頭宏さんの推測によっている)。つまり、多産多死短命社会の結果、この程度の人口に抑えられていたのだ。
しかも災害・冷害も多く、それがもとで数千人が死ぬような飢饉が起きるという、気候変動に影響を受けやすい時代だった。
これは江戸時代だけに限らない。明治に入っても、相変わらずその傾向は続いた。
例えば、ちょうど今から100年前の1907年(明治40)がどのような年であったか? この年の4月、国産ガソリン自動車「タクリー1号」が製作されている。日本の近代経済成長(1世紀以上の期間にわたって人口が持続的に増加し、それを上回る率をもって産出高が成長を続ける現象)の初期を飾る出来事があった年だ。この年の人口は約4700万人。ところが、この年の8月24日、関東地方は大暴風雨に見舞われ、流失家屋18万7499戸、死者459名、東京市内の浸水家屋6万4000戸と、現在の感覚からするととんでもない災害が起きている。
このような脆弱さを併せ持っていたのが、江戸時代に象徴される社会システムだったのだ。
人と自然のかかわり方についてはどうか。これが如実に表れるのが環境問題だが、江戸時代にだって公害問題はあった。ただ、その調停・解決の方法が現在と違い、地域に応じて是々非々でなされていたという点では、良い悪いは別として、曖昧さを許容する社会であったということができよう。
温暖化は警鐘の一つ
多くの科学的レポートが地球温暖化の悲観予測を唱えると、私たちの多くは「おそらく本当なのだろうな」と思う。しかし、自分の行動となると「わかっちゃいるけどやめられない」と、切迫感が生まれてこない。このような反応に陥る原因は、予測の正確さなどではなく、ソフトを「不確実」として軽視する科学的予測が本来的に持っている論理の立て方にあるのではないだろうか。要するに、気温が2℃上がることと3℃上がることの「暮らし」への影響度合いを、私たちにわかる言葉で話せないという、説得力の無さにある。
温暖化は先進国の近代経済成長と重なっている。人類の近代経済成長が地球環境にハイインパクトを与えた事実は、否定しようがない。だからこそ、それ以前の社会システムを「バックキャスティングの視点で100年後をつくる」ための指針として評価するのは大切なことだ。
その際の人類の立ち位置は、ヒトというたった1種類の生物が、短期間にここまで地球環境にハイインパクトを与えて許される理由が見出せない、ということだ。そこには国境も民族の違いもない。
今、私たちは「経験したことのない科学的予測をもとに対策をたてる」という、初めての体験に直面している。未知のことには深い政策的想像力が働きにくく、社会的合意も得にくい。
例えば「温室効果ガス排出抑制」対策は自明の理だが、経済的見地に立つ少子化対策、持続的見地に立つ国土開発などが、果たして相互に整合性を取ることができる問題なのかといった点も、不確実な中に埋没している。
方法論としてバックキャスティングに効果が見出せるとはいうものの、「未来の望ましい社会像」、つまり目標とすべき100年後の夢は、案外描きにくい。それは、現実に享受している便利さや現段階での常識・システムを抜きにして、100年後を捉えることが難しいからだ。
新江戸シナリオ
国立社会保障・人口問題研究所が2006年に公表した2100年の推計人口(参考値)は、中位推計で約6400万人、低位推計で約4600万人。低位推計だと102年前の1905年(明治38)に戻る計算だ。いわば、近代経済成長が始まった時代、CO2が急激に上昇し始める前の時代の人口である。
江戸時代にまるごと戻れるわけがないことは、百も承知だ。しかし、人口趨勢は江戸社会システムのころに戻りつつあり、江戸社会システムの時代には地球環境が温暖化の影響を受けない範囲で、持続的に循環型システムが機能していたことは間違いない。
予測の正確さを競うよりも、目指すべき社会像を明確にしたほうが生産的に思えるし、その道具として「江戸シナリオ」を使うのは効果がありそうだ。
江戸の社会システムは、これまで「進歩の一段階として乗り越えられるべき時代」として見られてきた。しかし、未来に向けた予測と対策を実現するための道具として、この時代をきちんと評価することは賢明な歴史活用法といえる。
グローバル化と脆弱さと曖昧さが共存する「新江戸シナリオ」と捉えれば、なかなか魅力的ではないか。
山折哲雄さんは『日本文明とは何か―パスク・ヤポニカの可能性―』(角川書店2004)の中で、平安時代の350年、江戸時代の250年という持続された「平和」を再評価し、なぜ実現可能であったのか、を問うている。ヨーロッパ、中国、インドの歴史を通観しても見られない、長い平和の歴史をひもとくことで、これから100年先の目標が見えてくるのではないか。
納得がいくシナリオが明るい未来を実現しようと掲げれば、人々は元気になる。明るさは、予想もしない革新を生む原動力だ。古今東西、悲観的なイノベーターなどいなかった。ならば、正確な予測を競って憂いを深めるのではなく、クリエイティブなシナリオでクールに社会を変える。実効的な温暖化対策とは、そういうものだろう。