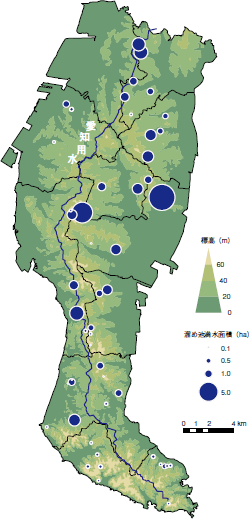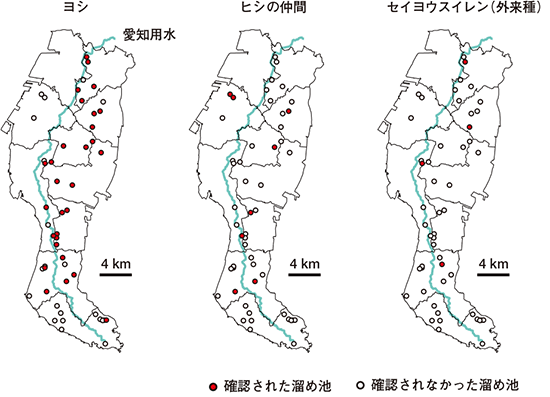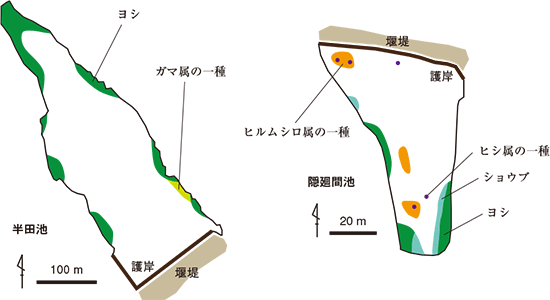機関誌『水の文化』36号
多様な生きものを育む水辺
保全意識を喚起するきっかけとは

写真:「なごや 野の花」
-

-
名古屋大学グローバルCOEプログラム COE研究員
富田 啓介 (とみた けいすけ)さん -
1980年愛知県半田市生まれ。1999年信州大学農学部森林科学科入学、翌年中退し、2000年名古屋大学文学部入学、地理学を専攻し卒業。2009年同大学大学院・環境学研究科・社会環境学専攻・地理学講座・博士後期課程を修了。博士(地理学)。
2009年8月より名古屋大学大学院環境学研究科研究員、同10月より現職。都市近郊に広がる丘陵地の自然・植生について広く関心を持ち、湧水湿地の植生発達、シラタマホシクサの生育環境、溜め池の植生などを研究テーマとする。2010年より、知多半島の生態系ネットワーク形成に向けた検討会構成員として、計画の検討を行なっている。
2010年(平成22)10月11〜29日に愛知県・名古屋で「生物の多様性に関する条約(Convention on Biological Diversity)のCOP10」(注1)が開催される。
この影響で、生物多様性に俄然注目が集まっているが「大切に守っていかなくてはならない」という趣旨には誰しも賛成するものの、産業構造の変化などによって脅かされている現状に対して、一般人である私たちが日々の暮らしの中で何をしたらいいのか、といった「解」は見えてこない。 そこで地生態学の立場から、知多半島の水辺の植生と人とのかかわりを研究している、名古屋大学環境学研究科グローバルCOE 研究員 富田啓介さんにフィールドを案内していただきながら、保全意識を喚起する方法などをうかがった。
(注1)COP
締約国会議(Conference of the Parties)のことで、「生物の多様性に関する条約のCOP10」は、生物多様性の保全は、ラムサール条約やワシントン条約などの特定の地域、種の保全の取り組みだけでは図ることができないとして、新たな包括的な枠組みとして提案された条約について、締約国が協議する第10回目の会議である。ちなみに第1回会議は、1994年(平成6)にバハマのナッソーで行なわれた。
地生態学
地理学というのは、地表面における現象すべてを扱う学問である。
地理と聞くと、地形や地質を研究する学問を思い浮かべてしまうが、文化地理学とか民俗地理学、歴史地理学という領域では、地域に入り込んで聞き取りをしたり、古文書を読んだりもするという。
また、関東の大学では、地理が理学部にあるところが多いようだが、名古屋から西の大学では、どちらかというと地理は文学部にある。最初に地理学の教室ができたのが、東京大学と京都大学だったらしく、そのときからの伝統といわれているとか。
実際には、地理学は地表面における現象であれば何でも扱えるので、理学部にあっても文学部にあっても、どちらでも構わないのだそうだ。
富田さんが専攻しているのは地生態学で、地形など地表の物理的なことと、植物や動物といった生物とのかかわりを研究する領域をいう。
生物の中でも、特に植物の分布を調べて他地域との比較を行なっている。現在取り組んでいるのは、里山の生態を視野に置き、溜め池や湧水湿地などでの植物の分布を調べることで、生態系と人とのかかわりを検証しているという。
溜め池も湿地も、人の手が入っている場所。そこでの分布の差異(場所の違い)や年代での差異を調べることで、人間の影響を計ることができる。例えば戦後禿げ山だったところが現状では豊かな森になっている、といった違いから、何の影響でそのような結果がもたらされたのかを知ることができる。
現在、大変問題視されている外来植物も、人の管理の範囲内であれば、これほどまでに問題が大きくはならなかったという。だから、「今の状況は『人と植物のかかわりが薄れた結果引き起こされた』ということができる」と富田さん。
富田さんがこういうことに興味を持ったのは、もともと植物が好きだったということもあるが、中学生ぐらいのときに『なごや野の花』(エフエー出版 1990)という写真集を図書館で見つけたことが大きな動機となったそうだ。
この本は、名古屋市内の野草を撮影した写真集。当時、富田さんは「名古屋市は都会」というイメージを持っていたため、100種類以上の草花を見て、こんなにたくさんの植物があることに、ちょっとビックリしたという。
「それで、名古屋にこんなにあるんなら、知多半島にはもっとあるんじゃないか、と思って、自転車であっちこっち見て回るようになったんです」
自然が残っているように思える知多のほうが、植物が多いかというとそんなことはなく、名古屋にあって知多にないものもあった。こういうことに気づきながら見ていくと、見て歩くのが楽しくなって、毎週のように出かけているうちに「こういう場所にはこんなものがあるんだ」ということもわかってきた。
つまり場所によって生態に違いがあることが面白い、と思ったのだ。このことが、やがて地理に結びついていく。普通はそこで生物学のほうに進んだりすると思うのだが、実は富田さんは理系の科目が大の苦手。それで、名古屋大学文学部に進学し、地理学を専攻することにした。
地元を探査
知多半島をフィールドにしているのは、知多が面白いからというよりは、自分が住んでいる場所を掘り下げてみたいから。もしも別の所に生まれ育ったとしたら、やはりそこをフィールドにしていたんじゃないか、と富田さん。
でも、そういうことを言うと「それは学問的な興味に基づいていない」と、大学の先生に怒られるらしい。
学問には全体の体系がある。過去に確立した論文などの文献をベースにして、そこに新しい問題をつけ加えていくというのが、学問の進展に寄与することになる。だから、富田さんみたいに自分の住んでいる所にパッと行って「こうなっていました」というのは、大枠として存在する体系にとって意味がないと見なされてしまうんだそうだ。
ある意味、アカデミックな世界は閉鎖的なのかもしれない。一本の道があって、それの先を目指さないといけない。単に、自分の興味に基づいてやっていても認められないのだ。
逆に学芸員なら、地域に密着した研究ができる。ただし、そういう研究を中央の学会で発表しても、あまり評価を受けることがないそうだ。
だから、富田さんが今やっている湧水湿地の研究も、「ただこうなっていました」というのではなく、「現在、湿地の研究の流れというのはこういうようにするべきだ。そうでないと湿地の研究というのは大成できない。だから、私はここの部分の問題をこのように研究する」と掘り下げていかないと認められない。
ただ、そういう風に考えを深めていくと、世界が広がって見えてくるのは事実。学問の世界に入ってよかったと思うのは、こういう方法で幅広く世界を見られるようになったことかもしれない、と富田さんは言う。
知多半島の溜め池
知多半島には正式に記録があるだけで1300カ所の溜め池がある。富田さんはその内の50カ所で、継続的に植生を調べている。
知多では、昔、溜め池をたくさん持っている家は貧乏な家で、少ない家はお金持ち、と言われていたそうだ。水を得られる条件の良い土地を持っていれば、溜め池がそれほどなくても済んだからだ、と言ったおじいさんがいたという。皿池と呼ばれるほど貯水量が少ない池では、条件の悪い土地ほど溜め池が幾つもないといけないから、数が多くなるということもあったのだろう。
溜め池周辺の生物層に関しては、だいたい1980年(昭和55)以降の記録しか残っていない。それも溜め池全体についての記録があるわけではなく、ある人が「この池が面白そうだな」とピンポイントで調べたデータが、自治体史や溜め池の自然研究会史などに残されているに過ぎない。
魚になると、もう少し遡って1950年(昭和25)ぐらいからの記録が残っている。溜め池自体の形の変遷などは、江戸時代の絵地図にも残されているから、今の私たちでも知ることができる。
COP10の影響で、生物多様性が取り沙汰されているが、農業離れが進み、農地が宅地化する中で、全部の溜め池を今までどおりに保全するというのは無理なことかもしれない、と富田さん。
「溜め池の使われ方自体が、昔とは違ってしまっているわけですから、ゾーニングした上で選別を行なう必要があります。『この池は現在多様性が担保されていないから、守っていく池だ』とか『この池は開発されても止むなし』というように選別していく上で、判断の根拠となる事前調査の必要性を感じます」
知多半島の地勢
知多半島を地質的にいうと、北と南で大きく性質が違う。北は常滑層群、南知多町から美浜町あたりは師崎層群と呼ばれている。
師崎層群は2000万〜1500万年前の海底に堆積した地層。だから、今でも海の生きものの化石がたくさん見つかっている。常滑層群は、約700万〜200万年前に知多北部を含む東海地方一帯にできた堆積盆地に堆積した地層。
このように、知多半島では南側が北より高く、より古い地層からできているのである。
知多に広がるなだらかな丘陵は、常滑層群がもたらしたもので、粘土層と砂層とが交互に重なっている。粘土層はあちこちに露出していて、これが常滑焼きの原料となった。常滑だけでなく岩滑(やなべ)といった地名に使われる「滑」という字は、ぬたぬたした状態を表わすといわれており、まさに粘土層を指していたのだと思われる。
師崎層群は硬い地質なので、山が削られずに残った。国営農地開発事業の農地にも見られる頁岩(けつがん)なども、師崎層群の特徴的な地質である。
常滑層群の砂層は、保水能力が低い。また、高く残った師崎層群では、降雨はすぐに海へと流れてしまうために、水を得にくい土地柄が形成された。
粘土質の層は水を通さず、砂の層は水を通す。だから地質の影響で、場所によって水が出てくる所がある。ちょろちょろっと出てきた水が谷に集まってくるので、そういう所に溜め池がつくられたというわけだ。
数値ではわからない、溜め池の個性
現在、愛知県でも環境全体をみて、生態系のネットワークをつくろうという動きがある。それに対して富田さんは、
「どうしても数字で判断する傾向があります。しかし、数字だけではなくて、一つひとつの池の個性をよく見て、判断していく方法をとらないとうまくいかないんじゃないか、という感触を持ちました」
と言う。また、個性を認めるために、細かい気配りが欠かせないとも言う。
「もちろん数値化できるものは数値化する必要があります。しかし、例えば集水域にどれぐらいの森林があるからこれだけの生物が生息できる、という考えで計画をつくったりしますが、そう単純にはいえないことも多いのです。
森林でもドングリが実るコナラの森と、松林では違うし、同じ松林でも小さな木と、よく育った木とでは、条件が異なる。こういうことも、まずはきちんと調べる必要がある。
もっと言うと、〈質〉。質が浮き出てくるような数値化の手法が求められています。
それをするためには、1回見て『ここはこういう所だ』と決めつけるのではなく、時間を追って、何度も通い、観測することが求められます。
そうやって足繁く通い、そこの〈質〉をよく知っているのは、やはり地元の方なんです。そういう方に話をうかがい、昔ながらの知恵というのを現代的に見直してみることは大変重要です」
求められる、多様な視野
今、富田さんは豊田市の矢並湿地の研究をしている。ここの昔から現代までの人とのかかわりを見ていくのだが、湿地の中まで入って草を刈ったとか、周りの山が禿げ山で木を植えたとかいう話を地元の昔を知る方々からうかがったそうだ。しかし、実際に保全計画を立てる人たちが、その情報に接しているかというと、必ずしも充分ではなかった。
やはり、こういう過去の環境もふまえた上で、保全計画を立てれば、「多少、中に入って草を刈っても大丈夫なんだ」ということがわかってくる。こういう経験から富田さんは、時間をかけた細かい調査が、溜め池に関しても必要なのかな、と思っている。
環境保全にも難しいところがあって、虫が好きな人は虫のことばかり考えてしまうし、植物が好きな人は植物ばかり考えてしまう。「この木を伐ったら、虫がいなくなる」「でも、伐らないと鳥が通れない」というように、あちらを立てればこちらが立たず、ということはよくあることだ。そういうときは、実際に元にあった自然の姿を真剣に考えていかないと答えは出せない。ちょっと見ただけではわからないことがあるのである。
見て、感じて、触れる
生態系への関心を持ってもらうためには、やはり触れる機会を増やすこと。しかし、いきなり山や川に行きましょう、といっても難しいことがある。そういうときには、博物館が良い役割を果たせると思う、と富田さんは言う。興味を喚起するような展示など、工夫次第でいろいろな可能性が広がるだろう。
しかし、実際には、そういう場所に足を踏み入れることにアレルギーがある人がいる。博物館の展示の仕方にも問題があって、学問的になり過ぎるから敬遠されるのかもしれない、と富田さん。
まずは「こんなに面白い場所があるんだ」と感覚的に好きになってもらうことが、大事。頭の中に入れる〈勉強〉というよりも、身体で感じることが先。そういう体験をしてから、フィールドに出ると、もっと楽しめるんではないだろうか。
富田さんのやっている研究を、里山林を思い浮かべて考えてみよう。
それがどういう場所にあったかとか、どういうメンテナンスをしてきたかという要素を加味しながら、森林の在り方や植物の種類を見ていく。もともとあった原生林を、再生しながら利用した過程でできたのが里山だ。このように植生と人とのかかわりは切っても切れない関係にあるから、背後にある条件を探ることは里山の植生を探るのに有効なのである。
里山の森林だけに限らず、土手の草地とかも見て、人がどのように手を入れるとどういう植生になって、手を入れなくなるとどうなるか、といったことも調べている。
そこには土地自体の「個性」もある。人があまり手を入れなくなっても、里山の性格が維持される場所と、すぐに原生林のような状態に戻ってしまう場所という差異が、実際には表われてくる。同じように働きかけても、違う結果になるのは、やはりその土地にある「個性」と考えることができる。だから地質とか地形も合わせて見ていくことが大切だ。
こうしたことを追っていこうとすると、観察に長い時間がかかる。古い資料を探したり、お年寄りから昔の話をうかがったりするのは、長いスパンで観察するのと同じ効果を得ることになる。50年ぐらいのスパンでは、航空写真や衛星写真もあり、そういうものもうまく利用しているそうだ。
暮らしにつなげる
富田さんが目指しているのは、研究していることを普通の人の暮らしにつなげていくような活動。地元企業が地域の生態系を学ぼうと開催しているイベントに協力したりするのも、そういう気持ちからである。
ところが残念なことに、そういうことはアカデミックな世界からは、本筋から外れた活動だとみなされてしまうこともある。農学部や工学部などの応用分野ではそうでもないが、基礎研究をやっている研究分野では、まだその傾向が強いのだという。
逆に参加する市民の人たちも、大学から人が来る、というと「何か小難しい話をするんではないか」と身構えてしまうようだ。これからは互いがもう少し理解を深めて、歩み寄れるようになったらいいと思う、と富田さんは願っている。
「研究のための研究だけしていたのでは、みんなに納得してもらえなくなるんじゃないでしょうか。基礎研究の分野でも『こういうことがわかるようになるために、こういう研究をしています』と説明して、一般の人から理解と賛同が得られるようにしていくことも、必要とされていくように感じます。
私もあちこちでお話しさせていただく機会があるんですが、『地域の溜め池にこんな稀少植物が残っているんですよ』と言うと、『こんなに身近な場所に、そんな貴重なものがあるんですね』とみなさん関心を持ってくれます。そこにそういう生きものが生息している、という基本的な事柄さえ、地元でも知らない人のほうが多いのが現状なのです。
三河のほうの溜め池で、ワニガメがいると問題になっていると聞きました。ブラックバスやアカミミガメ(通称ミドリガメ)などの外来生物が放されて繁殖が進むことで、固有種の絶滅などが深刻になっています。こういうことも、知らないでやってしまったことから始まっています。
生態系の保全、と一言で言うのは簡単ですが、やはり知ってもらって、関心が湧かないと、守ろうという気持ちが生まれません。知ってもらうための活動をコツコツ続けていきたいですね」
富田さんの子供時代には、身近に豊かな植生を見ることで「見て」「感じて」「触れる」ことが体験できた。本やテレビの知識だけではなく、生きた体験からさまざまな学びが得られるはずだ。
普通の人がわかる言葉で語り、関心を引き寄せられるフィールドへ連れて行ってくれる富田さんは、そうした学びを広めていく、いわば伝道師的な存在。これからも多くの人に、足下に在る多様性を気づかせていってほしい。