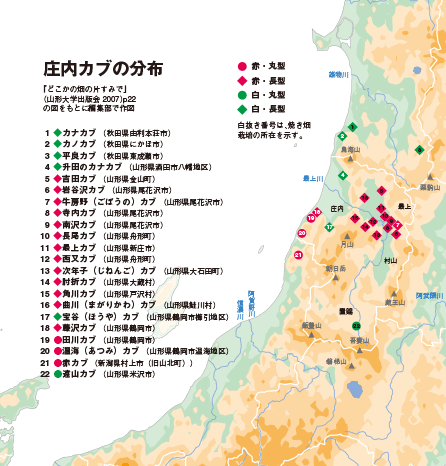機関誌『水の文化』43号
種を守る人々
山形に息づく在来作物の多様性

山形在来作物研究会編で刊行された2冊。(山形大学出版会 右:2007 左:2010)
農学博士の青葉高先生が遺した「野菜の在来品種は生きた文化財」という言葉と、KJ法を考案した川喜田二郎先生の提唱した「〈野外科学〉的アプローチの重要性」に後押しされ、在来作物研究に取り組んできた江頭宏昌さん。在来作物を継承するのはなぜか、という問いが発せられるとき、地域の先人たちが、何を、どう食べてきたかということを伝えていく〈メディア〉としての価値、というのもたくさんの答えの中の一つではないでしょうか。
-

-
山形大学農学部 食料生命環境学科 准教授 農学博士
江頭 宏昌(えがしら ひろあき)さん -
1964年福岡県北九州市に生まれる。1990年京都大学大学院農学研究科修了。同年に山形大学農学部助手。2001年より現職。「在来野菜は地域の文化財であり、その保存が急務である」という故・青葉高博士の考えに共鳴し、山形県内の在来作物を中心にその研究や保存活動などに積極的に取り組んでいる。山形在来作物研究会会長、エダマメ研究会幹事。専門は植物遺伝資源学。
主な著書に、『植物遺伝育種学実験法』(分担執筆/朝倉書店 1995)、『どこかの畑の片すみで』(共著/山形大学出版会 2007)、『伝統食の未来』(共著/ドメス出版 2009)、『おしゃべりな畑』(共著/山形大学出版会 2010)、『ユーラシア農耕史第5巻農耕の変遷と環境問題』(共著/臨川書店 2010)『地球環境学事典』(共著/弘文堂 2010)、『焼畑の環境学』(共著/思文閣 2011)、『火と食』(共著/ドメス出版 2012)ほか
在来作物ってなんだ
在来作物には定義がありません。敢えて言えば「ある地域で、世代を超えて、栽培者によって種苗の保存が続けられ、特定の用途に供されてきた作物」。これからお話しする在来野菜は、その在来作物の一部です。
在来作物は、単に種苗が守られてきたというだけではありません。採種方法、さし木や接ぎ木、株分けの仕方、芋類の保存方法といった種苗保存のノウハウから、在来野菜であれば、いつ、どのように食べるかに至るまで、さまざまな技術と文化が一緒に残されてきたのです。
山形県には現在どれぐらいの在来野菜があると思いますか。足掛け5年かけて〈山形在来作物研究会〉が確認したものは、実に150品目以上に上ります。その中には栽培の歴史が300年以上になるものも含まれています。
青葉高(たかし)(注1)という先生が山形大学農学部に在籍されて、野菜生産の研究をされていたんですが、青葉先生は「野菜の在来品種は生きた文化財である」という言葉を著書『ものと人間の文化史43 野菜—在来品種の系譜』(法政大学出版局 1981)に残されています。
(注1)青葉高(1916〜1999年)
農学博士。専攻は蔬菜園芸学。
埼玉県生まれ。1937年千葉高等園芸学校卒業。1964年山形大学農学部教授。1976年千葉大学園芸学部教授に就任し、1982年退官。勲三等旭日中綬章受章。主な著書に、『北国の野菜風土誌』(東北出版企画 1976)、『ものと人間の文化史43 野菜ー在来品種の系譜』(法政大学出版局 1981)、『青葉高 著作選2 野菜の日本史』(八坂書房 2000)ほか。
在来野菜の魅力
鶴岡にあるイタリアンレストラン〈アル・ケッチアーノ〉を経営する奥田政行シェフは、在来野菜に光を当てた人です。私はお客さんとして、たまに食べに行くという間柄でした。
あるとき「なんでアル・ケッチアーノをつくったの」と聞いたところ、地元の食材の良さを地元の多くの人に知ってもらうためにつくったんだという答えが返ってきました。店の名前は、「(こんなおいしいものが)あったんだね」という庄内弁なんだということを聞きました。
ちょうど、そのころに私も在来作物を調査しようとした矢先だったので、その後、二人で一緒に農家を回ったりしました。そんな二人三脚が始まったのが、2002年(平成14)。奥田さんは私より6歳年下ですから、当時33歳でした。奥田さんが地域のコミュニティ雑誌『庄内小僧』の連載の話を持ってきたのが、その翌年です。7月ごろから月1回のペースで、「在来作物探訪記」という連載を始めました。私が農家の方の苦労話やその作物の特性などを書き、奥田さんは新しい食べ方を考案する、という企画でした。
1年間、12回連載したんですが、始めた当初は在来野菜という言葉も認知されていないし、そもそも「どうしてそんな古くさい野菜を今さら取り上げるのか」と言われたこともありました。しかも、そういう野菜はつくったからといってお金にもならないし、どこに価値があるんだ、というのが世の中の風潮でした。
ところが奥田さんがつくり出す料理は、毎回、画期的だった。在来作物って、癖があるんですよ。苦いとか、辛いとか、えぐ味があるとか。普通だったら湯がいてえぐ味を減らすとか、ソースの味で食べやすくしがちですが、奥田さんは逆に野菜の特徴を生かす(癖をおいしさに変える)料理をつくった。それで奥田さんの店にどんどんお客さんが集まるようになって、在来野菜という言葉も定着していきました。
そうこうしているうちに、2005年(平成17)山形新聞社から連載のお声が掛かりました。これは隔週でしたから、大変でした。取材に行こうと思ったら1日丸々開けなくてはいけませんし、アポ取りやなんやらで、ものすごく時間が取られるのです。〈山形在来作物研究会〉の幹事や県の職員の人にも手伝ってもらい、私が書いたのは5〜6割ぐらい。全部で100回、4年やりました。取材先も、まあ、山形にはそれぐらいはあるだろうとは思っていましたが、まだ取材しなくちゃいけないものを数えたら30や40はある。山形って、すごい在来作物の宝庫なんだ、と改めて実感しました。
山形新聞での連載を一番喜んでくれたのは、野菜を継承してきた農家の人たちでした。それまで、たった一人で種子を守ってきて、自分は大事だと思っているんだけれど、変わった人だと思われたり、金にもならんものを栽培してなどと、言われたりしたかもしれません。積極的に評価してくれる人がほとんどいなかったでしょうから。
在来作物に至るまでの道
私が在来作物に取り組むようになったのは、それほど前のことではありません。
学生時代は、育種学を専攻し、イネの草丈をコントロールする遺伝的な仕組みを研究しました。山形大学に赴任してから約10年間はトマトの品種改良のための基礎的な研究をしていました。
栽培種が持たない野生トマトの新たな形質を、交配で導入するという研究です。普通に交配してもそういう形質はできない、というか、雑種は生まれないんです。生殖を隔離している機構があって、同じトマトの中でも隔離の度合いが大きい種は雑種がつくりにくいんです。
普通は果実の中で退化してしまう種を採り出して、試験管内で丁寧に培養してやると芽が出て個体になっていきます。私が取り組んでいた野生種は特に雑種ができにくかったので、そういう方法で雑種を取り出していました。バイオテクノロジーを応用した品種改良の研究をやっていたわけです。それで学位をとって一区切りついたのが1999年(平成11)のことです。
だだちゃ豆とか温海(あつみ)カブとか、山形に来て、ここにしかない個性豊かな野菜の在来品種を食べたときに、バイオテクノロジーの研究を続けながら「いつかはこういう在来作物を研究したい」と思うようになっていたのです。次に何をテーマにしようかとなったときに、地元に根差した研究をやりたいと思って出合ったのが、青葉先生の『北国の野菜風土誌』という本でした。
青葉先生も大阪のほうから赴任されて、だだちゃ豆や温海カブと出合った。1960年代の日本にまだ焼畑農業が残っているということにもたいそう驚かれたようですね。『北国の野菜風土誌』をまとめられた直後の1976年(昭和51)に、山形大学から千葉大学へ転出されました。
この本はもう絶版ですが、野菜に関する名著です。在来野菜というのが、地域の歴史や文化を物語る生き証人であることを、最初に示した本だと思います。
私は、この本を読んで「野菜は生きた文化財である」という考え方に触れたときに、本当に衝撃を受けたんです。
実は、私が在来作物にたどり着くには、もう一つ伏線があります。1994年(平成6)ころなんですが、KJ法(注2)を考案した川喜田二郎先生(注3)の著書から大きな示唆を受けた出来事がありました。
川喜田先生は『創造と伝統 人間の深奥と民主主義の根元を探る』(祥伝社 1993)という著書に、現代の問題点がどこにあって、何をどうすればいいかということを書かれました。それを読んだときに、私が大学時代に学んできたものは科学のほんの一部分だったのだ、ということが理解できたんです。
車に乗るようになれば、足腰が弱る。ワープロが普及すれば、漢字を忘れるといったように、科学技術の進歩はしばしば人間の能力とトレードオフの関係にあります。「科学技術の目指すところは、ひょっとして人間が何もしなくてもすべて自動で効率よく自分の欲求を満たせる世界をつくることだったのだろうか」と、私は自然科学の研究者を志しながらも思うことがあったのですが、その疑問が川喜田先生の著書で氷解したのです。
私たちがふだん科学といっているのは、18〜19世紀に欧米で創り出された西洋科学といわれるもので、川喜田先生は〈実験科学〉と呼んでいます。既にある仮説について実験を踏み台にして、トップダウン的に客観的に正しいか正しくないかを検証するのはすごく得意なんですが、現場の混沌とした状況から本質に近づくための仮説をつくり出す、つまり何を検証すればいいのかわからない状況で、全体感を体系化して問題を浮き彫りにするということは不得意なんです。
川喜田先生は、現場の混沌とした状況からボトムアップ的に問題を抽出する方法を〈野外科学〉、人間が今まで文献として残してきた知見を考察して新たな考えを導き出すギリシャ、ローマ時代から行なわれてきた手法を〈書斎科学〉と命名しています。
本当は〈野外科学〉と〈実験科学〉と〈書斎科学〉の三つをそろえてアプローチしないと問題は解決しないんですが、人間は有史以来、きちんとした〈野外科学〉的方法論をつくらずにきてしまったというんです。〈野外科学〉的手法というのは、まさに川喜田先生のKJ法そのものなんです。それで私は〈野外科学〉的アプローチの基礎を、研修に参加して学びました。
(注2)KJ法
川喜田二郎が、フィールドワークで収集した膨大なデータをまとめるために考案した手法。1967年(昭和42)に発表された。データをカードに記述し、カードを系統ごとに整理し、図解することで、方向性を導く助けとする。またチームで研究を進めたり、創造的問題解決に効果的な方法だと考えてまとめた研修方法は、『発想法』(1967年)として出版された。それ以降、川喜田が企業研修や琵琶湖移動大学などで指導を行ない、普及を図った。
(注3)川喜田二郎(1920〜2009年)
地理学者、文化人類学者。
三重県出身。京都帝国大学文学部地理学科卒業。文学士。大阪市立大学助教授、東京工業大学教授を経て川喜田研究所を設立。
京都帝国大学時代は、今西錦司、梅棹忠夫、吉良竜夫らと共に探検隊を結成し、ミクロネシア南部のカロリン諸島や中国・大興安嶺山脈を探検。のちにネパールを研究フィールドとするようになった。日本ネパール協会会長。財団法人日本エスペラント学会顧問。
ミッションと在来作物が合致
1994年(平成6)に自分は一体、今何をやりたいのかということをKJ法で組み立ててみたら、三つのことがわかりました。
一つは、足が地に着いた仕事がしたいということ。
もう一つは、世代から世代へ何かを伝える仕事がしたいということ。今はおじいちゃんおばあちゃんがお孫さんからパソコンなどの使い方を聞くことはあっても、逆に漬け物のつくり方のように生活の知恵を教えるということはほとんどなくなってしまった。しかし、それはここ20〜30年の出来事です。たったそれだけの期間の激変のために、何十年も何百年も伝わってきたこの地域で生きていくための知恵や知識の断絶が起こって伝わらなくなっている。私にとって、これは非常に由々しきことに思えてきたんです。
三つ目には、どうせやるなら市民と一緒に、力を結集して何かをやりたい、と思いました。
約6年間、問題意識はずっとあったんですが、具体的に何をやればいいのか見えてこなかった。自分は育種学というバックグラウンドを持っていて、ずっと植物資源にかかわってきたんだけれど、何をしたらいいか全然わからなかった。2000年(平成12)に「在来の野菜は生きた文化財」という言葉に出合い、私は本当に「これだ」と思い、在来の野菜をテーマにすると自分が本当にやりたい三つのことができるかもしれないと思ったのです。
また、川喜田先生のフィールドワークの手法を学んで、聞き取ったものを組み立てて文章にしたり、いくつかの柱を立てて研究するという基本的なことを学べたお蔭で、自分にとっては未知の在来作物研究を始めよう、と思えるようになったのです。そのとき、すでに庄内に来てから10年が経っていました。
一代雑種F1のこと
最近、よく話題に上るF1という種があります。F1とはFirst Filial Generation(雑種第一代)の略で、異なった遺伝子を持つ両親を掛け合わせてできた子孫(雑種)の第一世代を指す言葉です。メンデルのエンドウ豆の実験を覚えていますか。雑種第一世代には均一の形質が表われるのです。
両親のいずれよりも優れた形質が表われる場合を雑種強勢といい、逆に劣る場合には雑種弱勢といいます。現在の品種改良は雑種強勢の性質を利用して、より有用な形質を伸ばすように行なわれ、一代雑種や一代交配種などと呼ばれています。
なぜそんなことをするかというと、優秀性と均一性を併せ持つ品種をつくることができるからです。例えば、たくさん収穫できる、形や大きさがそろっている、日持ちが良い、病気に強い、味がよい、といった形質が表われるように雑種交配が行なわれます。
しかし、F1が良いことずくめなわけではありません。F1の子世代F2以降は、形質が兄弟間でそろわなくなり、両親より劣る形質も表われてきますから、品種改良の効果は一代限りで消えてしまうのです。そのため、常に優れた形質の作物を得るためには、毎回F1を購入しなくてはなりません。
逆に、在来作物は固定種とも呼ばれ、F1ほど兄弟間で形質がそろいませんが、世代を経ても、ある程度遺伝形質が安定しています。
その地域で栽培した個体の中から、良いと思う個体が、F2どころか何十年、何百年と選抜されながらつくられてきた品種だからです。
経済性では測れない価値
在来作物は、それ自体が残ることも大切ですが、要は料理して食べる人がいないと守っていかれないんですよ。庄内地方には市場出荷するものとしてではなく、細々と家内消費で守られてきた在来作物もあります。お金だけの価値で在来作物を継承させようとしたら、なかなか難しいですね。こんなに割の合わない仕事はありませんから。
山形県白鷹町でつくられている畔藤(くろふじ)キュウリという30〜35cmもある細長いキュウリがあるんですが、味が濃くてシャリシャリした食感でおいしいんです。
昭和30年代(1955〜)に、短くて艶々したF1の青キュウリが出回り始めました。F1のキュウリが1本4円で売れたのに対して畔藤キュウリは50銭。価格は8分の1です。しかも収穫量が非常に少ない。F1キュウリだと葉っぱ1枚に対して一つずつ実がつくのですが、畔藤キュウリは葉っぱ8枚に対して一つぐらいしかつかない。収穫期間はF1キュウリだと2カ月近く採れるけれど、畔藤キュウリは3週間で終わってしまう。うどんこ病にかかって茎や葉っぱがだんだん弱ってきて終わってしまうんです。出荷して流通商品になるには厳しいけれど、自分の家で食べる分には、おいしいから残るんですよ。
しかし農家の人にとっては、金にもならないものをつくり続けることには「恥ずかしい」という感覚がある。それでも「自分が良いと正直に思えるものをつくり続けたい」と考えてきた人が、山形にはこんなにたくさんいるんです。それがすごいことだと思います。
生産や流通に携わる人々が、その保存と特産品化を目指すために独自の条件を設けるようになって、京野菜や加賀野菜は特に伝統野菜と呼ばれるようになりました。〈京の伝統野菜〉は絶滅したものも含めて41品目(2003年〈平成15〉4月現在)、加賀野菜は「1945年(昭和20)以前から、主に金沢で栽培され続けている野菜」という定義で15品目が認定されています。
京野菜や加賀野菜は、すっかりブランド化しています。ブランド化も確かに生き残るための一つの戦略だとは思います。しかし一つ問題なのは、地元の人でさえなかなか買えなくなってしまうことです。お金持ちの人や料亭などでしか食べられない野菜になってしまうんです。
山形ではブランド化ではなく、地元の人がふだんの食卓で食べ続け、余剰が出れば地域外にお福分けのようにして出していく、というのが本来の在り方ではないか、と考えてきました。
例えば、東京の人が食べておいしかったからといって山形にやって来たときに、山形では地元の大部分の人が誰もその野菜を食べていなかったらどうでしょうか。
もちろん地元への衆知と同時に、ブランド化も全否定するわけではなく、そういうことができる野菜はやっていく。モノを売るんじゃなくて、それがあることでお客さんを呼べる、というところにつなげる。だだちゃ豆解禁日をつくって、他所から大勢の人に食べに来てもらうとか。それだけの力が、在来作物にはあると思います。
例として〈宝谷蕪主会(ほうやかぶぬしのかい)〉があります。宝谷カブは、鶴岡市宝谷地区で古くから栽培されてきた細長い青首大根のような形をした在来野菜。畑山丑之助さんという生産者がたった一人で栽培しているだけの宝谷カブを応援しようと、地元の蛸井弘さんが蕪主を募って、2007年(平成19)から5年間蕪主の会が開かれました。
カブは頑張って手間をかけて栽培・収穫し、洗ってヒゲ根を取ったり出荷調整したものを売っても、多分、よくて1kg200円くらいでしょう。そのカブを食べたいと、多いときで、北海道、仙台、名古屋、京都などからお客さんが来たんですよ。こんなことは、商業品種のカブであれば、どんなに上手に栽培したとしても絶対に起こりえないことじゃないかと思うんです。だから、ここにしかないモノの価値、特に在来野菜は人を集わせる魅力というのがあると思うんです。その力を、私は〈宝谷蕪主会〉で実感させてもらいました。
在来野菜と焼畑
実はカブは典型的な焼畑作物です。山形に在来種のカブがたくさん残っているのは、寒冷な中山間地では、米の収穫量が不安定だった時代が長かったからではないでしょうか。実際に、カブの栽培は米の豊凶の目処が立つ8月のお盆以降でも間に合いますから、救荒作物としても役立ってきたのです。
植物生産にとって必要な養分は、窒素、リン酸、カリです。
窒素は化石燃料を使って空気中の窒素から合成してつくります。
リン酸、カリは日本に資源がないので、100%輸入です。その資源は偏在していて、中国は肥料資源を持っている国なんですが、豊かになったこともあって、あまり輸出しない方向になっています。国際価格はどんどん上がっていて、2005年(平成17)と比較して2.5倍以上に高騰しています。
肥料一つとっても、そういう状況。でも、昔の人は化学肥料に頼って農業をやってきたわけではありません。永続的に営んできた農業は、どうやって地力を維持してきたのでしょうか。それは焼畑か有機農業です。
焼畑は、窒素、リン酸、カリを最も簡単に得る方法です。
窒素とリン酸に関しては、もともと生物の体内には大量に含まれている成分なのですが、大きな分子の状態では作物が利用することはできません。火入れでできる木灰の主成分はカリウムですし、その熱でタンパク質が分解されてアンモニアの形の窒素源に、有機体のリン酸化合物が分解されてリン酸になるというように、焼畑で火入れして小さな分子に分解し、根から吸収できるようにします。
もう一つは、微生物に分解してもらう方法。それが有機農業です。微生物がじっくり時間をかけて分解して、窒素、リン酸、カリを植物が利用できるイオンにします。
微生物を使うと養分ができるのに長い時間がかかりますが、焼畑だと火入れ直後にできてしまいます。しかも、同時に病害虫を防除しますから農薬が不要。木材伐採時に出る大量の枝葉の残渣(ざんさ)がなくなるので、速やかに植林する準備を整えるのにも役立ちます。しかも、食べたらおいしい。一挙両得じゃなくて、一挙で何得もある。
焼畑の火入れには、ものすごい技術があります。上から下に焼いていくと火の勢いがほどほどに抑えられて山火事防止上、安全だということもありますけれど、ゆっくり燃えるので肥料がよくできます。逆だと一瞬にして焼けるけれど、山の斜面の表面を火が走るように焼け、土の中まで熱が伝わらないから肥料がうまくできないのです。
炎は山の斜面に対して水平に一直線の形で下ろしていくのですが、炎のラインの両端がやや早めに下りるように、つまり炎がアーチ型になるように下ろしてくると、周囲への延焼が防止できるといいます。炎の力学とでもいったらいいでしょうか。上下左右に防火帯を切ってあるので、燃えるものがある下へ下へ、そしてアーチの中心へと炎は進み、一番下に到達すると何もしなくても炎は消えます。これは伝承と経験から得られた高度な技術なんです。
生業として数十戸以上の集落単位で焼畑が残っているのは、全国的に見ても、鶴岡ぐらいじゃないかと思います。
在来作物を残す理由
現代社会では、種子の価値がなくなって、単なる商材の一つになってしまいました。
かつて種子は、自分の命をつなぐために一番大切なものだったはずです。またかつての農民は、普段から生活に必要なさまざまな作物の種子を収集・栽培し、何年もより良い種子を残す選抜を行ないながら自慢の種子をそろえていたと思います。
そうした種子を誰かに渡すというのは、信頼の証しでもあったのです。旅先でお世話になった人にお礼の印として種子を置いていったというのはよく聞く話です。山形県酒田市飛鳥には、北前船で上方からやってきた商人が地元の人に水をもらったお礼として赤ネギの種子を置いていったといういわれが残っていて、今もその赤ネギ栽培が盛んです。
「種子が嫁入り道具になった」という話もよく聞かれます。今の山形市蔵王堀田地区に南陽市からお嫁入りした方が、ふるさとで栽培されていたカボチャの種を持ってきて、それが今では蔵王カボチャという在来種になっています。
真室川町には勘次郎キュウリという白いキュウリがあるんですが、それも代々母から娘に受け継がれてきました。
このように種子が人と人をつないできたということを、今はほとんどの人が知りません。
庄内の温海地区(鶴岡市)の早田(わさだ)瓜は、大正時代からつくり続けられていました。味はプリンスメロンみたいに甘いのです。早田瓜をつくっていた本間さんご夫妻は、私が尋ねたときにはお元気だったのですが、残念ながらお二人とも他界されてしまいました。生前に早田瓜の種子をいただいていたので、山形大学農学部の農場で栽培・保存していますが、多くの場合、栽培している人が亡くなると、種も一緒になくなってしまうんです。
なんとかして種子とその作物を利用する文化の消失を防ぎたい、というのが〈山形在来作物研究会〉の当初の目的でもあります。会誌を『SEED』と名づけたのも、在来作物の種子と、その文化を次代へと引き継いでいきたい、という想いからです。
かつての種屋さんは、信頼のおける農家と提携して種を採ってもらって、その店オリジナルの種をいっぱいそろえていました。種を買いに来た人には、栽培方法や調理・加工の仕方まで指導していました。つまり販売だけではなく、その作物が持っている文化を伝えるために機能していたのです。
〈ひょうごの在来種保存会〉の山根成人(しげひと)さんという人が紹介してくれたのですが、姫路市内の米田種苗という種屋さんは今でもそういう仕事をしておられるそうです。鶴岡にも江戸時代から200年以上にわたって、温海カブの焼畑農家と種子を取引している種苗店があります。有機農業作業グループでは、種の交換会もやっているようですね。栽培だけでなく、自家採種という行為は、種の大切さを思い出させてくれます。
在来作物をなぜ残さなくてはならないのか、という理屈を、私も研究者として考え続けてきました。
その答えの一つとして、私たちの暮らしというのがすべて石油や化石燃料に依存しているという危機感から説明できると思います。肥料もそうですし、ビニールマルチやビニールハウスなどに使う農業資材もそうですし、運搬も耕運機も田植え機もすべて化石燃料に依存しています。「今日から石油がありません」と言われたら、私たちの食べるものはなくなります。そういう中でこういった伝統的な野菜とか伝統農法には、石油を使わなかった時代に生きていた地域の知恵があるんですね。
在来作物の存在意義というのは、地域の先人たちがこういうものを食べてきたということを伝えていくメディアとしての価値にあると思うんです。私たちが在来作物を〈生きた文化財〉と呼ぶのは、そういうところにあり、自家用でもいいから、メディアとして継承していくことが大事なんじゃないかな、と思います。
お正月のTV番組でも放送されていましたので日本の食文化を世界遺産にというプロジェクトがあるのはご存じかと思います。それと並行して今、鶴岡市は食文化創造都市づくりを目指していて、鶴岡食文化創造都市推進協議会が立ち上がりました。食文化創造都市というのは、ユネスコが推進する創造都市ネットワーク(注4)の一分野です。
鶴岡食文化創造都市推進協議会では、山形の在来作物を次の世代に継承するためのレシピ集を出版したりしています。
(注4)創造都市ネットワーク
Creative Cities Network
グローバル化の進展により固有文化の消失が危惧される中で、文化の多様性を保持するとともに、世界各地の文化産業が潜在的に有している可能性を、都市間の戦略的連携により最大限に発揮させるための枠組みが必要、との考えの下、2004年(平成16)ユネスコが創設したプロジェクト。文学、映画、音楽、クラフト&フォークアート、メディアアート、デザイン、食文化の7分野において特色があると認められた都市を認定し、ネットワークを構築する。
多様である価値
かつて日本全国各地には地域固有の野菜や果物や穀物の品種がたくさんありました。農家は生活に必要なものの大半を、お金を出して買うのではなく、できる限り自家採種しながらそこで栽培できるさまざまな作物をつくってきました。
また、冷害や干ばつなどの気象災害に備えて、例えば主食のイネなら全滅の危険を分散するために、一軒の農家だけでも早生から晩生まで10品種以上を栽培していましたし、万一、イネが凶作に見舞われてもカブやソバのような冷害に強く短期間に栽培・収穫できる作物も併せて栽培しました。味噌や漬け物、山菜やキノコの塩蔵物、トチの実なども常備して飢饉に備えたのです。
戦後、ベビーブームの大量需要に応えるために大量生産、大量流通、大量消費の時代が到来したことで、全国流通に耐える、より高品質な品種が育種されて全国共通の品種が流通するようになって、地方品種は次第に姿を消していきました。消費者にとっては日本全国どこへ行っても類似の品種になり、地方色豊かな野菜を楽しむ機会が減ってしまったわけです。
また金銭経済が浸透すると、農家はイネでも野菜でも市場が買ってくれる限られた品種しか栽培できなくなりました。しかも作物が豊作になると、価格が暴落して、収益の確保が難しくなることもありました。
一代雑種F1のような近代品種は、品種内の個体間の特性が高度にそろっていて、一斉に花が咲いて、一斉に収穫できる。そのお蔭で機械作業が可能になり、栽培コストを下げることができるとともに、私たちは作物の形態や品質も安定したものを入手することができます。コシヒカリが食べたいと思って買ったお米が、買うたびに予想とまったく違う味だったということがないのは、そうした近代品種を栽培しているお蔭だともいえます。
一方、在来品種はF1に比べれば開花期も収穫期もそろいが悪くなります。収穫物の形態や品質も多少ばらつく。江戸時代の農家が農薬を使わずにイネを栽培できたのは、品種内の個体間に形質のバラツキがあったからだと思います。例えば、田んぼの中でイネのある個体が〈いもち病〉にかかったとします。しかし、隣の個体はその病菌への抵抗性があったりして、すぐには罹病しません。
ところが近代品種のように、品種内の個体間の遺伝的性質が極めて斉一になると、集団が同じ反応を示すので、あっと言う間に全個体に病気が広がってしまうのです。だから、近代品種は、どうしても農薬散布などをして作物を保護してやる必要が生じるのです。
在来種というのは遺伝的な多様性を内在しているから、適応性に幅があるんです。他所の土地に持っていっても少しは適応したものができる。そういう種採りをしていくと、徐々にその土地の環境に適応した固定品種ができます。
在来種の多様性には、適応してきた地域の風土や人々の嗜好、利用の文化などに関する膨大な魅力的な情報が詰まっています。いったん絶やしてしまったら、どんなに高度なバイオテクノロジーを使っても、まったく同じ品種をつくり出すことは二度とできません。
多くの在来作物が残っている山形でも、栽培に携わっているのは高齢者がほとんど。その価値を多くの人に知っていただき、存亡の危機をどうしたら回避できるか、一緒に考えていきたいと思います。
(取材:2012年7月17日)
カラトリイモの生産者
添津(そえづ)カラトリ部会のみなさん(東田川郡庄内町添津)
庄内町の添津は、土が粘土質で、地下水位が高い土地柄のお蔭で芋がおいしくできるの。この会は「日本一、おいしいカラトリイモをつくって次世代に伝えたい」という思いで、青年部が1981年(昭和56)に立ち上げました。
羽黒山に至る羽黒山道路を観光バスが通るもんで、以前は街道沿いに幟旗をずらっと並べて、観光の目玉として販売キャンペーンを行なったりしました。
会をつくった当初は26名いたんですが、だんだん年を取ってきて現在は8名ほどがつくり続けています。今は農協を通じて出荷しています。各自の畑でつくって、種芋も自分で採って、共同の地下室で保存します。
今は全部で1万2000本。それを8名のばあちゃんがつくるんだから、結構、重労働ですよ。夏になるとすぐ緑の絨毯になっちゃうから、草取りが大変。
カラトリイモというのは学術上の系統名で、地元では「からどりいも」とか、略して「からどり」と濁って発音されます。別名で、ズイキ芋、じき芋ともいわれています。全国的には、ズイキというと茎のことだけれど、ここでは芋をそう呼びます。えぐみが少ないので、親芋、小芋、葉柄、葉も食べられます。茎は干せば保存が利くので、納豆汁に入れたり。芋は保存が難しいですが、今は冷凍庫があるので皮をきれいに剥いて生のまま冷凍すれば大丈夫。
最上川のやや南側を境として、北側が青茎(緑色)、南側が赤茎。その境界線がもう何十年も一度も変わらずに続いています。添津では青茎の芋です。やはりあちらの人は赤じゃないと食べられない、私らは青じゃないと食べられない、長年親しんだ味でそうなっているんでしょう。
カラトリイモは年越しに欠かせないんです。年越しには、季節の野菜を味噌で煮たご馳走があるんですが、その中に必ずカラトリ芋を入れるので、これがないと正月が迎えられない。他所に行った子どもたちにも送ってやります。だから、各家庭で自家用としてつくられてきました。
子どものころから慣れ親しんでいると、孫たちも「おいしい」と言って食べてくれるけれど家で料理しないと敬遠されるようになる。それで子どもや若い人たちも食べてくれるように、新しい料理法を考えたりしています。給食に提供したりもしています。
カラトリイモは水苗代でつくる芋です。苗をつくり終えたあとの水苗代でカラトリイモをつくっていたんです。苗を採ってしまうと水苗代には利用価値がないもんで、肥料分もまだたくさん残っているし、それを利用したんです。
昭和30年代以降は農業用ハウスで苗をつくるようになったから、カラトリイモも畑地でつくるようになりました。湛水栽培と畑地とでは味が全然違うけれど、作業することからいえば畑地のほうが楽なの。
4月20日過ぎに播種して、5月半ばに定植、収穫は10月です。連作していると茎がだんだん伸びなくなって、芋も小さくなる。やっぱり親が立派でないと、子どもも立派にならないのね。
私は畑地でつくった芋でも、種芋は流し水に入れて一日置く。それから陰干ししておくと、傷みにくいです。
みんな、自分のとこの芋が一番おいしいと思ってつくっている。添津の湧き水は月山からの恵み。その水で育った芋は格別だという想いがありますよ。きめが細かくて、ねっとりしている。いくら口で説明してもわからないから、食べに来たほうがいいですよ。
江頭宏昌さんの解説
カラトリイモの記録は、1735年(享保20)の『羽州庄内領産物帳』に見られ、当時、既に庄内の産物であったことがうかがえます。ここでは「たうのいも からとり」と書いてあり、唐芋のこと。京野菜の一種エビイモと同じ系統のイモです。私の研究室で卒論を書いた小西由佳さんがDNAマーカーを使って関西から取り寄せた唐芋とカラトリイモを調べたところ、ごく近い関係にあることがわかりました。
湛水栽培は、亜熱帯や熱帯地域で行なわれるサトイモの栽培方法と同じです。イモだけでなく、栽培方法も一緒に伝わって、たまたま庄内地方に痕跡が残ったのかもしれない、と考えられます。
最近は畑地でつくられることが多いですが、種芋に残すものは湛水栽培する、という話を聞いたことがあります。保存性が格段に良いのだそうです。
種芋をきちんと残すことには、みなさん長年気を使っていて、台所のすぐに目が届く所に保管箱を置いて、毎日、霧吹きで水分を与えるとか、籾殻に包んで、という工夫をしています。暖かい所で温度変化が少ないようにしないとだめなんです。10度以上で保存しないと腐ってしまいます。だから、こんなに寒い所で270年以上つくり続けられてきたというのは、生産者の努力の賜物なんです。
外内島(とのじま)キュウリの生産者
-

上野 武さん(鶴岡市外内島)
明治の終わりか大正のはじめごろからつくっている、と聞いていますから、だいたい100年間はつくってきたと思います。
昔は鶴岡市の周辺は、全部、このキュウリをつくっていたんです。うちでもここ以外にも3カ所ぐらい畑がありました。朝日が上ると、陽射しが目に入ってキュウリを見落とすからか、朝日が上がらない内に採るために、子どもたちも手分けして手伝ったもんです。採り終わったら、もう一度見落としがないか見回るんですが、それでも見落としがあって、育ち過ぎて大きくなっちゃうんですよ。
私は専業農家ではなかったので、本格的につくるようになったのは仕事を退職してからで、もう7年になります。
やはり外内島キュウリじゃないと、という人もいてつくり続けていましたが、1株ぐらいしかつくっていなかったんですよ。もうやめようかな、と思っていたところに、在来野菜を使っての漬物づくりに力を入れる漬物店〈つけもの処 本長〉から「材料として使いたい」と頼まれるようになりました。それで、近所の人にも声をかけて栽培を続けています。遊びみたいなもんだけれど、小学校の3年生が総合学習の時間につくっていて、もう4年になります。
漬物店に卸す以前は、仲買人さんが来て集荷して、小売店に売っていました。出荷の基準は13cmからで、せいぜい15cmほどまでに出しますが、昔はもっと大きくなってから出荷していたという記憶があります。
3〜3m50cmの栽培棚を組んでツルを絡ませてつくります。今の人はみんなパイプで棚をつくりますが、うちでは粟島(新潟県村上市の岩船港から高速船で60分の離島)から持ってきている竹を使っています。森の木を間伐するときに伐っているそうで、安く手に入るから毎年補充しているんです。
とにかく病気に弱いキュウリです。ツルが旺盛に伸びて重なっちゃう所が蒸れて病気にかかりやすい。今の農薬は前日に施して24時間あけなさい、というものが多い。朝晩収穫するキュウリだから使えないんです。気温が低くて乾燥しているといいんですが、雨が降って気温が上がると途端に蒸れて病気が出ます。
5月の20日ごろ播種して、1カ月後ぐらいから収穫できるようになって、収穫期間はだいたい1カ月。40日間採れるということは滅多にありません。地所が30坪ほどありますが、そこで輪作しながら毎年場所を変えてつくっています。
今年は低いうちは雌花が咲かなくてね。採れないんじゃないかと心配していたんですが、途中まで伸びたら、急に咲き始めて安心しました。自然受粉なんですが、最近は蜜蜂がめっきりいなくなりましたね。雨が少なくて乾燥しましたから3回ぐらい水を撒いています。水っぽいキュウリだし、葉っぱも大きいから、水を欲しがるんでしょう。
外内島キュウリは、ちょっと苦いんですよ。一時期、その苦みが嫌われて消えていったんだと思います。でも最近は、ゴーヤなんかも人気ですから、苦みを気にしないようになりました。ところが最近、逆に苦くないのができるようになった。自分で種を採り続けているんですが、少しずつ性質が変わっていくんですね。
すぐに黄色くなって日持ちがしないのも消えていった理由でしょう。自分ちで食べる分は、新聞紙でくるっと巻いておくと少しはもちます。
収穫が終わったら根っこから引っこ抜いて整理するんですが、そのときまで熟させておいて種を採ります。種を採るのは、いっぱい実がなる株で、格好が良い実を残しておいて採ります。
実を割るとゼリー状の果肉に種が包まれていて、果肉をきれいに洗い流して乾燥させて保存します。発芽率がよくって、90%以上が発芽しますから、余計に種を採っておく必要がないんですよ。
やはり、つくる人が減っているのを盛り返すのは、かなり大変。産地の中には種を外に出さないところもありますが、私はつくってくれる人を増やしたいから、余分にたくさん蒔いておいて苗で分けることもありますし、種もどんどん分けています。
江頭宏昌さんの解説
キュウリはインドのヒマラヤの南山麓に起源するといわれていますが、そこから中国を経由して日本へ伝播したルートに北回り(いわゆる華北系キュウリ)と南回り(いわゆる華南系キュウリ)があります。華南系キュウリは黒イボ(果実表面のトゲが黒色のものをそう呼ぶ)で短日性(注)の形質を持つものが多く、華北系キュウリは今のF1キュウリと同様、白イボで長日性、シャキシャキしてサラダに向くものが多いです。
外内島キュウリは、鶴岡市外内島で生産が続けられている固定品種で、瑞々しく、皮が薄く、肉厚で、好ましい歯触りが特徴です。成熟すると尻や肩部から褐変しやすく、つる首側にやや苦味があります。苦味の成分は、ゴーヤと同類のククルビタシンです。
果実は長楕円、半白で首側3分の1程度が淡緑です。黒イボであることから華南系の血を引いていると思われますが、長日性で肉質が優れることから、華北系の特徴も備えています。華北系と華南系の雑種であろうと思われます。
外内島キュウリの来歴は不明で、江戸時代の古文書には登場しませんが、大正時代の里謡には登場するので、ざっと100年以上の歴史があると思われます。5年くらい前までは上野武さんを含めて2、3軒しか栽培していませんでしたが、ここ2年くらい、鶴岡市内で少しずつファンと栽培者が広がりつつあります。
(注)短日性と長日性
短日性とは、幼苗時に日長が短くないと雌花が咲かない(つまり果実がつかない)性質で、日本では2月ごろに播種しないと果実がつかないものもある。長日性の性質を持つものは、例えば5月上旬播種でも雌花がつき、収量が落ちない。