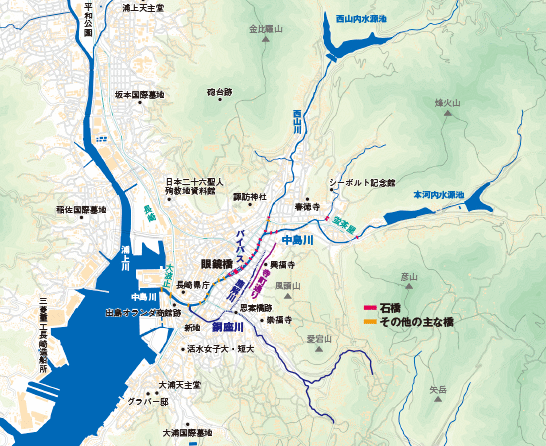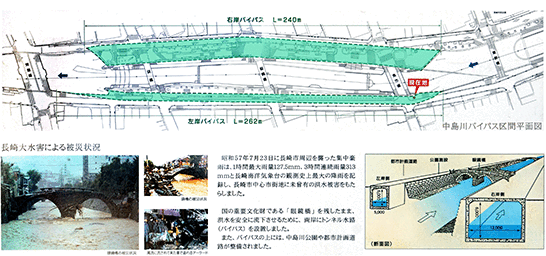機関誌『水の文化』47号
長崎・眼鏡橋復元の物語

眼鏡橋。石垣や石畳の遊歩道、沈下橋などのしつらえも、味わいのうち。
長崎大水害が起こって、30年以上が経過しました。九州から離れた地域でも、その悲惨な光景と地域の宝である眼鏡橋復元への取組みを覚えている人は多いのではないでしょうか。しかし、水害の原因やバイパス工事の妥当性をはじめ、その実態は断片的にしか伝わっていません。鎖国時代、全国で最も先進的な技術や情報が集まった国際都市長崎で、愛されてきた石橋群。その象徴である眼鏡橋復元に、川への愛着を取り戻す運動が果たした役割についてうかがいました。
-

-
まちづくりプランナー、環境芸術家
工学博士、技術士
片寄俊秀(かたよせ としひで)さん -
1938年生まれ。京都大学工学部建築学科卒業。1961年京都大学アフリカ類人猿学術調査隊設営担当としてタンガニーカ(現タンザニア)調査に参加。同大学院修了後、大阪府技師として千里ニュータウン開発事業等に従事。1970年転職して長崎総合科学大学(元・長崎造船大学)、関西学院大学総合政策学部教授を経て、大阪人間科学大学教授(2013年3月まで)。現在NPOほんまちラボまちづくり道場を主宰。主な著書に『ブワナトシの歌』(朝日新聞社 1973。羽仁進監督、渥美清主演で映画化)、『千里ニュータウンの研究』(産報出版 1979)、『ながさき巡歴』(日本放送出版協会 1982)、『スケッチ全国町並み見学』(岩波書店 1989)、『まちづくり道場へようこそ』(学芸出版社 2005)、『いいまちづくりが防災の基本』(イマジン出版 2007)ほか
山に囲まれた過密都市
長崎造船大学(現・長崎総合科学大学)建築学科の助教授として赴任し、初めて長崎市内の中島川を見たのは、1970年(昭和45)32歳のときです。
川はとにかく汚れていました。当時の我が国の都市河川はどこも悲惨な状況で、ちょうど合成洗剤が大量に使われるようになった時代で、川の水が泡立つような状態でした。ゴミは捨て放題で、臭くてたまらないようなドブ川だったのです。下水道も普及しておらず、家庭の雑排水が全部、川に流れ込んでいました。
その汚れた中島川の上に、1634年(寛永11)に架けられた〈眼鏡橋〉をはじめ、江戸時代に建造されたアーチ石橋が14橋もずらりと並んでいる様子は圧巻でした。
長崎という町は、海外(ポルトガルと中国)との交易のために無理やりつくられた町です。深い入り江の海に長く突き出した台地があり、長崎という地名の由来になったといわれますが、1571年(元亀2)長崎開港にあたり、ポルトガル人宣教師の主導の下に、まず6カ町がこの丘の上に建設されています。
1592年(天正20)には、丘の下を流れて長崎湾に注ぐ中島川沿いの干潟の埋め立てと田畑の市街化が進められて内町23町が、さらに1692年(元禄5)には外町が開かれて市街77町(丸山、寄合、出島を入れて80町とも)が確立しました。
開港当初は1500人ほどだった人口も、外町が開かれた元禄中期(1694〜1696年)には約6万5000人のピークに達し、その後若干減少して幕末に至ります。
山がちの地形を流れ下る急流の中島川が町の中心部に位置するというのは、水源が川沿いにあったこと(のちの民営水道 倉田水樋)と、貿易のための水運に川が利用されたことによります。
鎖国時代にはオランダと中国との対海外貿易の港として特権をほしいままにした長崎の繁栄は、まさに中島川を中心として形成されたのですが、それゆえ低い平地部に水害リスクを抱えた町という宿命がありました。
長崎大水害
私は大阪で行政技術者としてニュータウン造成の現場で働いていた経験がありましたから、流域面積の割に河川容量が小さい中島川の水害リスクが常に心に引っ掛かっていました。治水安全を上げるには、河川管理者の意思決定が必要と考え、いろいろ働きかけた結果ようやく1982年(昭和57)7月16日、大水害が起きるまさに1週間前に、県の担当部局との会合を持つことができました。
1973年(昭和48)に始まった中島川1万人大清掃運動や中島川まつりを通して、市民の関心が川へ向いてきたタイミングで、県もその気運に呼応して何とか腰を上げてくれた矢先でしたが、そこに大水害が長崎を襲ったのです。
梅雨末期の1982年7月23日の夕方、これまで経験したことのない物凄い集中豪雨がやってきて、しかも長時間続きました。長崎市の北に位置する西彼杵郡(にしそのぎぐん)長与町では午後7〜8時の1時間に187mmの雨量を観測し、これはいまだに我が国の歴代最高記録となっています。
午後8時過ぎに中島川が氾濫し、濁流は近くの商店街に、あっと言う間に流れ込みました。
走行中や駐車中の自動車が流されたり、車ごと生き埋めになったことも長崎大水害の特徴です。翌日、長崎県警が道路などから排除した車は市内だけで約500台。その後、掘り出した車は450台に上り、中から遺体が見つかった例もありました。長崎大水害は、クルマ社会化の進んだ時代の都市水害として、最初の実例となったのです。
復旧の実態は
この災害で中島川石橋群の内、6橋が流失、3橋が大破しました。災害のさなか、報道関係者は被害の大きかった都市周辺部に近づくことすらできず、都市中心部の報道で精いっぱいでしたから、世界に知られる被爆都市・長崎の被災地としての報道映像には、中島川の氾濫の光景ばかりが映し出されました。このため長崎豪雨災害イコール中島川の氾濫による被害と誤解され、県や旧・建設省が打ち出した石橋撤去の口実になったように思います。しかし実際には、亡くなった300人近くの9割は、周辺部の山手で起こった土石流や地滑りなど土砂系災害の犠牲者でした。
私は行政技術者であった経験から、大規模災害は、それ自体の被害に加えて、災害復旧、復興工事で町の風情が大きく破壊されることを知っていました。それで、これは何とか先手を打たねばならないと考え、被害のあった翌朝早く、かねて私淑していた高橋裕先生(東京大学名誉教授で河川工学者)のご自宅に思い切って電話をしました。先生のお言葉によると「中島川の眼鏡橋が壊れた。復元に立ち上がるから、すぐ来てくれ」と涙ながらに要請した、とのことです(高橋裕著『川と国土の危機』岩波新書 2012)。
大規模災害が発生すると、激甚災害特別補助事業の適用を受けて全額国庫負担で復旧工事ができます。それも災害発生から2週間以内に行政は手続きをとらねばならず、充分に吟味する時間がないのです。「石橋があったから、中島川があふれた。危険な石橋を撤去して近代的な自動車も通れる橋に架け替えたほうがいい」という意見が出る可能性が高いと予測して、行政に影響力をお持ちと勝手に考えて高橋先生を頼ったのですが、それほど面識もなかった私の願いに応えて、先生はいくつかの的確なアドバイスをくださいました。
この時点では人命が奪われたのは中島川が氾濫したから、と思われていましたから、一部の人からは、私が人命を軽視して石橋保存を訴えていると非難されたりもしました。
災害は、時間の経過とともに被害の様相が変わり、人々の受け止め方も揺れ動きます。私は被災者であると同時に、国土問題の研究者として、目先にとらわれず、まちづくりの正しい方向性をもって復旧復興にあたるべきであると行政に訴え、マスコミにも情報を発信し続けました。
「長崎大水害を考える」という私の投稿は、見開き2面にわたって8月1日の長崎新聞に掲載されました。この原稿は、救援と調査活動で疲れた体にムチ打って、停電のさなかに懸命に手書きし、私の家と市の中心部の間が土石流で通行止めになっていたため、山を越えてトンネルを歩いて新聞社に持ち込んだものです。この記事には、住宅の供給、災害の構造、斜面災害、河川氾濫、自動車と災害、中島川の復活、再生・観光長崎―という7項目の総合的な対策を盛り込みました。
この寄稿で意識したのは、恩師 西山夘三(注1)先生が敗戦と廃墟で国民の多くが打ちひしがれていた1946年(昭和21)に『新建築』に書かれた「新日本の建設」の壮大な論文です。規模も立場も違いますが、こういうときにこそ師の教えを果たさねば、という責務のようなものを感じて必死に書きました。
誤解は徐々に解けていき、テレビ局が主催する市民討論会が開かれるなど、次第に長崎の町の風情の保存を求める声が上がるようになりました。
(注1)西山夘三(1911〜1994年)
建築学者、都市計画家。京都大学名誉教授。生活実態の詳細な調査から住宅内の「食寝分離」を提唱し、住宅計画に応用。戦後の公営住宅の標準設計に影響を与えた。経済の高度成長期には、無謀な都市開発への警告と構想計画の必要性を説き、歴史的なまち並み保全とまちづくりへの住民参加をすすめた。
被害実態を明らかにする
一方で、市民活動の中島川を守る会と中島川まつり実行委員会は、早速、中島川復興委員会を発足させ、8月1日から延べ120人、680地点にも及ぶ浸水状況被害の調査を開始しました。
その結果、明らかになったのは
- 中島川とは別の川だった銅座川を、1954年(昭和29)の工事で十八銀行本店の所で中島川と一つにしてしまった。今回の浸水は、この旧河川沿いに起こった。
- このときの変流工事のために、もともと中島川より水位の低い鹿解川(ししときがわ)(寺町通りに並行して流れ、思案橋で銅座川に合流)の水の引きが一層悪くなり、磨屋(とぎや)小学校付近で市内最高水位2.67mを記録した。
9月3日、この調査結果を県庁で発表すると、大きな反響が起こりました。中心部での今回の浸水被害には、天災ではなく人災の要素が大きかったということが明らかになったからです。
11月3日には長崎から8人が上京し、東京の数寄屋橋で石橋復元を呼びかける署名活動を展開。これには〈よこはまかわを考える会〉や〈千葉県真間川の桜並木を守る会〉も駆けつけてくれました。
数寄屋橋での署名運動にたくさんの人が応援に来てくれたのは、横浜市役所の森清和(せいわ)(注2)さんの力に因るところが大きいのです。森さんは最初の著書『都市と川』(三木和郎のペンネームでの著作/農山漁村文化協会 1984)でも、私たちの活動を紹介してくれています。
森さんとの親交は、『環境文化』という雑誌に中島川での一連の活動を投稿したところ、記事を読んだ森さんが長崎まで訪ねて来られたところから始まります。「よこはまかわを考える会」の創設には、私も参加しました。こうして眼鏡橋保全は、地元長崎だけでなく、全国からも注目されるようになっていきました。
(注2)森清和(1942〜2004年)
横浜市環境科学研究所に所属しながら、よこはまかわを考える会、鶴見川を楽しくする会、全国水環境交流会など、多くの環境団体にかかわった水辺環境技術者。全国川の日ワークショップを創設。
現地保存に向かって
水害直後、県知事の諮問機関として〈長崎防災都市策定委員会〉が長崎出身で地域開発公団総裁の平田敬一郎さんの肝煎で設置されました。私は中島川を守る会の小川緑会長の代理でこの委員会に出席したのですが、県の意向をまとめる形で進められる会議で、当初は私の発言など聞く耳を持たぬという雰囲気でした。
しかし、会を重ねるうちに、市民の中から石橋保存を求める強い動きが出てきたこと、国の側にも文化庁がいち早く眼鏡橋の現地保存を主張し、建設省内部でも計画の見直しの方向が検討されたようです。裏で平田さんの後押しがあったか、また高橋先生のアドバイスもあったのか、そのあたりはわかりません。12月に入って、県側から突然、計画高水流量(注3)はそのままで、眼鏡橋現地保存の案が出されたのです。ただし、橋の両側にバイパスのトンネルをつくることが条件になりました。
私の考えとしては、より低い場所にある鹿解川に背後からの水が入るので、「中島川にバイパスをつくっても何の解決にもならない」と釈然としなかったのですが、高橋裕先生にご報告すると「やりましたね、片寄さん」と喜んでくださいました。よく考えてみると、決まっていた激甚災害特別補助事業を覆して文化財の現地保存がかなえられたというのは前代未聞のこと。奇跡が起こったというしかありません。
眼鏡橋の保全は、なぜかなえられたのでしょうか。被災後の一連の運動に先立って、早くも1970年代から川への市民の意識が甦るような活動を積み重ねていたことが、最大の要因だったように思います。
(注3)計画高水流量
河道を建設する場合に基本となる流量で、基本高水流量から各種洪水調節施設での洪水調節量を差し引いた結果として求められる河道を流れる流量。
きっかけは測量調査
中島川は原爆の直接的な打撃を受けていなかったので、江戸時代の石橋が14橋もずらりと並んで、その上を自動車が平気で通っていました。眼鏡橋は良く知られていましたが、他所者には驚くべき光景でした。
しかし、長崎大水害以前は、地元の人にとってはなんでもない日常風景で、汚れて臭いため、川に蓋をして駐車場にして、上には東京や大阪にも負けない高架道路をつくろうという提案が、市議会で真面目にやられていたぐらいです。
1964年(昭和39)、土地区画整理事業の一環として西川端に8mの車道が通るという事業が動き始めました。山門が計画道路にかかる光永寺から「参道は提供するが山門には手をつけないでほしい」という申し出があったのですが顧みられなかったため、当時の正木住職と壇信徒総代だった赤瀬守さんを中心に「車道ではなく中島川大遊歩道を」という運動が始められました。所得倍増論が打ち上げられ、車社会への転換を目指していた時代ですし、まだ住民運動とか環境活動などという言葉すらなかったころの、まさに先駆的な運動でした。
その後、私が赴任した大学に「石橋オタク」の学生が現われ、測量調査の指導を頼まれました。学生たちとともにむかつくような悪臭の中、一つひとつの石橋の実測調査をやりました。
その調査データは、のちに「中島川の石橋群」として長崎市の指定文化財になるときの基礎データとして役立ちましたし、赤瀬さんに大学で講演を依頼したことで、学生たちの調査活動と結びつき、「川沿いにはクルマのための道路ではなく人間のための遊歩道を」という〈中島川大遊歩道構想〉の実現を目指す、「市民+学生」の運動へと広がりました。
石橋を見ると、硬くて重いはずの石が虹のように軽やかに空に浮いている感じを受けます。調査しているうちに、私も石橋の魅力に取り憑かれ、やがて諫早(いさはや)市の土木技師だった山口祐造さんとも出会うことができました。
諫早にも眼鏡橋があって非常に堅牢だったために、1957年(昭和32)7月25日から28日にかけて降った豪雨のときに、橋桁に流木が引っ掛かって川がダムアップし、多数の死者を出す大災害となりました。
恨みの石橋を爆破せよという声もあった中で、諫早市長が文化財としての意義を認め、当時の文部省に掛け合って、重要文化財の指定を取り移設保存したのですが、それを担当したのが山口さんです。
以来、彼は石橋の魅力に取り憑かれ、九州各地に現存する石橋を訪ねて実測し、写真を撮影し、記録をつくりました。山口さんによると、長崎の眼鏡橋に始まる石橋は、中島川に20橋も架けられて、ここから九州各地に伝播したそうです。こうして山口さんは我々の石橋研究の師匠となりました。
川への関心がよみがえる
住民運動だけでなくて、汚い川の現状を具体的になんとかしなくては、という思いもありました。これには長崎青年会議所が動いてくれて〈中島川1万人大清掃運動〉を提唱し、我々も参加して1973年(昭和48)8月に実施。この大清掃運動には、本当に1万人ぐらいの人が集まりました。市民も川の汚れをとても気にしていたのですね。
掃除に加えて楽しみの要素が必要と考え、〈中島川まつり〉を発案して、学生たちとともに5月の連休の2日間で5万人を集める大イベントを成功させました。そうこうするうちに、市民の見方も変わり、川に目が向くようになりました。すると、不思議なことに川もだんだんきれいになっていったのです。中島川まつりは、12年も続きました。
「まつりのあとは、前よりきれいに」をスローガンに、毎回まつりの1週間前には市民参加の大掃除をし、掃除をしない人はまつりに出店できないというルールをつくって学生が取り仕切りました。
汚れた川から社会をみつめると、さまざまな矛盾が見事に浮かび上がることに気づき、大学の講義のフィールドを中島川にして学ぶやり方に変え、川をきれいにする研究、歴史的な景観の保全、観光の研究などを展開。「掃除に参加したりイベントの事務局をやったら成績に上乗せするぞ」とやりましたら、学生がものすごく熱心に動いて。面白かったですね。
シーボルトも龍馬も石橋群を足繁く渡ったわけで、いわば歴史の生き証人である中島川に「長崎の母なる川」というネーミングもしました。まつりは、提唱する大遊歩道のイメージを実感できる社会実験でしたが、その後、紆余曲折を経て、今では川沿いにつながった遊歩道ができ上がっています。
こうした活動で「中島川を守る会」は1979年(昭和54)第1回サントリー地域文化賞を受賞、日本河川協会賞など数々の賞をいただきました。
壊れてはつくり直す仕組み
石橋は、迫持(せりもち)(アーチ)の理論で支えられています。アーチ石橋の部材は、上が広くて下が狭い台形の石。その石を組み合わせていくと外に広がろうとする力がかかって、隣り合った石同士が支え合います。アーチの頭頂部に楔石(くさびいし)(キーストーン)を入れると、石は下に落ちることがありません。ただし、水に浸かると石が浮き上がってバラバラになります。
江戸時代の中島川は、10年に一度ぐらい氾濫していました。眼鏡橋も大きく破損したりしているのですが、その度に修復しています。中島川のアーチ石橋は何度も流され、多いものでは3度も架け替えられています。壊れても部材の石はそんなに遠くまで流れていきませんから、それを使って、またつくり直すのです。
もちろん、そのための費用はかかりますが、江戸時代の長崎には、それだけの財力と石橋にかける愛情があったということでしょう。九州各地にはたくさんの石橋がありましたが、近代化の過程で次々とコンクリート製や鋼製の橋につくり替えられました。しかしコンクリートは耐用年数がたかだか60年ほどで意外に短寿命なのです。それに比べて石橋は江戸時代のものがまだ現役です。
石橋は、リユースが可能な、小さなポータブルな部材で大きな構造物をつくり上げる技術の結集ですから、ある意味ではきわめて現代的な構造物だと思います。壊れてつくり直すことで技術も伝承されます。強い力の洪水には、電気のヒューズのように、いったん飛んで力を受け流し、あとでリセットすれば何事もなかったように復活できる仕組みなのです。山口さんや私が石橋に惚れ込んだのは、そんなところに魅力を感じたこともあります。
一病息災のまちづくり
災害大国日本においては、自然の厳しさと巧みに共存して生きていく姿勢こそが大切だし、それが日本の文化の基層を形成してきたと考えます。自然の猛威をハードな技術で抑え込もうとしても限界があることを知らねばなりません。
水害リスクを抱える長崎のような都市では、まず「予報、警報、避難」のソフトなシステムを確立することで「人が死なない」仕組みを確立し、その上に立って、いかに被害を少なくするか、まちの風情をどう守り育てるか、という二段三段の構えが必要だと思います。
中島川にはたくさんの橋が架かって、川の中にも飛び石が置かれて、暮らしと川がいかにも近い距離にありますから、いつも川や周りの自然の様子を観察して変化に対応する、一病息災の生活作法を忘れずにいてほしいと思います。
アーチ石橋の謎
アーチによって構造物をつくる技術は、どこで誰が発明したのでしょうか。古代中国か、メソポタミアか、古代エジプトか。あるいはインカ・マヤ文明が円形アーチを知らなかったと言われていたものが、1950年代に遺跡から発見されて、その説も覆されています。石橋以外にも、焼きものの窯や沖縄の墓もアーチ。ヨーロッパやイスラム建築ではドームも多用されています。それぞれ独自に発明された可能性もあれば相互の交流の中での技術革新もあったようです。
長崎の眼鏡橋にはポルトガルの技術が入っているという説もありますが、中国・江西省出身で興福寺2代住持の黙子如定(もくすにょじょう)禅師による1634年(寛永11)の創建とされていますから、中国から技術が入ってきたのは間違いないでしょう。九州や沖縄にはアーチ石橋が今も多くあり、それ以外の本州地域に少ないのは、長崎から伝わった技術が高度化され、秘伝として伝承されたからとされています。
中国には古代からの100万橋を超える石橋が現存しているといわれます。中でも河北省の趙州には7世紀初頭の建造とされるスパン37mの壮麗な扁平アーチ橋が現存しており、その時代に既に高い技術レベルに到達していたようです。一方ヨーロッパでは、ローマのテヴェレ川に架かるファブリッチオ橋がBC62年の建造で、今も現役で機能しています。
幕末期の甲突川(こうつきがわ 鹿児島)の石橋群や通潤橋(熊本)などには、九州の石工に培われた技術に加えて、ヨーロッパの技術の影響も見られます。外来技術を受け入れたあと独自の工夫を凝らして発展させるという、我が国の技術発展の典型的な事例の一つといえるでしょう。
合意形成に役立ったもの
人類が開発してきた「早く、安く、大量に」の技術には、根本的な問題があると思っています。なぜなら、月にまで行く時代に、川一つきれいにできないからです。
川を汚したのも人間ですが、きれいにできるのも人間です。中島川をきれいにして石橋を地域の誇りに思う気持ちを醸成していたから、長崎大水害の後に眼鏡橋が残ったのだと思います。
長崎大水害から30年以上が経過した今、あの水害自体を知らない人も増えましたが、眼鏡橋を残せた背景にある、この事実は語り継いでいかなくてはなりません。
川への意識がよみがえるような活動の積み重ねが、残そうという合意形成へとつながりました。この長崎市民の経験が、多くの地域の参考になれば幸いです。
(取材:2014年2月14日)