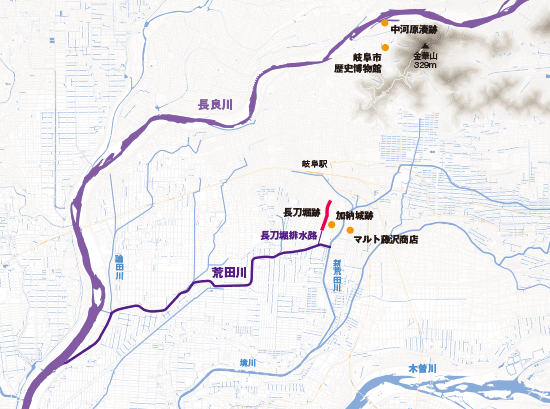機関誌『水の文化』50号
江戸時代から続
岐阜・加納の和傘づくり

長良川の中河原湊跡。現在は鵜飼観覧船乗り場となっているが、かつては上流からの材木や和紙、
真竹などが荷揚げされて、加納地区へと運ばれた
江戸時代から突出した和傘の生産地として知られる岐阜市加納地区。和傘の複雑な工程を分業化した生産モデルと長良川の舟運によって発展したが、今ではたった3軒に。多角化による経営努力と市民講座などで伝統継承に励む株式会社マルト藤沢商店の藤沢健一さんと、サポートする岐阜市歴史博物館の大塚清史さんを訪ねた。
-

-
株式会社 マルト藤沢商店 代表取締役
岐阜市和傘振興会 会長
藤沢 健一(ふじさわ けんいち)さん -
慶應義塾大学卒業後、家業である藤沢商店を継ぐ。創業84年の和傘製造卸企業の代表として経営の多角化などに努め、岐阜和傘を伝え広める活動を続けている。
-

-
岐阜市歴史博物館 学芸員
大塚 清史(おおつか きよし)さん -
東京都出身。1991年(平成3)から岐阜市歴史博物館に勤務。前館長・薮下浩さんから岐阜和傘の研究を継ぐ。2012年(平成24)には同館発行の『館蔵品図録 和傘 資料選集』の執筆・編集を務めた。
分業システムと長良川の舟運で栄えた岐阜和傘
傘骨(かさぼね)にする真竹(またけ)割りから、油を引き天日で干す仕上げまで。細分化すれば100工程に及ぶ和傘は、つくるのにもっとも手間のかかる伝統工芸品の一つだ。江戸時代から和傘づくりが盛んで、今も芸能や舞踊などで使われる和傘のほぼ9割を生産しているといわれるのが、岐阜市加納地区。多岐にわたる工程を職人が分業し、問屋が全体を差配する大量生産システムを築いたことで岐阜は和傘の一大産地となった。最盛期の昭和20年代半ばには年産1000万本を超えている。
1756年(宝暦6)、加納藩主・永井直陳は下級武士の生計を助けるため和傘づくりを奨励した。分業体制の確立に加え、美濃和紙の産地に近く、周辺の山間地で良質の竹が採取できるなど、原材料に恵まれたことも加納の和傘が栄えた理由だ。
原材料と製品の搬送経路として「長良川の舟運が大きな役割を果たした」と教えてくれるのは、岐阜市歴史博物館学芸員の大塚清史さん。「長良川から伊勢湾の桑名に出て、廻船によって江戸・大坂などの大消費地へ輸送したので、広範囲に和傘を販売することができたわけです」
岐阜市の加納城跡は公園になっており、西側は「加納長刀堀(なぎなたぼり)」(写真1)という。なるほど細い道を見通すと長刀のような形に湾曲している。このあたりはかつて加納城の「長刀堀」だった。通りの西側、少し高台になっている民家の石垣に、往時の武家屋敷の名残をかすかに見てとれる。さらに南へ下れば、住宅街の間を「長刀堀排水路」(写真2)が貫通し、荒田川と合流して長良川本流へ。長い時を経て埋め立てられ、流路も変わったものの、産業としての和傘の発展と「堀」や「川」との密接な関係は、現在のまちなみと地形からも偲ぶことができる。
かつて岐阜の和傘は加納地区でつくられ、長刀堀から荒田川、さらに長良川を経て江戸や大坂に運ばれた
職人芸を競う細物(ほそもの)の蛇の目や日傘に特長
精緻な技を凝らした岐阜和傘が岐阜市歴史博物館に展示されている。例えば「松葉骨(まつばぼね)」という意匠。傘紙の土台となる親骨が周縁部に向かって二股に分かれ、まるで松葉のよう。大坂や和歌山では、主に無骨で頑丈な「太物(ふともの)」の番傘がつくられていたが、職人芸を競った岐阜和傘は、畳むと細く収まる「細物」の蛇の目傘(注)、日傘、舞踊傘を得意とした。
蛇の目傘は、番傘に比べて1本ずつの骨が細い。色とりどりの傘紙や羽二重(絹と和紙を貼り合わせた傘紙)を張り、親骨を支える小骨(しょうぼね)には飾り糸を付ける。傘を彩る模様も紙を貼りつけるのではなく、平紙をあらかじめ模様に合わせて切り抜いたり、異なる色柄の傘紙を切りつないで模様をつくる「切継ぎ」という独自の手法を編み出した。これによって内側から模様が透けて見える。技術と手間を要する高級品だ。
日用品としての番傘は、高度経済成長期以降、たちまち洋傘に取って代わられた。かろうじて岐阜和傘が残るのは、高度な技術で多品種を生産でき、歌舞伎や祭礼などで使う特殊な和傘の需要にこたえているからにほかならない。
「伊勢神宮の式年遷宮で使われる大ぶりの差し掛け傘などを見るとよくわかるのですが、傘骨のソリや間隔に細心の注意が払われていないと丈夫でないし美しくありません。均等に配置された竹の骨は優美です。どうしても私たちは、傘紙の色や模様で〈きれい〉と感じてしまうのですが、道具としての本来の美しさは構造にあります」と、大塚さんは岐阜和傘の工芸的な真価を強調した。
(注)
和傘(蛇の目傘)の構造については「資料 傘の構造と和傘の工程」を参照。
伝統を絶やさないため経営を多角化
いまや岐阜和傘を製造販売するのは加納地区に3軒のみ。その1軒、株式会社マルト藤沢商店は1931年(昭和6)に和傘問屋として創業した。同年生まれの藤沢健一社長が大学を卒業して家業に入った1954年(昭和29)、すでに和傘の需要は下り坂だったが、それでも「見本を持って東北に販売ルートを開拓すると、大卒初任給1万円の20倍は稼げました」と当時を振り返る。
しかし洋傘の普及にシェアを奪われ、雪崩を打つように右肩下がりとなり、最盛期には加納地区に500軒以上あった傘屋が5分の1以下に減った。1970年(昭和45)に始まった国鉄(当時)の「ディスカバー・ジャパン」キャンペーンで和傘も多少は見直されたが、需要の減少に歯止めはかからない。70年代半ばに和傘職人を元気づけようと発案した品評会を藤沢さんは思い出す。
「料亭に職人を招待し、同じ材料で競作した傘を、京都のお得意さまに審査して頂きました。ところが、すべてあまりにもきれいにできているので甲乙つけられなかったのです」
品評会用に競作した、絹と和紙を貼り合わせた真紅の羽二重傘は、今も自宅に保管してあるという。
職人の丹精込めた和傘づくりの伝統を絶やさないためには、新たな収益の柱を築かなければならない。藤沢さんは和傘の技術を使い経営の多角化に乗り出した。和傘でつくったクリスマスツリーなどを東京の表参道で販売してもらうと米国人に大ヒット。返還前の沖縄でも駐留兵の家族に好まれ、アメリカ本国へと輸出された。その余勢を駆り、オルゴールがクリスマスソングを奏でるオーナメントが売れ筋商品となった。
「急激な円高に振れた1985年(昭和60)ごろまでは、オリジナル・デザインの雑貨商品だけで年間5000万円の売上でした」と藤沢さんは回想する。
ミニ和傘と中国生産、そして職人の育成まで
為替差損と新興国の台頭で輸出商品に見切りをつけてからは、本業の和傘を軸にした新規事業へ舵を切る。
社内ではミニチュア和傘を製作。藤沢さん自ら六十数点を一挙にデザインした。当初は土産物問屋を通じて全国の観光地で販売していたが、2年ほどで販売ルートとデザインを変更して京都のまちなかや空港などで売ると、外国への土産物として人気を呼んだ。
よさこいなど全国各地の祭礼舞踊の練習用に使う消耗品の和傘は常に一定の数量を見込めるが、単価が安く国内ではコストが見合わず人手も足りなくなっていた。
そこで、岐阜市と中国浙江省杭州市が友好都市提携を結んだのを機に、工芸品の輸出公司を窓口とし中国生産に踏み切った。最初の2年間は年に4回ほど藤沢さん自ら現地へ赴き指導した。それが1980年代末のことで、今も年間1万本以上、製造を委託している。
「数量を重ね経験を積んだ今では、国産に勝るとも劣らない品物ができています。骨組みに塗る漆ひとつとっても、驚くほどきれいに仕上がっていますよ」
かつて和傘づくりの後継者育成は、分業に携わる各工房に任せられていた。それができなくなり、2000年(平成12)にマルト藤沢商店が問屋として社員職人を募集し、育成に乗り出した。36名の応募者から5名を採用。藤沢さんによれば「ほんのわずかの一工程でも完璧にできるまでに3年はかかる」というが、これで「骨削り」や「紙張り」、手元ろくろ(小骨に柄竹をつなぐ部品)とはじき(傘が開いた状態を保つ部品)を取り付ける「繰り込み」などの基本工程を内製できる体制が整った。
和傘文化の灯火を未来へ渡すために
岐阜市歴史博物館では、マルト藤沢商店などの職人が指導する「岐阜和傘を作る」講座を年1回、開催している。10名ずつ2グループに分かれ、骨組みした傘に和紙を張り、糸かがりをする作業を4日間にわたって体験する。今年で24回目を数え、一度も定員割れしたことがない。子ども向けの講座も開催している。
一般市民が和傘の美しさを知り、広めてもらう意図で始めた講座だが、最近では他の産地からの参加者もあり、和傘技術入門講座の趣も呈している。こうした地道な試みが、やがては後継者を生むのかもしれない。
東京・銀座の文具店の吹き抜けで蛇の目傘を吊るすディスプレイが好評だったことがある。「和傘を目にする機会を増やしたい」と藤沢さんは望む。「銀座の歩行者天国で和傘をさした集団が練り歩く、なんていうイベントをやってみたいですね」
歌舞伎で使う和傘は国内でしかつくれない。消え失せてから気づくのでは遅いのだ。和傘文化の灯火が明るいうちに未来へ受け渡したい。
(2015年5月3〜4日取材)