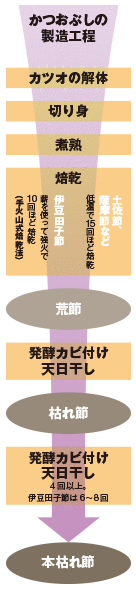機関誌『水の文化』52号

煙でいぶす
西伊豆に今も伝わる
本枯れ節の滋味

伊豆田子節の伝統製法「手火山式焙乾法」で蒸籠に入れたカツオをいぶし乾かす。
うまみ成分のイノシン酸を多量に含み、日本料理に欠かせないだしをとるのに使われるかつおぶし。カツオの身を煮て乾燥させるものだが、日に干すだけでなく、煙でいぶす「複合型」の保存食といえる。煙でいぶし乾かしたものが「荒節(あらぶし)」で、これにカビを付けて水分を抜くものが「枯れ節(かれぶし)」だ。そしてカビ付けと日干しを4回以上繰り返すものは「本枯れ節(ほんかれぶし)」と呼ばれ、極上品に位置づけられている。伊豆半島の西部には昔ながらの焙乾(ばいかん)手法を守る地域があると聞いて伺ったが、想像以上に繊細かつ複雑な手作業を、長期間かけて生み出すものだった。
-
静岡県賀茂郡西伊豆町田子
昔ながらのいぶし方
「手火山式(てびやましき)焙乾法」
子どものころ家の手伝いでかつおぶしを削らされた。そんな記憶のある人は多いだろう。だが、かつおぶしを削って「だし」をとる家庭はいまや少ない。そもそも削り器が入手しにくく、かつおぶしと聞けばパック入りの削り節を思い浮かべる世代も増えた。
しかしかつおぶしは今も昔ながらの製法で手づくりされている。だしが命の和食の伝統をつなぐ料理店や親から受け継がれた味を大事にする家庭の根強い需要に支えられている。
かつおぶしの製造は三十数工程に及ぶが、大きく分けると「切り身」「煮熟(しゃじゅく)」「焙乾」「発酵カビ付け」の四段階。生のカツオをおろし、煮込んで、いぶし乾かす(焙乾)までの工程で仕上げるものを「荒節」と呼ぶ。その後、さらに高温多湿の室に20〜30日間貯蔵する発酵カビ付けと天日干しを交互に4回以上繰り返したものを「本枯れ節」と呼ぶ。
かつおぶしは明治時代から土佐節(高知県)、薩摩節(鹿児島県)、伊豆節(静岡県)が名産品とされてきた。なかでも西伊豆町田子で発達した伊豆田子節は、薪で約20日間かけ10回ほどいぶし乾かす「手火山式焙乾法」が特徴だ。
1882年(明治15)の創業以来、この伝統的な製法を守りつづけているのが、カネサ鰹節商店五代目の芹沢安久さん。
「最初の1、2回は高温の強火で焙乾します。するとかつおぶしから水分が大量に出て一気に身が縮まり、表面が硬くなる。内部のうまみを外に逃がさないよう表面をコーティングするわけです。低温で長時間、15回ほど焙乾する薩摩節や土佐節は濃厚なだしがとれます。対して伊豆田子節でとっただしは、比較的濁りがなくあっさりめです」
和食の滋味を引き出すかつおぶしは料理によって使い分けられてきた。
ギャンブルに似ている本枯れ節づくり
荒節は1カ月で完成するが、発酵カビ付けと天日干しを繰り返す本枯れ節となるとそうはいかない。特に、西伊豆町田子の手火山式焙乾法は、焙乾回数が少ないため水分が取りきれず、発酵カビ付けと天日干しを6〜8回繰り返して水分を除去しなければいけない。カツオの大きさと天候に応じて4〜6カ月はかかる。
芹沢さんは「半年間デッドストックで、需要の多い年末に売れるかどうかもわからない本枯れ節は、ギャンブルみたいなもの」と苦笑する。
本枯れ節の価値は「削りやすいようにまっすぐにつくること」(芹沢さん)にかかっている。そのため繊細な手仕事が欠かせない。三枚におろした一尾のカツオを、背節、腹節各2本ずつ4本の身に切り分ける「合い断ち」と、そうやって身割りしたカツオを煮カゴに組み込む作業が、まっすぐきれいで削りやすい形を決める。切り方がまっすぐでも、90度の湯に2時間ほど煮込む際にねじれるので、煮上がったときの形をイメージして煮カゴに組み込まないと曲がってしまう。
煮熟した後と焙乾した後に行なう「骨抜き」も丁寧な手仕事。小骨を一本ずつ抜き、なおかつ、カツオの中骨に付いていたすり身を小骨の抜き跡に塗り込み穴を埋める。小骨を残しておくと身が引っ張られて曲がるし、抜き跡を修繕しなければ身が崩れてしまうのだ。
かつおぶしはまさに一本一本、丹精込めてつくられている。
おいしさをつくるのは効率悪く危険な方法
焙乾して水分を抜くかつおぶしの製造方法が確立したのは、17世紀中ごろの紀州(和歌山県)印南(いなみ)町。これが土佐、薩摩へと伝わった。1801年(寛政13)、その製造方法を知る土佐の与一が築地で働いていたとき西伊豆へ呼ばれ、発酵カビ付けの工程を加えた改良土佐節を教えたのだ。発酵カビ付けと天日干しの回数を増やすと水分がよく抜け、保存性と品質が向上する。これが江戸で高く売れることに大阪商人が目をつけ、4回以上カビを付けたかつおぶしを西伊豆田子に発注。その求めによくこたえたことから本枯れ節「伊豆田子節」が誕生した。
田子は古くからの漁師町。とりわけカツオ漁で栄え、全盛期には大型船40艘が港に出入りし、かつおぶしの製造業者は30軒に及んだ。1955年(昭和30)の記録ではカツオの水揚高は5億円。当時の田子町の予算は4000万円なので、10倍以上もカツオで稼いでいたことになる。
しかし一本釣り漁から巻網漁への変化、陸路交通の不便さ、オイルショックなどが重なりカツオ漁は衰退していく。21世紀に入るとカツオ船は姿を消し、かつおぶしの製造業者も3軒を残すのみだ。しかも、カネサ鰹節商店のように、昔ながらの手火山式焙乾法を守りつづけると職人の負担が大きい。
手火山式焙乾法は、約2mの縦穴式の炉に、カツオを並べた竹の蒸籠(むしかご)を3〜5枚重ね、薪をくべていぶす。熱が偏らずまんべんなく吹きつけるように、風向きと火加減を調節しつづけなければならない。「手火山」の名は、手で触ってかつおぶしの温度を確かめることからきている。もうもうと燻煙が立ちのぼるなか、炉に付きっきりの重労働だ。
「煙も匂いもきついので近くに民家があるとできません。当社も昔は港の近くにありましたが、50年前に山すそに移転しました。手火山式焙乾法はもっとも効率が悪い、危険な方法なのです」と明かす芹沢さん。それでもこの製法にこだわるのは「かつおぶしをもっともおいしくする焙乾法」と自負しているからだ。
また、創業当時から地元の薪を使っている。それゆえ、伊豆田子節の味になる。地元の薪を使うのは先人の知恵でもある。人間が一度手を入れた山は手を入れつづけないと守れない。地元の薪を使えば山が保全され、栄養分豊富できれいな水が海に注ぐ。その教えを忠実に守っている。
地域の味、家庭の味が伝わればかつおぶしも残る
かつおぶしなら田子節。カネサのものしか使いたくない。「そうおっしゃるお客さまがいてくださるのでつくりつづけています」と芹沢さん。「手間がかかる割に利幅が薄い本枯れ節をつくりつづけるのはプライドに近いですね。伝統のよさを残したいのです。それに、本枯れ節があるおかげで荒節や削り節、他のカツオ加工品も売れていると思います」
カネサ鰹節商店では、江戸時代から伝わる「潮鰹(しおかつお)」も製造している。カツオを丸ごと塩に漬け込み乾燥させた保存食だ。新巻鮭と同じように正月、軒先に吊るし、松の内が明けると焼いてほぐし、お茶漬けなどにして食べた。しかし、今は全国でも田子でしかつくられていない。地元の有志が結成した「西伊豆しおかつお研究会」では、潮鰹をトッピングした「しおかつおうどん」で観光振興を図る。西伊豆・沼津・三島の約30の飲食店や宿で食べられるが、潮鰹はとても塩辛いため、少量でも濃厚なカツオの風味とうまみがにじみ出る。うどんにはぴったりだ。
芹沢さんは、本枯れ節や潮鰹をもっとよく知ってもらう活動に取り組んでいる。地元の小中学校での食育講義や、大人向けのワークショップ、工場見学などだ。本枯れ節や潮鰹を味わってもらい、その歴史と文化を伝え、かつおぶし削りの体験もしてもらう。
「かつおぶしをきっかけに西伊豆へ遊びに来ていただき、地域の活性化につなげたい。それがゴールです」
かつおぶしは、頭の方が手前になるように持ち、皮の付いた尾から頭の方へ押して削るのが基本だ。刃の向きに逆らわない順目で削ると粉っぽくならない。このような削り方だけでなく、香りを逃がさないよう料理の直前に削ることや、冷蔵庫での保存方法などについても伝える。
効率性や利便性が優先される時代に〈かつおぶしを削る〉家庭文化の復活は難しいかもしれないが、和食が世界的に注目されるなか、その根幹を成すだしの元であり、保存期間がきわめて長い「究極の保存食」でもあるかつおぶしの需要は底堅い。
「お母さんの味、地域の味が和食の原点です。お盆や正月に親族が集まったら、お子さんたちに、家庭と郷土に伝わる料理を教えてあげてください」
かつおぶしの啓発活動では、必ずそう話すことにしている芹沢さん。その努力が実を結ぶことを強く願う。
(2015年12月3日取材)