機関誌『水の文化』52号
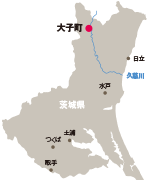
凍結乾燥
凍らせて乾燥させる
「幻のこんにゃく」

最低気温が氷点下になる日が続くと、ようやく凍みこんにゃくの製造は本格化する。
夜の間に氷になった水分が日中に溶けて蒸発。徐々に水分が抜けていく
食材から水分を抜いて保存性を高めるために、人はさまざまな手法を編み出してきた。その一つに「凍らせて乾燥させる」というやり方がある。高野豆腐が有名だが、寒い冬に昼夜を問わず屋外に置くと、夜の間に凍った水分が日中に日に照らされて蒸発する。これを繰り返すことで水分を抜くのだ。今は茨城県の北部だけで生産されている「凍(し)みこんにゃく」も同じ手法を用いた伝統的な保存食。真冬の田んぼで凍結・乾燥を繰り返してできた凍みこんにゃくは、普通のこんにゃくとは明らかに異なる味と歯ごたえがあった。
-
茨城県久慈郡大子町
奥久慈の暮らしを支えたこんにゃく
茨城県北部の久慈川に沿う山間部、奥久慈地方には、江戸時代から伝わる保存食「凍みこんにゃく」がある。冷え込むが雪は少ない気候を活かし、屋外でこんにゃくを凍結させ、昼の太陽の光で水分を抜いて凝縮させた乾物だ。まっ白でカチカチに固まった凍みこんにゃくは、普段食べているこんにゃくとは似ても似つかない。
茨城県大子蒟蒻(だいごこんにゃく)原料加工協同組合の専務理事、栗田晋一さんによると、凍みこんにゃくは精進料理の煮しめの具材として、昔から必ず使われてきたそうだ。
今、一般的に食べられているこんにゃくは、こんにゃく芋というサトイモ科の芋をスライスして乾燥し、粉にしてから固めてつくるもの。ここ奥久慈は古くからこんにゃくの産地として知られる。土壌が砂礫(されき)質のためほかの農作物には向かないが、南向きの斜面は適度な地中温度を保ち、水はけもよい。こんにゃく芋の栽培にはうってつけだったからだ。
日本でこんにゃく芋が本格的に栽培されるようになったのは江戸時代。しかし、寒さに弱く腐りやすいことから、商品作物としての価値を高めるために、保存が利いて、軽くする方法が求められ、奥久慈では凍みこんにゃくがつくられていた。丹波から伝播した説が有力で、冬の農閑期につくっていたとされる。
その後、1776年(安永5)、奥久慈の農家に生まれた中島藤右衛門(とうえもん)が「こんにゃく芋を粉こんにゃくに加工する」という現代に通じる技術を開発。以後その製法は奥久慈全体に普及し、水戸藩の専売品にもなった。こんにゃくの産地といえば今は群馬県が有名だが、実は茨城県が本家なのだ。
その一方、凍みこんにゃくは手間や根気が必要なため、次第に粉こんにゃくにとって代わられる。栗田さんによると、凍みこんにゃくの生産者はいまや3軒を残すだけとなった。
「最後の職人」からつくり方を受け継ぐ
実は、栗田さんは数少ない凍みこんにゃくの生産者だ。
栗田さんが凍みこんにゃくにかかわるようになったのは22年前。家業である粉こんにゃくの製造販売会社、株式会社クリタを継ぐために帰郷して1年後だった。それまでは凍みこんにゃくを知らず、「こんなもの売ってもしょうがないんじゃないの?」というのが本心だった。
クリタは「日本で最後の凍みこんにゃく職人」といわれた菊池銀三郎さんがつくる凍みこんにゃくを、山形県の米沢市などに卸していた。山形はこんにゃくの消費量が全国一。ことに米沢(置賜〔おきたま〕地方)では、昔から凍みこんにゃくが食べられている。
ところが、銀三郎さんが高齢のため凍みこんにゃくの製造を辞めたいと申し出る。後継者もいない。栗田さんがしかたなく得意先に事情を説明すると、「なんとかしてほしい」と懇願される。栗田さんは銀三郎さんに製造を続けるよう頼んだが「無理だ」と言われる。困り果てた栗田さんに銀三郎さんがかけた言葉は、「教えてやっからお前がつくれ」。奥久慈が誇る食文化をなくすわけにはいかず、栗田さんは決意する。
「実家の仕事もろくにわからないのに凍みこんにゃくもつくることになって、てんやわんやでした」と栗田さんは当時を振り返って苦笑いする。
教わるといっても、手取り足取りではない。見て覚えるしかなかった。目分量で教えられるものを自分で計量して数値化し、わからないことは聞く。栗田さんが凍みこんにゃくのつくり方を習得するまで3年もかかった。当初は失敗作を出してしまい、クレームがきたこともあった。
「失敗すると水でもどしたときにバラバラになる。でもあまり頑丈につくると、今度はかみ切れない。実際にできてみないとわからないので、さじ加減が難しかったですね」
一朝一夕ではできない過酷で複雑な工程
クリタでは、年間約5万枚(約1.8t)の凍みこんにゃくを生産する。機械制御が中心の今でも、銀三郎さん譲りの手作業に頼る部分が大きい。
まずこんにゃく芋の皮をむき、桶にすりおろしたら攪拌しながら練る。固めるための石灰を混ぜ、木箱に流しこむ。固まったら取り出して、さらに固めるために釜で煮る。
釜で煮たこんにゃくをスライスし、さらに石灰水に浸すこと数日。その後、藁を敷いた3区画の空き地に一枚一枚並べて干す。1区画に2400枚の凍みこんにゃくを並べるというから、想像するだけで気が遠くなってしまう。
栗田さんによると、藁を敷くのは藁に付いた納豆菌がこんにゃくの成分を分解し、石灰で固くなったこんにゃくを柔らかくするのだという。
また、この間は朝・昼・晩、三度の水かけが欠かせない。朝は夜間に凍ったこんにゃくを溶かすため、昼は乾燥して身が縮むのを防ぐため、夜は再び凍らせるために水をかける。これを繰り返すことで、白いスポンジ状の凍みこんにゃくになる。
全工程でもっとも重要なところは、「最初に干したときに完全に凍ること」と栗田さんは言う。条件は、雪が降らず氷点下になること。
「雪の下は温かいので、表面が凍っても中は凍りません。干しはじめに雪に降られたら、すべて捨てざるを得ません」。そのため、天気のチェックにはぬかりがない。
干した凍みこんにゃくは7日ほどで取り込むが、この状態ではまだ8割しか乾いていない。ここからは、縮みを防ぐために工場内で陰干しして仕上げる。完全に乾いて出荷できるのは、さらに3カ月後の3月。秋口の収穫から数えると、完成するまでに半年もかかるのだ。
「今はこんにゃく消費も減っているので宣伝になるならと続けていますが、利益を取ろうと思うならやらない方がいい」と栗田さんは言う。
クリタでは、社員2名が凍みこんにゃくづくりに携わっている。
活路を見いだすために海外進出も
利益が見込めず、割に合わない重労働。そんな厳しい状況下ではあるものの、栗田さんは「元祖・こんにゃくの本場」のプライドにかけて、凍みこんにゃくの宣伝活動や販路の拡大に余念がない。
凍みこんにゃくのPRに徹して立ち上げた「大子グルメフーズ」では、ネット通販で商品が買えるほか、日常的に凍みこんにゃくを食べてもらうため、さまざまなレシピを提案する。興味深いのは、煮しめやフライなどの定番に混じり、カップケーキやグラタン、鶏すきなどバラエティに富んだメニューが多いこと。
この日、初めて凍みこんにゃくのフライとお吸い物を味わった。「これがこんにゃく?」と思うほどの歯ごたえは肉のようでもある。柔らかさのなかにほどよい固さがある。スポンジ状なので味が染みこみやすく、かむたびにジワッとしみ出る。
凍みこんにゃくは、1枚食べれば板こんにゃく一丁分を消費したことになる。「そこがいちばんいいところ」と栗田さんは言う。こんにゃくは「からだの砂おろし」と言われるように、腸の動きを活発にし、不要物を体外に出す働きのある健康食品だ。カロリーもほとんどなく、ダイエット食としての人気も高い。
また、2015年には海外へも打って出た。凍みこんにゃくをミラノ万博(注1)に出展したところ、好感触だった。「プルプル感が苦手な外国人にとって凍みこんにゃくは好都合」なのだそう。グルテンフリー(注2)がうたえることも海外では大きなメリットになる。
「海外メディアに取り上げられることで日本に逆輸入できれば」と栗田さんは今後の目論見を話す。この春にも、パリのスーパーマーケットで展示即売会を行なうことが決定している。
「ここまできたらやめるわけにはいかない」という思いが栗田さんを突き動かし、なんとか活路を見いだそうと日々奔走する。生産者も流通量も少ない幻の伝統食が「幻」でなくなる日がくるかもしれない。
(注1)ミラノ万博
万博初となる「食」をテーマに、2015年5月1日〜10月31日に開催。
(注2)グルテンフリー
グルテンは小麦などイネ科植物の貯蔵たんぱく質の一種。グルテンを含まないグルテンフリーは、ここ数年ダイエット食として注目されている。
(2015年12月26日取材)





















