機関誌『水の文化』52号
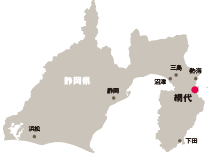
塩を使う+干す
干物が生活に根ざすまち
「網代」

日に照らされるサバのみりん干し。特製のタレに数時間漬け込んでから干すので、照りも味もよい
魚の干物といえば、塩に漬けて干す「塩干し」の代表格だ。縄文時代の貝塚からは、魚や貝の干物をつくっていたと思われる道具も発見されているという。海に囲まれた島国・日本にとってまさに伝統的な食べものだ。魚の干物は全国でつくられているが、昭和40年代に「ひもの銀座」と呼ばれたのが静岡県熱海市の網代地区。今も天日干しにこだわっている生産者が多いと聞く。現地に向かうと、自らつくった干物を、自信をもって売る人たちがいた。
-
静岡県熱海市網代
民家の庭先で干物をつくる人々
静岡県熱海市の南東部に位置する網代地区。潮の香りが漂い、漁師町特有の庶民的でのどかな風情が残る。南から押し寄せる外洋の波は陸地で防ぎ、東からの大風も地形で守られている網代の港は、古くから伊豆東海岸随一の天然の良港だった。江戸に物資を運ぶ廻船で賑わい、その繁栄ぶりは「京・大坂・江戸・網代」と謳われたほど。山野が乏しく狭隘(きょうあい)な土地の網代では、米や野菜を手に入れるため、魚を貨幣に換える必要があった。そのころから漁業が唯一の産業だった。
アジやサバ、カマス、イカなどの干物は、網代の名物だ。中心を貫く国道135号沿いには、現在8軒の干物店が立ち並ぶ。毎年11月〜2月の休日に開催される「網代温泉ひもの祭り」には、脂ののった干物を目当てに多くの観光客が訪れる。
網代の干物は「天日干し」にこだわる。天日干しには「日」と「風」が重要で、山からの乾いた西風が吹き抜ける網代は干物づくりに向いている。
まちを歩いていて気づくのは、一般家庭の玄関先で干物をつくる光景が珍しくないこと。尋ねると、自分たちで食べるほかに遠方の家族や親戚に送るのだという。よく見ると、軒先に立てかけている干すための網や台も、各家で手づくりしたオリジナルだ。
「朝、港に行って魚が手に入れば毎日でもつくります。味つけや干し加減はつくるうちに覚えたけど、まあ適当なもんだよ」と笑って話してくれたのは、八百屋を営む岡田さんご夫婦。
一般家庭の人たちが魚をさばき干物をつくるほど、干物は生活に根ざしているようだ。それはなぜなのか?
「ひもの銀座」を生んだウマヅラハギの大漁
網代が「干物のまち」として知られるようになったのは、昭和40年ごろからだ。当時を知る1969年(昭和44)創業の弁天ひもの店の納屋(ないや)三千代さんによると、転機となったのはウマヅラハギの大漁が続いたことだった。それまでは、ほとんどの人が漁師を生業にしていたが、網代で盛んだった定置網に、ウマヅラハギが大量にかかりはじめる。しかしウマヅラハギは皮が硬く、加工に手間取るため、捨てるしかなかった。だがあまりに獲れるので、「誰だかわからないけれど」(三千代さん)ウマヅラハギをみりん干しにして売ったところ、観光客に大ヒット。これを境に、多くの漁師が干物加工業に切り替えたが、弁天ひもの店もその一つだった。
「創業前は人を雇いながら漁師をしていました。もともとこの地域は各家庭で干物をつくっていたので、ウマヅラハギのみりん干しはあっという間に広まりました。私たち夫婦も干物店をはじめたらどんどん売れてね。寝ずに働きました。店頭で干物を焼いて食べてもらって、お客さんを引っ張るためにみんな競争。それはそれは賑やかでしたよ」と三千代さんは述懐する。
網代の干物店は国道135号の西側(山側)にある。観光地として人気の高い伊豆下田から東京への帰り道で、店先に車を停めやすいため、土産として干物を買い求める人が列をなした。全盛期には国道沿いのわずか500mほどに30軒とも40軒ともいわれるほどの干物店がひしめき、「ひもの銀座」と呼ばれるようになった。
仕上がりを左右する乾燥にかける手間
このように一時は隆盛を極めた干物店だが、ウマヅラハギが獲れなくなったころから看板をおろす店が後を絶たない。しかし、今も変わらず干物をつくりつづける小売店や加工業者がある。弁天ひもの店を経営する有限会社納屋商店代表、納屋久さんもその一人だ。
訪ねたときは真イカを一夜干しにするためさばいているところだった。耳から足の方へスーッと包丁を入れ、ワタ、スミ袋、目玉、くちばしを取り出す。ワタがまったく傷ついていないのは、力加減が絶妙なのだろう。
アジやカマス、サバなど魚の場合は、季節によって脂ののり方が違うし、一匹ずつ身の厚さも異なる。常に安定した味にするには、塩水に漬ける時間を変え、塩水の塩分濃度も調整する。「魚をさばくときに脂ののりはわかるね。味つけは店ごとに違うよ。魚によっても気温によっても変わる。いろんな微調整が必要」と納屋さん。受け継いだ味つけの工夫は企業秘密らしい。
山が迫っているので日の当たらない時間帯が長い網代。干す際は西日が主となる。夏場は日差しがきついため、身が焼けてパサパサになってしまいがちだ。季節や天候で干し方、干す場所、干す時間などを変えるため、移動や陰干しといった手間が欠かせない。
干物の仲買と加工業を営む有限会社藤長(ふじちょう)商店代表の藤田法彦さん、小澤(こさわ)商店の小澤紳一郎さんにも話を聞いた。ともに仕入れた原料を加工し、熱海や網代の土産物店や旅館などに納めている。
小澤さんは、湿気の多い梅雨時期以外は自社の屋上で天日干しをしている。屋上にはネットを張り、鳥などの害から守っているそうだ。
藤田さんは、15年ほど前から機械乾燥を取り入れている。機械でも温風ではなく冷風で乾燥することで、時間や仕上がりに差は出ないそうだ。冷風乾燥では、じっくり3時間以上乾かす。天日干しの方が手間がかかると思いがちだが、天日干しは条件がよければ2時間ほどで乾くため、機械の方が時間がかかる場合もある。
「温風乾燥だと乾きは早いですが、身が黄色くなり仕上がりがイマイチ。また、冷風乾燥でも乾きが甘いと水っぽくなり、焼いていて身崩れを起こしてしまいます」と藤田さん。
天日干し、機械乾燥ともに、さじ加減一つで仕上がりが変わるのだ。
効率のよさよりも「質」へのこだわり
乾燥方法にしてもそうだが、網代の人たちは完成度の高い干物にするための手間を惜しまない。「簡単に仕上げようと思えばもちろんできますが、それでは網代の干物じゃなくなってしまう」と藤田さんは言う。
例えばみりん干し。時間短縮のためタレをハケでサッと塗って出荷する産地や業者もあるそうだが、網代ではしょうゆやみりん、砂糖、酒を用いたタレに2〜3時間漬け込み、味を浸みこませる。しかも着色料や酸化防止剤は一切使わない。
下ごしらえにも抜かりがない。血が残ると生臭くなるため、藤田さんは血を洗い流したうえで、歯ブラシを使って骨の際に付いた血やワタまで落とす。
干物の仕上がりを左右する大前提として、二人は「よい原料を仕入れること」と口をそろえる。脂ののった魚の方が干物にしてもおいしいが、卸値も高くせざるを得なくなる。「卸値との釣り合いを考えながら、いかにいい原料を調達するかがこだわり」と小澤さん。網代で獲れる魚は脂が少ないため、九州などから原料を調達することも多い。ただし、どこで仕入れようとも「網代の干物」として出すために妥協はしない。
「天日干しも無添加も価値のあるように思われがちですが、親の代から当たり前のようにやってきたこと。地域の名物なので、そこは今後も守っていきたい」と小澤さんは言う。
懸念は、全国的な漁獲減に伴い良質の原料が減っていることと後継者問題。しかし不思議と悲壮感はない。
「先細りはしているものの、魚がある限り干物は日本の食文化としてなくならないし、やりようはまだある」と藤田さんと小澤さんは笑う。納屋さんにしてもそうだが、網代の人たちはカラッとしていて根が明るい。それは、今できることを誠実にやっていることへの自信の表れのようにも見える。
古くから魚を貨幣に換えて生きてきたように、漁業は今も変わらず網代を支える大黒柱。だからこそ商品となる干物には手間を惜しまず、質を追い求めるのだろう。
この地には「海の水が塩辛い間は私達は飢えることはない」という言い伝えがある。網代の人の気質には、今もこの精神が息づいているのかもしれない。
(2015年12月16日取材)











