機関誌『水の文化』52号
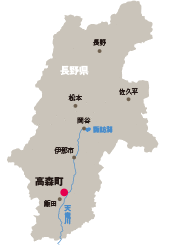
日に干す
先人の挑戦を受け継ぎ
干し柿をブランド化

表面に付いている粉は、糖分が水分とともににじみ出たブドウ糖の結晶。この粉が均一に薄く覆っているものが極上品とされる
干し柿は各地でつくられているが、なかでも長野県の飯田市・下伊那郡地域で栽培・加工される「市田柿(いちだがき)」は、他の産地を圧倒する生産量だ。農林水産省「平成24年特産果樹生産動態等調査」の干し柿生産出荷実績調査(注1)によると、市田柿は全国の干し柿の出荷量の48.8%を占める。2006年(平成18)には地域ブランドとして登録された(注2)。どのような風土が市田柿を育てたのかを探ると、失敗しても挑戦しつづけた先人の歴史に、ブランドを守ろうとする生産者の努力が積み重なったものだった。
-
長野県下伊那郡高森町
(注1)干し柿生産出荷実績調査
出荷量のおおむね8割を占める上位都道府県を対象に、50アール以上栽培され、かつ出荷実績のある品種に関する動向を、農林水産省生産局園芸作物課が各地方農政局などを通じて取りまとめたもの。
(注2)地域ブランド
地域名と一般的な商品名を組み合わせただけの商標は認められていなかったが、「地域ブランド」を守ろうと2006年(平成18)にできた「地域団体商標制度」によるもの。市田柿は長野県でもっとも早く登録された。
もっちりして甘い極上の干し柿
干し柿は全国に数あれど、「市田柿」はシェアナンバーワンを誇る。上品な甘さともっちりした食感が特徴で、果肉の表面は糖分が外ににじみ出てできた白い粉(ブドウ糖の結晶)で覆われている。百貨店で販売されるような高級品は1個400円から500円はする。
産地である飯田・下伊那地域では、毎年10月下旬から原料となる生柿を収穫すると同時に皮をむき、のれんに吊るして乾燥させる。乾燥期間はおよそ1カ月。元の重量の3分の1の重さになると、のれんから下ろして「柿もみ」をする。もむことで水分とともに糖分を押し出すのだ。さらに寝かせて粉を出す。これを3〜4回行なってから出荷となる。
11月下旬、「発祥の地」と呼ばれる下伊那郡の高森町(注3)を訪ねると、年末の出荷に向けた加工作業の真っ最中だった。しかし今シーズンはとても難しい気候だったという。
「秋は雨の日が多かったうえ気温が下がらなかったので、カビが生えてしまって廃棄が多いんですよ」
そう話すのはキタザワ農園の北沢義弘さん。妻の貞子さんも「こんなおかしな天気は今までなかったですね」と首を傾げる。
(注3)高森町
1957年(昭和32)7月1日に市田村と山吹村が合併して発足。市田柿の名は合併前の市田村に由来する。
気候と「川霧(かわぎり)」がもたらす独特な食感
元来、この季節は晴天が続き、さらに河岸段丘に沿って冷たい風が吹きあがるため、柿を乾燥させるには適した土地だ。しかし、乾燥しすぎると表面が硬くなり、糖分が出てこない。市田柿に欠かせない要素として、義弘さんは天竜川から発生する「川霧」を挙げた。
「霧が適度な湿気になって、柿が一気に乾かない。それが市田柿独特の食感を育てるといわれています」
かといってただ干しているだけではおいしくならない。乾燥の工程では適切な温度と湿度を保つためにハウスや干し場の窓を開け閉めしたり、柿のれん(写真4)の入れ替えなど、天候を読んだ作業が重要になる。
市田柿の振興に取り組むJAみなみ信州から生産者に「柿情報」がファクシミリで送られてくる。「3日間は雨が降るからカビが生えないように」など注意を促すほか、作業に対する指示もある。通常は年1回の硫黄燻蒸(カビ防止)を今年は3回実施した。しかし、最後は経験知から自分で決めると貞子さんは言う。
「作業の目安はありますが、そのとおりではうまくいきません。柿の状態を見て、のれんからいつ下ろすのか、何回もむのかなど判断します」
高低差の大きい高森町では各家で条件が異なるため、マニュアル化は難しい。個々の経験知に加え、生産者同士の情報交換が大切だ。
「『もう下ろした?』とお互いに聞いていますよ。抜け駆けなんてしませんよ。自分の家だけうまくいってもダメ。農協の共同出荷は各家の柿が混じります。出来の悪いものが1つでも入ったら台無しですから」
そう言って笑う貞子さんからは、市田柿のブランドを傷つけまいとする強い気概を感じる。
「焼柿(やきがき)の古木」を接ぎ木で広めた村人たち
市田柿は、なぜここまで盛んになったのか。高森町役場産業課の前島登志夫さんは「『儲かるはずがない』という冷ややかな目のなか、果敢に挑戦した先人たちがいたのです」と語る。高森町歴史民俗資料館の館長、松上(まつがみ)清志さんも「気候風土もさることながら、市田柿を広めようと一所懸命に努力した人がいたことがポイントです」と明かす。
市田柿の始まりは、市田村にかつてあった伊勢社の境内に生える「焼柿の古木」が原木との説が有力だ。「焼柿とは、囲炉裏の灰のなかに渋柿を放り込んでおくこと。渋が抜けて甘くなるそうです」と松上さん。この食べ方は江戸時代後期、伊勢社の境内で寺子屋を開いていた漢学者、児島礼順高智(こじまれいじゅんたかとも)が伝え、村人たちは焼柿の古木を接ぎ木で増やした。
ここで登場するのが、前島さんが「果敢に挑戦した先人」と称した人々だ。市田柿を都会の市場に出した上沼(かみぬま)正雄・鉄男親子、苗木を広めた福澤利喜三郎(りきさぶろう)・伝蔵親子、焼柿を市田柿と名づけた橋都正農夫(はしづめまさのぶ)、生産農家を増やした酒井安の6人である。
1907年(明治40)、上沼正雄は福澤利喜三郎から仕入れた焼柿の苗木を200本植え、1921年(大正10)には橋都と酒井の協力を得て市田柿と改称した焼柿を東京や名古屋、大阪の市場へ出荷する。売れなかったものの、岐阜や山梨など柿の先進地に足を運び、農法や加工法を学ぶ。その夢は上沼鉄男が継ぐ。1954年(昭和29)ごろ、ようやく都会の市場で品質を認められ、福澤伝蔵が南信州一帯に苗木を広めた。
背景には、交易が盛んだった地域性もあるはずと松上さんは推測する。
「ここは東山道(とうさんどう)(注4)で、京都から岐阜を越えて信濃に入る玄関口です。東に行くと碓氷峠を経て東北まで続いています。また、馬の荷を載せ替えずに物資を運べる中馬(注5)も盛んでしたから」
同館には、戦後まもない時期に出荷で用いた秋田杉の化粧箱が所蔵されている。柿のラベルデザインも多彩だ。ブランディングという言葉などない時代に、柿の先進地を追い越そうとした努力の跡が窺える。
(注4)東山道
律令時代の五畿七道の一つ。五畿は山城、大和、河内、和泉、摂津。七道は東海道、東山道、北陸道、山陰道、山陽道、南海道、西海道。
(注5)中馬
17世紀、伊那地方の農民が農閑余業として始めた。江戸時代の荷物の運搬は宿場ごとに人馬を付け替えて運ぶリレー形式だったが、中馬は付け替えずに目的地まで運送した。18世紀初めに信州一円、そして尾張や三河、江戸まで広がった。
次世代に継承される市田柿のブランド
先人による下地があったうえ、昭和40年代以降に進んだ養蚕業の衰退が、市田柿の増産に拍車をかけた。天竜川のそばに住む柏原昌弘さんは、父親の代から市田柿をつくりつづけている。その作業場は、1928年(昭和3)に先々代が建てた養蚕小屋を改造したものだ。
「昭和40年には蚕をやめて、桑畑に柿と梅を植えました。20年ほど前、全面的に柿に切り替えたのです」と言う柏原さん。30アールの農地に90本の柿をもつ。市田柿のブランド力を実感するかと尋ねると「威力はあるね。自分の家だけでは干しきれないから、他の農家に生柿を卸しているけれど、ダブついて困ることはないです」と話す。稲作もしているが、売り上げは圧倒的に柿の方が多い。
問題は、高齢化が進み、柿の生産・加工をやめる農家が現れていること。JAみなみ信州は、農家の労力を軽くするために2013年(平成25)「市田柿工房」を稼働。町役場も、農地を借り上げて柿を収穫する農業法人の立ち上げを準備している。
高森町は、先人の挑戦が生んだ市田柿を、次代に継承することに力を注ぐ。小学生には市田柿の料理教室を行ない、中学1年生は毎年農家で柿もぎを体験する。12月1日の「市田柿の日」には、町内の小・中学生の給食に市田柿を提供した。こうした活動は先々必ず実を結ぶだろう。
(2015年11月27日取材)












