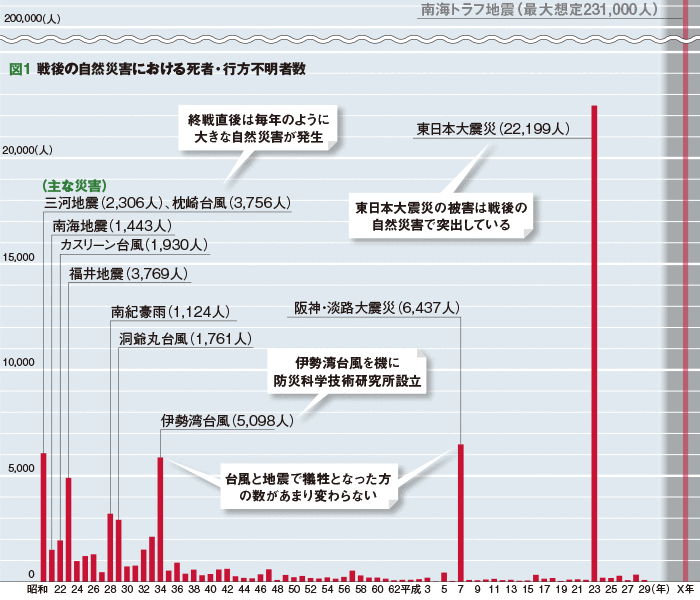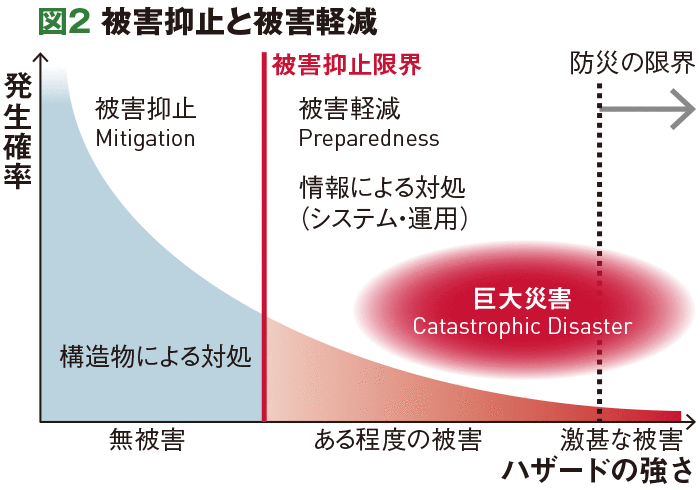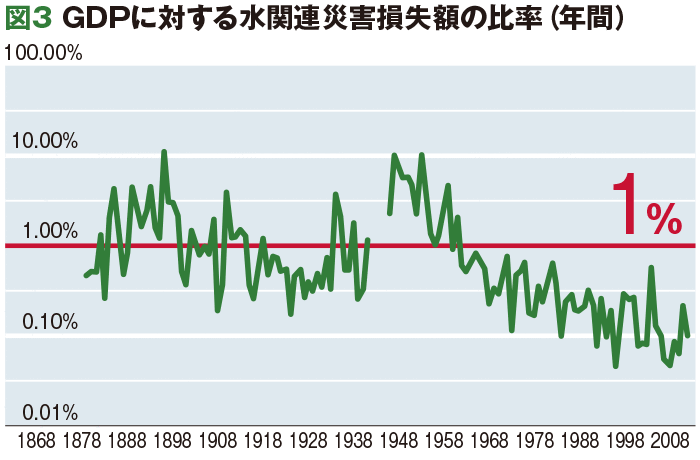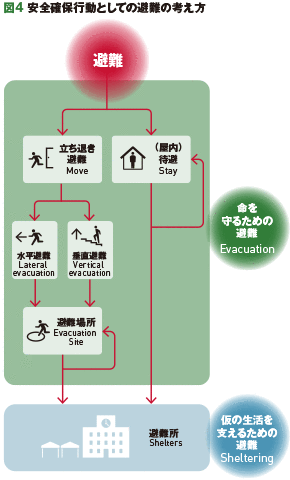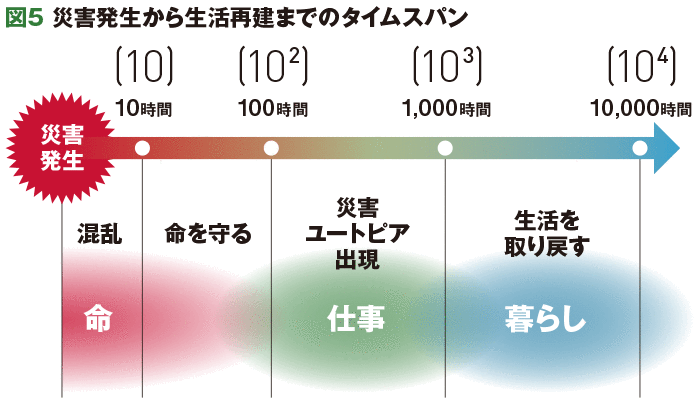機関誌『水の文化』62号

総論(防災)
災害列島に住む日本人に求められる心構えとは?
昨今の異常気象および頻発する水害を見るにつれ、不安になる人は多いだろう。私たちはどう対処すればよいのか、そもそも防災とはどういうことなのか。この難問について、災害発生時の人間行動学から復旧・復興のあり方まで幅広い視野で災害を見つめ、阪神・淡路大震災では兵庫県や神戸市で、新潟県中越地震では小千谷市でそれぞれ復興計画の策定に携わった林春男さんにお聞きした。
-

-
インタビュー
国立研究開発法人 防災科学技術研究所理事長
林 春男(はやし はるお)さん -
1951年東京生まれ。早稲田大学文学部心理学科卒業、早稲田大学大学院修士課程修了。カリフォルニア大学ロスアンジェルス校(UCLA)大学院博士課程に留学、博士号(Ph.D.)取得。弘前大学人文学部などを経て京都大学防災研究所巨大災害研究センター教授。2015年10月から現職。専攻は社会心理学(災害時の人間行動/防災心理学/日系人の強制収容体験)。『防災の決め手「災害エスノグラフィー」—阪神・淡路大震災秘められた証言』『災害のあと始末』など著書多数。
災害に向き合う四つの力「予測」「予防」「対応」「回復」
防災科学技術研究所(以下、防災科研)は1963年(昭和38)に科学技術庁所管の研究所として設立されました。契機となったのは紀伊半島から東海地方にかけて甚大な被害をもたらした伊勢湾台風(1959年)。その教訓を踏まえ、防災の科学技術を進展させるための研究所として発足したのです。(図1)
現在の防災科研が標榜している理念は「生きる、を支える科学技術」。地震、津波、噴火、豪雨、豪雪、洪水、地すべり……あらゆる自然災害が研究対象となります。しかし残念ながら自然の脅威を人間はコントロールできません。その前提に立つと、人間にできるのは、自然の脅威が生み出す災害の方をなくしていくことです。
防災用語では自然の脅威を「ハザード」と呼びます。災害が生まれるかどうかは、社会がもつ防災力とハザードのせめぎ合いです。ハザードが勝てば災害になるし、防災力が勝てば未然に防げます。(図2)
防災の科学技術を進展させるには、第一にハザードの性質を正確に理解すること。制御はできないにしろ、少なくとも「予測」はしたい。孫子の兵法ではないですが、敵を知らずには勝てません。
第二に己を強くする、つまり社会の防災力を上げること。災害が起きないよう「予防」に注力することが大切です。しかし近年続いている大規模なハザードを見ると決して予防しきれるものではありません。予防だけで乗り切れないとすれば、起きてしまった災害にどう効果的に立ち向かうかというフェイズも重要です。発災直後の「対応」が問われ、長期的な復旧・復興の「回復」が欠かせません。
災害に向き合うには「予測」「予防」「対応」「回復」の四つすべてのフェイズを視野に入れることが必須であり、防災科研もこの全フェイズを研究対象としています。
21世紀前半には国難というべきかつてない大規模な災害が予測されており、私たちはそれを乗り越えなければなりません。東日本大震災の被害総額は17兆円でしたが、南海トラフ地震と首都直下型地震が起きれば最低でも100兆円、最大だと300兆円を超える被害が予想されています。それを乗り越えて人々の命と暮らしを守るには、一秒でも早い予測と効果的な予防、そして起きた災害への迅速な対応と一日でも早い回復を目指さなければいけません。
「生きる、を支える科学技術」の英語表記は“Science For Resilience”。「レジリエンス」は防災の分野でも国際的なキーワードになりました。国連の世界防災会議が2015年に仙台で採択した2035年までの「仙台防災枠組み」には「レジリエンスを高める」とあります。
レジリエンスという言葉は「回復力」や「弾力性」などと訳されることが多いですが、それだと意味が限られてしまいます。防災におけるレジリエンスとは、まさに予測・予防・対応・回復の四つの力にほかなりません。それらを総合的に高める必要があるのです。
大きく舵を切った国の水防方針
ハザードによる災害は大きく「気象災害」と「地変災害」に分かれます。どちらも日本は多発する地帯です。
モンスーン帯に位置するため、梅雨時の集中豪雨、そして秋雨前線が来るまでの間は台風に毎年襲われています。国土の8割が山地なので土砂災害も多いですね。
火山帯があり地震が多発するプレートの境目が日本には陸側に二つ、海側に二つあります。国土面積は世界の3%足らずですが、地震エネルギーの解放量は世界の10〜20%に達しているのです。ミュンヘン再保険会社の評価によると、世界でもっとも地震のリスクが高い地域はスコア710の日本の関東圏。第2位が関西圏で200程度、第3位がサンフランシスコのベイエリアで100程度ですから、ダントツで日本が危ない。
そういう場所に文明を築き大都市を構えていることを私たちは自覚しておかなければなりません。
例えばGDPに対する水害被害額の割合の経年データ(国土交通省)を見ると、戦前から戦後にかけ10%近くに達していた時期もありました(図3)。戦争で国土整備が放置されていたからです。1960年代以降、GDP自体も増大しましたが5年ごとに国土整備計画が進んでいき、今では0.1%を切っています。これは紛れもなくハードのしくみのおかげです。ハード整備抜きに防災はあり得ません。
しかし0.1%よりはなかなか小さくできない。それが現実です。国土交通省はこれまで統合治水管理の考え方に基づき、流域単位でダムと堤防により氾濫を防ぐ方針で進めてきました。2000年代に入ると水防法が改正され、国土交通省の認識も「整備途中なので水害は起きるかもしれませんが基本的には私たちにお任せください」から「皆さんも一緒に水防災について考えてください」という方向に大きく舵を切ろうとしています。
近年の水害の特徴として、川の堤防が決壊する「外水氾濫」と、下水の処理能力を超えてまちじゅうが水びたしになる「内水氾濫」が同時に起きることが多いです。つまり、川べりに限らず都市全域が洪水の危険にさらされています。そうなると、もはや国のハード整備だけに任せておくわけにはいかず、避難のしくみを含めてソフト的な防災の取り組みを強化しなければなりません。
災害発生後のタイムスパン
日本語の「避難」という言葉には“Evacuation”(命を守るための避難)と“Sheltering”(仮の生活を支えるための避難)の二つの意味が混合されていますから、分けて考える必要があります。避難は、必ずしも避難所へ行くことに限りません。水害などでは自宅の2階や3階に退避することも避難なのです。(図4)
地域によっては、水害に遭うと高台に設けてある小屋に退避し、いよいよとなれば天井や軒先に吊り下げてある舟で逃げる、といった手立てを古くから伝承しています。こうした多重防御による防災の知恵も、これからは取り戻す必要があるでしょう。
予防しきれなかった場合、災害による被害の様相は「命」「暮らし」「仕事」の3段階にわたります。(図5)
「命」に関しては、発災後の72時間が生存救出のほぼ限界です。したがって少なくとも上限100時間をめどにどれだけの救助資源を被災現場に投入できるかということが社会としての課題になります。
「暮らし」については、生活の基盤である住まいが崩壊すると再建には長い時間がかかります。暮らしの復興には、およそ1万時間程度かかる見通しが必要でしょう。
「仕事」とは要するに「事業継続」の問題です。電気、ガス、水道、交通などのインフラが機能しないために中断した日常業務をどう回復させるか、あるいは事業を停滞させずにどう継続させるか。これは1000時間程度のタイムスパンで考えるべきです。
被災地では3段階の被害が入り混じるので大変なのですが、冷静に仕分けして取り組むことが速やかな対応と回復につながります。
自助・共助・公助は「7対2対1」の割合
社会の変化につれて、災害への対応も進展しました。農耕社会から工業社会になり、多くの人々が都市に移住し福祉国家化してくると、それまでの自分で自分の身を助ける「自助」、近所の人で助け合う「互助」に加え「公助」が生まれます。そして、情報社会で新たに誕生したのは、見ず知らずの人たちが助け合う「共助」です。日本では阪神・淡路大震災をきっかけに広がりました。
自助・互助・共助・公助の四つの救助のうち、税金の再配分によって成り立つのが公助です。現在のところ、災害が起きた場合、四つのうち公助が担う比率は正直いって1割でしょう。互助も含む共助で2割、自助が7割と考えられます。
私は阪神・淡路大震災からの生活再建調査を兵庫県と一緒に実施しました。2年に一度、4回にわたって復興のありようをモニタリングしたのです。「震災のとき、どこにいましたか?」と時間経過も含めて質問したところ、被災地全域にわたって、もっとも少ない時期でも60%以上は自宅にいました。1カ月も経てば75%の人が自宅で生活しています。350万人の被災者のうち避難所へ行ったのは32万人ですから、せいぜい1割です。
7割が自宅(自助)で、1割が避難所(公助)ならば、血縁や社縁による互助+ボランティアが担う共助の割合は2割。先の比率の根拠はこの調査によります。
したがって、災害に対する心構えとしては「自助を確保する。互助・共助の環境をつくる。公助は期待しない」が正解でしょう。
公助が1割で期待できない、というのは受け入れにくいかもしれませんが実態であることは間違いないのです。公助の役割は、経済的に恵まれていない高齢者など社会的弱者を優先的に守ること。発災時にそれ以上はできません。これも先の調査に基づく結論の一つでした。
この列島に住むために忘れてはいけないこと
災害はいつどこで起きるかわかりません。レジリエンスの点で、配慮すべきことは何でしょうか。
ボランティアが駆けつける共助はすばらしい取り組みですが、あくまでも短期的な支援であることもわきまえなければなりません。共助が有効な発災後1000時間を「災害ユートピア」と呼びます。電気・ガス・水道・交通が遮断されると、原始共産制のような社会が出現するので、お金を持っていても役に立たないし、配給に並ばなければ水も食料も得られません。そうなると価値観の転倒が起き、ふだんと違う価値観が生まれます。オートバイ好きのやんちゃに見えたお兄さんが、そのオートバイで物資を運んでくれます。おばあちゃんも他人の子守で活躍するでしょう。見ず知らずのボランティアが全国から入れ替わり立ち替わり駆けつけ、いろんな支援をしてくれます。
しかしそれはあくまでも仕事を取り戻すまでの1000時間程度の期間のこと。暮らしを取り戻す1万時間となると、ボランティアによる共助に代わり血縁、社縁、地縁による互助が求められます。
災害は被災地にとって、起きたときだけのことではありません。メディアを通じて知るだけならば、災害はニュースの一つにすぎないかもしれませんが、被災した人たちにとって災害はニュースではなく、新しく生まれた現実にほかなりません。新しい現実への適応過程の始まりです。生活の変化が激しいほど、適応には長い時間がかかります。その長いプロセスをずっと見ていかなければ真の対応・回復になりません。
どんな自然災害が起きてもおかしくない日本列島に住む私たちは、そのことを肝に銘じておく必要があります。
(2019年4月19日取材)